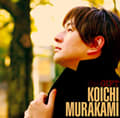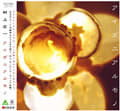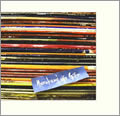日本語にこだわって、と「アイダニアルモノ」のことを語ってきたが、
日本語にというより日本にこだわろうと思ったきっかけのひとつを紹介する。
やっぱりインド・ネパール独り旅の影響がとてもとても強い。
インドにいる間の一ヶ月間は、全く日本人との接触を持たず、
なるべく地元の人達と接触しようと踏ん張ってたが、
気がついたら逆に日本人を探すのが困難なくらいマイナーなところへ踏み込んでた。
そしてさらに、インド文化の懐に飛び込もうと、
頼りないイングリッシュを絞り出すように使いながら孤軍奮闘したが、
そこで何度も実感したのは、生活の軸に宗教が大きく存在している文化の違い。
それは何度も問われた気がする。
こういう場合、日本ではどうするんだって。
えー、ホンの一部のインド人(10億分の30くらい)としか接触していませんが、
日本人の代表として恥ずかしいと思われるような行動はとってないつもりですので、
ご心配なく・・・たぶん。
例えば、食事の前の祈り。
これは、ヒンドゥだけではなくカトリックも同じでしょう。
一緒に食事をしたときの話。彼らが食前のお祈りを捧げた後、
日本だとどういう祈りをするのか?と問われた。
この場合、どう答えればいいと思う?
その時、咄嗟に出たのは、
手を合わせ、目を閉じ、そして一礼をしながら「いただきます」。
迷わず咄嗟に出たにしては間違っていなかったと思う・・・(日本代表)。
確かにこれは日本ならではの食事の前の祈り。
獣や植物の命を自然の恵みとし、それをいただくことへの感謝の気持ちを一言、
「いただきます」の言葉に込めてる。
彼らにそう説明した。頼りないイングリッシュで。
もちろん「いただきます」なんて食事の前のごく普通の当たり前の行為であるし、
単なる挨拶だと捉えているところもあるだろう。
最近では外食しても「ごちそう様」さえも言わない人達が増えている。
なんだか、そんなことへの感謝なんか遠い昔に忘れてしまっている飽食の日本という国を、
あらためて外から眺めるている気分だった。
ゆっくりと「いただきます」をしてみせた目の前のジャパニーズを見て、
彼らも「イタダキマス」と手を合わせて真似をしてくれた。
その瞬間、宗教を越えて、とても通じ合えたような気がした。
意味もしっかりと伝わったようで安心した。
自分が日本人だということを実感した瞬間・・・(日本代表!)
結局のところ、どんな宗教でも祈っている内容は同じではないだろうか。
食事が出来ることへの感謝する気持ち。
結局、それは宗教という枠を越えて、人間が自然に持つべき思考なのではないか。
それを確認しあってからは、食卓を囲んで、
それぞれ違うやり方で食事の前の祈りをしていた。
彼らの祈りの中に混じって大声で「いただきます」と。
インドではジプシースタイルのように、床のカーペットの上に食事用の布を敷き、
それをあぐらを組んで囲む。そしてもちろん右手で食す。
一週間もするとどんなに手を洗っても、右手の指先は黄色く変化し、
しかもカレーを入れた後のお弁当箱のどんなに洗ってもうっすら残ってる匂いのようになってくる。
確かにイメージ通り、彼らは毎日カレーを食べている。だが、毎日味が違う。そして飽きない。美味しい。
ちなみに、インドの偉大なる指導者、マハトマ・ガンディーの話になると、
当然のように熱く語りだす彼ら。(すでに英語ではない)
非暴力と不服従という争いを避ける平和な方法だが、
長期断食をも含むとても難儀なやりかたでイギリスからの独立を導いた国民的英雄。
熱い話の最後に、とても難しい問いをしてくる。
そんなガンディーのような偉大な人物は日本にはいるのか?と。
申し訳ない。答えることが出来ず、自分に失望しました。
頭に浮かぶのはダライ・ラマや、マーティン・ルーサー・キングといった、
よその国の偉大なる指導者ばかり。さらにがっくし・・・(日本代表失格!)
もっと自分の国のことを誇りを持って語れるような人間にならねばと決めた瞬間、のひとつでした。
| Trackback ( 0 )
|