前のコラムでも触れたが、70年代のBLUE NOTEレーベルの作品群について、紹介しよう。

このブログで扱うのは、主に90年代~00年代、つまり「現在進行形」の作品なので、70年代の作品は、個々には扱わない。
が、この時代の諸作を抜きにしてアシッド・ジャズというジャンルを語る事はできない。
いわゆる「ニューノート」あるいは「BN-LA」とも呼ばれるこの時代を、コラムで扱うことにする。
ブルーノートの総帥、アルフレッド・ライオンが引退し、BLUE NOTEレーベルはLibertyというレーベルの傘下に入る。
ライオンが引退したことで、以降の作品は「純粋なBLUE NOTEレーベルの音とは言えない」というお固いジャズファンもいるかも知れないが、
それには納得できる側面もある。
時代はエレクトリック楽器全盛に移ってきていて、James Brown や Sly などファンクが黒人音楽に台頭してきていた時代だった。
ジャズも旧来のスタイルでは食えなくなってきていたし、だからこそMiles Davisも “電化した” などと揶揄されながらも、
新しい表現を模索していた。
レーベル売却は、時代の波に飲まれた不可避なものだったかも知れない。
それはさて置き、この時代の録音にはまた違った魅力がある、というのは、ジャズファン、DJら双方から評価の高い事実である。
前にも書いたとおり、まずSKY HIGH Productionsの存在が大きい。
彼らの関わった作品を追っていけば、このブログで紹介しているアシッド・ジャズに繋がる。
まずはDonard Byrd。 名作『Steppin' Into Tommorow』。
名作『Steppin' Into Tommorow』。
# Think Twice や # You And The Music を含む、全体的にメロウなアルバム。
# Think TwiceはErykah Baduのアルバム『Worldwide Underground』でもカバーされていて、
そこで官能的なトランペットを吹いているのはRoy Hargrove! 『Places And Spaces』
『Places And Spaces』
これぞ、SKY HIGH Productionsの代名詞と言うべき作品。
サンプリングソースとしても有名で、DJやヒップホップ・ヘッズにとってはクラシックのひとつ。
ジャケットも印象的で、いろいろパクられている(笑)。 Bobbi Humphley『Blacks And Blues』
Bobbi Humphley『Blacks And Blues』
これもFREE SOUL界隈では定番中の定番。
彼女のアルバムは他にも数枚あるのだが、どれも似たり寄ったりな印象がある・・・。
もちろん他のアルバムにも佳曲はあるので、ベスト盤を入手するのがおすすめ。 『The Best of Bobbi Humphley』
『The Best of Bobbi Humphley』
Gary Bartzはのちにマイルス・バンドに加入するサックス奏者。 『Music is Sanctuary』(1977)
『Music is Sanctuary』(1977)
タイトル曲が有名。この曲構成は、今ではかえって新鮮に聴こえる。
だが、他の曲に関しては印象が薄い気が・・・ Eddie Henderson『Heritage』(1975)
Eddie Henderson『Heritage』(1975)
トランペット / フリューゲルホルン奏者のEddie Henderson のアルバム。
リズム隊が Herbie Hancock の『Thrust』と同じメンツ。当然強力かつタイトなファンク!
# Kudu はいかにも彼ららしいビートで、素晴らしいグルーヴ。
日本のクラブ・ジャズ・ユニット、KYOTO JAZZ MASSIVE がトランペットリフを女性ヴォーカルに差し替えてカバーしている。
前にも書いたとおり、再評価が著しいこの時代の作品群。もちろん企画コンピレーションも多く出ている。
その中で、本家BLUE NOTEが出しているコンピがある。 Capitol Rare (vol.1)
Capitol Rare (vol.1)
レーベルがCapitolに移行した時代のレア・グルーヴ、といったところか(LibertyはのちにCapitolに買収される)。
Vol.3まで出ているのだが、さらにその3枚からよりすぐったベスト盤まで出ている。
現代のBLUE NOTEレーベルにおけるメイン商品の一つは、豊富かつ高クオリティな音源を活用した、こういう企画コンピにある。
このシリーズ(背面が白青で統一されたシンプルなデザイン)のコンピは、中古レコードショップで大量に見ることができる。
『ジャズ-オムニバス』のセクションに、「BLUE NOTE」としてコーナー分けされるほどだ。
アシッド・ジャズというジャンルが、こうした70年代のジャズ(~クロスオーヴァーと呼ばれるジャンルまで)に
多大な影響を受けている、ということは前のコラムでも触れた。
アシッド・ジャズの音的特徴を考える上で、やはり「ニューノート」、「BN-LA」時代のこれらの作品は外せない。
どことなくざらついたような、洗練されていない感触は、おそらく電気楽器のギターやベース、鍵盤類と、
アコースティック楽器であるサックスやトランペットのせめぎあい、折り合いのつけ方を模索しているような感じに起因するのではなかろうか。
しかし、これがグルーヴの鍵を握っているようにも思う。
80年代に入るとそういったものは洗練されきってしまい、お互いが収まるべきところに収まり、
聴きやすいが耳に残らない印象となってしまう。
このブログでは、「アシッド・ジャズ」という言葉を、「ジャズっぽい雰囲気を持ったクラブミュージック」と捉えている。
“ざらつき”感を持った作品・ミュージシャンを、今後も紹介していくつもりだ。
最新の画像[もっと見る]
-
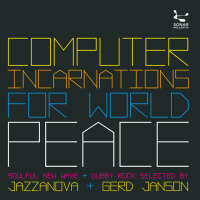 Computer Incarnations for World Peace / JAZZANOVA + GERD JANSON
1年前
Computer Incarnations for World Peace / JAZZANOVA + GERD JANSON
1年前
-
 Underground / COURTNEY PINE
2年前
Underground / COURTNEY PINE
2年前
-
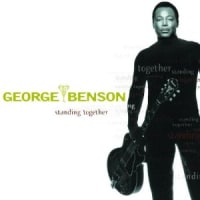 Standing Together / GEORGE BENSON
3年前
Standing Together / GEORGE BENSON
3年前
-
 Journey to Truth / STEVE WILLIAMSON
3年前
Journey to Truth / STEVE WILLIAMSON
3年前
-
 「ベストアルバム」について
4年前
「ベストアルバム」について
4年前
-
 Ulf Sandberg Quartet
4年前
Ulf Sandberg Quartet
4年前
-
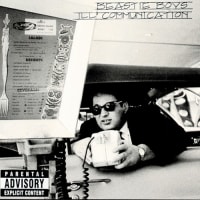 Ill Communication / BEASTIE BOYS
5年前
Ill Communication / BEASTIE BOYS
5年前
-
 Man Made Object / GO GO PENGUIN
6年前
Man Made Object / GO GO PENGUIN
6年前
-
 In The Mode / RONI SIZE REPRAZENT
6年前
In The Mode / RONI SIZE REPRAZENT
6年前
-
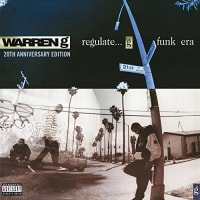 G Funk Era / WARREN G
7年前
G Funk Era / WARREN G
7年前














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます