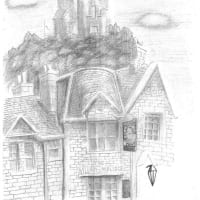この公的部門の公的部門管理の構造の変化と都市化の進行から見て、人間個人達は経済的利便性により更に都心部にて移住し生活するようになる。 その他の地方の人口はより減少傾向をたどり、すべての産業はより分業と専門化が進み一極集中化が進み、地方で根強く残れる産業は自然資源の採取により成り立つ産業ぐらいではないか。
この現象により、世界中で限られた数の都市部がより拡大していき、地方の市町村などは縮小していく傾向にある。 それゆえに、地方における公的部門や民間の公益事業に対する投資も減少していくであろう。 それは、縮小していく地方に対しての投資費用に対してその見返りが低いためであり、税金を納めている個人達にもより都会に移住するようになるために地方への公共投資はより要求しないようになるであろう。 故に、国民国家によるその国家への税制交付もより現象するために、地方の国民国家への信頼はより減退していく傾向になる。
行政は、採算が合わない地方への支出を減らし、人的および物的資源の分配が効果的に行われ採算が取れやすい都市部へより支出を重視するようになるであろう。 地方の人口が減少すると、行政に対して支援を要請する交渉力が弱まる。 そして、都心部に住む住人等がより自分たちの生活の快適さと発展の維持を要求するために、そして行政も都心部への公共投資の方が採算が合うために、都心部への投資に重点が置かれる。 都心部の住人もその国家の住人として地方への考慮を行うよりも、より個人の生活が重要になる。 グローバルな交易が活性化し情報技術と情報交換もグローバル化すると個人等も国民国家の住人というアイデンティティから世界に生きる一個人というアイデンティティの方が強くなる。
国民国家への忠誠から成り立っていた公的部門管理の重要性も失われることも必然的な現象である。 グローバルに影響力のある個人や団体がより公的部門管理への発言力が増してくる。 特に多く納税している個人や団体の発言が強くなるために、公的部門管理も彼らの提案によって動くようになる。 そして各国に存在する公的部門管理を担う行政組織も、国民国家のためではなく、グローバル化された世界とそこに生きる個人達のために存続する組織という性格が色濃くなる。
だがその一方で、情報技術のグローバル化の恩恵により、労働組合や学生組合など比較的に納税率の低い大多数の個人が団結して交渉力をつけることもあり得る。 そして、グローバルに拡大し進化した情報技術を素早く自分のものとして吸収できる若い個人達はより一段と国境を越えて団結することが可能になった。 近未来によって国境を越えた学生集団や労働組合的な組織の結成もありうるし、一部ではそれらしきものは密かに誕生していたりする。 とにかくこのように下から沸き起こる運動も国民国家を中心としたものから国境を越えたグローバルなものになっていることも注目できる。
殆どの国家において、国力の有無はグローバルに影響力がある個人や団体などの支援を受けていることによって影響する。 もはや国家が国益のために国政を誘導するよりも、そのグローバルに影響力がある個人や団体がその国に対して影響力を強めている。 故に、今の世の中は National Interest ではなく Global Interest グローバル利権によって動かされているといってもおかしくない。
この政治の転換は、国家の存在というものを前提としてきた近代哲学や政治思想の終焉でもある。 マルクス主義のような果敢な革命思想も国家を支配する古体制の打倒を主張しているが、旧体制に支配された国家を新体制が乗っ取るということなので結局は国家という構造に依存している。 またリバタリアン(自由意志論)のような国民国家権力そのものに対して懐疑的な政治思想の存亡もまた危ない。 マルクス主義のような前者の例は国民国家の存在なしには語れない政治構造であるし、リバタリアンのような後者の例は単に個人の民意の反映を強調させるために中央政府の権力を比較的に減少させる政治構造なので結局は国民国家の範疇である。
この世界を覆うグローバル化現象は徐々に数々の党の対立によって形成させる政治体制をも覆すであろう。 近未来において、各地域の行政運用は、各党が掲げる政治思想によって導かれるのではなく、より実利的な各個人等の要求と世界全土の経済情勢が求めている政策運用によって成り立っていくであろう。
この現象により、世界中で限られた数の都市部がより拡大していき、地方の市町村などは縮小していく傾向にある。 それゆえに、地方における公的部門や民間の公益事業に対する投資も減少していくであろう。 それは、縮小していく地方に対しての投資費用に対してその見返りが低いためであり、税金を納めている個人達にもより都会に移住するようになるために地方への公共投資はより要求しないようになるであろう。 故に、国民国家によるその国家への税制交付もより現象するために、地方の国民国家への信頼はより減退していく傾向になる。
行政は、採算が合わない地方への支出を減らし、人的および物的資源の分配が効果的に行われ採算が取れやすい都市部へより支出を重視するようになるであろう。 地方の人口が減少すると、行政に対して支援を要請する交渉力が弱まる。 そして、都心部に住む住人等がより自分たちの生活の快適さと発展の維持を要求するために、そして行政も都心部への公共投資の方が採算が合うために、都心部への投資に重点が置かれる。 都心部の住人もその国家の住人として地方への考慮を行うよりも、より個人の生活が重要になる。 グローバルな交易が活性化し情報技術と情報交換もグローバル化すると個人等も国民国家の住人というアイデンティティから世界に生きる一個人というアイデンティティの方が強くなる。
国民国家への忠誠から成り立っていた公的部門管理の重要性も失われることも必然的な現象である。 グローバルに影響力のある個人や団体がより公的部門管理への発言力が増してくる。 特に多く納税している個人や団体の発言が強くなるために、公的部門管理も彼らの提案によって動くようになる。 そして各国に存在する公的部門管理を担う行政組織も、国民国家のためではなく、グローバル化された世界とそこに生きる個人達のために存続する組織という性格が色濃くなる。
だがその一方で、情報技術のグローバル化の恩恵により、労働組合や学生組合など比較的に納税率の低い大多数の個人が団結して交渉力をつけることもあり得る。 そして、グローバルに拡大し進化した情報技術を素早く自分のものとして吸収できる若い個人達はより一段と国境を越えて団結することが可能になった。 近未来によって国境を越えた学生集団や労働組合的な組織の結成もありうるし、一部ではそれらしきものは密かに誕生していたりする。 とにかくこのように下から沸き起こる運動も国民国家を中心としたものから国境を越えたグローバルなものになっていることも注目できる。
殆どの国家において、国力の有無はグローバルに影響力がある個人や団体などの支援を受けていることによって影響する。 もはや国家が国益のために国政を誘導するよりも、そのグローバルに影響力がある個人や団体がその国に対して影響力を強めている。 故に、今の世の中は National Interest ではなく Global Interest グローバル利権によって動かされているといってもおかしくない。
この政治の転換は、国家の存在というものを前提としてきた近代哲学や政治思想の終焉でもある。 マルクス主義のような果敢な革命思想も国家を支配する古体制の打倒を主張しているが、旧体制に支配された国家を新体制が乗っ取るということなので結局は国家という構造に依存している。 またリバタリアン(自由意志論)のような国民国家権力そのものに対して懐疑的な政治思想の存亡もまた危ない。 マルクス主義のような前者の例は国民国家の存在なしには語れない政治構造であるし、リバタリアンのような後者の例は単に個人の民意の反映を強調させるために中央政府の権力を比較的に減少させる政治構造なので結局は国民国家の範疇である。
この世界を覆うグローバル化現象は徐々に数々の党の対立によって形成させる政治体制をも覆すであろう。 近未来において、各地域の行政運用は、各党が掲げる政治思想によって導かれるのではなく、より実利的な各個人等の要求と世界全土の経済情勢が求めている政策運用によって成り立っていくであろう。