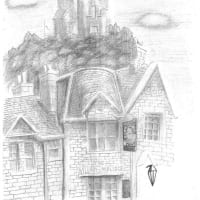既に風の時代へ突入し、地の時代の産物が斜陽傾向にあります。そこで今までの時代を哲学者の理論を至極簡潔にして比べて説明してみたいです。
まず火の時代ってマキャベリの君主論のイメージ。中世の混とん状態から社会をまとめ支配者となり統治し続けるためのパワーとカリスマが求められる。これは君主制だけでなく、いやよりむしろ人気投票がものをいう民主共和制でも当てはまる。この火の時代での成功者のたとえは、生き抜き勝ち残る力を持った、屈強な戦士と宗教の教祖。
次に来た地の時代ってホッブスのリヴァイアサンのイメージ。中世も終わりを告げルネッサンスと宗教改革を経てフランス革命と産業革命の2つの革命を経て、近代の経済と国家が制定され安定化していく。富の蓄積と社会の安定を担う組織力が求められる。この地の時代の成功者は組織への忠誠心を持って勤勉に従順に働く者、もしくは社会に認められた学者や芸能家。
風の時代はサルトルの政治哲学のイメージですね。サルトルの政治哲学は当初は個人の個性が組織や社会、そして経済に束縛されない世界を目指した。だが、より個性が自由になればなるほど愛国心や地元愛への依存が強くなる一見矛盾しているようで実は説明がつく現象がおこる。
例えばサルトルは自由市場経済は実は市場の需要により個人の個性が選別され淘汰されてしまうので本来の自由は担保されないと説いた。それで徹底的な個の自由を説いたところ、なんとサルトルはマルクス主義に迎合してしまったのだ!ただ旧来のマルクス主義を批判しつつもであるが。絶対的な個人主義を貫く自由を担保するにはそれを守る社会主義の制度が必要となる結論が生じた。(古典的)自由主義の終焉と計画経済の導入を唱えたマルクスとは矛盾する響きではある。
これはサルトル自身も自身の政治哲学を客観的に観て、結局人間とは完全に他人に極端に違うことを恐れる生き物なので、自分が個性的であることを続けるならば自分以外の周りの他人等も個性的であることで安心感を得られ、そうでなければ不安になる、みたいなことを説明していた。
風の時代で皆が個性的に生きるということは、地の時代のような組織力と努力の積み重ねによって築き上げられる富と安定にすがれず、地の時代より富の総量は下がり全体的には物質的に貧しくなる。だからこそ、風の時代では逆説的に地の時代の会社や役所のような組織よりも大きな枠組みである国家や社会への依存と郷愁は強くなる。正にサルトルの政治哲学のように個人の完全自由を目指せば目指すほどその個人集団を纏める社会への依存が強くなる。
やはり風の時代はマルクスが目指しサルトルが迎合した本来の社会主義の姿に近いのかもしれない。ただマルクスの提唱した世界とは違い、資本主義は風の時代では残り続ける。風の時代は思想の対立の時代でもあるため、資本主義が残り続ける中でサルトルの唱えた社会主義的な要素が浸透していく感じ。むしろ、資本主義が加速し富の分配が偏り、多数の個人が組織へすがり富を獲得する機会が減少するからこそ、組織から離れこの自由を追求せざるを得ない。
つまり、好きなことをして生きていくとは、組織に依存しながら富を得れないのであれば、物質的に貧しくなっても精神的に満足いくことで生きる意味を探ること。また、皆が個性的になるということは皆が一緒になるという意味でもある。
恐らく風の時代はマクロ経済的な富の総量が減退してもミクロ経済的な技術躍進は更に進むと予測される。それと同時に倫理観もかなりドライなものとなるだろう。そこでトランスヒューマニズムも進むと同時に尊厳死も認められるだろう。そして得れる情報量は肥大化していくがそれを使える個人とそうでない個人で生活環境だけでなく人生そのものの質に格差がでてくる。トランスヒューマニズムによる延命の恩恵に授かれ情報を活用する個人とそれができずこの世に見切りをつけ尊厳死を選ぶ個人に分かれていく。
その行きつく先に水の時代、そこは生と死の堺がテーマになる、ハイデガーの哲学のイメージ。本来の生と存在、そして死とは何か、その存在そのものの存在が問われる。この世への未練が残り煩悩が強い強者よりも、むしろこの世の未練を断ちあの世か次の世と呼ばれる段階へいち早く辿り着いた弱者の方が救済される時代かもしれない。
ハイデガーの時間と存在の哲学がとても興味深く好き。彼の哲学で「長く存在する時間」を「長い停滞した時間」を完全に区別した。生きる存在とは根本となる部分は存続し続けると同時に多くの部分は変化し続けていくものである。何もかも変わらないものは存在しているのではなく停滞しているのである。そして、その存在の物質的な死である第一の死があり、その存在が皆の記憶に存在し続けるがその個人の概念的存在が終わる第二の死がある。
この世の第一の死を受け入れると同時に、死後の世界だけでなくこの世の第二の存在と死への感心がより高まる。そしてほぼ永遠の命を得たとしてもそれが本来の意味で生き存在することと直結しなくなる。イエス・キリストは迫害された後に早い段階で第一の死を選ぶと同時に永遠の存在を得た。迫害されていた弱い立場のキリスト本人とその従者等は殉教し死に行くと同時に存在そのものとして永遠の命を得たのである。弱者こそ強者なりえるのが水の時代。
まず火の時代ってマキャベリの君主論のイメージ。中世の混とん状態から社会をまとめ支配者となり統治し続けるためのパワーとカリスマが求められる。これは君主制だけでなく、いやよりむしろ人気投票がものをいう民主共和制でも当てはまる。この火の時代での成功者のたとえは、生き抜き勝ち残る力を持った、屈強な戦士と宗教の教祖。
次に来た地の時代ってホッブスのリヴァイアサンのイメージ。中世も終わりを告げルネッサンスと宗教改革を経てフランス革命と産業革命の2つの革命を経て、近代の経済と国家が制定され安定化していく。富の蓄積と社会の安定を担う組織力が求められる。この地の時代の成功者は組織への忠誠心を持って勤勉に従順に働く者、もしくは社会に認められた学者や芸能家。
風の時代はサルトルの政治哲学のイメージですね。サルトルの政治哲学は当初は個人の個性が組織や社会、そして経済に束縛されない世界を目指した。だが、より個性が自由になればなるほど愛国心や地元愛への依存が強くなる一見矛盾しているようで実は説明がつく現象がおこる。
例えばサルトルは自由市場経済は実は市場の需要により個人の個性が選別され淘汰されてしまうので本来の自由は担保されないと説いた。それで徹底的な個の自由を説いたところ、なんとサルトルはマルクス主義に迎合してしまったのだ!ただ旧来のマルクス主義を批判しつつもであるが。絶対的な個人主義を貫く自由を担保するにはそれを守る社会主義の制度が必要となる結論が生じた。(古典的)自由主義の終焉と計画経済の導入を唱えたマルクスとは矛盾する響きではある。
これはサルトル自身も自身の政治哲学を客観的に観て、結局人間とは完全に他人に極端に違うことを恐れる生き物なので、自分が個性的であることを続けるならば自分以外の周りの他人等も個性的であることで安心感を得られ、そうでなければ不安になる、みたいなことを説明していた。
風の時代で皆が個性的に生きるということは、地の時代のような組織力と努力の積み重ねによって築き上げられる富と安定にすがれず、地の時代より富の総量は下がり全体的には物質的に貧しくなる。だからこそ、風の時代では逆説的に地の時代の会社や役所のような組織よりも大きな枠組みである国家や社会への依存と郷愁は強くなる。正にサルトルの政治哲学のように個人の完全自由を目指せば目指すほどその個人集団を纏める社会への依存が強くなる。
やはり風の時代はマルクスが目指しサルトルが迎合した本来の社会主義の姿に近いのかもしれない。ただマルクスの提唱した世界とは違い、資本主義は風の時代では残り続ける。風の時代は思想の対立の時代でもあるため、資本主義が残り続ける中でサルトルの唱えた社会主義的な要素が浸透していく感じ。むしろ、資本主義が加速し富の分配が偏り、多数の個人が組織へすがり富を獲得する機会が減少するからこそ、組織から離れこの自由を追求せざるを得ない。
つまり、好きなことをして生きていくとは、組織に依存しながら富を得れないのであれば、物質的に貧しくなっても精神的に満足いくことで生きる意味を探ること。また、皆が個性的になるということは皆が一緒になるという意味でもある。
恐らく風の時代はマクロ経済的な富の総量が減退してもミクロ経済的な技術躍進は更に進むと予測される。それと同時に倫理観もかなりドライなものとなるだろう。そこでトランスヒューマニズムも進むと同時に尊厳死も認められるだろう。そして得れる情報量は肥大化していくがそれを使える個人とそうでない個人で生活環境だけでなく人生そのものの質に格差がでてくる。トランスヒューマニズムによる延命の恩恵に授かれ情報を活用する個人とそれができずこの世に見切りをつけ尊厳死を選ぶ個人に分かれていく。
その行きつく先に水の時代、そこは生と死の堺がテーマになる、ハイデガーの哲学のイメージ。本来の生と存在、そして死とは何か、その存在そのものの存在が問われる。この世への未練が残り煩悩が強い強者よりも、むしろこの世の未練を断ちあの世か次の世と呼ばれる段階へいち早く辿り着いた弱者の方が救済される時代かもしれない。
ハイデガーの時間と存在の哲学がとても興味深く好き。彼の哲学で「長く存在する時間」を「長い停滞した時間」を完全に区別した。生きる存在とは根本となる部分は存続し続けると同時に多くの部分は変化し続けていくものである。何もかも変わらないものは存在しているのではなく停滞しているのである。そして、その存在の物質的な死である第一の死があり、その存在が皆の記憶に存在し続けるがその個人の概念的存在が終わる第二の死がある。
この世の第一の死を受け入れると同時に、死後の世界だけでなくこの世の第二の存在と死への感心がより高まる。そしてほぼ永遠の命を得たとしてもそれが本来の意味で生き存在することと直結しなくなる。イエス・キリストは迫害された後に早い段階で第一の死を選ぶと同時に永遠の存在を得た。迫害されていた弱い立場のキリスト本人とその従者等は殉教し死に行くと同時に存在そのものとして永遠の命を得たのである。弱者こそ強者なりえるのが水の時代。