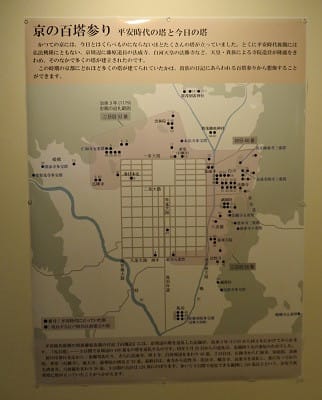昨年2018年に茅ヶ崎市美術館で行われた展覧会で一躍人気を集めた小原古邨(おはらこそん)。木版画とは思えない美しい花鳥画を再び味わえる展覧会が、東京・原宿の太田記念美術館で開催されています。
- 2018年の茅ヶ崎市美術館での展覧会とは出展作がかなり異なる、古邨の新たな魅力が味わえる
- 原画→試摺→完成作と製作過程での変化をたどれる展示が面白い
- 少数ながら風景画もあり、花鳥画とは異なる趣の表現が魅力的
茅ヶ崎市美術館での展覧会を観た人も観なかった人も、古邨ワールドに深く陶酔することは間違いありません。私が鑑賞したのは後期展示ですが、素晴らしい作品が揃っていました。
太田記念美術館
茅ヶ崎市美術館で行われた展覧会で、小原古邨を初めて知った方が多いと思われます。私もその一人で、以来すっかり古邨ワールドに陶酔しています。言われなければ水彩画にしか見えないような緻密な木版画の絵師であること、明治以降の日本の木版画では珍しい花鳥画が得意。この2点の個性が際立っていることがその魅力の源泉です。
この展覧会では、古邨作品の大半を占める版元・松木平吉(通称:大平、だいへい)以外の版元(はんもと)の作品が比較的多く出展されています。秋山武右衛門(あきやまぶえもん)が率いた滑稽堂、渡辺庄三郎(わたなべしょうざぶろう)が率いた渡辺版画店、酒井好古堂&川口商会の共同出版、の3つです。
版元とは現在の出版社のような存在で、木版画の版木を製造・所有することで出版の権利を握っていました。絵師の創作は当然、版元の意向に沿うことになり、版元が代わると作風が代わります。古邨は、昭和になってから付き合いの始まった渡辺版画店からの作品では祥邨(しょうそん)、酒井好古堂&川口商会からの作品では豊邨(ほうそん)と落款の号まで変えています。
版元の違いを確認しながら作品を鑑賞すると、版元による顧客ニーズの違いが見えてきます。より興味深く古邨ワールドの奥の深さを理解することができます。
昨年2018年の茅ヶ崎市美術館「小原古邨」展
今回の太田記念美術館の展覧会は、異なる版元それぞれの作品をある程度まとまって展示できたこともあり、時系列で作品を展示しています。古邨の画業の変化がわかりやすくなっています。一方昨年2018年の茅ヶ崎市美術館の展覧会は、作品のモチーフを四季で分類した展示でした。出展作のほとんどが古邨作品の大半を占める版元・大平からの作品だったためでしょう。
【美術館公式Twitterの画像】月に木菟
「月に木菟(みみずく)」は同名で複数の作品が展示されていますが、唯一の滑稽堂からの作品(後期のみ展示)に、獲物に向かって急降下していくような躍動感を最も感じます。版元が大平の作品は全般的に落ち着いた静かな表現が見られます。
鎌倉仏師で言うと、滑稽堂作品は運慶、大平作品は快慶でしょう。滑稽堂はグロテスクな無惨絵で知られる月岡芳年(つきおかよしとし)、大平は文明開化の明治の町並を光と影を巧みに組み合わせて表現した光線画で知られる小林清親(こばやしきよちか)を、それぞれ抱えていました。両版元が追及した顧客ニーズの違いがよくわかります。
【美術館公式Twitterの画像】雨中の小鷺(左)
「雨中の小鷺」はより一層、時代と版元による顧客ニーズの違いが顕著に表れています。背景がベージュ色の作品(後期のみ展示)は明治末、背景が黒色の作品(前期のみ展示、渡邊木版美術画舗蔵)は昭和の作品です。色彩の表現を明確にすることで、より欧米の顧客の嗜好に合わそうとしたのでしょう。
また両作品とも雨が降る様子を描いていますが、雨の線がきわめて細く1mmもありません。この細さで”しとしと降り”感を見事に表現しています。まさに木版画とは思えません。明治の超絶技巧は木版画の世界でも凄腕を見せています。
【美術館公式Twitterの画像】鷹と温め鳥
「鷹と温め鳥」というタイトルの意味が一見よくわからなかったのですが、よく見ると鷹の足元に小さい雀がいます。真冬に鷹の羽毛で暖を取っている構図です。現実に見られる光景かわかりませんが、古邨作品としては珍しくユーモアを感じます。長澤芦雪のような雀の配置です。太田記念美術館所蔵の名品です。
【美術館公式Twitterの画像】月夜の桜(左:完成品、右:原画)
古邨が描いた原画→試擦→完成品と三段階の対比展示は、渡辺版画店(現:渡邊木版美術画舗)にのこされていたことで実現しました。後期展示の「雪中南天に瑠璃鳥」は画像が掲載されていないため、参考として前期の「月夜の桜」で対比をご確認ください。
試擦までは原画にほぼ忠実ですが、完成品はポイントとなるモチーフの色使いをがらりと変えています。版元が大平だったころにはおそらくありえない変更でしょう。より顧客ニーズを意識しています。
【美術館公式Twitterの画像】柘榴に鸚鵡
「柘榴に鸚鵡(ざくろにおうむ)」は、オウムの真っ白な羽毛に凹凸がつけられており、”フワフワ感”を強く感じさせます。空摺りという技法で、版木に絵具を付けずに強くすることで紙に凹凸を付けます。背景を黒ベタにすることでオウムの羽毛のリアル感がさらに引き立っています。こちらも超絶技巧を感じさせる逸品です。
【美術館公式Twitterの画像】雪中の柳橋
古邨では数少ない風景画は見逃せません。後期展示の「品川の美人」は画像が掲載されていないため、参考として前期の「雪中の柳橋」で風景画の趣をご確認ください。古邨の風景画は、花鳥画に比べてより江戸時代の情緒が表現されているのが特徴です。「品川の美人」は茶屋の2Fでたたずむ芸者を、ほとんど黒ベタのシルエットで描いています。モダンな構図で、月夜の情景に絶妙に合っています。
【美術館公式Twitterの画像】猫と提灯(左)
「猫と提灯」は「豊邨」落款の作品では最も目に留まりました。小林清親が提灯の中に潜む鼠をのぞき込む錦絵を描いており、豊邨はその続きを絵にしたと解説されています。ネタのパクリとしてもとてもユーモアにあふれています。
とても充実した内容の展覧会でした。新版画の作家は多数名前を確認することができます。古邨のような”発見”を求めて、これからも機会を逃さず観に行きたいと思います。
こんなところがあります。
ここにしかない「空間」があります。
日本語の画集では古邨作品を最も多くカバー、345点掲載
________________
太田記念美術館
小原古邨
【美術館による展覧会公式サイト】
会期:2019年2月1日(金)~3月24日(日)
原則休館日:月曜日、展示替え期間(2/25-28)
入館(拝観)受付時間:10:30~17:00
※2/24までの前期展示、3/1以降の後期展示で全展示作品/場面が入れ替えされます。
※この展覧会は、今後他会場への巡回はありません。
※この美術館は、コレクションの常設展示を行っていません。企画展開催時のみ開館しています。
◆おすすめ交通機関◆
JR山手線「原宿」駅下車、表参道口から徒歩5分
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅下車、5番出口から徒歩3分
JR東京駅から一般的なルートを利用した平常時の所要時間の目安:30分
東京駅→東京メトロ丸の内線→国会議事堂前駅→東京メトロ千代田線→明治神宮前駅
【公式サイト】 アクセス案内
※この施設には駐車場はありません。
※道路の狭さ、渋滞と駐車場不足により、健常者のクルマによる訪問は非現実的です。
________________
→ 「美の五色」とは ~特徴と主催者について
→ 「美の五色」 サイトポリシー
→ 「美の五色」ジャンル別ページ 索引 Portal