● 浄土宗
◇選択集について
選択集は、建久8年(1197)に現在でいえば「前総理大臣」という立場にあった九条兼実公の「浄土の教えの大事なことをまとめてほしい」という切望に応じられ、建久9年(1198)の春、法然上人は、浄土宗の根本宗典である『選択本願念仏集』という書物を著されました。
【選擇本願念佛集】
法然上人の選擇本願念佛集を読んでみましょう。 原文は漢文で書かれていますが、今回は書き下してあります。
第一 聖道浄土二門篇
第二 雑行を捨てて正行に帰する篇
第三 念仏往生本願篇
第四 三輩念仏往生篇
第五 念仏利益篇
第六 末法万年に特り念仏を留むる篇
第七 光明ただ念仏の行者を摂する篇
第八 三心篇
●第九 四修法篇
第十 化仏讃歎篇
第十一 雑善に約対して念仏を讃歎する篇
第十二 仏名を付属する篇
第十三 念仏多善根遍
第十四 六方諸仏ただ念仏の行者を証誠したまう篇
第十五 六方諸仏護念篇
第十六 弥陀の名号を以て舎利弗に付属したまう篇
【第九章段】
念仏の行者四修の法を行用すべきの文
善導の『往生礼讃』に云く、また勧めて四修の法を行ぜしむ。何者をか四とす。一には恭敬修。いわゆる彼の仏、および彼の一切の聖衆等を恭敬礼拝す。故に恭敬修と名づく。畢命を期として、誓って中止せざる、すなわちこれ長時修なり。
二には無余修。いわゆる専ら彼の仏名を称して、彼の仏および一切の聖衆等を、専念し、専想し、専礼し、専讃して、余業を雑えず。故に無余修と名づく、畢命を期とし誓って中止せざる、すなわちこれ長時修なり。
三には無間修。いわゆる相続して、恭敬礼拝し、称名讃歎し、憶念観察し、回向発願し、心心に相続して、余業を以て来し間えず、故に無間修と名づく。また貧瞋煩悩を以て来し間えず、隨犯隨懺して、念を隔て、時を隔て、日を隔てしめず。常に清浄ならしめるをまた無間修と名づく。畢命を期として、誓って中止せざる、すなわちこれ長時修なり。
『西方要決』に云く、ただ四修を修するを以て正業とす。一には長時修。初発心より乃至菩提まで、恒に浄因を作して、ついに退転ずること無し。二には恭敬修。これにまた五有り。一には有縁の聖人を敬う。謂く行住坐臥、西方に背かず、涕唾便痢、西方に向わず。二には有縁の像教を敬う。謂く西方の弥陀の像変を造る。広く作ること能はざれば、ただ一仏二菩薩を作るもまた得たり。教とは『弥陀経』等を、五色の袋に盛れて、自ら読み他を教えてこの経像を室中に安置して、六時に礼懺し、香華供養して、特に尊重を生せ。三には有縁の善知識を敬う。謂く浄土の教を宣べる者は、もしは千由旬十由旬より巳来、ならびにすべからく敬重し親近し供養すべし。別学の者にも、すべて敬心を起し、己と同じからざるをも、ただ深く敬うことを知れ。もし軽慢を生ずれば、罪を得ること窮まり無し。故にすべからくすべて敬うべし。すなわち行障を除く。四には同縁の伴を敬う。謂く同修業の者なり。自ら障重くして、独業成ぜずといえども、要ず良朋に藉って、まさに能く行を作す。危うきを扶け厄を救い、力を助けて相い資く。同伴の善縁、深く相い保重せよ。五には三宝を敬う。同体別相、ならびに深く敬うべし。つぶさに録すること能わず。浅行の者の、依修することを果さざるに為ってなり。住持三宝とは、今の浅識の与に大因縁と作る。今ほぼ料簡せば、仏宝と言うは、謂く檀を雕り。綺に繍い。素質金容、玉を鏤め、(カトリ=糸+曾)に図し、石を磨き、土を削る、この霊像特に尊承すべし。暫爾、形を観れば、罪消じ福を増す。もし少慢を生ずれば、悪を長じ善亡ず。ただし尊容を想うこと、まさに真仏を見るがごとくすべし。法宝と言うは、三乗の教旨、法界所流の名句の所詮なり。能く解を生ずるの縁なり。故にすべからく珍仰すべし。慧を発するの基なるを以てなり。尊経を鈔写して、恒に浄室に安じ。箱篋に盛れ貯えて、ならびに厳敬すべし。読誦の時は、身手清潔にせよ。僧宝と言うは、聖僧と菩薩と破戒との流、等心に敬を起せ。慢想を生ずること勿れ。三には無間修。謂く常に念仏して、往生の心を作す。一切の時において、心に常に想巧すべし。譬えばもし人有って、他に抄掠せられて、身下賤と為って、つぶさに艱辛を受く。たちまち父母を思って、走って国に帰らんと欲すれども、行装いまだ弁ぜず。なお他郷に在って、日夜に思惟して、苦しみ堪え忍びず。時として暫くも捨てて、耶嬢を念ぜざること無し。計を為すことすでに成って、すなわち帰って達することを得て、父母に親近し、縦任に歓娯す。行者もまた然なり。往し煩悩に因って、善心を壊乱し、福智の珍財ならびに皆散失す。久しく生死に流れて、制するに自由ならず。恒に魔王の与に、僕使と作って、六道に駈馳せられて、身心を苦切す。今善縁に遇って、たちまち弥陀慈父の弘願に違せず。群生を済抜したまうを聞いて、日夜に驚忙し、発心して往くことを願ず。所以に精勤して倦まず、まさに仏恩を念じて、報の尽きるを期と為して、心に恒に計念すべし。四には無余修。謂く専ら極楽を求めて、弥陀を礼念す。ただ諸余の業行雑起せしめざれ。所作の業には、日別にすべからく念仏誦経を修して、余課を留めざるべし。
私に云く、四修の文見つべし。繁を恐れて解せず。ただし前の文の中に、すでに四修と云って、ただ三修有り。もしその文を脱するか。もしはその意有りや。更に脱文に非ず、その深意有り。何を以てか知ることを得る。四修とは、一には長時修、二には慇重修、三には無余修、四には無間修なり。而るに初めの長時は、ただこれ後の三修に、通用するを以てなり。謂く、慇重もし退せば、慇重の行、すなわち成ずべからず。無余もし退せば、無余の行、すなわち成ずべからず。無間もし退せば、無間の修、すなわち成ずべからず。この三修の行を成就せしめんが為に、皆長時を以て、三修に属して、通じて修せしむる所なり。故に三修の下に、皆結して畢命を期として、誓って中止せざる、すなわちこれ長時修と云うこれなり。例せば彼の精進、余の五度に通ずるがごときのみ。
◇選択集について
選択集は、建久8年(1197)に現在でいえば「前総理大臣」という立場にあった九条兼実公の「浄土の教えの大事なことをまとめてほしい」という切望に応じられ、建久9年(1198)の春、法然上人は、浄土宗の根本宗典である『選択本願念仏集』という書物を著されました。
【選擇本願念佛集】
法然上人の選擇本願念佛集を読んでみましょう。 原文は漢文で書かれていますが、今回は書き下してあります。
第一 聖道浄土二門篇
第二 雑行を捨てて正行に帰する篇
第三 念仏往生本願篇
第四 三輩念仏往生篇
第五 念仏利益篇
第六 末法万年に特り念仏を留むる篇
第七 光明ただ念仏の行者を摂する篇
第八 三心篇
●第九 四修法篇
第十 化仏讃歎篇
第十一 雑善に約対して念仏を讃歎する篇
第十二 仏名を付属する篇
第十三 念仏多善根遍
第十四 六方諸仏ただ念仏の行者を証誠したまう篇
第十五 六方諸仏護念篇
第十六 弥陀の名号を以て舎利弗に付属したまう篇
【第九章段】
念仏の行者四修の法を行用すべきの文
善導の『往生礼讃』に云く、また勧めて四修の法を行ぜしむ。何者をか四とす。一には恭敬修。いわゆる彼の仏、および彼の一切の聖衆等を恭敬礼拝す。故に恭敬修と名づく。畢命を期として、誓って中止せざる、すなわちこれ長時修なり。
二には無余修。いわゆる専ら彼の仏名を称して、彼の仏および一切の聖衆等を、専念し、専想し、専礼し、専讃して、余業を雑えず。故に無余修と名づく、畢命を期とし誓って中止せざる、すなわちこれ長時修なり。
三には無間修。いわゆる相続して、恭敬礼拝し、称名讃歎し、憶念観察し、回向発願し、心心に相続して、余業を以て来し間えず、故に無間修と名づく。また貧瞋煩悩を以て来し間えず、隨犯隨懺して、念を隔て、時を隔て、日を隔てしめず。常に清浄ならしめるをまた無間修と名づく。畢命を期として、誓って中止せざる、すなわちこれ長時修なり。
『西方要決』に云く、ただ四修を修するを以て正業とす。一には長時修。初発心より乃至菩提まで、恒に浄因を作して、ついに退転ずること無し。二には恭敬修。これにまた五有り。一には有縁の聖人を敬う。謂く行住坐臥、西方に背かず、涕唾便痢、西方に向わず。二には有縁の像教を敬う。謂く西方の弥陀の像変を造る。広く作ること能はざれば、ただ一仏二菩薩を作るもまた得たり。教とは『弥陀経』等を、五色の袋に盛れて、自ら読み他を教えてこの経像を室中に安置して、六時に礼懺し、香華供養して、特に尊重を生せ。三には有縁の善知識を敬う。謂く浄土の教を宣べる者は、もしは千由旬十由旬より巳来、ならびにすべからく敬重し親近し供養すべし。別学の者にも、すべて敬心を起し、己と同じからざるをも、ただ深く敬うことを知れ。もし軽慢を生ずれば、罪を得ること窮まり無し。故にすべからくすべて敬うべし。すなわち行障を除く。四には同縁の伴を敬う。謂く同修業の者なり。自ら障重くして、独業成ぜずといえども、要ず良朋に藉って、まさに能く行を作す。危うきを扶け厄を救い、力を助けて相い資く。同伴の善縁、深く相い保重せよ。五には三宝を敬う。同体別相、ならびに深く敬うべし。つぶさに録すること能わず。浅行の者の、依修することを果さざるに為ってなり。住持三宝とは、今の浅識の与に大因縁と作る。今ほぼ料簡せば、仏宝と言うは、謂く檀を雕り。綺に繍い。素質金容、玉を鏤め、(カトリ=糸+曾)に図し、石を磨き、土を削る、この霊像特に尊承すべし。暫爾、形を観れば、罪消じ福を増す。もし少慢を生ずれば、悪を長じ善亡ず。ただし尊容を想うこと、まさに真仏を見るがごとくすべし。法宝と言うは、三乗の教旨、法界所流の名句の所詮なり。能く解を生ずるの縁なり。故にすべからく珍仰すべし。慧を発するの基なるを以てなり。尊経を鈔写して、恒に浄室に安じ。箱篋に盛れ貯えて、ならびに厳敬すべし。読誦の時は、身手清潔にせよ。僧宝と言うは、聖僧と菩薩と破戒との流、等心に敬を起せ。慢想を生ずること勿れ。三には無間修。謂く常に念仏して、往生の心を作す。一切の時において、心に常に想巧すべし。譬えばもし人有って、他に抄掠せられて、身下賤と為って、つぶさに艱辛を受く。たちまち父母を思って、走って国に帰らんと欲すれども、行装いまだ弁ぜず。なお他郷に在って、日夜に思惟して、苦しみ堪え忍びず。時として暫くも捨てて、耶嬢を念ぜざること無し。計を為すことすでに成って、すなわち帰って達することを得て、父母に親近し、縦任に歓娯す。行者もまた然なり。往し煩悩に因って、善心を壊乱し、福智の珍財ならびに皆散失す。久しく生死に流れて、制するに自由ならず。恒に魔王の与に、僕使と作って、六道に駈馳せられて、身心を苦切す。今善縁に遇って、たちまち弥陀慈父の弘願に違せず。群生を済抜したまうを聞いて、日夜に驚忙し、発心して往くことを願ず。所以に精勤して倦まず、まさに仏恩を念じて、報の尽きるを期と為して、心に恒に計念すべし。四には無余修。謂く専ら極楽を求めて、弥陀を礼念す。ただ諸余の業行雑起せしめざれ。所作の業には、日別にすべからく念仏誦経を修して、余課を留めざるべし。
私に云く、四修の文見つべし。繁を恐れて解せず。ただし前の文の中に、すでに四修と云って、ただ三修有り。もしその文を脱するか。もしはその意有りや。更に脱文に非ず、その深意有り。何を以てか知ることを得る。四修とは、一には長時修、二には慇重修、三には無余修、四には無間修なり。而るに初めの長時は、ただこれ後の三修に、通用するを以てなり。謂く、慇重もし退せば、慇重の行、すなわち成ずべからず。無余もし退せば、無余の行、すなわち成ずべからず。無間もし退せば、無間の修、すなわち成ずべからず。この三修の行を成就せしめんが為に、皆長時を以て、三修に属して、通じて修せしむる所なり。故に三修の下に、皆結して畢命を期として、誓って中止せざる、すなわちこれ長時修と云うこれなり。例せば彼の精進、余の五度に通ずるがごときのみ。










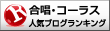

 18:00-18:40 常行院
18:00-18:40 常行院

 8:30-17:00 神社
8:30-17:00 神社

 白山宮
白山宮


 足の神様(…サッカー日本代表チームが参詣されました)
足の神様(…サッカー日本代表チームが参詣されました) 今神社
今神社




