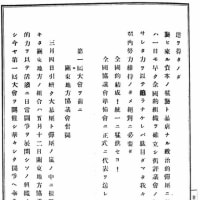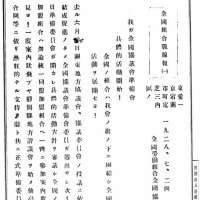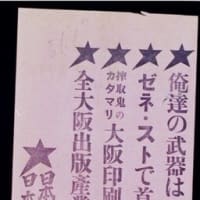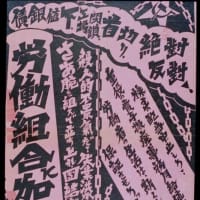『溶鉱炉の火は消えたり』浅原健三著(九~十)
―八幡製鉄所の大罷工記録—
九 鬨(かちどき)は揚がる
斯くて、いろいろの小悲喜劇はあったが、罷工はプログラムどうりに進行した。
各工場から順次に雪崩出た職工群は、行列を遮ぎらうとする監督連や守衛を××にして、気勢をあげたほかには、別段の故障も、紛擾もなく、幾十度となき調練を経た軍隊でもあるかのように、隊伍堂々と目的地に進行して行った。
八時頃には赤煉瓦の建物前の広場は群衆で埋まった。二万余の作業服で本事務所は包囲しつくされた。ここに集合したのは、全員を集める広場が他にないのと、示威力を発揚する絶好地なのと、四日代表資格を認めないといった当局の前に、生きた証拠、二万人の顔をつきつけるためであった。
暁からの霙(みぞれ)は小雪となって降り続く。寒風は肌を刺す。当時、製鉄所の人夫は雨中を簑笠で働いていたので、沢山の簑(みの)が本事務所の前のトロッコに積み込まれていた。これを見つけた加藤義雄の命令一下、×××××××××××××。人々は××××××××暖をとる。ある集団で朝飯が始まった。皆はそれに倣(なら)った。五人、十人と自然に群が出来た。朝出の職工が夜勤で腹の空いている同僚に自分達の中食の弁当を頒(ゎ)けてやった。
本事務所正面の玄関の階段に立って、西田が演説を始めた。降りしきる雪を頭から浴びて立つ彼の顔は蒼白、凄惨。この異常時に於けるこの男の絶叫。悲壮、痛烈骨を刺される思いであったという。「あの時の西田の演説だけは一生忘れない」と、今も私に述懐する職工は少なくない。引続いて、十数人が入り代わり、立ち替わり、昂奮の極点に登りつめた演説が続いた。生活苦を叫ぶ者、労働条件の劣悪を罵る者、賃金労働の不合理を論難する者、当局の無誠意を呪ふ男、結束を求め団結を誓う者、悲痛、血を吐く叫びが続く。準備せられ、組立てられた他所行(よそゆき)の言葉ではない。平常の鬱憤(うっぷん)の爆発だ。胸底からの不平不満が礫(つぶて)となって叩きつけられるのだ。言々句々、肺腑から迸(ほとばし)り出る血の叫びだ。
粉雪を浴びて、立ち聴く群衆の昂奮は、刻一刻に高まる。拍手、嵐の如き喊声(かんせい)、怒濤の如き叫喚(きょうかん)。
急を聞いて駆けつけて警官三十人ばかりも、二百人の守衛、監督も手のつけようがない。たゞ袖手傍観(しゅうしゅぼうかん)するばかりだ。
正午前、吉村、廣安、鳥居、福住の四代表と書記の山田栄三とが中川次長、竹下工場課長に面会して、前日の嘆願書を要求書として提出した。長官は罷工の第二日目に東京から駆け戻ったが、この日は留守であった。折衝三十分余。屋外の大喊声に脅かされて竹下課長の面上、昨日の威容はない。中川次長の顔も当惑、混乱の極を語る。回答期限を当局は四日間、代表者は二日間を主張し、結局代表者の主張が容れられて、二日目の七日午後六時と定めて訣別した。
代表者の報告。一万五千の大行列は、東門を出、雪をついて春ノ町の豊山公園に引き上げる。演説、指令、結束を誓つて、ひとまず解散。
一部分は工場に残ったが、誰一人働き出す者は勿論ない。働かうにも朝来、重要機関は停止している。三々伍々、群をなして、放歌、高談、鬨(とき)を揚げて気勢を煽る。間もなく退散。工場は死の如くに黙然。
一〇 炉は消えたり
ストライキへのスタートの状況、当局と会見の始末は、四人の伝令によって本部に居る私に知らせることになっているが、まだ一人も姿を見せぬ。各工場からの引揚げが成功して本事務所前に集合したら、その時、汽笛を鳴らす約束であった。その汽笛、中央汽鑵場の大汽笛が、八時頃五六声鳴り響いて、中絶した。「引揚は成功したぞ!」私は病み臥している田崎と二人で、万歳を叫んだ。一旦中絶していた汽笛は前よりも急速に鳴り出した。
「成功は確実だ。」今度は鳴り熄まぬ。最高潮の強音は、強く、鋭く、長く、全八幡の空に、ビュー、ビューと鳴り響く、突き破る勝利の雄叫(おたけび)が鳴る。
聞けば、朝鮮人の金泳文が非常汽笛を鳴らし始めた、と見た十数人の守衛が一気に押寄せ、金君を追いのけてその場を守備した。その時中絶したのである。それを観た百余の職工は、ドッと殺到、守衛連を突き落して汽笛台を××した、金は再び引綱を掴んだ。乱れた髪、喰いしばった歯、蒼白の顔、ランランたる目、彼は四十年の恨を二本の手に託して、死んでも放さない。
この汽笛は日露戦争に捕獲せられたロシア船に備付けていたものだと聞いている。日露戦争後の×××××××××××の青年がこの大ストライキの凱歌を奏する役目に就いたのだ。
汽笛は確かに成功を語る。しかし伝令が見えない。「大じょうぶだ」と思いながら、一抹の不安が残る。
八時半頃、来合はせていた女事務員を「豊山公園に行って様子を見て来い」と、買い物に出かける態(てい)で出してやる。もうその時分、この診療所は十数人の警官に包囲せられているので、私が今出てゆくわけにはゆかない。
間もなく帰って来た女事務員は「ひと筋の煙も立ってゐない。機関車も一台も動いていない。トロツコ一つ動いている様子も見えぬ。工場はガラーンとして人っ子一人姿を見せぬ」という。
だが、自分で様子を見ないと安心がならぬので、和服の着流し、雨傘をさして家を出る。四人の巡査が尾行する。
豊山公園は全工場を大観するのに、この附近では一番都合のよい小丘である。懐から望遠鏡を取り出して俯瞰(ふかん)する。
八幡駅を通過する旅人は見るであらう。あの資本主義の典型的縮図たる大工場の偉観壮観を。八幡の街頭、輝ける太陽と澄み渡る青空を望見しうる日は一年一日も有り得ない。墨汁をブチ撒いた様な煙幕、行人の白服は黒点に彩どられ、鼻孔は煤煙の貯蔵庫となる。黒煙の都! 煤煙の街! 轟然として耳を聾する大機関の響音は、血に餓えたる殺人鬼の狂声のように耳を劈(さ)く。狂蛇の如く駛走する機関車、鳴り破る幾十条の汽笛の声、溶炉の搬出を告知する警鐘の響き、声と響きとの乱舞の巷。
この塵埃と煤煙と騒音との渦巻く裡に、生不動の姿そのまゝに働き続ける労働者、地獄絵を観るような、焔と肉との相撃つ惨憺たる鎖縛の労働状姿よ! 最高無比の大××地、それは政府の名に依って成され、××の××に懸けて××せらるゝ労働××である。
その日本最大の大工場は今死淵の底に沈みゆきつゝある。女事務員の報告どうり、煙は絶え、音は消え、響はやんで、幾百棟の建物は幽魂の如く冷然と立って居る。
八幡市は二十年前の八幡村に帰っている。
「アゝ炉は消えた!」
無声の叫びが私の咽喉を裂く。武者震いか、全身がワナワナと打ち震う。握りしめた両掌が汗だ。
生をこの世にうけて二十余年。じらい十年。私にとってこの瞬間の如き激情の時はない。誰かゞ傍にいたら、私はなぐり倒したかもしれぬ。
本事務所は工場や煙突のかげになっていてここからは見えない。が、時々、ワアッという力強い喊声が本事務所と思われるあたりに揚る。何のための喊声か、眼には見えぬ。しかし、その声調は断じて敗者の唸(うめ)きではない。勝利者の歓呼である。進撃者の鯨波(ときのこえ)である。×の本城に突貫する××隊の鬨(かちどき)である。
この声、この叫び、終生忘れ得ざる感銘である。男子一生のうち、この声を聞くは、一度か、二度か、将(は)た三度か? 何たる痛快さだ。言葉がない。現わすべき言葉も文字も無い。
「スタートは確かだった。」
「仕事はこれからだ。」
「さあ、根限り、腕限り、ウントやるぞ!」
私は独語(ひとりご)しつゝ本部に引返した。手も、足も、目も口も、歓喜に戦(おのの)く。