
ニュース詳細
3月の消費支出 過去最大の下げ幅
5月1日 10時48分
ことし3月の家庭の消費支出は、消費増税前の駆け込み需要がピークだった去年の同じ月と比べて、ほとんどの品目で支出が減ったことから、去年の同じ月を10.6%下回って比較可能な平成13年以降で最大の下げ幅となりました。
総務省の発表によりますと、ことし3月の消費支出は、1人暮らしを除く世帯で31万7579円となり、物価の変動を除いた実質で去年の同じ月を10.6%下回って、12か月連続の減少となりました。
これは比較可能な平成13年以降で最大の下げ幅です。
総務省は「去年の3月は消費税率の引き上げ前の駆け込み需要がピークで、自動車やエアコンといった耐久消費財だけでなく、保存ができる食料品など幅広い品目で支出が増えたことから、今回はその反動が大きく出た」としています。
一方で、足元の消費については増加傾向が続いていることから、「全体として緩やかに回復している」という見方を維持しました。
また、自営業者などを除いたサラリーマン世帯のことし3月の収入は44万9243円で、物価の変動を除いた実質で前の年の同じ月を0.3%下回って、18か月連続の減少となりました。
関連リンク
景気回復はどこまで ~検証・日本経済~ クローズアップ現代 (4月16日)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150501/k10010066851000.html
ニュース詳細
消費者物価指数 22か月連続で上昇
5月1日 11時33分

ことし3月の全国の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月を2.2%上回り、22か月連続の上昇となりました。
総務省の発表によりますと、モノやサービスの値動きを示すことし3月の全国の消費者物価指数は、天候による変動の大きい生鮮食品を除いて、平成22年を100とした指数で103.0となり、去年の同じ月を2.2%上回って、22か月連続の上昇となりました。
これは、▽このところ原油価格が底を打ち、ガソリンや灯油の価格が上昇したことや、▽海外のパック旅行も円安の影響で値上がりしたことなどによるものです。
この結果、昨年度1年間の全国の消費者物価指数は、平均で前の年度を2.8%上回り、平成2年度以来の高い伸びとなりました。
ただ、日銀の試算では、去年4月の消費税率の引き上げで全国の消費者物価指数は2%程度、押し上げられるとされ、これを当てはめた場合、増税分を除いた上昇率は3月は0.2%程度、年度では0.8%程度とみられます。
一方、先月の東京都区部での消費者物価指数の速報値は、生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月を0.4%上回り、24か月連続の上昇となっています。
総務省は「原油価格の値動きが落ち着き、今後、消費増税の影響も薄れるため、物価の上昇率はほぼ横ばいで推移するのはないか」と話しています。
関連リンク
景気回復はどこまで ~検証・日本経済~ クローズアップ現代 (4月16日)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150501/k10010066751000.html
ニュース詳細
野菜の卸値 日照不足で今月前半は高値に
5月1日 16時05分

農林水産省は今月の野菜の卸売価格について見通しを発表し、先月上旬の西日本や東日本を中心とした記録的な日照不足の影響で、今月前半は主な野菜のほとんどが平年より高くなる見込みだとしています。
農林水産省は東京都中央卸売市場の情報などを基に、毎月、主な野菜14品目について卸売価格の見通しを発表しています。
それによりますと、大根、白菜、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、レタス、きゅうり、なす、トマト、ピーマン、それにジャガイモの11品目は今月前半の卸売価格が平年を20%以上、上回る見通しだということです。
これは、先月上旬、西日本や東日本を中心とした記録的な日照不足の影響で主な産地で野菜の生育が遅れ、出荷量が落ち込む見通しとなったことが主な要因です。
一方、にんじん、里芋、それにたまねぎの3品目は、生育が順調なため、卸売価格は今月を通して平年並みの水準が続くということです。
農林水産省は日照不足の影響が続くのは今月前半までとみていて、後半は野菜の生育が回復し、卸売価格はすべてで平年並みになると見通しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150501/k10010067111000.html
ニュース詳細
3月の完全失業率 3.4%
5月1日 8時36分

ことし3月の全国の完全失業率は3.4%で、前の月に比べて0.1ポイント下がり、改善しました。
総務省によりますと、3月の就業者数は6319万人で、前の年の同じ月に比べて21万人増えて、4か月連続で増加しました。
一方、完全失業者数は228万人で、前の年の同じ月に比べて18万人減って、58か月連続で減少しました。
この結果、季節による変動要因を除いた全国の完全失業率は3.4%で、前の月に比べて0.1ポイント下がり改善しました。
また、パートや派遣社員、アルバイトなどの非正規労働者は、前の年の同じ月に比べて9万人増えて1973万人でした。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150501/k10010066741000.html
*非正規労働者の割合は4割くらいだが、この人たちの所得が上がらないと、本格的な景気回復は困難と言える。
その事が「遅かったり、出来ない」、となれば、日本経済は人口の多い途上国に追い抜かれて行く事になる。
強欲な経営者らが、労働者に対して、多くの賃金を支払わなければ、日本経済の活力はドンドン落ちて行き、途上国にも抜かれて行く、と言う事になる。
そのようになってしまうと、国内の製造業は今よりもより苦しくなるのでは?と思える。
「従業員に投資する」と言う考え方が必要と言える。
しばらくすれば、自社の需要も高まってくると言う事が言える。
ニュース詳細
大手デパート4社 売り上げ大きく上回る
5月1日 18時06分
大手デパート4社の先月の売り上げは、消費税率引き上げの直後の去年4月に販売が大幅に落ち込んだ反動で、いずれも前の年の同じ月より大きく上回りました。
大手デパート4社のグループ全体の先月の売り上げの速報値は、「大丸松坂屋百貨店」が前の年の同じ月より21.7%増加したのをはじめ、「高島屋」が16.7%、「三越伊勢丹」が15%、「そごう・西武」が12.2%増えました。
これは、消費税率引き上げの直後の去年4月に販売が大幅に落ち込んだ反動で売り上げが伸びたことや、外国人旅行者向けの販売が引き続き好調だったためです。
また、消費増税の影響を差し引いたおととし4月との比較でも売り上げは4社とも上回っており、各社は富裕層を中心にして消費は徐々に回復傾向にあると分析しています。
デパートの担当者は「少し高くても品質のいい商品を買う傾向は幅広い層で見られる。賃上げや夏のボーナスの増額で今後も売り上げの伸びが続くことを期待したい」と話していました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150501/k10010067261000.html
ニュース詳細
新車販売台数 4か月連続で減少
5月1日 15時52分

先月、国内で販売された新車の台数は、乗用車などの販売が増加に転じたものの、軽自動車の販売が増税の影響で大幅に減少したことから、去年の同じ月を7%余り下回って、4か月連続で減少しました。
日本自動車販売協会連合会などによりますと、先月、国内で販売された新車の台数は合わせて31万9482台で、去年の同じ月を7.4%下回り、4か月連続のマイナスとなりました。
このうち、軽自動車を除く乗用車などの販売台数は19万8371台と去年の同じ月を5%上回り、9か月ぶりにプラスに転じました。
一方、軽自動車は12万1111台と22%も下回りました。
軽自動車の販売が大幅に減少したことについて、業界団体は、先月から実施された軽自動車税の増税の影響や消費税の引き上げを前に大量に受注された車の販売が去年の4月も続いていたため、その反動が出たことが主な要因だとしています。
業界団体は「消費増税の影響も依然として続いている印象がある。
軽自動車税の増税の影響がどこまで続くか読み切れず、回復のめどはまだ分からない」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150501/k10010067101000.html
ニュース詳細
新たにがんと診断 98万人と予測
5月1日 11時49分

ことし、国内で新たにがんと診断される患者は去年よりも10万人増え、98万人に上るとする予測を国立がん研究センターが発表しました。
この患者数の予測は、毎年、国立がん研究センターが、がん対策に役立ててもらおうと行っているものです。
それによりますと、ことし1年間に新たにがんと診断される患者は、男性が56万300人、女性が42万1800人の合わせて98万2100人で、高齢化などの影響で、去年の予測と比べおよそ10万人増えるということです。
がんの種類別に見ますと、大腸がんが13万5800人と最も多く、次いで肺がんが13万3500人、胃がんが13万3000人となっていて、去年は3番目に多かった大腸がんがことしは最も多くなっています。
また、男女別に見ますと、男性では、血液検査の普及などで前立腺がんが最も多くなっていて、9万8400人、女性では、乳がんが最も多く、8万9400人となっています。
また、がんで死亡する人の数は男女合わせて37万900人に上ると予測されていて、去年の予測と比べておよそ4000人増えました。
この結果はインターネット上の「がん情報サービス」で公開されていて、国立がん研究センターがん対策情報センターの若尾文彦センター長は「患者の数やどういったがんが増えてきているのか参考にしてもらい、国や都道府県のがん対策に役立ててもらいたい」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150501/k10010066931000.html


















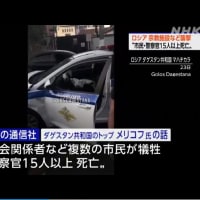






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます