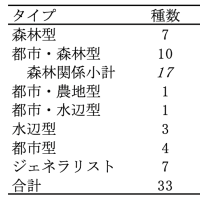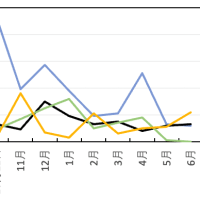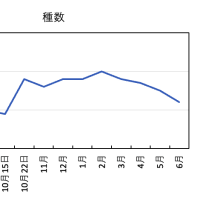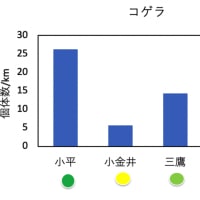7月8日に井の頭コミセンで三鷹市区域の玉川上水整備に関する説明会があったので内容を報告します。
鈴木浩克
管理者側参加者
水道局9名、東京水道(株)2名、三鷹市1名(三鷹市緑と公園課)、
境浄水場場長の富永さんの挨拶があったあと、スライド映写で今年度の整備の説明が始まりました。
昨年までは整備活用計画の中身を説明し「それに添って整備します」というような形でしたが、今年は整備活用計画は説明せず、下記の3点を方針として説明しました。
1:台風や強風で倒れた樹木の除去、枯死している樹木の除去
2:成長により周辺住宅、歩行者、車両に影響を与えている樹木の管理
3:警察や道路管理者からの指示による管理
この3点に関して、現地の写真を映写して説明がありました。これまでと同じですが、家屋との接触、歩行者や車両との接触、標識や信号が見えない箇所など、これらの管理は妥当なものと思います。
そして、管理のお知らせは橋に近いところに掲示板を設置して1か月前に告知するとのこと、対象の樹木には赤テープ(伐採)、青テープ(剪定)を巻き、これも1か月前に巻いて知らせるとのこと。
昨年、市民の方からも「告知をもっと徹底して欲しい」という意見が出ていたので、掲示方法などを改善していただいたようです。
去年までは整備活用計画にある『高木は危険だから除去』『法面を壊すから除去』『眺望の確保のために除去』というのを管理の理由として挙げていましたが、今年はその説明はありませんでした。現在の整備活用計画は、玉川上水を文化財として保存することを主目的にしていて、自然の保存は二の次にされている内容です。ところが過去の新聞記事でもわかるように、文化財としてだけでなく『岸辺の雑木林ともども永久保存』というのが本来の玉川上水の保存目的です。こういった過去の経緯が明らかになってきたことや、三鷹市議会や三鷹市長から要望書が出たことも影響して改善していただいていると感じました。
続いて、法面補強の計画がまた出ました。今回は幸橋新橋ではなく、宮下橋上流右岸の20メートルと東橋長兵衛橋間の130メートル(左岸)、135メートル(右岸)で法面補強工事を行う予定とのこと。
宮下橋上流20メートル・・・高密度ポリエチレン工法(重機不要で人力でできる)
法面平坦部と法肩は良い状態(過去に段々にする工法をしてある)なので、法面中部から法尻にかけて施行する。
法面中部と法尻はかつて玉石が積まれていたのが崩れている。
ポリエチレンでハチの巣状の枠を組んで、中に客土して法面を補強し、その上に植生シート(肥料と在来種の種入り)のものを被せる。
法尻は水による浸食を防止するため擬木杭と擬木板をあてる。
このカバー工法のために3本の樹木を伐採する予定。
東橋長兵衛橋130+135メートル‥‥連続繊維補強工法
この箇所は垂直面が多く、土壌流失が多く、補強が必要。
ポリエステル繊維と砂を混ぜて法面に吹付け、法面と結合させ崩落を防止する。
その後の植生カバーと法尻の擬木は宮下橋の工法と同じ。
要するに井の頭橋~松影橋間でやったのと同じ工法です。しかし、この工事では樹木の伐採は0本でやる予定とのこと。
井の頭橋~松影橋のように、現存する樹木のほとんどを伐採したうえでカバーを掛けることに比較すれば、伐採本数を0本にして計画していることは評価できるものだと思います。しかし、130メートルもの距離の法面が、本当に補強する必要がある状態なのか?は疑問が残ります。
木を切らないとしても石綿のような化学繊維と化学物質の素材を吹き付ければ、多少の草木は生えてきますが、自然環境としてはマイナスになると思います。
続いて昨年出た質問への回答がありました。
1:整備活用計画は当面延長としているが、当面とはどのくらいか?
A:大型台風への対応や法面の補強が必要な箇所があるので整備活用計画は続ける。『当面』はとく期間を定めていない。
2:整備活用計画を見直さないのか?
A:現段階で見直しの段取りは無い。整備をすすめながら検討していく。
3:枯木や倒木が放置されている
A:放置しているつもりはない(でも放置されてるけど)
4:法面の崩落量を実測しているのか?
A:やっていない。しかし法面補強工事をする際には測量し、過去の測量データと比べることで崩落量を把握できる
5:土圧やN値の測定を工事前にやっているのか?やっているなら数値を出せ
A:仮設構築物指針にしたがって測定などやっている
10年計画の「整備活用計画」はもう期限が切れています。そして計画の内容が文化財保存に偏っていること、文化財保存としても科学的にマイナスな内容になっています。この計画を見直さずに「当面続ける」「続けながら検討する」と進めば、文化財の保存も自然の保存も失敗に終わると思います。
計画の見直しは今後も求めていかなければならないと思います。
ここから参加住民からの質問コーナーになりました。
トップで私が質問したのは
私:施行前に測量によって流出量を把握していると説明したが、今回の東橋130メートル区間など、どれくらい流出していたのか?
A:多いところは8年間で1メートル後退していた。
私:私は法面を写真撮影して比較したが、1年経過して流失はほとんど認められなかった。8年間で1メートル後退した箇所は、何か特殊な現象があった箇所だと思う。130メートルの区間が一律1メートル後退しているのか?
A:ほとんど後退していない箇所もある
私:1メートル後退した箇所は130メートルの計画区間の中で何メートルくらいあるのか?
A:それはちょっと把握していない
ということでした。
そのほか市民の皆さんから
●環境局が協議会をネットでやったが、今日環境局が来ていないのはおかしい。
●行政職員は異動があるので話しあいが生かされない
●鈴木都政で清流復活してからは土壌流失していない
●過去に法面補強について住民の詳しい人がアイデアを出すと、検討して実施してくれていた。木製の自然素材とシダを生やすなどで法面を守ろうとしていた。
●上水は人工の構造物だから自然というより適正な管理が必要(里山的な)
●新橋~松影橋のクズの大繁茂はひどい。左岸の竹藪もひどい。
●東橋の崩落箇所は大木のヒノキを伐採した箇所だと思う。いままで大木を伐採するとその周りの崩落が進行していた。何が原因で流失したのか?を正しく把握して欲しい。
●生物のモニタリングなどもして、できる限り小規模に、少しずつやって欲しい。
●大木の根が民地に侵入していると話がある。民地へ伸びている根を調査しているのか?
●私が子供のころはこんなに木々は生い茂っていなかった
●投げ入れられたごみをなぜ放置する?住民も手伝うからごみ掃除しないか?(会場拍手)
などの意見がありました。
市民意見の中でも、上水として運用されていたころを知っているご高齢の方は、ひたすら昔の姿が正しいと感じているようです。一方、近年に玉川上水近辺に家を建てた方は自然環境の良さに魅力を感じて家を建てているので、環境を大事にしたいと思っている方が多いです。市民意見も様々です。
もっと樹木を切って手入れをして欲しい方々からは『行政のみなさんは専門家でプロなんだから、いちいち反対しないでプロに任せればいい』という発言もあり、それには『まったくプロじゃない、ひどい管理だから意見してる』『予算があるから過剰に切っているだけ』というような住民間での不規則発言の応酬も多少ありました。
最後に私が『東橋でカバーするのは何メートルなのかだけ、最後に教えてください』と質問すると
A:まだ具体的にはこれから検討なので言えない
というこということでした。
化学繊維や化学物質を混ぜたものを吹き付けてカバーするのが1メートルなのか?、100メートルなのか?で大きな違いです。私はもし法面の流失が著しい箇所があれば、その原因を特定し、適切な補強工事は必要だと思います。しかし、流失していないならカバーを掛ける必要はありません。私が「カバーする距離を言えないようでは、工事を説明したとは言えない』と発言したら、会場の方々が拍手してくれました。
三鷹市長が要望で『法面補強や樹木などの伐採等を実施するにあたっては、時期、方法などについて、地域の住民や自然保護団体から事前に意見を聴く場を設け、また、十分な周知や説明をするなど、丁寧な対応をお願いします。』と要望しているのだから、今後も「カバーする必要がなるのか?無いのか?」市民が納得できるまで説明して欲しいと思います。
井の頭自然の会
鈴木浩克