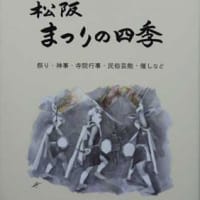(クイーン松阪の表彰式がありました)
江戸時代中・後期の国学者・本居宣長の功績を顕彰する「宣長まつり」が平成30年4月1日に松阪市殿町の松坂城跡を中心として開催されました。この祭りは松阪市観光協会が主催して毎年この時期に行われるもので、この日城跡では本居宣長に関するいろいろなイベントが行われ、松阪市観光協会の会員による出店もあり、満開の桜の下、多くの市民で賑わいました。
本居宣長は享保15年(1730)伊勢国松阪本町の小津定利の長男として生まれました。小津家は江戸に店をもつ木綿商でありましが、宣長が家督を継ぐ頃には店は窮地に陥り、ついには破産してしまいました。
宝暦2年(1752)23歳の宣長は、母の志を受け、医学を修めるために京都に入り、儒学者・堀景山より漢籍を、針灸の大家・堀元厚に医書を、高名な小児科医・武川幸順に医術を学びました。28歳で帰郷して、町医を開業して生計を立てながら『源氏物語』などの日本の古典の研究を続けました。
宝暦13年(1763)松阪日野町の旅館「新上屋」に宿泊中の賀茂真淵(かものまぶち)に対面し、古事記研究の志を告げました。これが「松阪の一夜」として知られるもので、その年の末に真淵の門人となりまた。
翌明和元年(1764)宣長35歳のとき、西暦712年に書かれた日本最古の歴史書『古事記』の研究に着手し、35年の歳月を費やして大著『古事記伝』全44冊を完成させました。享和元年(1801)72歳で生涯を閉じた宣長は、遺言により山室山の奥墓に葬られました。
この日会場となった松坂城跡の音楽堂では式典のあと、クイーン松阪の表彰式がありました。クイーン松阪は中日新聞と中日写真協会松阪支部が主催して行われるもので、今年の新しい3人のクイーンに表彰状や記念品が贈られました。この日桜松閣では「宣長茶会」や「子ども茶会」があり、本居宣長記念館では「のりなが紙芝居」がありました。また松阪ガイドボランティア友の会の人たちによる「のりながお城ウォーク」があり、城跡内の説明がありました。
この日は本居宣長記念館を始め、歴史民俗資料館、松阪商人の館、宣長書斎「鈴屋」などが無料開放されました。
この祭りは私のブログ「松阪市内の祭り100選」に掲載してあります。
宣長まつりのあった4月1日から新しい年度に入りました。本居宣長記念館の吉田悦之館長が3月を末で定年退職の年齢を迎えていましたが、引き続き館長をしてもらうことになりました。「吉田さん以外に館長はいない」「ずっと活躍してもらいたい」などと大変評価が高く、公益財団法人鈴屋遺跡保存会は続投を決めました。吉田館長は宣長研究の第一人者で説明を聞いても大変わかりやすく、ユーモアを交えて話されます。吉田館長の続投を私も大変うれしく思います。なお余談ですが、館長は笹川町にお住まいで、朝のウォーキングでお会いさせてもらうこともあります。
江戸時代中・後期の国学者・本居宣長の功績を顕彰する「宣長まつり」が平成30年4月1日に松阪市殿町の松坂城跡を中心として開催されました。この祭りは松阪市観光協会が主催して毎年この時期に行われるもので、この日城跡では本居宣長に関するいろいろなイベントが行われ、松阪市観光協会の会員による出店もあり、満開の桜の下、多くの市民で賑わいました。
本居宣長は享保15年(1730)伊勢国松阪本町の小津定利の長男として生まれました。小津家は江戸に店をもつ木綿商でありましが、宣長が家督を継ぐ頃には店は窮地に陥り、ついには破産してしまいました。
宝暦2年(1752)23歳の宣長は、母の志を受け、医学を修めるために京都に入り、儒学者・堀景山より漢籍を、針灸の大家・堀元厚に医書を、高名な小児科医・武川幸順に医術を学びました。28歳で帰郷して、町医を開業して生計を立てながら『源氏物語』などの日本の古典の研究を続けました。
宝暦13年(1763)松阪日野町の旅館「新上屋」に宿泊中の賀茂真淵(かものまぶち)に対面し、古事記研究の志を告げました。これが「松阪の一夜」として知られるもので、その年の末に真淵の門人となりまた。
翌明和元年(1764)宣長35歳のとき、西暦712年に書かれた日本最古の歴史書『古事記』の研究に着手し、35年の歳月を費やして大著『古事記伝』全44冊を完成させました。享和元年(1801)72歳で生涯を閉じた宣長は、遺言により山室山の奥墓に葬られました。
この日会場となった松坂城跡の音楽堂では式典のあと、クイーン松阪の表彰式がありました。クイーン松阪は中日新聞と中日写真協会松阪支部が主催して行われるもので、今年の新しい3人のクイーンに表彰状や記念品が贈られました。この日桜松閣では「宣長茶会」や「子ども茶会」があり、本居宣長記念館では「のりなが紙芝居」がありました。また松阪ガイドボランティア友の会の人たちによる「のりながお城ウォーク」があり、城跡内の説明がありました。
この日は本居宣長記念館を始め、歴史民俗資料館、松阪商人の館、宣長書斎「鈴屋」などが無料開放されました。
この祭りは私のブログ「松阪市内の祭り100選」に掲載してあります。
宣長まつりのあった4月1日から新しい年度に入りました。本居宣長記念館の吉田悦之館長が3月を末で定年退職の年齢を迎えていましたが、引き続き館長をしてもらうことになりました。「吉田さん以外に館長はいない」「ずっと活躍してもらいたい」などと大変評価が高く、公益財団法人鈴屋遺跡保存会は続投を決めました。吉田館長は宣長研究の第一人者で説明を聞いても大変わかりやすく、ユーモアを交えて話されます。吉田館長の続投を私も大変うれしく思います。なお余談ですが、館長は笹川町にお住まいで、朝のウォーキングでお会いさせてもらうこともあります。