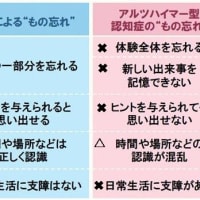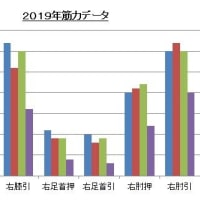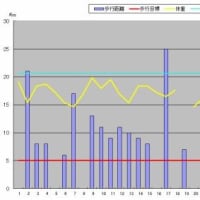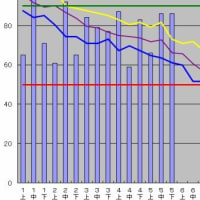1番 ~ 9番 地蔵 歩行月日2013/09/10
歩行時間:6時間30分 休憩時間:2時間00分 延時間:9時間00分
出発時間:8時00分 到着時間:17時00分
歩 数: 歩 GPS距離:31.1km
行程表
島田駅 0:40> 1番 0:45> 2番 0:20> 3番 0:30> 4番 0:35> 5番 0:20> 6番 0:05> 7番
2:00> 8番 0:40> 9番 0:35> 焼津駅
1番 吉三地蔵(八百屋お七)
地蔵巡りは百地蔵の中で一番西にある大井川川越遺跡の吉三地蔵から始めた。
島田駅から川越遺跡までは旧東海道を歩く事にしたが、途中にある大井神社や大井川の時の鐘で知られている
大善寺はパスして川越遺跡に直行。


大井川川越遺跡 大井川川越遺跡3番宿
大井川川越遺跡は何度も歩いているので、通りから写真を写すだけで通過する。代わりに今まで余り興味を覚え
なかった「朝顔の松」の碑の建つ広場に行ってみた。
広場には石碑の他に「あさがほ堂」「朝顔目明観音・川除地蔵」と表示のあるお堂が二棟と歌碑や案内板が建っている。
朝顔の松など今まで聞いた事はなく案内板を読むと
「安芸の国の娘、深雪は、京で宮仕使いをしているとき宮城阿曽次郎と恋仲になった。その後、国元に帰った深雪は、
親から駒沢次郎左衛門という武士を婚約者に決めたと聞かされた。深雪はその人が駒沢家を継いだ阿曽次郎であった
とは知らず家出をしてしまった。深雪は朝顔という名の門付けとなり、阿曽次郎を探し諸国をさ迷ううちに目が見えなく
なってしまった。
ある時、島田宿で門付けををしていると座敷から声がかかった。その声の主こそ阿曽次郎だったが、朝顔は目が
見えないので判らない。また、阿曽次郎も主命をおびた急ぎ旅のため、名乗りあえずに別れてしまった。
あとで阿曽次郎と知った朝顔は、急いで追いかけて大井川まで来ると生憎の川止め。半狂乱となった朝顔は激流に
飛び込もうとすると、。宿屋の主人に助けられ、その犠牲的行為により目が見えるようになった。
その時、初めて朝顔の目に映ったのが、大きな一本の松でした。
この物語は江戸後期に浄瑠璃として上演されて大評判となり「生写朝顔話」は今でも上演されているという」
この説明では、話が分かったようで分からない。どうも釈然としない。
先ず何故朝顔という門付けになったのか? 急用で名乗りあえない人が門付けを呼ぶ? 宿の主人の犠牲的行為で
他人の目が治る? と思いませんか。そこで、「生写朝顔話」を検索すると納得できた。
阿曽次郎と深雪が初めて会った時、阿曽次郎が扇に「朝顔の歌」を書いて深雪に渡していたのです。これなら門付けに
なって朝顔と名乗った理由が分かりますよね。
次の門付けを呼ぶ余裕があるのに名乗りをあげなかった処は大分省略されていた。
島田の宿で阿曽次郎は衝立に書かれた「朝顔の歌」を見て宿の主人から、流浪しているうちに目を泣き潰してしまった
哀れな門付けの話を聞く。話を聞いた阿曽次郎は、その門付けが深雪ではないかと思い朝顔を呼んでもらう。
朝顔の話を聞き、深雪だと確信した阿曽次郎は、名乗りたかったが近くに悪人がいて名乗れない。
あとでもう一度朝顔に会おうとしたが、朝顔は出かけてしまったあとだった。
出発の時刻が近づいてきたので阿曽次郎は、宿の主人にお金と扇と薬を朝顔に渡して欲しいと依頼する。
その薬は甲子歳生まれの男性の生き血で飲むと、どんな眼病でも治るという薬だそうです。(ここで最終話の伏線が)
朝顔の眼病の治った理由は、宿の主人が犠牲的行為で朝顔の川越しを止めたからではなく、甲子歳生まれだった
主人が自害して、その生き血で深雪の目を治そうとしたのでした。自害こそが犠牲的行為だったのです。
尤も見も知らずの門付けのために自害したのではなく、宿の主人は深雪の父親にかって恩を受けていたからでした。
今の案内板でも随分長いので、これ以上浄瑠璃話を詳細に説明する余裕はなかったのでしょう。
しかしこの場所は朝顔の松とかあさがほ堂と朝顔を売りにしている。それなら深雪が門付けの名前を朝顔にした理由を
もっと説明する必要があったのではないでしょうか。
哀話が伝わる朝顔の松公園だが、何でもない広場で、あさがほ堂はトイレのようにも感じた。勿体ないな。


朝顔の松の碑34 朝顔目明観音・川除け地蔵堂37
朝顔の松公園の地図
道を少し戻り川越遺跡の中に立つ「関川庵 八百屋七の恋人吉三郎の墓」の杭の横の路地に入る。
「八百屋お七とは天和の大火のとき、避難した寺の小姓吉三郎と恋仲となったが。帰宅してから恋情は募り逢いたい
一心で放火をする。しかしお七は放火犯で捕らえられ、鈴ヶ森刑場で火刑に処された」
お七が処刑された鈴ヶ森刑場は、去年の東海道街道歩きで寄っていたので、その恋人の墓なら縁がある。
しかもその恋人が吉三地蔵となって百地蔵の一つになっているので更に興味も湧く。
関川庵は名前の通り庵のような感じで小さな建物だった。だが本堂の隣の庫裏には人が住んでいる気配もあり
無住ではなさそうだ。狭い境内にお地蔵様を探して歩いたがそれらしき物は見つからない。
印刷してきた百地蔵の一覧表を見ると設置場所は「本堂正面」になっている。これでは諦めるしかなさそうだ。
代わりに「吉三郎の墓」なる物を写真に写した。


関川庵 吉三郎の墓
関川庵の地図
駿河百地蔵を提唱した顕光院のHPから吉三郎の話を引用させてもらいます。
「関川庵は大井川の川越えを前に亡くなった旅人も葬られた。また、関川庵の名前は大井川の別名、「関所川」に
由来するという。
関川庵の伝承によれば、吉三郎はお七の菩提を弔うために、江戸から西国に向けて旅立った。しかし、吉三郎は
大井川を前にして亡くなり、この地に葬られた。
さらに幾年か後に、廓應という名の僧が江戸からやってきた。この僧はお七と吉三郎の息子だと言い、終生、関川庵で
二人の菩提を弔ったという。
同庵で祀られている吉三地蔵は、吉三郎が江戸から背負ってきたものとも、廓應がこの地で刻んだものともいわれて
いる。尊像の裏側には、「經蓮社願譽夢覺信士大徳、寶永七年正月十九日、妙譽貞經信女靈位、元祿五年八月十五日、
願主廓應」と記されている」
ヤー面白いですねー。八百屋お七と恋人吉三郎の間に子供がいたなんて初めて聞く話だ。興味を覚え更に検索すると
「天和3年(1683)3月29日、江戸に大火をもたらした14歳の八百屋お七は江戸市中を引き回しの上、鈴が森の処刑場で
火焙りの刑に刑に処せられました。お七は2才上の寺小姓生田庄之助に激しい恋心を持ち、火を点ければ逢えるだろうと
思ったのです。庄之助はお七の処刑後、僧となって、名を「西運」と改め諸国を行脚、後に大円寺の下隣りの明王院に
入って、お七の菩提を弔うために往復十里、およそ40kmの道のりを、夜から明け方に掛けて浅草観音まで鉦を叩き
念仏を唱え歩き続けました。
大円寺の阿弥陀堂にお七地蔵が祀られています。磔にされた時、お七は役人に向かってこういったそうです。
「ありがとうございました」と。ふと首を傾げたあどけないお顔のお七地蔵は、隔夜日参り一万日の行を27年5ヶ月
かけて満行した日に、お七が夢枕に立って成仏したことを告げた姿を西運が仏師に彫らせたものです。」
更にウィキペディアを引用すると
「お七の家は天和2(1683)年12月28日の天和の大火で焼け出され、避難先の寺で寺小姓の生田庄之介と恋仲になる。
やがて店が再建され、寺を引き払ったお七の庄之介への想いは募るばかり。そこでもう一度自宅が燃えれば、また
庄之介がいる寺で暮らすことができると考え、庄之介に会いたい一心で自宅に放火した。火はすぐに消し止められ
小火にとどまったが、お七は放火の罪で天和3年3月28日捕縛されて鈴ヶ森刑場で火あぶりに処された。」
どうですか関川庵の伝承とは随分違いますよね。だいたいお七が焼け出された火事は天和2年12月の事。そこで
吉三郎と出会い恋仲となり深い関係になったとしても、お七が処刑された天和3年3月では十月十日どころか4か月
にしかならない。これでは超未熟児で、当時はおろか現代でも助かる可能性は低い。
これらの事を考えれば、関川庵に居ついた僧は二人の子供ではない事は確かだ。
更に地蔵像の後ろに書かれた年号は、お七の死んだ年と思われるが元禄5年(1693)では、お七の処刑されてから
10年も過ぎている。そうなるとこの地蔵尊もお七や吉三郎には関係なさそうだ。
また、吉三郎と生田庄之介の名前の違いは、この事件の後、多くの物語が作られ、その物語での名前が吉三郎とか
吉三だったので何通りもの名前があるらしい。
それにしても寺の僧が二人の子供だったら、父親の像の名前を本名でなく物語の名前を使うなんて考えられない。
しかしこういう事があると歩いていても楽しいし、ブログを書く興味も湧いてくる。


角度のある舟型の石仏 石仏拡大
長くなってしまったが関川庵ではもう一つ気になった物があった。
それは石仏の舟型光背石というのか、石仏の形が舟型なのは一般的なのだが、その水平面が平らではなく
像の中心から角度をもっていることだ。この角度を持った石仏は、ここ志太地方ではよく見かけるが他の地区では
水平な物が多いように感じる。
今回の遍路は志太地方だけでなく、駿河一国全体に広がっているので比較してみよう。
歩行時間:6時間30分 休憩時間:2時間00分 延時間:9時間00分
出発時間:8時00分 到着時間:17時00分
歩 数: 歩 GPS距離:31.1km
行程表
島田駅 0:40> 1番 0:45> 2番 0:20> 3番 0:30> 4番 0:35> 5番 0:20> 6番 0:05> 7番
2:00> 8番 0:40> 9番 0:35> 焼津駅
1番 吉三地蔵(八百屋お七)
地蔵巡りは百地蔵の中で一番西にある大井川川越遺跡の吉三地蔵から始めた。
島田駅から川越遺跡までは旧東海道を歩く事にしたが、途中にある大井神社や大井川の時の鐘で知られている
大善寺はパスして川越遺跡に直行。


大井川川越遺跡 大井川川越遺跡3番宿
大井川川越遺跡は何度も歩いているので、通りから写真を写すだけで通過する。代わりに今まで余り興味を覚え
なかった「朝顔の松」の碑の建つ広場に行ってみた。
広場には石碑の他に「あさがほ堂」「朝顔目明観音・川除地蔵」と表示のあるお堂が二棟と歌碑や案内板が建っている。
朝顔の松など今まで聞いた事はなく案内板を読むと
「安芸の国の娘、深雪は、京で宮仕使いをしているとき宮城阿曽次郎と恋仲になった。その後、国元に帰った深雪は、
親から駒沢次郎左衛門という武士を婚約者に決めたと聞かされた。深雪はその人が駒沢家を継いだ阿曽次郎であった
とは知らず家出をしてしまった。深雪は朝顔という名の門付けとなり、阿曽次郎を探し諸国をさ迷ううちに目が見えなく
なってしまった。
ある時、島田宿で門付けををしていると座敷から声がかかった。その声の主こそ阿曽次郎だったが、朝顔は目が
見えないので判らない。また、阿曽次郎も主命をおびた急ぎ旅のため、名乗りあえずに別れてしまった。
あとで阿曽次郎と知った朝顔は、急いで追いかけて大井川まで来ると生憎の川止め。半狂乱となった朝顔は激流に
飛び込もうとすると、。宿屋の主人に助けられ、その犠牲的行為により目が見えるようになった。
その時、初めて朝顔の目に映ったのが、大きな一本の松でした。
この物語は江戸後期に浄瑠璃として上演されて大評判となり「生写朝顔話」は今でも上演されているという」
この説明では、話が分かったようで分からない。どうも釈然としない。
先ず何故朝顔という門付けになったのか? 急用で名乗りあえない人が門付けを呼ぶ? 宿の主人の犠牲的行為で
他人の目が治る? と思いませんか。そこで、「生写朝顔話」を検索すると納得できた。
阿曽次郎と深雪が初めて会った時、阿曽次郎が扇に「朝顔の歌」を書いて深雪に渡していたのです。これなら門付けに
なって朝顔と名乗った理由が分かりますよね。
次の門付けを呼ぶ余裕があるのに名乗りをあげなかった処は大分省略されていた。
島田の宿で阿曽次郎は衝立に書かれた「朝顔の歌」を見て宿の主人から、流浪しているうちに目を泣き潰してしまった
哀れな門付けの話を聞く。話を聞いた阿曽次郎は、その門付けが深雪ではないかと思い朝顔を呼んでもらう。
朝顔の話を聞き、深雪だと確信した阿曽次郎は、名乗りたかったが近くに悪人がいて名乗れない。
あとでもう一度朝顔に会おうとしたが、朝顔は出かけてしまったあとだった。
出発の時刻が近づいてきたので阿曽次郎は、宿の主人にお金と扇と薬を朝顔に渡して欲しいと依頼する。
その薬は甲子歳生まれの男性の生き血で飲むと、どんな眼病でも治るという薬だそうです。(ここで最終話の伏線が)
朝顔の眼病の治った理由は、宿の主人が犠牲的行為で朝顔の川越しを止めたからではなく、甲子歳生まれだった
主人が自害して、その生き血で深雪の目を治そうとしたのでした。自害こそが犠牲的行為だったのです。
尤も見も知らずの門付けのために自害したのではなく、宿の主人は深雪の父親にかって恩を受けていたからでした。
今の案内板でも随分長いので、これ以上浄瑠璃話を詳細に説明する余裕はなかったのでしょう。
しかしこの場所は朝顔の松とかあさがほ堂と朝顔を売りにしている。それなら深雪が門付けの名前を朝顔にした理由を
もっと説明する必要があったのではないでしょうか。
哀話が伝わる朝顔の松公園だが、何でもない広場で、あさがほ堂はトイレのようにも感じた。勿体ないな。


朝顔の松の碑34 朝顔目明観音・川除け地蔵堂37
朝顔の松公園の地図
道を少し戻り川越遺跡の中に立つ「関川庵 八百屋七の恋人吉三郎の墓」の杭の横の路地に入る。
「八百屋お七とは天和の大火のとき、避難した寺の小姓吉三郎と恋仲となったが。帰宅してから恋情は募り逢いたい
一心で放火をする。しかしお七は放火犯で捕らえられ、鈴ヶ森刑場で火刑に処された」
お七が処刑された鈴ヶ森刑場は、去年の東海道街道歩きで寄っていたので、その恋人の墓なら縁がある。
しかもその恋人が吉三地蔵となって百地蔵の一つになっているので更に興味も湧く。
関川庵は名前の通り庵のような感じで小さな建物だった。だが本堂の隣の庫裏には人が住んでいる気配もあり
無住ではなさそうだ。狭い境内にお地蔵様を探して歩いたがそれらしき物は見つからない。
印刷してきた百地蔵の一覧表を見ると設置場所は「本堂正面」になっている。これでは諦めるしかなさそうだ。
代わりに「吉三郎の墓」なる物を写真に写した。


関川庵 吉三郎の墓
関川庵の地図
駿河百地蔵を提唱した顕光院のHPから吉三郎の話を引用させてもらいます。
「関川庵は大井川の川越えを前に亡くなった旅人も葬られた。また、関川庵の名前は大井川の別名、「関所川」に
由来するという。
関川庵の伝承によれば、吉三郎はお七の菩提を弔うために、江戸から西国に向けて旅立った。しかし、吉三郎は
大井川を前にして亡くなり、この地に葬られた。
さらに幾年か後に、廓應という名の僧が江戸からやってきた。この僧はお七と吉三郎の息子だと言い、終生、関川庵で
二人の菩提を弔ったという。
同庵で祀られている吉三地蔵は、吉三郎が江戸から背負ってきたものとも、廓應がこの地で刻んだものともいわれて
いる。尊像の裏側には、「經蓮社願譽夢覺信士大徳、寶永七年正月十九日、妙譽貞經信女靈位、元祿五年八月十五日、
願主廓應」と記されている」
ヤー面白いですねー。八百屋お七と恋人吉三郎の間に子供がいたなんて初めて聞く話だ。興味を覚え更に検索すると
「天和3年(1683)3月29日、江戸に大火をもたらした14歳の八百屋お七は江戸市中を引き回しの上、鈴が森の処刑場で
火焙りの刑に刑に処せられました。お七は2才上の寺小姓生田庄之助に激しい恋心を持ち、火を点ければ逢えるだろうと
思ったのです。庄之助はお七の処刑後、僧となって、名を「西運」と改め諸国を行脚、後に大円寺の下隣りの明王院に
入って、お七の菩提を弔うために往復十里、およそ40kmの道のりを、夜から明け方に掛けて浅草観音まで鉦を叩き
念仏を唱え歩き続けました。
大円寺の阿弥陀堂にお七地蔵が祀られています。磔にされた時、お七は役人に向かってこういったそうです。
「ありがとうございました」と。ふと首を傾げたあどけないお顔のお七地蔵は、隔夜日参り一万日の行を27年5ヶ月
かけて満行した日に、お七が夢枕に立って成仏したことを告げた姿を西運が仏師に彫らせたものです。」
更にウィキペディアを引用すると
「お七の家は天和2(1683)年12月28日の天和の大火で焼け出され、避難先の寺で寺小姓の生田庄之介と恋仲になる。
やがて店が再建され、寺を引き払ったお七の庄之介への想いは募るばかり。そこでもう一度自宅が燃えれば、また
庄之介がいる寺で暮らすことができると考え、庄之介に会いたい一心で自宅に放火した。火はすぐに消し止められ
小火にとどまったが、お七は放火の罪で天和3年3月28日捕縛されて鈴ヶ森刑場で火あぶりに処された。」
どうですか関川庵の伝承とは随分違いますよね。だいたいお七が焼け出された火事は天和2年12月の事。そこで
吉三郎と出会い恋仲となり深い関係になったとしても、お七が処刑された天和3年3月では十月十日どころか4か月
にしかならない。これでは超未熟児で、当時はおろか現代でも助かる可能性は低い。
これらの事を考えれば、関川庵に居ついた僧は二人の子供ではない事は確かだ。
更に地蔵像の後ろに書かれた年号は、お七の死んだ年と思われるが元禄5年(1693)では、お七の処刑されてから
10年も過ぎている。そうなるとこの地蔵尊もお七や吉三郎には関係なさそうだ。
また、吉三郎と生田庄之介の名前の違いは、この事件の後、多くの物語が作られ、その物語での名前が吉三郎とか
吉三だったので何通りもの名前があるらしい。
それにしても寺の僧が二人の子供だったら、父親の像の名前を本名でなく物語の名前を使うなんて考えられない。
しかしこういう事があると歩いていても楽しいし、ブログを書く興味も湧いてくる。


角度のある舟型の石仏 石仏拡大
長くなってしまったが関川庵ではもう一つ気になった物があった。
それは石仏の舟型光背石というのか、石仏の形が舟型なのは一般的なのだが、その水平面が平らではなく
像の中心から角度をもっていることだ。この角度を持った石仏は、ここ志太地方ではよく見かけるが他の地区では
水平な物が多いように感じる。
今回の遍路は志太地方だけでなく、駿河一国全体に広がっているので比較してみよう。