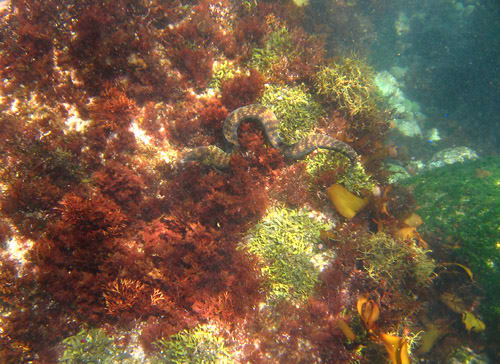酒田からは陸羽西線、陸羽東線と乗り継いで、鳴子温泉へ。
陸羽東線のほうは、山間部を通る路線で、鳴子峡の写真が有名なのだが、一瞬だったで、撮影できなかった。
ところで、ここに掲げた写真は、鳴子温泉の路地で撮影したもの。
僕は愉しんでいると写真を撮ることを忘れていることが多くて、鳴子温泉では殆ど写真を撮らなかった。撮ったものといえば、つまりこんな写真。ここまで来て、一体何を撮影しているのだろう。
この鳴子温泉には湯めぐりチケットというものもあるのだが、なにせ時間的にはそれほど余裕もなかったため、共同湯に入ることにした。鳴子には二つの共同湯があって、一つは早稲田の学生が発見したという「早稲田桟敷湯」で、もう一つが鳴子最古の湯で、1000年の歴史があるとも言われている「滝の湯」。僕たちは「滝の湯」の方に入った。大人が150円という驚きの値段。勿論建物は最近のものだが、風情は残っている。強烈な硫黄の匂いで、芯まで温まった。

ところで鳴子は、画家谷内六郎ともゆかりの深い温泉。
この寂れているというか、鄙びているというか、その雰囲気が彼に触れたのだろうか。
最初この温泉地に着いたときは、温泉地としての名前が有名なだけに、その鄙び方に驚くほどだったのだが、風呂を上がって、だれもいない路地を歩き、道端で休んで空を見ているうちに、次第に肌にしっくりと馴染むような気がしてきた。今、こうして書いていても、何となく懐かしくなってくる。