
先日『書き下ろし歌謡曲』(岩波新書)という100篇の歌詞を、注文を受けることではなくしかもわずか20日間で書いたという本を読んでいたら、その奥書に『愛すべき名歌たち』も同じ岩波新書に宣伝が載っていてつい買いました。オリジナルは1997年から1999年まで朝日新聞に連載されました。
前者が100篇の書き下ろしなら、後者は阿久悠という一人の作詞家が生きてきた時代の中で、その周りで聴いていた歌や自作した名歌100篇(自分で名歌と言うのも憚られたと想いますが)の解説やエピソードを書いたものです。2冊が姉妹編のような企画で面白く、あるいは後者も出版社の企画というよりも、著者自身が書いて置きたかった自分史のように想われます。阿久悠さんはよく「歌詞とは時代の飢餓感を表現するものだ」と書かれています。自分史を借りて過去・現在そして未来という時代の、飢餓感の変遷や予測を書こうとしたものでしょうか。
僕自身の歌の体験史とも重なる部分が多いので、共感できる文章ばかりのような気もしますし、途中から著者自身が作詞家としてクリエイターの立場になりますから、その名歌達の受け手の僕らとはまったく違う次元の感覚も表現されています。
『湖畔の宿』から『川の流れのように』まで採り上げられた殆どの曲は知っていますが、特に昔の歌は生まれる前のものにもかかわらず憶えています。それだけ時もゆっくり流れ歌の生命も長かった時代だったということでしょうか。あの歌の時には僕がどこで誰と何をしていたとか、色々と自分の想い出もも振り返らせて貰える懐かしい本でもあります。
 | 愛すべき名歌たち (岩波新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 岩波書店 |
☆ 東日本大震災・津波復興支援チャリティーソング にご協力お願いします!











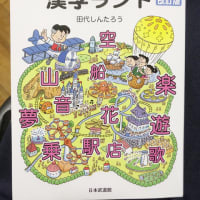



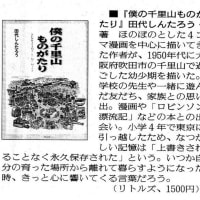


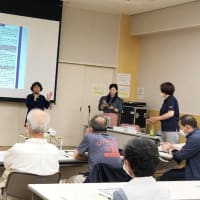

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます