
小笠原諸島にある島のひとつ、硫黄島。日本から約1300キロ沖にある。水もなく、島全体を硫黄が覆い、ガスが噴出しているが、日本の最後の砦、本土防衛のためのどうしても死守しなければならない。そこに1000人ほどの住民がいたということを知ってまず驚いた。

ここを本土防衛のための砦とするために栗林忠道中将が着任したのが1944年の6月。当時の陸軍の軍人としては珍しく親米派で、非常に合理的な考えを持っていたという。柔軟で兵を大事にする。こういう人間がもっと陸軍にいたら、日本の戦い方も随分と違っていたのではないかと想像するが、それは言ってはならない。陸軍の軍人はあくまでも自分の身体が大きな武器で、上官の命令をまっすぐ聞き、ためらわずに突撃できる兵隊でなければ意味がない。
当然ながら、ここ硫黄島でも今までの太平洋戦で行ってきた水際戦を敢行しようとしたが、それを却下。島の地下にトンネルを作り、トンネルで往来を自由にし、持久戦に持ちこたえようという戦略をとった。これに対し、陸軍・海軍双方から突き上げを食らう。そんな作戦はありえない。上陸した兵隊に捨て身で攻撃し、とにかく死守する。それが今までの戦いの常套手段であり、そして敗れてきた。
砂場での塹壕掘りもやめさせ、体罰を禁止。万歳攻撃を禁止し、玉砕は許さない。命を守り、一日でも長く戦いを続けることこそが一番の価値と兵隊たちに教える。『生きて虜囚の辱めを受けず』を叩き込まれてきた軍人には受け入れがたい作戦であったが、それでも自らの信じる道をつき進んでいく。そして引くことも厭わない。

島での兵たちが描かれる。腹を壊し、戦う前に疫病で死んでいった兵隊。3万の兵がいれば3万人分の糞尿が出る。ご飯を食わないといけない。祖国に家族を残してきた。まだ自分の子供の顔も見ていない。何を好き好んで見たこともないアメリカ人と戦わなければならないのか・・・。一市民の代表で、普通の人間代表が二宮演ずる西郷に思えた。
映画全体のできとして見たならば、『父親達の星条旗』に軍配が上がる。初めから題材があって、明確なビジョンの元に作られ、映画全体のバランスが取れている。その映画を作るためにさまざまなリサーチをした結果、日本側からの視点も描かなければならない、として作られた本作は、映画としての波が低かったような気がする。すべてを公平な、俯瞰して見る立場として、あまねく描く、もれなく見せる、とことん見せると言う使命感が強すぎた。それが悪いのではなく、そこまでしてくれなくても、という脱帽の思いだ。
命を大事にするというごくごく当たり前の、生きるものの根っこが覆されるのが戦争だ。アメリカ軍はとにかく兵の命を大事にしてきた、という常識も鵜呑みに出来ないことも知った。そこで面と向かって戦いあう双方の兵士には家族がいて、愛するものがいて、一人で生きてきたものなどいない。そして虫けらのように死んでいった。

戦争に英雄などいない。栗林中将は確かに素晴らしい指揮官だった。なるべくなら戦争を忌避し、アメリカと戦うなどという無謀なことをしたくはなかった。しかし、避けることも逃げることもできなかった。そしてそのことを十分認識して戦った。彼ですら英雄ではない。
2作を見て、クリント・イーストウッドという人間の徹底振りとバランスの卓越さとゆるぎない姿勢を感じた。そして20年近く歴史を教えてきて、戦争の経過で硫黄島にほとんど目を向けてこなかったことを痛感した。南洋諸島の悲惨な戦いにはさまざまな資料を探し、ドキュメンタリーを見、日本軍の愚かさをあざってきた。なぜ硫黄島での戦いがクローズアップされてこなかったのを探るのがこれからの私の課題になりそうだ。
一点だけ。戦争に行く前の二宮君の着物が立派過ぎた。いい紬着てたなあ。伊原剛志、おいしかった。

『硫黄島からの手紙』
監督 クリント・イーストウッド
出演 渡辺謙 二宮和也 伊原剛志 加瀬亮 裕木奈江 中村獅童

ここを本土防衛のための砦とするために栗林忠道中将が着任したのが1944年の6月。当時の陸軍の軍人としては珍しく親米派で、非常に合理的な考えを持っていたという。柔軟で兵を大事にする。こういう人間がもっと陸軍にいたら、日本の戦い方も随分と違っていたのではないかと想像するが、それは言ってはならない。陸軍の軍人はあくまでも自分の身体が大きな武器で、上官の命令をまっすぐ聞き、ためらわずに突撃できる兵隊でなければ意味がない。
当然ながら、ここ硫黄島でも今までの太平洋戦で行ってきた水際戦を敢行しようとしたが、それを却下。島の地下にトンネルを作り、トンネルで往来を自由にし、持久戦に持ちこたえようという戦略をとった。これに対し、陸軍・海軍双方から突き上げを食らう。そんな作戦はありえない。上陸した兵隊に捨て身で攻撃し、とにかく死守する。それが今までの戦いの常套手段であり、そして敗れてきた。
砂場での塹壕掘りもやめさせ、体罰を禁止。万歳攻撃を禁止し、玉砕は許さない。命を守り、一日でも長く戦いを続けることこそが一番の価値と兵隊たちに教える。『生きて虜囚の辱めを受けず』を叩き込まれてきた軍人には受け入れがたい作戦であったが、それでも自らの信じる道をつき進んでいく。そして引くことも厭わない。

島での兵たちが描かれる。腹を壊し、戦う前に疫病で死んでいった兵隊。3万の兵がいれば3万人分の糞尿が出る。ご飯を食わないといけない。祖国に家族を残してきた。まだ自分の子供の顔も見ていない。何を好き好んで見たこともないアメリカ人と戦わなければならないのか・・・。一市民の代表で、普通の人間代表が二宮演ずる西郷に思えた。
映画全体のできとして見たならば、『父親達の星条旗』に軍配が上がる。初めから題材があって、明確なビジョンの元に作られ、映画全体のバランスが取れている。その映画を作るためにさまざまなリサーチをした結果、日本側からの視点も描かなければならない、として作られた本作は、映画としての波が低かったような気がする。すべてを公平な、俯瞰して見る立場として、あまねく描く、もれなく見せる、とことん見せると言う使命感が強すぎた。それが悪いのではなく、そこまでしてくれなくても、という脱帽の思いだ。
命を大事にするというごくごく当たり前の、生きるものの根っこが覆されるのが戦争だ。アメリカ軍はとにかく兵の命を大事にしてきた、という常識も鵜呑みに出来ないことも知った。そこで面と向かって戦いあう双方の兵士には家族がいて、愛するものがいて、一人で生きてきたものなどいない。そして虫けらのように死んでいった。

戦争に英雄などいない。栗林中将は確かに素晴らしい指揮官だった。なるべくなら戦争を忌避し、アメリカと戦うなどという無謀なことをしたくはなかった。しかし、避けることも逃げることもできなかった。そしてそのことを十分認識して戦った。彼ですら英雄ではない。
2作を見て、クリント・イーストウッドという人間の徹底振りとバランスの卓越さとゆるぎない姿勢を感じた。そして20年近く歴史を教えてきて、戦争の経過で硫黄島にほとんど目を向けてこなかったことを痛感した。南洋諸島の悲惨な戦いにはさまざまな資料を探し、ドキュメンタリーを見、日本軍の愚かさをあざってきた。なぜ硫黄島での戦いがクローズアップされてこなかったのを探るのがこれからの私の課題になりそうだ。
一点だけ。戦争に行く前の二宮君の着物が立派過ぎた。いい紬着てたなあ。伊原剛志、おいしかった。

『硫黄島からの手紙』
監督 クリント・イーストウッド
出演 渡辺謙 二宮和也 伊原剛志 加瀬亮 裕木奈江 中村獅童










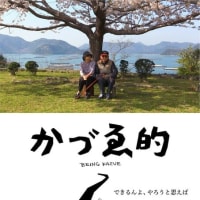
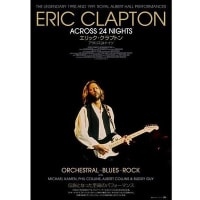
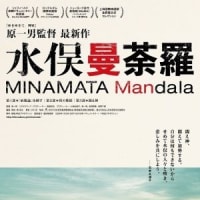
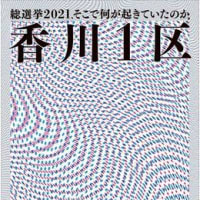






伊藤中尉と憲兵上がりの清水2人の心情の移ろいが
とても興味深かったです。
栗林中将や山本元帥のように軍人でありながら反戦
を唱える人たちって皆、前線送りにされていたのがな
んとなく胸が痛みました。彼らのような人たちが当時
の政権をとってれば日本はまた違った道を歩んだの
かなと思ってしまいました♪ (゜▽゜)v
海軍、山本五十六ですよねぇ。
ちゃんとバランスのいい人がいたのに、とっても悔しいのですが、そういうバランスのいい人のことを日本人でなくアメリカ人に描かれちゃった、、、というのがまた悔しかったりして。
いつも有難うございます
栗林中将のような方がおられた事には
お国のために死ぬ
だったのですからね。でも生きて戦い続けるのも
凄いこと。どちらにしても、極限状態になったら・・・。
人間の精神状態ってどうなのでしょうか
絶対極限状態に行っても女は強いと思うな。
妙な開き直りと、立ち直りが早いのが女だと思うから。
だからきっと女はアホな戦争なんかしないと思うのですが。
って全然ヘンな方向に物を考えてしまいました。
それぞれの登場人物の背景を考えてしまいました。
二宮演ずる西郷に赤紙が来た時に
近所のおばちゃんが西郷の身重の妻(裕木奈江)に言った台詞・・・
「そんな事を言っている時代じゃないんだよ。」
これにつきますね。戦争ってそういうものなんですね。
あと、西(伊原剛志)が負傷した米兵サムと心を通わせるシーンも良かった。
アメリカ人も日本人も同じ心を持った人間ですものね。
「父親たちの星条旗」に続き、TBさせていただきました。
栗林中将がいなければ、あの人々も全滅するところだったわけですね。
私も「父親たちの星条旗」があればこそ、だと思います。ぜひ2部作で観て欲しいですね~、これだけ観るのではなくて。
それをすべて無にしてしまうのが戦争なのですよね。
そうやって一所懸命生きてるのも人間、殺し合う戦争を起こすのも人間。まったく人間って奴は・・・です。
そして目をそむけないでいただきたいと思います。
むごいけど、痛いけど、あれが戦争の姿なんだということをちゃんと目を開いて見てもらいたいものです。
初日に行ったのですが、凄い人でビックリ。
「父親たちの・・」の5倍は入ってたわ!
なので、あのTVでやったドラマは見てません。
そこでも少年たちの悲劇を映していたと聞いたのですが、そっちを見なかったこともちょいと惜しかったです。
テレビドラマは子どもと見ました。作りは日本のドラマらしいつくりでしたが、ちょっとだけドキュメントにしてあって、その分、息子が戦争に行かなくて良いこの時代に、本当に感謝しました。
戦争を知る人間はいなくなっても、どういう形でもいいから伝えていく事が大切だと思います。
はなっから戦争の道を選んだ日本の選択肢の甘さを露呈したと。
日本がなぜ軍部主導の政治の道に行ってしまったのかあたりは何かに記そうと思ってます。明治の元勲あたりに原因があると思っているのですが。
そこで最も大事なのが判断力。人が皆右を向くときにそれはおかしい左だといえる正しい判断力と勇気っすかね。それを養うために勉強しとんじゃああ、と言ってるのですが、うーーんん、難しいです、ハイ。