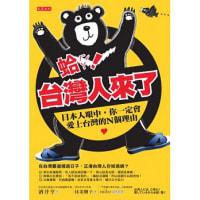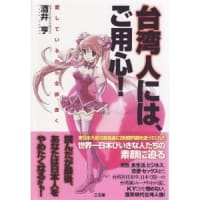人間は不思議なことだらけだ。
数を数えたり、色を表したり、関係代名詞などで入れ子構造をつくったりすることは、普通人間の言語なら当たり前に存在すると思われているが、ところがアマゾンのど真ん中にするピラハン族Pirahãの言語ピラハン語(自身の言語ではxapaitíiso アパイティイソ)には、数詞も、色彩をあらわす形容詞・名詞も、右左を示す言葉も、入れ子構造もない。
米国の言語学者ダニエル・エヴェレットが書いた「眠り込んじゃいけない、蛇がいるから」は、そうしたピラハン族の文化と言語を専門書でなく、一般向けに平易な文体で描いたノンフィクションだ。
Don't Sleep, There Are Snakes: Life and Language in the Amazonian Jungle
Daniel L. Everett (Author)
Publisher: Vintage (November 3, 2009)
ISBN-13: 978-0307386120(ペーパーバック)
作者Dan Everett's HP http://llc.illinoisstate.edu/dlevere/
数詞は最初は3までしかないとされていたが、厳密には2と3とみられたものも曖昧な「いくつか」を示すものに過ぎず、数詞そのものがないことがわかった。
数の概念そのものがなく、本来数詞がなかったと思われるパプアのある言語が近隣言語から借用したように、数詞を借用することもしなかった、という。
色彩については、「赤い」という言葉はなく、「血のような」など具体的なものの比喩で表す。
自分の身体を基軸にした右・左を示す言葉もなく、自分たちの集落を流れる川のほうかそうではないかという地理的絶対方位の表現しかとらない。したがって「これは私の右手、こっちは左手」という表現はない。
入れ子構造もない。だから、「私が昨日見たジャガーを今日狩った」という複文は表現せず、事象を細切れに単文を並べて表現する。
また、日常生活でも、自分たちが見たこともない空想、仮定、伝説は存在しない。日々の食事は、そのつど採集し、保存することはしない。本書のタイトルにもあるように、夜は大蛇や猛獣に襲われる危険があるから、昼夜問わず細切れに眠り、夜は大声で談話する。子どもはたとえ2歳程度でも大人と同等に扱われる。
ーーーなどなど、米国人作者の「常識」を超える発想がそこに展開している。
しかも、作者も人間の多様性を知り、米国人の思考が実は特殊なものに過ぎないことも自覚する。
特に、言語学者としての作者の、チョムスキー理論に対する批判は厳しい。
まあ言語学やったことない人には、チョムスキー批判の部分は読んでも意味がわからないだろうが、私もはっきりいってアンチチョムスキアンなので、作者の批判には完全に同意する。
てか、チョムスキーってイラク戦争批判で思想・論壇界でも脚光を浴びたけど、彼自身の言語理論はブッシュを批判できる資格がない、完全に英語帝国主義、英語中心主義の謬論なんだよな。
だから、イラク戦争のときに左翼の友人がチョムスキーを知って評価していたときにも、私は鼻で笑っていたのだ。アナキストを気取っているチョムスキー。実は単なる英語中心主義の醜悪な帝国主義者なんだから。
作者はもともと福音派の宣教師として、聖書をピラハン語に翻訳し、布教することを目的にピラハンの人たちと接触したのだが、上記述べた言語構造や思考構造の理由から、「とても聖書を翻訳して、さらに本人たちに受け入れさせることは不可能だ」と悟り、あっさり宣教師をやめて、言語学の学位をとり研究者になる。
福音派といえば、一番米帝国主義的というか、米国が世界一だという狂信にとらわれている人たちなはずだが、作者のようにあっさりその限界に気づくところも、ある意味では米国知識人のナイーブさというか、良さかも知れない。そういう意味では、私も同じように善良な米国人を何人も知っている。
政府や企業の帝国主義的悪辣さと対照的に、市民レベルの善良さと柔軟さが、米国の救いなのかもしれない。
ただ、不思議なのは、本書に登場する人の年齢が、40代とか60代とか書かれているんだが、「数」の観念がない人の年齢をどうやって割り出したのだろうか?もちろん、ブラジル政府への出生登録かなんかを基にしたのかもしれないが、その点明らかにされていないのは、ちょっと疑問だった。
数を数えたり、色を表したり、関係代名詞などで入れ子構造をつくったりすることは、普通人間の言語なら当たり前に存在すると思われているが、ところがアマゾンのど真ん中にするピラハン族Pirahãの言語ピラハン語(自身の言語ではxapaitíiso アパイティイソ)には、数詞も、色彩をあらわす形容詞・名詞も、右左を示す言葉も、入れ子構造もない。
米国の言語学者ダニエル・エヴェレットが書いた「眠り込んじゃいけない、蛇がいるから」は、そうしたピラハン族の文化と言語を専門書でなく、一般向けに平易な文体で描いたノンフィクションだ。
Don't Sleep, There Are Snakes: Life and Language in the Amazonian Jungle
Daniel L. Everett (Author)
Publisher: Vintage (November 3, 2009)
ISBN-13: 978-0307386120(ペーパーバック)
作者Dan Everett's HP http://llc.illinoisstate.edu/dlevere/
数詞は最初は3までしかないとされていたが、厳密には2と3とみられたものも曖昧な「いくつか」を示すものに過ぎず、数詞そのものがないことがわかった。
数の概念そのものがなく、本来数詞がなかったと思われるパプアのある言語が近隣言語から借用したように、数詞を借用することもしなかった、という。
色彩については、「赤い」という言葉はなく、「血のような」など具体的なものの比喩で表す。
自分の身体を基軸にした右・左を示す言葉もなく、自分たちの集落を流れる川のほうかそうではないかという地理的絶対方位の表現しかとらない。したがって「これは私の右手、こっちは左手」という表現はない。
入れ子構造もない。だから、「私が昨日見たジャガーを今日狩った」という複文は表現せず、事象を細切れに単文を並べて表現する。
また、日常生活でも、自分たちが見たこともない空想、仮定、伝説は存在しない。日々の食事は、そのつど採集し、保存することはしない。本書のタイトルにもあるように、夜は大蛇や猛獣に襲われる危険があるから、昼夜問わず細切れに眠り、夜は大声で談話する。子どもはたとえ2歳程度でも大人と同等に扱われる。
ーーーなどなど、米国人作者の「常識」を超える発想がそこに展開している。
しかも、作者も人間の多様性を知り、米国人の思考が実は特殊なものに過ぎないことも自覚する。
特に、言語学者としての作者の、チョムスキー理論に対する批判は厳しい。
まあ言語学やったことない人には、チョムスキー批判の部分は読んでも意味がわからないだろうが、私もはっきりいってアンチチョムスキアンなので、作者の批判には完全に同意する。
てか、チョムスキーってイラク戦争批判で思想・論壇界でも脚光を浴びたけど、彼自身の言語理論はブッシュを批判できる資格がない、完全に英語帝国主義、英語中心主義の謬論なんだよな。
だから、イラク戦争のときに左翼の友人がチョムスキーを知って評価していたときにも、私は鼻で笑っていたのだ。アナキストを気取っているチョムスキー。実は単なる英語中心主義の醜悪な帝国主義者なんだから。
作者はもともと福音派の宣教師として、聖書をピラハン語に翻訳し、布教することを目的にピラハンの人たちと接触したのだが、上記述べた言語構造や思考構造の理由から、「とても聖書を翻訳して、さらに本人たちに受け入れさせることは不可能だ」と悟り、あっさり宣教師をやめて、言語学の学位をとり研究者になる。
福音派といえば、一番米帝国主義的というか、米国が世界一だという狂信にとらわれている人たちなはずだが、作者のようにあっさりその限界に気づくところも、ある意味では米国知識人のナイーブさというか、良さかも知れない。そういう意味では、私も同じように善良な米国人を何人も知っている。
政府や企業の帝国主義的悪辣さと対照的に、市民レベルの善良さと柔軟さが、米国の救いなのかもしれない。
ただ、不思議なのは、本書に登場する人の年齢が、40代とか60代とか書かれているんだが、「数」の観念がない人の年齢をどうやって割り出したのだろうか?もちろん、ブラジル政府への出生登録かなんかを基にしたのかもしれないが、その点明らかにされていないのは、ちょっと疑問だった。