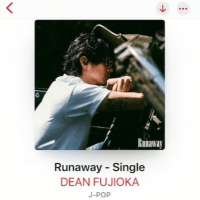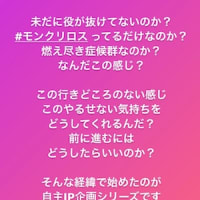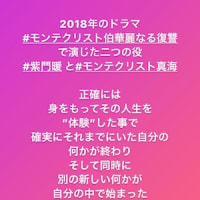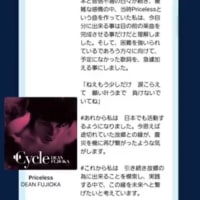浮世之介は十三世仁左衛門さんも演じられた役。
雀々さんのオフィシャルサイトの日記(ブログ)によれば、なん
と孝夫さんも新橋演舞場で「好色一代男」に出演されたことがあ
るとのこと。(孝太郎さんのブログにもそう書かれていた。)
その新橋の舞台では雀々さんの師匠である枝雀さんが共演された
らしい。
おそらく映像化されないだろうし、舞台写真もないこの作品。
やっぱり書いておこう、自分用備忘録。
幸いプログラムには全幕全場のタイトルとあらすじがあるしね。
※参考:プログラム、原作『好色一代男』、手元メモ
<第一幕>
●第一場 島原「扇屋」(夢)
幕があくと、舞台前方にパーッと艶やかな遊女たちの舞い姿が。
両端で踊っているのは太鼓持ちふうの男二人。(あ、純也くん!)
花道をやってくる男あり。
世之介だ。(おお~、愛之助さん♪)
顔は白塗りの歌舞伎風。衣装はたぶんポスターの写真と同じ。
上には紫色の羽織(だったと思う)。
皆に歓迎されながらお座敷にあがると、夕霧太夫(愛原実花)が
待っていた。
「今日こそ色よい返事を聞かせてぇな~」と迫る世之介は、すば
やく羽織の片肌を脱いで郭遊びの男の風情プンプン。
先約があるからと断る夕霧のところへ、別の男がやってくる。
尾張の伝七(原田龍二)だ。
なんと二人は手に手をとり、花道を仲良く去って行くのだった。
「人生楽ありゃ、苦もあるさ」と言葉を残して。(黄門さまネタ
だぁ!どひゃ~。)
世之介が花道七三まで追いかけて伏せると、舞台が暗転。
周囲が明るくなり、世之介が目覚める。
「なんや、夢かいな~」。
世之介 VS 伝七 の女をめぐる関係を暗示する始まりだ。
世之介は男前で色気はあるし、お金もある。
だけど、意外にもおちゃめで無邪気な三枚目キャラだ。
女性を好きになるきっかけはほぼ<一目惚れ>。~でんな、~で
おま、のような上方の町人言葉で親近感を与え、話の面白さと熱
心さで相手のハートをガッツリ掴むタイプ。これは今につながる
上方男子の特権かもしれない。
一方の伝七は真っ向勝負な二枚目キャラ。
長身・オトコマエ・お金持ちの完全無欠。口は巧いとはいえない
が、その男っぷりのよさに女が惚れてしまうタイプのようだ。
●第二場 夢の屋奥座敷
本舞台に戻った世之介。女医(遼河はるひ)の診察を受けている。
現実でもやはり金には困らない生活をしているようだ。が、近頃
人生に無常を感じ、気力がわかない様子。
「最近はおなごを見ても、心も手も動かん」と言いつつ、女医の
手を握る世之介。「手は動いてますよ」とつっこまれる。
元気がないのは「腎虚です」との診たてをする女医。
(症状を遠回しに医学的に説明する女医に、言葉の意味を嬉々と
して尋ねる世之介はいたずらっ子という感じ。)女医、開き直っ
て「やりすぎなんだよ!」。再び楚々とした感じで去る。
そこへ面白メイクをした手代の瀬平(桂雀々)がやってきて
「でかい人やなあ」。
>> 幻の女(竹下景子)登場。
お前の元気のないのは迷っているからではないのか、と告げる女。
好色一代男として芝居の幕引きをどうするか。その答えを出すには
今までの人生を振り返ることだ、と。
「あんさんには素直に心を打ち明けられる気がする」と世之介。
が、触れようとしてもすぐに姿を消してしまう。
手代の瀬平に続いて、世之介の遊び仲間がなだれ込んできて、全員
で郭に繰り出すことに。
ここからは世之介の回想、思い出話に飛ぶ。
●第三場 夢の屋奥座敷(回想)
★世之介の衣装:格子か縞のカジュアルな着物
父親・夢助はその昔、男伊達を競い、島原一の太夫を身請けし妻と
した。その女は世之介を産むとすぐに死ぬ。以来、夢助は商売に励
み、夢の屋を大店の両替商にした。
「世之介は7歳になると自分で着物を着て香をたきこめ、9歳で女中
の行水を覗く」と言いながら、遠メガネみたいなもので覗きながら
登場する世之介。おませなガキンチョを演じる愛之助さんがすんご
く可愛いの♪
初めて郭に行ったのが11歳(だったと思う)。
★世之介の衣装:萌えいずるような緑色の羽織に白っぽい着物
「おなごにこれもろうた」と瀬平に見せびらかす世之介、手に持っ
ているのは<女の髪>と<起請文>(←これがのちの伏線になる)。
「必死のパッチでもろうてきた」という台詞に客席がわく。
(当初はなかった台詞。「必死のパッチ」は雀々さんのHPのタイト
ルでもあり、著書名でもあるようだ。)
●第四場 山科の水茶屋
お錦(紅萬子)がきりもりする場末の水茶屋「すずかぜ」は、遊女
とは呼べない接待女たちのいる場所。「お前も物好きよのう」と幻
の女にも笑われる始末。
世之介はすっかり若旦那の色気と華やかさを備えている。ある日、
店の金をちょろまかして、瀬平といっしょに「すずかぜ」に来た。
入ろうとした矢先に父親がやってきて阻止する。
吉弥さん演じる父親の夢介は、色気もあってしかも大店のあるじら
しく太っ腹で頼もしい。見るからにええ男♪
「お前は江戸に行って商売の修行をしてこい」と我が子を旅に出す。
(この後も何かにつけて父と対話のシーンが出てくる。)
紅萬子さんのお錦はお笑いキャラで、世之介のゆく先々で登場して
は絶妙のタイミングで盛り上げる。話のつなぎ役に欠かせない人物。
●第五場 吉原仲ノ町
★世之介の衣装:小荷物を肩にかけた旅装。
花道に花魁道中の一行がやってくる。先導係の男、赤い衣装の二人
の禿。別の男が大きな傘を高々とさしかける。
高尾太夫(紫吹淳)だ。音楽は「帰れソレントへ」。
黒地の衣装に高下駄で、客席の視線を引きつけゆっくり歩いてくる。
優雅さと大きさは、さすがに宝塚の元トップの存在感たっぷり。
(歌舞伎ファンとしては本物志向で、ここはぜひ外八文字を披露し
てほしかったところ。ちなみに紫吹さんのマネージャーによれば、
高下駄は何の細工もなくかなり重いものだったそう。さすがに女性
が舞台で毎回、外八文字をするのはムリと思われ。『巨人の星』の
鉄下駄になってしまう。←ふるっ!!! でも当初はただのすり足
だったのが、前楽では若干工夫されていたのがわかった。)
舞台上手で道中を見ている世之介と瀬平。
二人いっしょに、眉も目もたれ下がり、だらり膝を曲げたまま見と
れている。高尾太夫が世之介を振り返り、視線が合う。
「天女や~~~!」と世之介。(彦摩呂ふうに)
●第六場 吉原仲ノ町「兵庫屋」
★世之介の衣装:・・・失念(郭で遊ぶ衣装だけどね)
高尾太夫に夢中になり、不幸な身の上を聞きかじった世之介。
ある日人払いし、本人の口から仔細を聞き出そうとする。
「花魁言葉やのうて、自分の言葉でしゃべってほしい。好きなおな
ごのことはなんでも知りたいねん・・・」と優しく迫る。
元は武家の娘だったが、ある時父親が策にはまってお家断絶となり、
自分が身売りすることになった・・・という話をする高尾。
そこへ女将が来て、たまには他のお客の相手もしてくれないと商売
が立ちゆかぬと言う。ヨーシそれなら、自分が身請けするっ!
「千両持って来い!」と世之介。
(届いたのは千両箱じゃなくサンタクロースが背負うような袋♪)
自由になった太夫に「里の親許のところへお帰り」と明るく言う。
そう言ったあとで、高尾の目を見ながら「会いとうなったら、また
会いに行ってええか?」としんみりあったかく言うのが世之介流。
もう会えないとわかっていながら。
(くううう~っ、カッコイイ!!)
高尾の心からの褒め言葉は武家の娘らしく、花魁らしく、誇り高い
響きがこもっていた。
「あんさんはほんにこの国に似合わぬ男でありんすなあ」。
太夫に感謝され、世之介は有頂天になっている。
そこへ父親、夢助が現れ「あほか、かっこつけて。店の金で」。
(客席、どっとわく。)
即、勘当され、出家させられる世之介なのだった。
このとき舞台セット設営中の幕の前で毎回、吉弥さんと愛之助さん
の楽しいおしゃべりタイムが♪
勘当を言い渡された世之介が父に果敢に絡んでいくので、吉弥さん
が吹き出したり、台詞を間違えたり、静かにしてと訴えたり。その
たびに客席から笑いが起きていた。
勘当しても奉公先は見つけてやるという流れで、世之介が勤務条件
をリクエストする。「お給料がいっぱいもらえて、月に2回ぐらい
は御園座で上村吉弥さんの芝居が見られたらええなあ」。
8月7日夜と前楽の昼は吉弥さんだったが、前楽夜は「紫吹淳さん」
になっていた。それを受けて吉弥さんが「ええなあ、淳ちゃん!」
二人して「淳ちゃん、淳ちゃん、ええなあ」と言いながら手をとり
あってグルグル回るのがメチャクチャかわゆらしかった。
「そんなとこがあったらワシも行きたいわ。ここまでやったらこの
世に未練はないやろ」と出家を言い渡されるのがこの場のオチ。
>> 備忘録2につづく。
●このブログ内の関連記事
御園座「好色一代男」 観劇メモ(1)
御園座「好色一代男」 観劇メモ(2)
御園座「好色一代男」 観劇メモ(3)備忘録1
御園座「好色一代男」 観劇メモ(4)備忘録2
御園座「好色一代男」 観劇メモ(5)備忘録3
御園座「好色一代男」 観劇メモ(6)備忘録4