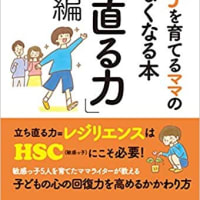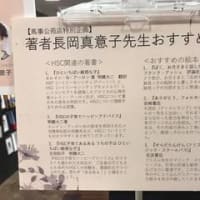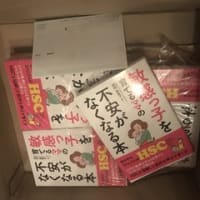私自身のウェブやブログ以外の媒体で、
初めて「ハイリーセンシティブチャイルド(ひといちばい敏感な子)」について書かせていただきました。
これまで、書きたいことがありすぎて、
とてもとても「一記事」としては仕上げられないなと、
他媒体では、手をつけられなかったテーマです。
それでも、接する大人が少し視点を変えることで、随分と楽になるHSCがいるはず。
1人でも多くのHSCが、少しでも生きやすくなってほしい。
少しずつであっても、伝えられることを伝えていこう、
今回、そんな気持ちを込めて書きました。
「親が子供の『敏感さ』に気づく大切さは、いくら言っても足りません」とするエレイン・アーロン氏
HSCという特性を提議した心理学者のエレイン・アーロン氏は、
ドキュメンタリー映画『Sensitive』の中で、
ハイリーセンシティブチャイルドについてこう話しています:
(https://vimeo.com/135066589より)
「早い時期から、親が子供の『敏感さ』に気づく大切さは、
いくら言っても足りないんです。
なぜなら、子供時代の体験が、
センシティブな人々にどれほど大きな影響を与えるか、分かっているからです。
もし、子供時代を『台無しにする(mess up)』なら、
センシティブな人というのは、
うつで不安感に溢れ様々な問題を一生抱える大人になる傾向がより強いんです。
一方、子供時代に適したケアがされるならば、
センシティブな人というのは、
最も生産的で、思慮深い社会の一員となります。
社会は、
深く考え、強い感情で対応し、
微妙な物事に気がつく人々を、
あらゆる場で必要としています。」
HSCとは、周りの関わり方次第で、生き生きと活躍する大人にもなり得れば、
メンタル面に問題を抱えたり、引きこもりがちで社会への扉を閉ざしてもしまえるんですね。
こうした強烈に感じやすい分、良くも悪くも環境から影響を受けやすいといったHSCの特性は、
「遺伝子レベル」で決定されているといいます。
(「 5-HTTLPR :the “short-short” of the serotonin transporter gene」
と呼ばれる「遺伝的変異(genetic variations)」
http://hsperson.com/faq/when-i-look-for-studies-i-hardly-see-any/より)
誤解されてきた「ひといちばい敏感」な特性
「不幸なことに、我々の社会ではこの特性はいささか誤解を受けてきました。そのため、ほとんどの心理学者や親たちは、HSCのごく一部分だけを見て、内気、引っ込み思案、怖がり、細かすぎる、あるいは”過敏性”と呼んできたのです。でも、もし彼らの中の一人でも、HSCの心の中を覗いてみることができたなら、その人は子供たちの中で起こっている ― 創造性、閃き、驚くべき賢さ、他者への共感、等々 ― を理解したことでしょう。」
ネガティブなレッテル貼りではなく、
HScの持つ、「創造性、閃き、驚くべき賢さ、他者への共感」などに目を向けてやりたいですね。
人見知りや場所見知りも、
観察したり感じることがあまりにもあり過ぎて、
圧倒されている状態。
「よく観察しているのね」「強烈に感じているのね」ぐらいの気持ちで、
その場の興味ありそうな物事に注意を向けたりと接しているうちに、
周りより時間がかかっても、次第に緩んでくることもあるものです。
「シャイ」「内気」「神経質」とその子を型に押し込めてしまわないよう気をつけたいですね。
ここからは、
様々な研究に基づく、あくまでも私自身のイメージの話です。
慣らす=「大丈夫回路」を刻んでいくということ
私自身は、HSCは高感度な分、習慣や性格へと繋がる脳の回路が、
瞬時に刻まれやすいというようなイメージを持っています。
「慣らすのが鍵」とされるのは、そうした「初めの強烈なインパクト」の上から、
「いやいや、大丈夫なんだよ」という回路を、
何度も何度もなぞり直し刻んでいく作業のようにも感じています。
例えば水辺で、恐がるHSCを、無理やり水の中に投げ入れたり、
「いいのよママが一緒にいるから一生入らなくていいのよ」と一切水に入らせないのなら、
「初めの恐いという強烈なインパクト」が深く刻まれたままです。
それでも、少しずつ少しずつ慣れさせ、
「いやいや大丈夫」と何度もなぞり直す内に、
初めの「強烈な恐れ」は機能しなくなり、「大丈夫回路」が活発となっていきます。
そして、何度も何度もなぞり直したこの「大丈夫回路」が定着すると、
つまり「慣れてしまう」と、
HSCは驚くほど生き生きと力を発揮していくことになるのじゃないか、
そう感じています。
「慣らす」を邪魔する完璧主義に注意
もうひとつ、気を配りたいのが、
HSCにとって、こうして「慣れることが鍵」にも関わらず、
HSCがもつ「完璧主義」が、その邪魔をしてしまう場合があるということ。
初めてだったり、経験も浅いので当たり前にもかかわらず、
「うまくできない」ということが強烈に迫り、
オールオアナッシングで、それ以上続けることを止めてしまいます。
HSCは「慣れて」からこそ、持てる力を存分に発揮できるにも関わらず、
初めの「圧倒され緊張した身体でのたどたどしい取り組み」のみで、
「ああ、私はだめだめ」と扉を閉ざしてしまっては、
もったいなさすぎます。
以下、完璧主義についてまとめたものです:
・子供の成長に悪影響!行き過ぎ「完璧主義」への対処法
・http://blog.goo.ne.jp/managaoka/c/ea27326c0d2d31aa9944051b9a05720e
例えば、以前の友人の息子君娘ちゃんの場合も、
(・日常風景、敏感な子とスポーツ&「じっとできない子」が学校に合わないのは成長の仕方が異なるため)
この後、ママやパパが近所を走ったりと何度か連れ出し、
走るということに慣れるにつれ、
今では、楽しそうに練習に通っています。
「慣れる」につれ、驚くほど伸びていくHSCの姿を何度も目にしています。
HSCの伸び方は、一直線でなく、
「慣れる」をポイントに急上昇していくのかもしれません。
今回の『オールアバウト』への記事は、
初めて「ハイリーセンシティブチャイル」「ひといちばい敏感な子」という言葉を目にした方でも、
「基本中の基本」を押さえられるようにまとめてあります。
コンセプトを既に知っている方にも、
HSCに接するうえで「これだけは覚えておきたいエッセンス」のおさらいになると思います。
興味ある方是非どうぞ!
こちらは、「ハイリーセンシティブチャイルド(ひといちばい敏感な子)」についてこれまで書いてきた68の記事です:
http://blog.goo.ne.jp/managaoka/c/799bdc6ec6ad9c8a15c5841831b99aec
最後に、ちょっと長いですが、再びアーロン氏のウェブから、著書『The Highly Sensitive Child』についての引用(「」内)です。:
「私がこの本を書いたきっかけは、とても多くの大人になったHSPから、彼らの子ども時代が非常に辛かったと聞かされてきたからです。彼らの両親が最善の子育てをしようとしている時でさえそうでした。理由は、誰もこの子たちの育て方を知らなかったからです。先生や親たちは彼らに言ってしまいます。”繊細すぎる”、”内気すぎる”、”感情が強すぎる”と。そうして、この子たちは自分を変えようと努力し、それができないことから、ますます自分は他の子たちと違っている、自分を恥ずかしいと思うようになってしまうのです。私はこの子たちに、これ以上このような無用な苦しみを与えたくありません。そしてこの世界にも、これ以上たくさんの才能を無駄にするようなことはしてほしくないのです。なぜなら、HSCはこの世界に与えることのできる、たくさんの素晴らしいものを持っているのですから。」
一人でも多くのHSCが、これ以上「無用な苦しみ」を味わうことなく、
「この世界に与えることのできる、たくさんの素晴らしいものを」差し出せますように。
「ただそのためには、この子たちに合った育て方が必要になります。彼らを正しく評価してあげること、彼らの特別なニーズに応えてあげること、そして時に彼らが激しい反応や態度を示した時には、それを理解してあげること。そして、何か間違いを正す必要がある時には、彼らが不安になったり、失敗を恥ずかしいと思わないように、彼らに合った接し方が必要なのです。」
そのために、HSCへの接し方を理解し、見直し、実践していくことが不可欠ですね。
私自身も、日々様々な子どもたちに接する中で、できる範囲で行動していきます。
さて、こちら今日は、なんと33度!まで気温が上がりました。
真夜中を越してしまいましたが、
これから原稿をひとつ仕上げて寝ます。
みなさん、今日も良い日を!