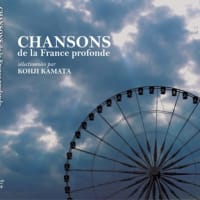なんてアメリカ映画は、BSで放送されなきゃまず観なかっただろう。随分前に公開されたらしいが、全然知らなかった。偏屈屋の大学教授の家にシリア人の移民青年が転がり込んでくる話。暇つぶしのタネに録画しておいたのだが、観るまでは、おおかたフランス映画の『最強のふたり』みたいな能天気コメディだろうとタカをくくっていた。
まったくの見当外れ。外科用メスで病巣を切り裂くようにアメリカ社会の現実を描き切った、目を剥くほどシャープな映画だった。久々に震えが来るほど胸を打たれた。
青年はアラブ系の外見ゆえに些細なきっかけで逮捕され、不法滞在がバレて問答無用で強制送還される。老教授は彼を救おうと奔走するが、9.11後のアメリカ社会の不寛容に跳ね返される。青年の母親は「シリアと同じね」とつぶやく。
このプロットを軸に、普通の市民がセネガルと南アの区別もつかなかったり、路上マーケットでイスラエル青年とイスラム女性が並んで屋台を出していたり、勝ち組のアラブ系弁護士が不法移民にまるで冷淡だったりと、アメリカの今が活写される。
しかし、もっとも胸を打つのは、クラシック好きでヘタなピアノを弾いていた教授が、シリア青年の案内でアフリカ音楽に目を開かれていくシーンだろう。クラシックは基本4拍子だがアフリカ音楽は3拍子なんだと言って、青年はジェンベをたたき出す。実際にはハチロクだが、そんなことはどうでもよろしい。軽やかなビートが生命の脈動に呼応していることを、すっと納得させられる。
見よう見まねでジェンベをたたき始めた教授は、見るみる生気を取り戻す。12年間、機械のように同じ授業をくり返してきた大学を捨て、人間として生き直し始める。
画面は一目で低予算と分かるし、無名に近い俳優たちの演技にも雑なところがある。それでもこの映画はメッセージの真摯さ、作り手の誠実さによって欠点を忘れさせる。母親役のヒアム・アッバースの清楚な気品が印象的だ。
オレは普段アメリカの悪口ばかり書いているが、こういう性格の映画を制作し、公開できる余裕はやっぱりアメリカならではだと思う。ネットで調べたら、半年ロングランしたそうだ。それだけ支持する人々がいたわけだ。
日本でも4年前、中学生の娘を一人残して両親をフィリピンに強制送還する事件が起きた。ほかにも移民関連で、表沙汰にならない事件がいくつもあるはずだ。しかし日本の映画人は、そういう日本の現実を描こうとはしない。あるいは、描きたくても描ける環境がない。
かつてはアート・シアター・ギルドという、低予算で作家性の強い映画を撮るシステムが日本にもあったんだけどねえ。そのおかげで唐十郎の『玄界灘』とか、名作が多数生まれた。あれは今どうなってるのだろう。フィルムが劣化してなきゃいいが。
まったくの見当外れ。外科用メスで病巣を切り裂くようにアメリカ社会の現実を描き切った、目を剥くほどシャープな映画だった。久々に震えが来るほど胸を打たれた。
青年はアラブ系の外見ゆえに些細なきっかけで逮捕され、不法滞在がバレて問答無用で強制送還される。老教授は彼を救おうと奔走するが、9.11後のアメリカ社会の不寛容に跳ね返される。青年の母親は「シリアと同じね」とつぶやく。
このプロットを軸に、普通の市民がセネガルと南アの区別もつかなかったり、路上マーケットでイスラエル青年とイスラム女性が並んで屋台を出していたり、勝ち組のアラブ系弁護士が不法移民にまるで冷淡だったりと、アメリカの今が活写される。
しかし、もっとも胸を打つのは、クラシック好きでヘタなピアノを弾いていた教授が、シリア青年の案内でアフリカ音楽に目を開かれていくシーンだろう。クラシックは基本4拍子だがアフリカ音楽は3拍子なんだと言って、青年はジェンベをたたき出す。実際にはハチロクだが、そんなことはどうでもよろしい。軽やかなビートが生命の脈動に呼応していることを、すっと納得させられる。
見よう見まねでジェンベをたたき始めた教授は、見るみる生気を取り戻す。12年間、機械のように同じ授業をくり返してきた大学を捨て、人間として生き直し始める。
画面は一目で低予算と分かるし、無名に近い俳優たちの演技にも雑なところがある。それでもこの映画はメッセージの真摯さ、作り手の誠実さによって欠点を忘れさせる。母親役のヒアム・アッバースの清楚な気品が印象的だ。
オレは普段アメリカの悪口ばかり書いているが、こういう性格の映画を制作し、公開できる余裕はやっぱりアメリカならではだと思う。ネットで調べたら、半年ロングランしたそうだ。それだけ支持する人々がいたわけだ。
日本でも4年前、中学生の娘を一人残して両親をフィリピンに強制送還する事件が起きた。ほかにも移民関連で、表沙汰にならない事件がいくつもあるはずだ。しかし日本の映画人は、そういう日本の現実を描こうとはしない。あるいは、描きたくても描ける環境がない。
かつてはアート・シアター・ギルドという、低予算で作家性の強い映画を撮るシステムが日本にもあったんだけどねえ。そのおかげで唐十郎の『玄界灘』とか、名作が多数生まれた。あれは今どうなってるのだろう。フィルムが劣化してなきゃいいが。