サー・アイザック・ニュートンの伝記を読んだのは、子供の頃になります。もう亡くなられて随分となるけれど、父が若い頃お世話になったYさんの書斎からいただいたものです。父親が仕事の話をしている間、おとなしく読みふけっていたのですが、万有引力の法則とかプリズムの解析とか『プリンキピア』の執筆などの偉業の一方で、ゆで卵と間違えて懐中時計を茹でてしまうなどのウッカリさ加減も魅力的でした。子供向けの伝記なんてのはそういうものです。フックやライプニッツとの論争は言及されていても、権力獲得後にフックの業績をすべて抹殺してしまったような猜疑心が強く執念深い一面などには触れていません。
さて、2005年7月4日の朝日新聞朝刊に「ニュートンの錬金術覚書が発見された」という記事が掲載されていましたので、軽くネット検索してみました。できるだけ、元に近いソースで確認しないとね。
ロンドンのロイター通信によると、王立学士院の目録作成の過程で、1936年のオークションにおいて15ポンドで落札されたまま紛失したと思われていた直筆手記が発見されたそうです。ニュートンといえば、偉大なる科学者として有名ですが、彼の活躍した18世紀というのはまだ科学と錬金術がはっきり分離していなかった時代です。ニュートンを研究したケインズが「彼は最初の科学者ではない。最後の錬金術師だ」と指摘したくらい。この22頁の手記にも彼が研究した錬金術書に関するメモが記載されているそうです……って、ほとんど日本語記事のままですな。
で、そもそも、なんで経済学者のケインズが自然科学者のニュートンを研究していたかというと、ニュートンは造幣局長官として1ギニー金貨=21ペニーシリング銀貨という金と銀の交換レートを定めた……つまり金本位制の生みの親みたいなものだったからですね。
「最後の錬金術師」たるニュートンは自然科学から政治行政の分野に転出した後も「金」から離れられなかったのです。
この金本位制が崩壊するのは20世紀のこと。「経済の血液」ともいわれる「金」の流通バランスが崩れたのはもっぱら投機筋の「ゲーム」によるものだったといえます。同じように「産業の血液」と呼ばれた「原油」の流通バランスが崩れて高騰しているのも「ゲーム」が原因。
しかし「最後の錬金術師」たるニュートンが、「造幣局長官」として執拗に偽金作りを追いつめていったとか、未熟児として生まれながらも85歳まで生き(フックもライプニッツも論争に決着が付く前に墓石の下)、死ぬまで髪がふさふさしていて歯も1本しか抜けなかったというから……いろいろインスピレーションが湧きますね。
さて、2005年7月4日の朝日新聞朝刊に「ニュートンの錬金術覚書が発見された」という記事が掲載されていましたので、軽くネット検索してみました。できるだけ、元に近いソースで確認しないとね。
ロンドンのロイター通信によると、王立学士院の目録作成の過程で、1936年のオークションにおいて15ポンドで落札されたまま紛失したと思われていた直筆手記が発見されたそうです。ニュートンといえば、偉大なる科学者として有名ですが、彼の活躍した18世紀というのはまだ科学と錬金術がはっきり分離していなかった時代です。ニュートンを研究したケインズが「彼は最初の科学者ではない。最後の錬金術師だ」と指摘したくらい。この22頁の手記にも彼が研究した錬金術書に関するメモが記載されているそうです……って、ほとんど日本語記事のままですな。
で、そもそも、なんで経済学者のケインズが自然科学者のニュートンを研究していたかというと、ニュートンは造幣局長官として1ギニー金貨=21ペニーシリング銀貨という金と銀の交換レートを定めた……つまり金本位制の生みの親みたいなものだったからですね。
「最後の錬金術師」たるニュートンは自然科学から政治行政の分野に転出した後も「金」から離れられなかったのです。
この金本位制が崩壊するのは20世紀のこと。「経済の血液」ともいわれる「金」の流通バランスが崩れたのはもっぱら投機筋の「ゲーム」によるものだったといえます。同じように「産業の血液」と呼ばれた「原油」の流通バランスが崩れて高騰しているのも「ゲーム」が原因。
しかし「最後の錬金術師」たるニュートンが、「造幣局長官」として執拗に偽金作りを追いつめていったとか、未熟児として生まれながらも85歳まで生き(フックもライプニッツも論争に決着が付く前に墓石の下)、死ぬまで髪がふさふさしていて歯も1本しか抜けなかったというから……いろいろインスピレーションが湧きますね。













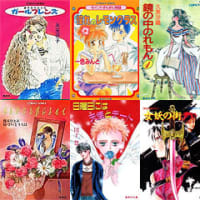

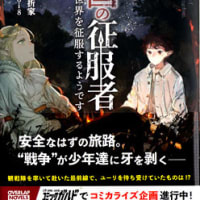

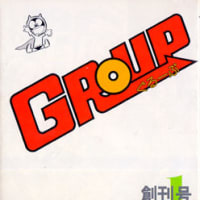
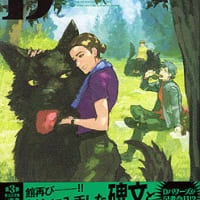
![「水路の夢[ウォーターウェイ]」 早見裕司](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/08/0c/ebdbd76e1b746940033530b209963446.jpg)





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます