『2月28日のNHKスペシャル:権力の懐に飛び込んだ湯浅誠の100日間の闘い』をみました。
職を失った人や派遣切りなど雇用を取り巻く情勢は厳しさを増すばかり、彼らの多くが、職もなければ住む家もなく、その日の生活にも事欠く人が多い。行政の窓口がそれぞれにバラバラで、彼らが抱えている複数のニーズに行政は応えていない。
湯浅氏はこれまで抱いていたワンストップサービスを試行することになった。彼が縦割り行政のなかで、それぞれの行政の壁にはばまれ、地方自治体の壁にぶっつかりながら、孤軍奮闘する姿を年末の年越し派遣村までカメラは密着取材しています。最後に、彼は内閣府参与を辞めることになります。辞表を提出した彼の本心はわかりませんが、彼は内閣府に残っても、大きな改革にはなり得ないことを自覚したのかどうか・・・。
彼が番組のなかで言った重い言葉、「生活保護や野宿生活者(ホームレス)に対する世間の偏見が変わらないかぎり、制度もなかなか変わらない」と言う趣旨のことを述べていた、つまり世論を動かさなければ、制度も政治も変わらないということです。
「世論を動かす」ことが極めて重要である。政治家を動かし官僚を動かすためには国民世論の後押しがなければ事が進まない、だがマスコミにしろ、ジャーナリストにしろ、学者でさえ福祉に冷淡な人が多い。
年末の年越し村の出来事にたいしても、詳細に分析もせずに、「ごね得」と言った産経新聞、「200人が無断外泊」と断罪した朝日新聞。石原都知事ごときは、失敗に終わったオリンピック誘致にのために使った費用が50億とも、150億円といわれている、自分の「甘え」のことはさておいて、「あの程度の行事」「甘えた話」と切り捨てた。
国民のレベル以上の政治は期待できない。また、政治家は自分が生き残る(選挙に落ちればただの人になる)ために、世論の動きに敏感であるが、その世論は腐ったマスコミが誘導する。政治家はTVに出演して自分の顔を売りたがる、結果としてマスコミの奴隷にもなる。
昔の日本は福祉という制度は確立していなくとも、隣近所で助け合う共同意識があった。今は他人に無関心、冷淡な世の中になっている。それでも1960年代には、良いか悪いかは別にして多くの若者が安保闘争に情熱を傾ける余裕があった。今の若者をけなすつもりはさらさらないけれど、この不条理なるものをぶち壊す意欲が乏しくなっているのは何故だろうか。
今回の湯浅氏が味わったもう一つの大きな壁が、地方自治体の壁だった。福祉の現場は地方が担っている、地方自治体の協力なしには実行できない。自治体が出してきた条件は、生活保護を入れるのだったら嫌だというわけである。生活保護費は自治体の大きな負担になる、ただでさえ苦しい予算のなかで更なる出費は防ぎたいからである。
結局行き着く先は「金」である、日本経済の長期不況が根底にある。日本の長期不況の原因は、政治不況である。アメリカに押し付けられた不当な円高と新自由主義(市場原理主義)に何らの異議異論を唱えず、唯々諾々と従ってきたこれまでの自民党政権の罪は重い。だがその長期不況の原因を糺し、打開する方法を説くマスコミもエコノミストもジャーナリストも政治家も学者もいないのだから情けない。
かっての安保闘争に情熱を注いだ人たちは今どうしているのだろうか。自らだけの安住の地でぬくぬくと老いの惰眠をむさぼっているのだろうか。少しでも湯浅氏の怒りを共有する老若男女が増えないものかと思う。そして大きな国民運動のうねりにならないものだろうか。










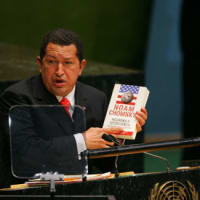
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます