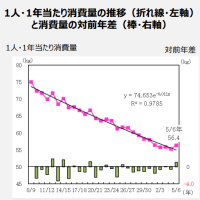当たり前といえば当たり前の商売の基本が、タイトル。
でも、本当に「お客様と向き合っているのか?」という、コトなのだ。
日曜日の新聞には、新刊や話題の書籍を紹介する頁があることが多い。
その中に、関西にある書店の営業部長さんのお話しが掲載されていた。
お話しというのは、東京国際ブックフェアで「お客様を知る力は日本一!の書店員 1500人の趣向を把握し、販売につなげる接客とは?」という講演をされた、隆祥堂書店営業部長のニ村知子さんの講演の内容だった。
今街中の書店は、イロイロな意味で岐路に立たされている。
先日も出かけた繁華街の大きな書店が閉店していて(内装改装の閉店ではない)、ガッカリしたばかりだ。
別に、その書店でなくては買いたい本がないわけでは無いし、近くには丸善などもあるので困ることは無いのだが、ファッションビル内にある書店というのは「買い物ついでに・・・」という気軽さがあり、便利だったのだ。
そして地方に行けば、昔ながらの商店街の本屋さんは商店街の衰退と共にシャッターを閉めていることが多い。
その理由の一つは、コンビニで雑誌が買えたりするコトだろうし、アマゾンのようなネットで本が買えるというのも、大きな理由だろう。
ただ、この二村さんの公演内容の記事を読むと、どれだけ特別な接客をしている訳では無いようなのだ。
違うのは「お客様と向き合う姿勢」というコトだろう。
「お客様の趣向を知り、提案をする」と言えば、「アマゾンでもやっている」と言われそうだ。
確かにアマゾンで本を検索したり購入したりすると、「この本を購入した人は、このような本にも興味を持っています」というリストが表示されたり、メールで送られてきたりする。
それはそれで、便利で親切な機能のように思えるのだが、私自身としては「余計なお節介」と感じている。
というのも、仕事で読みたい本と趣味として読みたい本はまったく違うジャンルだし、その趣向もバラバラ。
おそらく人というのは、そんな「一人十色以上の思考・趣向がある」と思っている。
そこが、アマゾンの提案の限界なのではないだろうか?
むしろその「一人十色以上」という点が、この二村さんの書店の接客の基本のように感じたのだ。
ビジネス書の常連のお客様に「リフレッシュのために、いつもと違うこんな本はいかがですか?」と、声を掛けられること。
それも「お客様の好みをある程度理解した提案」という難しさがあると思うが、「お客様が求める本は、草の根分けてでも探す」という本に対する姿勢が、常連さんたちから「的を得た、本を薦めてくれる」という言葉へと、つながるのではないだろうか?
停滞する小売りの基本的コトのように思われるかも知れないが、この「本気でお客様と向き合い、一緒に追求する」という姿勢は、どの業種であっても同じような気がする。
このような姿勢が、3.11以降のビジネスの一つのあり方なのではないだろうか?
でも、本当に「お客様と向き合っているのか?」という、コトなのだ。
日曜日の新聞には、新刊や話題の書籍を紹介する頁があることが多い。
その中に、関西にある書店の営業部長さんのお話しが掲載されていた。
お話しというのは、東京国際ブックフェアで「お客様を知る力は日本一!の書店員 1500人の趣向を把握し、販売につなげる接客とは?」という講演をされた、隆祥堂書店営業部長のニ村知子さんの講演の内容だった。
今街中の書店は、イロイロな意味で岐路に立たされている。
先日も出かけた繁華街の大きな書店が閉店していて(内装改装の閉店ではない)、ガッカリしたばかりだ。
別に、その書店でなくては買いたい本がないわけでは無いし、近くには丸善などもあるので困ることは無いのだが、ファッションビル内にある書店というのは「買い物ついでに・・・」という気軽さがあり、便利だったのだ。
そして地方に行けば、昔ながらの商店街の本屋さんは商店街の衰退と共にシャッターを閉めていることが多い。
その理由の一つは、コンビニで雑誌が買えたりするコトだろうし、アマゾンのようなネットで本が買えるというのも、大きな理由だろう。
ただ、この二村さんの公演内容の記事を読むと、どれだけ特別な接客をしている訳では無いようなのだ。
違うのは「お客様と向き合う姿勢」というコトだろう。
「お客様の趣向を知り、提案をする」と言えば、「アマゾンでもやっている」と言われそうだ。
確かにアマゾンで本を検索したり購入したりすると、「この本を購入した人は、このような本にも興味を持っています」というリストが表示されたり、メールで送られてきたりする。
それはそれで、便利で親切な機能のように思えるのだが、私自身としては「余計なお節介」と感じている。
というのも、仕事で読みたい本と趣味として読みたい本はまったく違うジャンルだし、その趣向もバラバラ。
おそらく人というのは、そんな「一人十色以上の思考・趣向がある」と思っている。
そこが、アマゾンの提案の限界なのではないだろうか?
むしろその「一人十色以上」という点が、この二村さんの書店の接客の基本のように感じたのだ。
ビジネス書の常連のお客様に「リフレッシュのために、いつもと違うこんな本はいかがですか?」と、声を掛けられること。
それも「お客様の好みをある程度理解した提案」という難しさがあると思うが、「お客様が求める本は、草の根分けてでも探す」という本に対する姿勢が、常連さんたちから「的を得た、本を薦めてくれる」という言葉へと、つながるのではないだろうか?
停滞する小売りの基本的コトのように思われるかも知れないが、この「本気でお客様と向き合い、一緒に追求する」という姿勢は、どの業種であっても同じような気がする。
このような姿勢が、3.11以降のビジネスの一つのあり方なのではないだろうか?