◆『いま本当に伝えたい感動的な「日本」の力 』
』
著者は、ウクライナ兼モルドバ大使をはじめ、イギリス、インド、イスラエル、タイ、キューバでの勤務経験をもつ外交官である。その豊富な外国経験から、多くの発展途上国が共通に、日本から是非とも学び取りたいと思っていることがあるのを知ったという。それは、日本がどのようにして近代化と文化のアイデンティティを両立させながら経済的繁栄を成し遂げたがということである。世界、とくに発展途上国から見ると、日本が日本らしさを失わずに近代社会を築いたことが奇跡と見えるらしい。生活水準は向上させたいが、伝統的な人間関係や共同体も失いたくない。日本はどのようにしてこの二つを両立させることができたのか。
その秘密を著者は、日本が古くからもっている「造り変える力」にあるとみる。それは西欧文明に代表される「破壊する力」に対比される。「破壊する力」は、一神教の対立的世界観に基づく権力政治の論理であり、西洋の植民地主義にみられる弱肉強食の論理である。16世紀のスペインによるラテン・アメリカの征服が、いかに残虐な「破壊する力」を行使したか、いまさら語るまでもないだろう。
こうした西欧の「破壊する力」に対し、日本人の「造り変える力」は、能動的な破壊力や攻撃力ではなく、一見消極的で受け身にみえる。しかし結果としてとてつもない力を発揮する。それは、外来の文物を受け入れながら、そのまま導入するのではなく、日本の伝統にあった形に変えて受け入れていく力である。しかも多くの場合、元の物より優れたものに改良してしまうのである。
たとえば中国文明を受容するにしても、そのままではなく独特の「造り変え」を行った。漢字という文字の体系をそのまま受け入れるのではなく、訓読したり仮名文字を発明したりして、あくまでも日本語の体系の中で使いこなしていった。長安の都市構造を真似ながら長安にあった強固な城壁は省略した。儒教を学びながら科挙は受け入れなかった。宦官も纏足も受け入れなかった。仏教を受け入れる際も、本地垂迹説や神仏習合思想によって神道と共存する形に「造り変え」を行った。
明治以降は、あれほど熱心に物心両面にわたって西欧文明を受け入れながら、その中核をなすキリスト教の信者は、総人口の1パーセントを大きく超えることはなかった。いわゆる「和魂洋才」だが、もちろん洋魂を無視したわけではない。洋魂も洋才も日本の伝統や習慣に馴染むように「造り変えた」のである。
(なお、本ブログでも、日本でキリスト教が広まらなかった理由を何度も考察してきた。その代表的なのは以下のものである。参照されたい。→キリスト教を拒否した理由:キリスト教が広まらない日本01)
この「造り変える力」はどこから来たのか。著者はフランスの駐日大使だったポール・クローデルの言葉をかり、日本は太古の昔から文明を積み重ねてきたからこそ、欧米文化を導入しても発展することができたのだという。つまり、明治初期の日本文化の水準が欧米文化を吸収して自分なりに消化できるレベルに達していた。さらに、日本文明がすでに高度な文明だったからこそ、欧米文化に一方的に圧倒されることなく、それを上手に独自な形で摂取し、発展させることができたというのである。
確かにその通りだろうが、これだけではもう一つ大切な要素が抜け落ちていると私は思う。実はこれについても本ブログでずいぶんと考察してきた。たとえば以下の考察である。
★『日本辺境論』をこえて(1)辺境人根性に変化が
★『日本辺境論』をこえて(2)『ニッポン若者論』
★『日本辺境論』をこえて(3)『欲しがらない若者たち』
★『日本辺境論』をこえて(4)歴史的な変化が
★『日本辺境論』をこえて(5)「師」を超えてしまったら
★『日本辺境論』をこえて(6)科学技術の発信力
★『日本辺境論』をこえて(7)ポップカルチャーの発信力
★『日本辺境論』をこえて(8)日本史上初めて
★『日本辺境論』をこえて(9)現代のジャポニズム
日本は「辺境」の島国であったために、これまで「世界標準」や「普遍的な文明」を生み出すことはなかった。大陸で生まれた「世界標準」をひたすら吸収してきた。そうやって形成された日本の文化は、「受容性」を特徴としていた。それは、もっぱら「師」から学ぶ姿勢で吸収し続けることである。そうやって中国文明を吸収し、それを自分たちの伝統に添う形で洗練させ、高度に発展させてきた。異民族に侵略・征服された経験をもたない日本は、海の向こうから来るものには一種の憧れをもって接した。そして外来の優れた文物(自分たちにとってプラスになるという意味で)だけをいいとこ取りして、利用することができた。西欧諸国による侵略を免れた日本は、かつて中国文明に接したときと似たような態度で、西欧文明に憧れ、その優れたところだけ(自分たちに必要なところだけ)を吸収することができたのである。
これに対して中国やインドはどうであったか。それらはいずれも「辺境」ではなく、かつて「世界標準」を発信した誇り高き文明であった。しかも近代、西欧文明の「破壊する力」の犠牲となり、その負の面をも実感として嫌というほど知っていた。だから「辺境日本」の如き、純粋な少年が崇拝する師に憧れ、夢中で師から学び取ろうとするような姿勢は取りえなかった。師を仰ぎみる純粋な少年と、その「破壊する力」にかつての栄光を粉々に打ち砕かれた年配者とでは、その吸収力に雲泥の差があったとしても不思議ではない。
もう一度、最初の問いに戻ろう。日本人が、外来の科学や文化を日本の伝統や習慣に合わせて「造り変える力」はどこから来るのか。実は、この問いヘの答えは、本ブログが、日本文化のユニークさを8項目の視点として論じてきた、ほとんどすべての項目に関係していると思う。次回は、この8項目との関連で、日本人の「造り変える力」の秘密をさらに詳しく追ってみたい。
《参考文献》
☆ふしぎなキリスト教 (講談社現代新書)
☆古代日本列島の謎 (講談社+α文庫)
☆縄文の思考 (ちくま新書)
☆人類は「宗教」に勝てるか―一神教文明の終焉 (NHKブックス)
☆山の霊力 (講談社選書メチエ)
☆日本人はなぜ日本を愛せないのか (新潮選書)
☆森林の思考・砂漠の思考 (NHKブックス 312)
☆母性社会日本の病理 (講談社+α文庫)
著者は、ウクライナ兼モルドバ大使をはじめ、イギリス、インド、イスラエル、タイ、キューバでの勤務経験をもつ外交官である。その豊富な外国経験から、多くの発展途上国が共通に、日本から是非とも学び取りたいと思っていることがあるのを知ったという。それは、日本がどのようにして近代化と文化のアイデンティティを両立させながら経済的繁栄を成し遂げたがということである。世界、とくに発展途上国から見ると、日本が日本らしさを失わずに近代社会を築いたことが奇跡と見えるらしい。生活水準は向上させたいが、伝統的な人間関係や共同体も失いたくない。日本はどのようにしてこの二つを両立させることができたのか。
その秘密を著者は、日本が古くからもっている「造り変える力」にあるとみる。それは西欧文明に代表される「破壊する力」に対比される。「破壊する力」は、一神教の対立的世界観に基づく権力政治の論理であり、西洋の植民地主義にみられる弱肉強食の論理である。16世紀のスペインによるラテン・アメリカの征服が、いかに残虐な「破壊する力」を行使したか、いまさら語るまでもないだろう。
こうした西欧の「破壊する力」に対し、日本人の「造り変える力」は、能動的な破壊力や攻撃力ではなく、一見消極的で受け身にみえる。しかし結果としてとてつもない力を発揮する。それは、外来の文物を受け入れながら、そのまま導入するのではなく、日本の伝統にあった形に変えて受け入れていく力である。しかも多くの場合、元の物より優れたものに改良してしまうのである。
たとえば中国文明を受容するにしても、そのままではなく独特の「造り変え」を行った。漢字という文字の体系をそのまま受け入れるのではなく、訓読したり仮名文字を発明したりして、あくまでも日本語の体系の中で使いこなしていった。長安の都市構造を真似ながら長安にあった強固な城壁は省略した。儒教を学びながら科挙は受け入れなかった。宦官も纏足も受け入れなかった。仏教を受け入れる際も、本地垂迹説や神仏習合思想によって神道と共存する形に「造り変え」を行った。
明治以降は、あれほど熱心に物心両面にわたって西欧文明を受け入れながら、その中核をなすキリスト教の信者は、総人口の1パーセントを大きく超えることはなかった。いわゆる「和魂洋才」だが、もちろん洋魂を無視したわけではない。洋魂も洋才も日本の伝統や習慣に馴染むように「造り変えた」のである。
(なお、本ブログでも、日本でキリスト教が広まらなかった理由を何度も考察してきた。その代表的なのは以下のものである。参照されたい。→キリスト教を拒否した理由:キリスト教が広まらない日本01)
この「造り変える力」はどこから来たのか。著者はフランスの駐日大使だったポール・クローデルの言葉をかり、日本は太古の昔から文明を積み重ねてきたからこそ、欧米文化を導入しても発展することができたのだという。つまり、明治初期の日本文化の水準が欧米文化を吸収して自分なりに消化できるレベルに達していた。さらに、日本文明がすでに高度な文明だったからこそ、欧米文化に一方的に圧倒されることなく、それを上手に独自な形で摂取し、発展させることができたというのである。
確かにその通りだろうが、これだけではもう一つ大切な要素が抜け落ちていると私は思う。実はこれについても本ブログでずいぶんと考察してきた。たとえば以下の考察である。
★『日本辺境論』をこえて(1)辺境人根性に変化が
★『日本辺境論』をこえて(2)『ニッポン若者論』
★『日本辺境論』をこえて(3)『欲しがらない若者たち』
★『日本辺境論』をこえて(4)歴史的な変化が
★『日本辺境論』をこえて(5)「師」を超えてしまったら
★『日本辺境論』をこえて(6)科学技術の発信力
★『日本辺境論』をこえて(7)ポップカルチャーの発信力
★『日本辺境論』をこえて(8)日本史上初めて
★『日本辺境論』をこえて(9)現代のジャポニズム
日本は「辺境」の島国であったために、これまで「世界標準」や「普遍的な文明」を生み出すことはなかった。大陸で生まれた「世界標準」をひたすら吸収してきた。そうやって形成された日本の文化は、「受容性」を特徴としていた。それは、もっぱら「師」から学ぶ姿勢で吸収し続けることである。そうやって中国文明を吸収し、それを自分たちの伝統に添う形で洗練させ、高度に発展させてきた。異民族に侵略・征服された経験をもたない日本は、海の向こうから来るものには一種の憧れをもって接した。そして外来の優れた文物(自分たちにとってプラスになるという意味で)だけをいいとこ取りして、利用することができた。西欧諸国による侵略を免れた日本は、かつて中国文明に接したときと似たような態度で、西欧文明に憧れ、その優れたところだけ(自分たちに必要なところだけ)を吸収することができたのである。
これに対して中国やインドはどうであったか。それらはいずれも「辺境」ではなく、かつて「世界標準」を発信した誇り高き文明であった。しかも近代、西欧文明の「破壊する力」の犠牲となり、その負の面をも実感として嫌というほど知っていた。だから「辺境日本」の如き、純粋な少年が崇拝する師に憧れ、夢中で師から学び取ろうとするような姿勢は取りえなかった。師を仰ぎみる純粋な少年と、その「破壊する力」にかつての栄光を粉々に打ち砕かれた年配者とでは、その吸収力に雲泥の差があったとしても不思議ではない。
もう一度、最初の問いに戻ろう。日本人が、外来の科学や文化を日本の伝統や習慣に合わせて「造り変える力」はどこから来るのか。実は、この問いヘの答えは、本ブログが、日本文化のユニークさを8項目の視点として論じてきた、ほとんどすべての項目に関係していると思う。次回は、この8項目との関連で、日本人の「造り変える力」の秘密をさらに詳しく追ってみたい。
《参考文献》
☆ふしぎなキリスト教 (講談社現代新書)
☆古代日本列島の謎 (講談社+α文庫)
☆縄文の思考 (ちくま新書)
☆人類は「宗教」に勝てるか―一神教文明の終焉 (NHKブックス)
☆山の霊力 (講談社選書メチエ)
☆日本人はなぜ日本を愛せないのか (新潮選書)
☆森林の思考・砂漠の思考 (NHKブックス 312)
☆母性社会日本の病理 (講談社+α文庫)











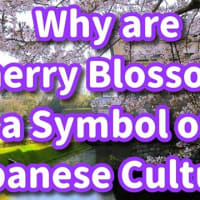
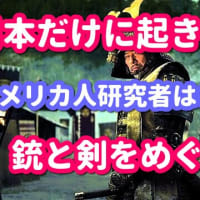

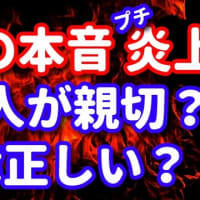




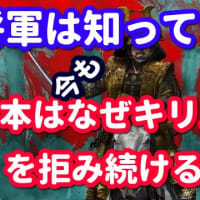







「支配されて押し付けられた」かの差だって気がするが。
日本は地理的要因も在って異民族戦争の経験が乏しく、
支配された事はほぼ無いと言っていいし。
アメリカに進駐された時には、とっくに日本の性格は確立してたワケで。