
一つ、記事をアップし忘れていました!
前後してしまい、すみません。。
引き続き、岡谷公二氏の「原始の神社をもとめて」のご紹介をさせていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
「神社」、「御嶽」、「堂」(とりわけ済州島の)の問題は、容易に説きがたい三つ巴である。
ともかく、現在済州島に残る「堂」と古代の「神社」と「御嶽」には共通するものがあり、互いに通底しあっているということだけは確かだ。
弥生人が朝鮮半島から渡来した人々だとするなら、「堂」の信仰が元であり、それが本土と南島へ波及し、その古い姿が済州島と沖縄とに残った、と考えることができれば話は簡単である。
しかしすでに見てきたように、神社の歴史は縄文まで遡る可能性があるのであり、一方、迫害をうけたことで文献や遺物が極端に乏しいため、「堂」の歴史、特に古代から中古にかけての歴史がほとんど分かっておらず、
更に沖縄の歴史も12世紀以前が闇に包まれていて、三者を時代の流れにそって比較検討することは不可能に近い。
「朝鮮南部と九州西海岸と南島とは、縄文時代の前期からひとつづきの文化の流れに属していた」とは、谷川健一氏の言葉である。
そしてこの流れに添って、済州島の「堂」や沖縄の「御嶽」と同様の、社殿のない、森だけの聖地が点々と存在するのだ。
これらの聖地は、対馬の天道山、壱岐から九州の西岸に沿って分布するヤポサ、薩摩・大隈のモイドン、種子島のガロー山、奄美の神山である。
神社には属さない、森だけの聖地は、実はこれだけではなく、他にも山口県の蓋井島(ふたおいじま)の森山、西石見の荒神森、福井県大島半島のニソの森が知られている。
これらのほとんどが、対馬暖流の洗う九州と山陰、北陸地方の沿岸部にあるのは興味深い。
「堂(だん)」とよく比較されるのは、対馬の「天道山」だ。
対馬には中世の神仏習合によって生まれた「天道信仰」という、天道法師なる神人をめぐる独特の信仰がある。
現在、対馬全域にわたって、この天道法師を祀るといわれる、天道山、天道地と称する聖地が30数か所確認されている。
これらは社殿を持たず、鬱蒼とした森や、木々の生い茂った山や藪であり、神体は自然石が置かれているだけで、何もないところもある。
原始的な神社の形式を保有している聖域ではあるが、神社ではない。
天道信仰のもっとも著名な聖地は、浅藻の八丁角である。
浅藻は豆酸(つつ)の隣村だが、明治になってから紀州の漁師たちがひらいた村で、それ以前は浜近くまで原生林であった。
海に注ぐ浅藻川という小さな川に沿って2キロメートルほど行くと、霊山・竜良山(たてらさん)=卒土山(そとさん)の麗の深い森の中に、高さ3メートルに近いピラミッド状の累石山があて、天道法師の墓と伝えている。
八丁角とは、八丁四方という意味で、この墓を中心とする方八丁=約1キロメートル四方の区域は「卒土の内(そとのうち)」と呼ばれ、「おそろしどころ」と言われて、かつては絶対侵入不可の土地であった。
現在はだいぶ原生林が取り払われ、入口のあたりには石の鳥居も建って、明るくなっているが、天道法師の墓のあたりまでくると、楠やタブや榊の古木が茂りあい、幽暗の気が漂って、今も「恐ろしどころ」の面影を残している。
ところで、この「卒土」という名称と、朝鮮半島のソトとの相似が、多くの人々の関心を引いてきた。
「鬼神を信じ、国村各一人を立てて、祭りをつかさどらしめ、これを名づけて天君となづく。また諸国には各別村あり、これを名づけてソトとなす。
大木を立て、鈴鼓をかかげ、鬼神に事う。諸亡逃れてはその中に入れば、皆これを返さず。好みて賊を作る。そのソトを建の義、浮薯に似るあり」
これは朝鮮半島南部にいた馬韓について記した「三国志」の一節で、3世紀初めごろの朝鮮半島の民間習俗をうかがい知ることのできる貴重な資料である。
「ソト」は一種のアジールで、そこへ逃げ込んだら、罪人も逮捕できなかったというのだ。
そして、「卒土」と「ソト」と、単なる音の一致だけなら偶然と考えることもできるのだが、対馬の「卒土」もまたアジールであったのである。
朝鮮通信使の一員として日本を訪れた人の記録がある。
「南北に高山あり。みな天神となづく。南は子神と称し、北は母神と称す。俗、神を尊び、家家、素撰をもってこれを祭る。山の草木、禽獣は人あえて犯すもの無し。罪人、神堂に走入すれば、すなわちこれあえて追捕せず」
天神は天道、北の母神は佐護の天道山、南の子神は豆酸(つつ)の卒土山に比定されている。
こうなるとたんなる偶然といって済ますわけにはいかない。
「ソト」は神をまつる治外法権の場所であると同時に、「ソトを立てるの義、浮しゅに似るあり」とあって、仏塔に似たものを意味するらしく、浅藻の八丁角の累石壇が連想される。
このような塁石壇は、本土の方ではあまり見かけないが、対馬にはあちこちにあり、対馬独特の風景を形作っている。
そしてこれらは、今でも韓国の田舎に行くと、至るところで出会うのである。
いずれにせよ、天道信仰に朝鮮半島の影が感じられるのは確かである。
韓国の学者も
「古代において、民族の移動とともに、彼らによって、信仰である「ソト」がもちこまれ、天道として定着したものと思われる」と書いている。
韓国に面した対馬の西岸に、主たる天道山が集中していること、「堂(だん)」山を思わせる「壇山」という山の多いことを根拠としている。
(引用ここまで)
*****
“純和風”というものが、もはや確信できなくなってしまいました。
“エキゾチックジャパン”(昔流行った言葉)が、日本の本当の姿なのでしょう。
対馬の天道信仰の地の「おそろしどころ」という庶民的な呼び名は、聞くも恐ろしげですが、歴史の深い闇の中を手探りすると、もっともっと深い闇に惹きつけられていく自分を感じます。
前に書いた対馬の天道信仰に関する記事の一つです。
アマテルとアマテラス(2)天道信仰とアメノヒボコ
対馬の地名「豆酸(つつ)」という文字が珍しいので調べてみたら、この地名の由来を書いていらっしゃる対馬に関するHPをみつけました。
HP「対馬全カタログ」
 関連記事
関連記事
「ブログ内検索」で
御嶽 8件
済州島 4件
対馬 6件
天道信仰 2件
谷川健一 1件
などあります。(重複しています)












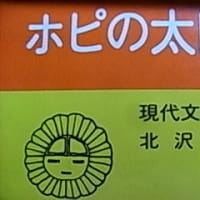

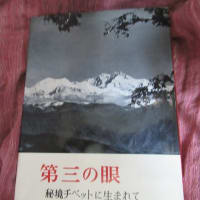







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます