
>>> ビジネス・ジャーナル『本能寺の変 431年目の真実』評
>>> 『本能寺の変 431年目の真実』珠玉の書評
>>> 『本能寺の変 431年目の真実』読者書評(続き)
No25以降はこちらへ
>>> 『本能寺の変 431年目の真実』武将ご子孫の書評
【2014年6月11日追記】No24
評論家の副島隆彦氏を御存知ですか?一言では表現しきれないかたのようです。その副島氏がメルマガに次のように書いています。お役に立てて光栄です。
---------------------------
私は、先週、4日間かけて、一冊の本を読みました。ものすごく勉強になりました。これで、日本の戦国時代ものの、歴史研究も、歴史小説が描き出す真実も、相当に進歩し、これまでの多くのウソの歴史書(ねつ造してきた古文書の数々。およびそれに加担してきた歴史学者たちの学問犯罪と責任)の悪が、満天下に、暴かれるでしょう。
その本とは、『本能寺の変 431年目の真実』(明智憲三郎著 文芸社文庫、2013年刊、720円)です。この本は、すごい。私は、この本からものすごく重要な多くの真実を学びました。
【2014年6月5日追記】No23
梅田で働く企画会社社員の日記「スタッフ日記」さんの書評です。拙著の面白さをご堪能いただけたようです。
---------------------------
先ごろ表記の題名の文庫本を購入。著者は明智光秀の子孫で、これまで世間で認識されている定説を当時の史料から証拠を洗い直し、著者の言う捜査内容(証拠と推理)の妥当性を切々と解き明かした傑作で実に面白い。
これほど忠実に史料と向き合い、調べあらゆる方面からその真実を見出していくという推理が見事で“本当にあり得る”と思わせる内容。
これまでの定説となっている怨恨説や野望説、謀反説、信長油断説、家康伊賀越え危険説、秀吉中国大返しの神業説等々がウソ!と思わずうなる明快な証拠を示し、順次解説し、謎解きをしている。どれもこれもうなずける。
歴史の見方、読み方は面白おかしく記載されている方に偏りがちで英雄を創るという点では楽かもしれない。
しかし、逆に被疑者側は一族すべて汚名を着せられたまま,終生苦しみ抜かねばならないことになりこんな辛いことはないのもまた一面である。
いつの時代も三面記事的内容は大衆受けするので人気を博し、いつのまにか真実になってしまう恐ろしさがある。
まして、歴史は勝者が作るのであるからなおさらと言える。
著者が史料を読み解き、推理し捜査解明して刊行し提起されたこの内容は、それだけに真に迫るものがある。
グイグイ引き込まれて完読したが、確かに面白い、今やベストセラーになっている模様。
歴史の綾、こうしてみると結構真実は隠され、通説が本物になってしまう。
たとえば、ここでこんなことが書かれている。
信長は光秀を見識ある人物として認め信頼し、片腕としていたとし怨恨説などどこにも史料に書かれていない、また家康と光秀は同盟を結んでおり本能寺の変が仕組まれていた、秀吉の中国大返しの速さは事前に変が知らされていたから等々実に愉快でもっともだと納得できる筋論が展開されている。
そのほか、なんと、へえ~、というような驚きの内容の連続。
ぜひ、一読されることをお勧めします。
【2014年5月24日追記】No22
「六城ラジウム」さんのブログの「ぐうの音も出ません」という題での書評です。この書評自体が、ただ一言、すごいです。
---------------------------
「本能寺の変 431年目の真実」(明智憲三郎 文芸社文庫)を読了しました。
それにしても著者の明智憲三郎氏の「歴史捜査」はすごい。
いろいろ書きたいのですが、何を書いてもこの本の衝撃がお伝えできません。
それに結末を書いてしまっては、これから読む方には申し訳ない。
だからただ一言、すごい、明智憲三郎氏の偉業であるとしかかけません。
どうか本屋で手にとって数ページ目を通してみてください。
一言感想を書けば
権力者による歴史の捏造というものがわかる
【2014年5月20日追記】No21
「夢酔_katsu」さんのつぶやきです。出版後すぐのものですが、今気付いたので掲載します。
---------------------------
明智憲三郎氏の「本能寺の変 431年目の真実」読了。名前からも想像できるように著者は明智光秀の子孫とのこと。著者の前作「本能寺の変 四二七年目の真実」も読んでいるが、この著者の推理は論理の飛躍がなく、いちいち納得できる気がするので、この本に書かれた説を真実と信じようと思う
【2014年5月15日追記】No20
「六城ラヂウム」さんの『これはすごい本だ!なぜ明智光秀が悪者とされたのか?虚構の「太閤記」』と題した書評です。まだ3分の1しかお読みでないとのことですが、その興奮が実感として現れた書評です。
---------------------------
「本能寺の変 431年目の真実」(明智憲三郎 文芸社)を読んでいます。
電車で読むのは注意した方が良いです。夢中になりすぎて私は行きと帰りで二駅も乗り過ごしてしまいました。
本書は「歴史捜査」と称して事件に対して関係者の日記といった記録と、史観との相違を徹底的に付き合わせていきます。
明智光秀の怨恨説や足利義昭による謀略説、個人の野望といった根拠が薄い「三面的な史観」を徹底的に否定していきます。
そして導き出される、豊臣秀吉による「惟任退治記(これとうたいじき)」の捏造の箇所の指摘。
【秀吉が信長の後継者としての正統性を訴えるため】
歴史は常に勝者が都合の良いように改竄していくという鉄則は日本書紀から現代まで一貫して続いているのであることがわかります。
のちに秀吉を題材とした読み物は「惟任退治記」を基としたために、光秀は野望を持つ裏切り者という紋切り型の人物像が定着してしまったのです。これが日本史を大きく歪めたことは間違いありません。
Q:明智光秀は誰の家臣であったのでしょうか。
信長の腹心でしょ?
半分正解ですが、誤りです。歴史好きなら当たり前のことなのでしょうが、私は知りませんでした。
Q:明智光秀は信長を恨んでいたのでしょうか?
信長は独断即決の豪勇な武将ですが、家臣や身の回りの女性には気配りを忘れませんでした。本能寺の変でも女官らを先に逃がすことに配慮しています。今で言う一世一代で大会社にしたオーナー社長のタイプです。
一方、光秀は明晰な頭脳で経営者からたよりにされた有名な経営コンサルタントのようです。
「信長公記」にも信長と光秀は常に相談し合う仲の良さが記されているほどです。
Q:明智光秀は信長に取り立てられる前には何であったのか?
著者の明智憲三郎氏はイエスズ会のフロイスや足利幕府の記録からも明智光秀は足軽であったことを突き止めます。
足軽とは歩兵の隊長に過ぎません。
足軽という一番低い身分の光秀が、足利義昭と信長に取り立てられていく様子を一つ一つ検証しています。
司馬遼太郎の「国盗り物語」「太閤記」でも、明智光秀を矮小化した小物としており、この二人の史観はNHKの大河ドラマで現代の我々に定着しています。(副島隆彦が指摘しているように、司馬遼太郎が日本人の歴史観を歪めた大罪人です)
Q:光秀が謀反に至る動機は何だったのか
怨恨やそそのかしといった軽い動機で明智一族の長である光秀が軽々しく大恩のある信長に弓矢を引くという「三面記事史観」ではないのです。
明智一族がどうしても信長の武力征伐と対峙しなくてはならなかった訳を明智憲三郎氏が解き明かしてくれました。本書で読んでいただくしかないでしょう。
このように今までの恨みを抱いた腹心の反逆で殺された信長という単純極まりない日本史から、武士の台頭によって続く戦乱の歴史の悲哀がずっとずっと奥深く見えてきます。
【単純にこいつ嫌いだから殺す、こいつ好きだから味方する】
そんな訳あり得ないのです。戦国大名は多数の一族郎党を抱える指導者であり、トップリーダーなのですから。
皮肉にも秀吉が光秀の人気を陥れるために(悪者として征伐したことにするため)、記録を改竄したことが明智憲三郎氏の「歴史捜査」で明るみになりました。
いままでの学校で習った日本史の薄っぺらいこと。
かたや本書の緻密な検証と立証過程を読めば読むほど、戦国武将とはどういう人達であったのか、そして家系、血筋を重んじるその重要さを思い知らされるに違いありません。
本書「本能寺の変 431年目の真実」は読了していないのですが、1/3でもこれでもかこれでもかと「歴史捜査」の結果を突きつけられて釘付けになっています。
【2014年5月14日追記】No19
amazonカスタマーレビューの「みーつけた」さんの書評です。見事に本当の「歴史に学ぶ」を実践されたようです。
---------------------------
・明智光秀という賢い人が怨みなどで信長という上司をころすか?
・千利休はなぜ切腹させられたか?
・敵方の娘である福がどうして,家光の乳母に採用されたのか。ならびに,家康はどうして家光を将軍にすることにこだわったのか。
これが,どうしても不思議だった長年の私のもやもやとした疑問でした。
これがみごと氷塊しました。なるほど,と思います。
丹念に文献にあたる著者は頭が下がります。理系畑というのは,真実の追求の欲求があるのですが,そういった姿勢が感じ取れます。まさに,歴史学者ではないからこそ,ここまでできたのではと思います。(歴史界については本書で触れており,私が思うに,そういったことは,薬害エイズ問題にも通じるところがあると思います)
もちろん,著者の「ご先祖さまの姿が知りたい」という原動力が働いてのことと思いますが,作者が切り込んで行く姿は,凄いと思いました。
そして,最後に やはり現代の政治家のいうことの本当のところを見抜く力を自分自身つけなくてはいけないな と思いました。
【2014年5月12日追記】No18
著者がこの本に注いだ全力投球のボールをここまでしっかりと打ち返してくれた書評はなかなかないです。「『自宅で立ち読み』〜Yokohama Book Cafeを主催する大嶋友秀の読書ブログ」さんの書評です。大嶋さんが拙著に受けた感動を私は同じように大嶋さんの書評からいただきました。誠に著者冥利に尽きます。
---------------------------
理屈とは力である。常識を覆す力は理屈にしか期待できない。この書は、「本能寺の変」にまつわる謎の全てを解明してくれた快書である。ここまですかっと「そうだったのか!」と思わせてくれる本などそうそうない。私は何度も感嘆の声をあげた。著者は、まるで犯人を執念深く追い詰めていくたたきあげの刑事のようでもある。だから、私は最近読んだ本の中で、いちばんわくわくしたのである。
ただ、次の瞬間にはこんな葛藤に悩まされる。この本は、「本能寺の変」の真実を語っている本である。それを読んでブログに書きたくなった。だが、何を書くのか。その真実を語ってしまえば、その本に興味を持った人に失礼になる。それこそ、本格推理の作品を語るのに、いきなり犯人を話してしまう愚におちいる。かといって、その真実にまったくふれずして、この本を読んだ興奮を伝えることができるだろうか。そんな迷いが出てきた。
だから、少しはふれながら、それができるだけわからぬようにがんばってみたい。勘のいい人なら、真実を読み込めるかもしれないが、この本の最大の醍醐味は、その真実にいたった筋道を知ることである。その精緻な論理構築をおっていくと、結論に納得するだけでなく、その過程の中に美しさも見出すことになるだろう。まるで、数学に美が存在するように、論理にも美が存在する。そんなことを感じられる論理がきらめく本と私は感じている。
私の理解している「本能寺の変」とは、繰り返し小説やらテレビで見ているものからの影響をうけているステレオタイプなものだ。中国征伐に出かける途中、信長が手勢をわずかに引き連れて本能寺にいたときに、明智光秀の謀反にあい、討ち取られてしまう。最後には、みずから本能寺に火をかけ、信長は非業の最後を迎える。明智光秀は、その後、中国地方(毛利との和睦をして)から大返りで戻ってきた秀吉との山崎に合戦に敗走し、逃げる途中の山の中で、落ち武者がりをしている農民に殺されてしまう。そんな筋書きだ。なぜ、光秀が信長を裏切るかは、信長への恨み辛みであり、信長も光秀を嫌っているからで、その二人に確執がはじけたものが本能寺の変にいたったという理解をしていた。
これは果たして正しいのか。そう問われると、答える術ももたず、ただおろおろしてしまう。明智憲三郎は、私たちの一般的にとらえている「本能寺の変」が、虚構であり誇張であり策略であったことをあきらかにしてゆく。歴史とはいつだって、その時の権力者が、みずからの正当を突き通すため書かれたご都合主義の産物である。そして、私たちが抱いている「本能寺の変」と、信長と光秀の関係なども、そのあと誰かの意図のもとにつくられたものが出発点になっている。そこに輪をかけて、物語のモチーフになる題材でもあるので、たびたび、誇張され、うそがまじり、面白おかしく、物語と仕上げられている。そんなことが、どういう文献で、どのようにされたか。誰が首謀者で、誰が実行してきたか。なぜ、それを結論づけできるのか。そんなことを、巨大なジグソーパズルを組み立てるように、明智憲三郎はそれをちまちまと合わせては確認し、これまで誰もが見ることができなかった絵を見せてくれる。
良くテレビドラマでも、映画でも、明智光秀は信長に恨みつらみがたまり、ついには裏切ることになるのだが、それを明智憲三郎は「三面記事史観」と呼び、真実のことが都合が良いように書き替えられているという。そして、それを書き替えたのはいうまでもなく、そのあと天下を掌握した男、豊臣秀吉なのである。だから後世の私たちは、秀吉がプロデュースした「ワイドショー的な説明」のもとに、「本能寺の変」を理解してしまったのである。数々の小説やドラマがそれを後押しし、私たちの「本能寺の変」のイメージはしかと固められていった。
そもそも「本能寺の変」とは何だったのか。あの用心深そうで、いつも論理的に考えただろう信長が、なぜすきだらけで本能寺にいたのか。そこはずっとしっくり来ていなかった。なぜ、明智光秀は謀反を起こしたのか。恨み辛みだけで、一国一城の大名が謀反など起こすのであろうか。そもそも、秀吉の大返りのような技がどうしてできたのか。あまりにも都合がつきすぎではないか。そんな歴史の中で、しばしば映画や小説になっていたところは、なんとも説明がつかないことが多い。だからこそ、そこに想像が広がり、創造がなされ、娯楽として面白い物語がたくさん誕生した。だが、そのことは実際に起こった出来事に肉迫することはない。そこを明智憲三郎は、まるで地面に埋まっている遺跡を発掘するようにやさしく、ていねいに、あきらめることなく、誇りを払い、その形が見えるまで気の遠くなるような作業を続けていく。
また、ひとつの視点から導かれた仮説、「唐入りする暴挙への反動」が、光秀の謀反を引き起こし、千利休の自死をいたらしめ、豊臣秀次を自死に追い込んだ。なぜ、「唐入り」だったのかー「織田信長や豊臣秀吉の唐入りは彼らの誇大妄想ではなかった。『御恩と奉公』の時代には領地の拡大が武将にとっては必然の目的であり、天下統一した後には国外に領地を求めるしかないと考えるのも必然の論理であった。唐入りは天下統一の先にある戦国武将の論理の帰結であったのだ」(p323、エピソード)ーそしてこのあとに、続く言葉が家康のことだー「徳川家康をその論理を断ち切ることによって二百六十年の平和国家を実現した」(p323、エピソード)
なんだか、たくさん書きたいのだが、書けば書くほど、少しずつその真実の断片を明かしてしまうことになりそうである。それは、避けたいと言っていたので、このあたりで今回の「立ち読み」は終えておきたい。ただ、本屋の宣伝で明かされている秘密ならば、ここで述べても構わないだろうと思うので、ひとつ私がショックを受けたことも述べておきたい。「本能寺の変」とは、信長が企てた徳川家康を暗殺するための罠であり、そこを明智光秀に討たせることになっていたと…。もちろん、歴史はそう動かなかった。真相なんだろうか。そんな問いをいただきながら、ぜひ読みすすめてほしい。そして、明智憲三郎の証明をあなたはどう判断するだろうか。いずれにしろ、真相は闇に葬られている。だからこそ、たくさんの物語ができ、あまたのドラマがつくられたのだ。さあ、431年目に明かされた真実をあなたはどう判断するのか!?
【2014年5月12日追記】No17
読書メーターに掲載されたgetsukiさんの感想です。確かに従来の本とはレベルが違うのです。
---------------------------
今までたくさんの本能寺の変に関する本は読んでいたけれど、ここまで徹底して史料を駆使して検証していなかった気がします。本能寺の変の後に天下を取った秀吉の情報操作のやり方などは、現代社会にも通用しそうな位に高度で、そりゃ騙されるよなぁと。面白かったです。
【2014年5月7日追記】No16
amazonカスタマーレビューに「日本アイン・ランド研究会」さんから「素晴らしい労作である!歴史研究の模範である!!」と題して 書評をいただきました。NHK大河ドラマ見たいですね。
---------------------------
作者は、明智光秀の子孫のひとりである。織田信長殺しには諸説あるが、私は、これが真実にもっとも近いと思う。
ネタばれになるから、詳しくは書かない。素晴らしい労作である。丹念な歴史研究の模範のような研究だ。
従来の「歴史研究」というものは、科学論文のコピペみたいなもんで、意外といい加減なもんなんだな。
軍記物みたいな物語を、歴史的資料として扱っちゃあ、あかんでしょ。
勝者が、自分の為政に都合良いように書かせた捏造歴史書(物語)を、事実の記録と思っちゃいかんでしょ。
実は、織田信長は、スペシャルに残虐非道でもなかったし、明智光秀と相性はすっごく良かった。
豊臣秀吉は、織田信長の忠犬ではなかったし、徳川家康は実は織田信長にとっては、もっとも排除したい存在だった。
そもそも織田信長ともあろう人物が、たった100人の手勢で寺なんかにいたのは、それなりの意図が信長にあったからだった。
その意図とは?
意外なことに、逆臣明智光秀の子孫は、今でもあちこちで健在である。
つまり、子孫たちを守る人々は多かったということだ…
是非とも読んでみてください。おもろいです!
NHK大河ドラマで「大沢たかお」で、「真実の明智光秀」っていうの制作されないかなあーー
【2014年5月4日追記】No15
「千のレゴリス」さんが「本能寺の変 431年目の真実が語る仰天の真相」を書いてくださいました。その中から抜粋しました。
---------------------------
本書が語る真相には、自分はかなりびっくりしたと同時にとても興奮したし、たしかにこれこそ真実にちがいない! と思わせる説得力もあります。著者はみずからの研究を「歴史捜査」と名付けていますが、まさにミステリーのようなエキサイティングな謎解き展開で、有酸素運動中はもちろん(自分の主な読書タイムは有酸素運動中)、風呂の中にも持参して、一気に読んじゃいましたよ!
最後までだらだら結論を先延ばしにせず、前半で結論を述べたうえで、後半では史実と照らし合わせながら時系列順に天正10年6月2日までの流れを丁寧に検証していく構成も非常によい。また読んでいると当然、誰もが頭に浮かんでくるであろうツッコミや疑問にも、都度都度、証拠を提示して説を補完していくという展開の仕方も著者の手練ぶりを思わせます。編集者がよかったのかもしれません。
そういうわけで、ネタバレになるので内容にはいっさい触れませんが、非常に良書です。自分、読書好きなんですが、ベストセラーものにはほとんどいつも目もくれないんですよね。だけど、これは本当にスリリングで面白かった。本書で提示される天下人や武将たちの隠された力学が真実だとすれば、信長~秀吉~家康と移行していく戦国の歴史もまったくちがって見えてくるでしょう。
【2014年4月20日追記】No14
須藤元気さんが2014年4月18日22:53にツイートしてくださいました。
---------------------------
明智憲三郎氏の「本能寺の変431年目の真実」(文芸社文庫)かなり面白いよ。司馬遼太郎で歴史を学んだ僕としては目からウロコでした。
【2014年4月15日追記】No13
ショウ井上の「黒革の投資手帳」さんから書評をいただきました。「子孫の色眼鏡」と誤解して拙著を読まない方も多いと思いますので、的確なうれしいコメントです。
---------------------------
明智憲三郎著の「本能寺の変 431年目の真実」を読んだ。
明智憲三郎氏は光秀の末裔でおられるので、単なる光秀贔屓のファンタジー小説ではないかと思って読み始めた。
しかし、なんのなんの過去の資料を丹念に読み解き、過去の定説の矛盾を論理的に解き明かしてある。
「信長公記」やイエズス会の資料、現存する数々の日記、記録を調べ上げて、当時の色眼鏡によって書かれた「惟任退治記」、「甫庵信長記」、「綿考輯録」などの矛盾を丁寧に修正している。
地道に積み上げた歴史捜査の先に、驚愕の結論が待ち受けている。
読書の春に、読むに値する一冊だ。
【2014年4月14日追記】No12
「戦国時代の魔女のブログ」さんから書評をいただきました。
---------------------------
高校生の時、明智光秀に狂っていた。生身の男性には興味はなく、ひたすら彼が好きだった。文学少女であった私は、粗野で権力志向で突き進む武将より、有職故実をはじめとする朝廷のマナーを熟知し、文芸面に優れ、洗練された光秀に憧れた。
その光秀が起こした「本能寺の変」は日本史上謎とされ、いろいろな憶測がされてきたが、近年、研究が進み、絡み合った糸が少しずつ解けてきている感がある。
著者は光秀の子・於つる丸の子孫。天正10年6月2日未明の謎を、詳細なデータ分析で書き上げた。人の心のミステリーが一点に集結した時の恐ろしさ。その時、歴史が動く!
>>> 本能寺の変:当日に発生した謎が解けるか
【2014年2月23日追記】No11
単身赴任おじさん「卓球三昧」さんのブログに書評をいただきました。途中のネタバレ部分を省略して最初と最後をご紹介します。
---------------------------
著者があの明智光秀の末裔と言うのにまずは興味惹かれます。天下の逆臣の末裔が現存していたなんてね。しかも本の内容が、歴史小説ではなく、過去に残された古文書や記録を丁寧に調査し、あの日に本当はなにがあったのかを推論する学術論文のようで、これまた興味惹かれました。
ということで、いくつか記録に残しておこうと思いますが、本の内容は膨大で緻密なので、それこそ要点のみ記載しておこうと思います。(中略(ネタバレになりますので本ブログには割愛しました))
というのが、この本の超概略ではないかと思います。すでに400年以上前の事件であるため、普段は面白おかしくドラマなどで見ている者としては、非常に新鮮な内容でした。また、最後の警鐘については、はるか昔から、歴史は繋がっているということを認識させて頂いたような気がします。本能寺の変については多くの謎と諸説が出されていますが、今回の説はなかなか説得力あると思います。
【2014年2月18日追記】No10
amazonカスタマーレビューの「福田正文」様の書評です。ありがとうございます。
---------------------------
文句なく面白いです!中盤までにざっと驚くべき説明があって、その後に精査していくのですが、そこでも愕然とする事実が浮かび上がってきて凄く面白かったです。歴史捜査という手法は説得力ありすぎ!
【2014年2月5日追記】No9
書店さんからの書評をいただきました。ブックエキスプレス・エキュート上野店さんです。
---------------------------
ズバリ「本能寺の変」の謎を解いてしまった作品だと思います。
無理のある通説、諸説にまどわされることなく、史料による裏づけを丁寧に行い、より自然に組み立てており、非常によく出来ていると思います。私はほぼすべて納得です
私の中の「本能寺の変」にまつわる「もやもや」は、これで完結しました。

【2014年1月24日追記】No9
amazonカスタマーレビューの「マリの兄」様の書評です。的確なご評価をいただきました。
---------------------------
歴史上の人物の評価は難しい。処々の経緯により、「定説」ができてしまうと、くつがえすことが難しくなる。明智光秀には豊臣秀吉の強力な反キャンペーンが存在していて、「いじめ抜かれて、ついに切れた」の人物評が定着してしまった。しかし有能な武将だからこそ、常に信長の側近であったという事実も無視できない。しかしなぜ叛いたか。
著者は、いわゆる定説に流されず、「その当時」の公家、僧侶、武将及びその家士の信書、日記など多数集め、それらを互いに突き合わせして、光秀像とその行動を再現してみせた。歴史の検証とはこのようにすべきだと学ばされた良書である。歴史マニアの必見の書と真に思う。
また、本能寺の変の前後の家康の行動が、いきいきと浮かび上がってきて、確信に満ち溢れていることにも注目されたい。
【2014年1月15日追記】No8
西洋史学に見識のある「フロイス・2」様からコメントをいただきました。西洋史学の視点から「歴史捜査」を高く評価してくださっています。
---------------------------
前著427を読んだときも、驚きの展開と同時に、論証の正確さ、裏づけの確かさなどに斬新な驚きを覚えましたが、431が単なるバージョンアップに留まらず、この手の歴史研究書としては例外的とも言えるレベルにまで深化されていることに更なる感慨を受けました。
ブログ、講演などを通して、427以来の著者のご活躍はずっと拝見してきましたが、その私にとっても期待を超える良書にめぐり会えてうれしく思っています。日本における歴史研究が方法論をあまりにも軽視し、その結果として論争の共通土壌さえ構築されていないことのもどかしさは、歴史好きの私にとっても忸怩たる思いでした。論拠も示さず「奇説」などと断罪された著者の心中は察するに余りあります。
そもそも方法論とは論証の概念化であり、研究者にとっての説明責任でもあります。
427の時から卓越した方法論であった歴史捜査を、今回は前面に出してさらに精緻な論証を展開されていることで、従来の歴史論争と称する結論のぶつけ合い、あえて言えば幼稚なけんか(これに関われば「怨恨説」に力を与えるところでしたね)と一線を画し、やっとまともな議論が出来る枠組みを独力で作られたことに感服しています。
ご存知のように私は欧米の歴史書はそこそこ読みます。だから言えるのですが、論拠の提示と資料の質・量、さらに史料の扱いに関して、日本の歴史研究とは雲泥の差があります。私見では、431は日本の歴史研究として例外的なレベルで、少なくとも本能寺に関しては初めてのワールドスタンダードであろうと感じています。
事実上すべての推論に根拠が明示され、その多くに史料的な裏づけがあり、さらに一次史料が多く含まれていること、史料・情報にかかっている潜在的なバイアスが考慮されていること、先行する研究を無批判に権威付けとして用いないこと、
これらが歴史研究の良書に必要なエレメントだと思いますが、それを高いレベルで実現されている事は間違いありません。 それ故、今まで見過ごしていたことにも気づきが得られました。
ひとつだけ例を挙げると、私は日本の歴史研究の遅れは史料が少ないことも原因かと安直に考えていましたが、史料の少なさだけでなく、史料の発掘努力の無さこそ問題なのではないかと…、これは特に「愛宕百韻」の解明を再読して感じた次第です。
【2014年1月14日追記】No7
「アフィシオナード!」さんも「子孫」でマイナス・イメージを抱き、読んで「歴史捜査」に納得していただいたとのことです。
---------------------------
日本史の中で未だに不可解とされている事柄は多々ありますがその中でも著名なのが 本能寺の変 ですよね。
現在、信じられていることは 織田信長の家臣 明智光秀が個人的な怨みを持って信長に謀反を起こし織田信長を本能寺で殺害し一時的に天下を取ったが 秀吉の予想外の速さで戻ってきた中国大返しと思いのほか光秀の元に協力者が集まらずに あえなく山崎の合戦で破れ逃亡途中、竹槍で刺されて落命した という 大筋のことが流布されてます。
明智光秀の子孫である著者が この本能寺の変 自体を根本から見直し歴史調査ではなく、 事件なので 歴史捜査を長い年月をかけて捜査をした結果を記したもので
これが真実である。 と 頑迷な人でない限り納得するでしょう。
その歴史捜査は半端なくすごいのです。
参考にした文献の数はおそらく 過去最多ではないでしょうか?
歴史、とりわけ戦国時代に惹かれる人は 是非とも読んでもらいたい。
著者が明智光秀の子孫ということもあり 創作だとか読む前に思う人もいるでしょう。私も最初は どうせ先祖の汚名をすすぎたい一心で 捻じ曲げているんだろうと思っていました。
しかし この歴史調査ではなく歴史捜査という科学的な切り口と証拠物件を照らし合わせる現在で行われている犯罪捜査と同じように積み重ねていったことによる結果を突き立てられると
これこそが真実ではないか! と思った次第です。
この本を読んでも どうせ脚色だ とか思う人も中にはいるかもしれません。
そういう人は 頑迷な人なので 勝者による嘘と利権にまみれて脚色された歴史で満足していてください。
明智光秀が一時的な感情で一族郎党が路頭に迷うようなことをする人ではないのは客観的資料から光秀の人となりが記された書物が多々ある中でわかります。(浅野内匠頭とは違うんです・・・)
現在も肖像画の主が 詳しく確認をしないまま決められていて最近になって こうした科学的な捜査の目で見直しされてますね。これと同じように見直しが必要となっている歴史上の事件は多々ありそうです。
【2014年1月12日追記】No6
拙著『本能寺の変 431年目の真実』の表紙をデザインしてくださった「デザイン軒」さんの書評をFacebookで偶然見つけました。「子孫」で持たれたマイナスの先入観を、読んでいただいて完全払拭できてよかったです。
---------------------------
『本能寺の変 431年目の真実』(明智憲三郎・著/文芸社文庫社)のカバーデザインを担当させていただきました。
著者は明智光秀の末裔の方。感情的な内容かと思いきや膨大な史実を照らし合わせ、数々の矛盾点を指摘また論理的な解釈から「本能寺の変」の謎に挑みます。
歴史解明本なのにミステリーを読んでいる感があり「本能寺の変」の謎(主犯は誰か?)では今までにない、新たな答えを提示。驚嘆させらます!
【2013年1月5日追記】No4
Facebookに書き込まれたTYさん(仮名)のレビューコメントを掲載します。秀吉は家康を殺さなかったために子の代に家康の手による一族滅亡を招きました。でも、秀吉の失敗はもうひとつあった、という卓見に感服しました。
---------------------------
早すぎた豊臣秀吉の「中国大返し」が、明智光秀の謀反「本能寺の変」の破綻に繋がった。光秀は秀吉の前に敗れ「本能寺の変」は永遠に"一件落着"したかに見えた。
しかし私は思う。秀吉がこの時犯したひとつの失敗があると。
それは「明智残党狩りを徹底しなかった事」だ。
残党狩りの手を逃れた光秀の子於寉丸の子孫が、431年の時を超え「本能寺の変」の謎を1から解明していく。
解明方法は、現代の警察が行う「犯罪捜査」の手法をとるという斬新さ。それだけではない、著者は当時の公家や武家の日記等もつぶさに読み解き、「定説」と言われている事と「真実」の照合を計っている。
歴史の人物は、「ヒーロー」である前に「人間」だ。
更に誤解を恐れず書けば、有名戦国武将は今で言えば有名大企業経営者のようなものかも知れない。
大きなビジネスを動かす「人間」なら、どう動くか。
そう思いながら読んでみると、この「本能寺の変の真実」が臓腑にストンと、落ちて来るのである。
【2013年12月28日追記】No3
amazonカスタマーレビューに掲載された中野義雄様の書評を掲載いたします。この本の面白さをよく表現していただいています。多少ネタバレにご注意してお読みください。
---------------------------
天正十年五月二十四日。五月雨。「時は今あめが下なる五月かな」―
秀吉による愛宕百韻改竄の事実が見事に暴かれることを皮切りに、これまで定説とされてきたことの怪しさが次々に指摘され、本能寺の変の真実がみるみるうちに解き明かされていくのが痛快です。『信長公記』をベースに、イエズス会の資料や現存する数々の日記、記録を丹念に調べ上げ、『惟任退治記』や『甫庵信長記』、『綿考輯録』などのバグを丁寧に取り除くことで真実の像を結んでいく歴史捜査の先には、驚愕の結論が待ち受けています。
主君信長のために身を粉にして八面六臂の戦闘を繰り広げてきた光秀が、本能寺での家康討ち計画を利用して信長を討ったのはなぜか?自分の家来だった光秀が信長に抜擢されていくのを見て、藤孝が下した決断とは?光秀との打ち合わせどおりに織田軍切り崩しにかかった家康が、光秀敗死を知ってどう動いたか?光秀の信長討ちを事前に知りながらも、秀吉はなぜ信長を見限り、どうやって誰よりも上を行って頂点までのし上がったのか?信長が警戒したとおり最終勝利者となった家康が、竹千代の元服を4年も延期して家光と命名した裏には何があるのか?これまで謎とされてきたことは今回の歴史捜査で全て解決されており、もはや謎ではありません。上記のような謎解きこそがこの本の醍醐味です。また、石谷頼辰、松井康之、杉原家次、彌介、島井宗室など、これまで見向きもされなかった人物が、今後は本能寺の変を語る上で超重要人物として知られることになるでしょう。
巻末の付録は、本編を読みながら逐一流れを確認するために重宝しました。欲を言えば、主要人物の動きが一目でわかる城入りの地図があると良かったです。しかし、全体の流れを一番理解し易くするためには、やはり本書の小説化、ドラマ化でしょう。各登場人物の思惑や策謀、誤算や決断が入り乱れる極上のエンターテイメントになること必至ですし、定説を覆して真実を広く世に問う絶好の機会となります。口に指を当てて、「余は余自ら死を招いたな。」と最初に演じる役者は誰がベストだろうかと思い巡らしながら、ドラマ化される日を心待ちにしています。
【2013年12月27日追記】No2
拙著「本能寺の変 431年目の真実」のamazonカスタマーレビューに「感動の書評」が掲載されました。このようにインテリジェンスに富んだ書評はこれまで見たことがありません。その中で、研究資料としての価値をご評価をいただきました。
さらに、このレビューコメントは拙著「本能寺の変 431年目の真実」批判(明智憲三郎批判)への見事な反論ともなっています。著者が言うよりもはるかに説得力があると思います。
-----------------------
明智氏の研究の特徴は、情報の4W1Hがしっかりしていること、つまり誰がどこで、いかなる情報をどのようにして知ったのか、そのプロセスのチェックを軸にしているところです。ご本人は「捜査」という言葉を使われていますが、伝統的には「認識論」と呼ばれる議論で、認識論的に吟味することで「誤った知識」と「正しい知識」を分けていく、本来の科学的姿勢を忠実に実行するものです。
歴史関連の本には、ある史料が「権力者の書かせたもので信用できない」といいながら、筆者の主張も同じ史料を根拠にしていたりと、正直読むに耐えないものが多いですが(とくに古代史関連では)、本書はそうした凡百の本と一線を画するものです。その意味でこの本は、「研究」とは何かを知りたい大学生など、初学者にも有益でしょう。
明智氏が「蓋然性の高い」と判断して最終的に提出した「仮説」を、「明智説」のように矮小化して取り出し、他の誰かも言っているとか、あるいは他のいい加減な説と並置して紹介したりするやり方では、この本の価値が損なわれることになります。批評をする人は、この本の史料批判と推論のプロセスにフォーカスすべきでしょう。
硬いことを書いてしまいましたが、研究にとってだけでなく歴史を生きる当事者たちにとっても、どんな情報をどのタイミングで手に入れ、自分の判断・行動に結び付けるのかはきわめて重要です。その意味で本書の描き出すドラマは、当時を生きた人々の緊張感が伝わってくるほど真実味のあるものでした。
歴史には不可解な事件が数多くあります。その意味で「本能寺の変」という事件について、自分が生きているうちにここまで綿密な研究にふれることができて幸せ、と感じました。
【2013年12月24日記事】No1
「調査と防犯ハマの私立探偵バンノリサーチ横浜・神奈川 ブログ」様の書評を転載いたします。好評価ありがとうございます。ご心配なく、「言い過ぎ」ではないです! ^_−☆
-----------------------
むむむ!?
この本は何年か前に出たやつの文庫版かな?
そんな本が12月にでました。
「本能寺の変 431年目の真実」明智憲三郎著 文芸社文庫
4年程前にでた
「本能寺の変 427年目の真実」明智憲三郎著
からさらに4年間の追跡捜査を盛り込んだ本が、「本能寺の変431年目の真実」だそうです。
もちろん買って熱心に読んでしまいました。。。
読んだ感想はですね。
「前回のよりとてもわかり易く、納得できた。一番しっくりくる」
「私が疑問に思っていたことも、この本で解決しちゃった♪」
です。
歴史資料の信憑性から、その裏付けまで徹底的に調べあげ、いわば本能寺の変の真相についての調査報告書のようです。
言い過ぎかな!?(笑)
これからの歴史ドラマやNHKの大河で戦国時代をやる場合、この説でやると、おそらくみんな、
「なるほど。そうだったかもしれないな。」
と共感される作品になるでしょうね。
NHK大河でやる場合、この「本能寺の変 431年目の真実」明智憲三郎著 を元にすることをお奨めしたい。そんな内容でした。
あえてここでは内容は書きませんが、興味のある人は是非読んでみてはいかがでしょう。
------------------------
>>> 『本能寺の変 431年目の真実』珠玉の書評
>>> 『本能寺の変 431年目の真実』読者書評(続き)
No25以降はこちらへ
>>> 『本能寺の変 431年目の真実』武将ご子孫の書評
【2014年6月11日追記】No24
評論家の副島隆彦氏を御存知ですか?一言では表現しきれないかたのようです。その副島氏がメルマガに次のように書いています。お役に立てて光栄です。
---------------------------
私は、先週、4日間かけて、一冊の本を読みました。ものすごく勉強になりました。これで、日本の戦国時代ものの、歴史研究も、歴史小説が描き出す真実も、相当に進歩し、これまでの多くのウソの歴史書(ねつ造してきた古文書の数々。およびそれに加担してきた歴史学者たちの学問犯罪と責任)の悪が、満天下に、暴かれるでしょう。
その本とは、『本能寺の変 431年目の真実』(明智憲三郎著 文芸社文庫、2013年刊、720円)です。この本は、すごい。私は、この本からものすごく重要な多くの真実を学びました。
【2014年6月5日追記】No23
梅田で働く企画会社社員の日記「スタッフ日記」さんの書評です。拙著の面白さをご堪能いただけたようです。
---------------------------
先ごろ表記の題名の文庫本を購入。著者は明智光秀の子孫で、これまで世間で認識されている定説を当時の史料から証拠を洗い直し、著者の言う捜査内容(証拠と推理)の妥当性を切々と解き明かした傑作で実に面白い。
これほど忠実に史料と向き合い、調べあらゆる方面からその真実を見出していくという推理が見事で“本当にあり得る”と思わせる内容。
これまでの定説となっている怨恨説や野望説、謀反説、信長油断説、家康伊賀越え危険説、秀吉中国大返しの神業説等々がウソ!と思わずうなる明快な証拠を示し、順次解説し、謎解きをしている。どれもこれもうなずける。
歴史の見方、読み方は面白おかしく記載されている方に偏りがちで英雄を創るという点では楽かもしれない。
しかし、逆に被疑者側は一族すべて汚名を着せられたまま,終生苦しみ抜かねばならないことになりこんな辛いことはないのもまた一面である。
いつの時代も三面記事的内容は大衆受けするので人気を博し、いつのまにか真実になってしまう恐ろしさがある。
まして、歴史は勝者が作るのであるからなおさらと言える。
著者が史料を読み解き、推理し捜査解明して刊行し提起されたこの内容は、それだけに真に迫るものがある。
グイグイ引き込まれて完読したが、確かに面白い、今やベストセラーになっている模様。
歴史の綾、こうしてみると結構真実は隠され、通説が本物になってしまう。
たとえば、ここでこんなことが書かれている。
信長は光秀を見識ある人物として認め信頼し、片腕としていたとし怨恨説などどこにも史料に書かれていない、また家康と光秀は同盟を結んでおり本能寺の変が仕組まれていた、秀吉の中国大返しの速さは事前に変が知らされていたから等々実に愉快でもっともだと納得できる筋論が展開されている。
そのほか、なんと、へえ~、というような驚きの内容の連続。
ぜひ、一読されることをお勧めします。
【2014年5月24日追記】No22
「六城ラジウム」さんのブログの「ぐうの音も出ません」という題での書評です。この書評自体が、ただ一言、すごいです。
---------------------------
「本能寺の変 431年目の真実」(明智憲三郎 文芸社文庫)を読了しました。
それにしても著者の明智憲三郎氏の「歴史捜査」はすごい。
いろいろ書きたいのですが、何を書いてもこの本の衝撃がお伝えできません。
それに結末を書いてしまっては、これから読む方には申し訳ない。
だからただ一言、すごい、明智憲三郎氏の偉業であるとしかかけません。
どうか本屋で手にとって数ページ目を通してみてください。
一言感想を書けば
権力者による歴史の捏造というものがわかる
【2014年5月20日追記】No21
「夢酔_katsu」さんのつぶやきです。出版後すぐのものですが、今気付いたので掲載します。
---------------------------
明智憲三郎氏の「本能寺の変 431年目の真実」読了。名前からも想像できるように著者は明智光秀の子孫とのこと。著者の前作「本能寺の変 四二七年目の真実」も読んでいるが、この著者の推理は論理の飛躍がなく、いちいち納得できる気がするので、この本に書かれた説を真実と信じようと思う
【2014年5月15日追記】No20
「六城ラヂウム」さんの『これはすごい本だ!なぜ明智光秀が悪者とされたのか?虚構の「太閤記」』と題した書評です。まだ3分の1しかお読みでないとのことですが、その興奮が実感として現れた書評です。
---------------------------
「本能寺の変 431年目の真実」(明智憲三郎 文芸社)を読んでいます。
電車で読むのは注意した方が良いです。夢中になりすぎて私は行きと帰りで二駅も乗り過ごしてしまいました。
本書は「歴史捜査」と称して事件に対して関係者の日記といった記録と、史観との相違を徹底的に付き合わせていきます。
明智光秀の怨恨説や足利義昭による謀略説、個人の野望といった根拠が薄い「三面的な史観」を徹底的に否定していきます。
そして導き出される、豊臣秀吉による「惟任退治記(これとうたいじき)」の捏造の箇所の指摘。
【秀吉が信長の後継者としての正統性を訴えるため】
歴史は常に勝者が都合の良いように改竄していくという鉄則は日本書紀から現代まで一貫して続いているのであることがわかります。
のちに秀吉を題材とした読み物は「惟任退治記」を基としたために、光秀は野望を持つ裏切り者という紋切り型の人物像が定着してしまったのです。これが日本史を大きく歪めたことは間違いありません。
Q:明智光秀は誰の家臣であったのでしょうか。
信長の腹心でしょ?
半分正解ですが、誤りです。歴史好きなら当たり前のことなのでしょうが、私は知りませんでした。
Q:明智光秀は信長を恨んでいたのでしょうか?
信長は独断即決の豪勇な武将ですが、家臣や身の回りの女性には気配りを忘れませんでした。本能寺の変でも女官らを先に逃がすことに配慮しています。今で言う一世一代で大会社にしたオーナー社長のタイプです。
一方、光秀は明晰な頭脳で経営者からたよりにされた有名な経営コンサルタントのようです。
「信長公記」にも信長と光秀は常に相談し合う仲の良さが記されているほどです。
Q:明智光秀は信長に取り立てられる前には何であったのか?
著者の明智憲三郎氏はイエスズ会のフロイスや足利幕府の記録からも明智光秀は足軽であったことを突き止めます。
足軽とは歩兵の隊長に過ぎません。
足軽という一番低い身分の光秀が、足利義昭と信長に取り立てられていく様子を一つ一つ検証しています。
司馬遼太郎の「国盗り物語」「太閤記」でも、明智光秀を矮小化した小物としており、この二人の史観はNHKの大河ドラマで現代の我々に定着しています。(副島隆彦が指摘しているように、司馬遼太郎が日本人の歴史観を歪めた大罪人です)
Q:光秀が謀反に至る動機は何だったのか
怨恨やそそのかしといった軽い動機で明智一族の長である光秀が軽々しく大恩のある信長に弓矢を引くという「三面記事史観」ではないのです。
明智一族がどうしても信長の武力征伐と対峙しなくてはならなかった訳を明智憲三郎氏が解き明かしてくれました。本書で読んでいただくしかないでしょう。
このように今までの恨みを抱いた腹心の反逆で殺された信長という単純極まりない日本史から、武士の台頭によって続く戦乱の歴史の悲哀がずっとずっと奥深く見えてきます。
【単純にこいつ嫌いだから殺す、こいつ好きだから味方する】
そんな訳あり得ないのです。戦国大名は多数の一族郎党を抱える指導者であり、トップリーダーなのですから。
皮肉にも秀吉が光秀の人気を陥れるために(悪者として征伐したことにするため)、記録を改竄したことが明智憲三郎氏の「歴史捜査」で明るみになりました。
いままでの学校で習った日本史の薄っぺらいこと。
かたや本書の緻密な検証と立証過程を読めば読むほど、戦国武将とはどういう人達であったのか、そして家系、血筋を重んじるその重要さを思い知らされるに違いありません。
本書「本能寺の変 431年目の真実」は読了していないのですが、1/3でもこれでもかこれでもかと「歴史捜査」の結果を突きつけられて釘付けになっています。
【2014年5月14日追記】No19
amazonカスタマーレビューの「みーつけた」さんの書評です。見事に本当の「歴史に学ぶ」を実践されたようです。
---------------------------
・明智光秀という賢い人が怨みなどで信長という上司をころすか?
・千利休はなぜ切腹させられたか?
・敵方の娘である福がどうして,家光の乳母に採用されたのか。ならびに,家康はどうして家光を将軍にすることにこだわったのか。
これが,どうしても不思議だった長年の私のもやもやとした疑問でした。
これがみごと氷塊しました。なるほど,と思います。
丹念に文献にあたる著者は頭が下がります。理系畑というのは,真実の追求の欲求があるのですが,そういった姿勢が感じ取れます。まさに,歴史学者ではないからこそ,ここまでできたのではと思います。(歴史界については本書で触れており,私が思うに,そういったことは,薬害エイズ問題にも通じるところがあると思います)
もちろん,著者の「ご先祖さまの姿が知りたい」という原動力が働いてのことと思いますが,作者が切り込んで行く姿は,凄いと思いました。
そして,最後に やはり現代の政治家のいうことの本当のところを見抜く力を自分自身つけなくてはいけないな と思いました。
【2014年5月12日追記】No18
著者がこの本に注いだ全力投球のボールをここまでしっかりと打ち返してくれた書評はなかなかないです。「『自宅で立ち読み』〜Yokohama Book Cafeを主催する大嶋友秀の読書ブログ」さんの書評です。大嶋さんが拙著に受けた感動を私は同じように大嶋さんの書評からいただきました。誠に著者冥利に尽きます。
---------------------------
理屈とは力である。常識を覆す力は理屈にしか期待できない。この書は、「本能寺の変」にまつわる謎の全てを解明してくれた快書である。ここまですかっと「そうだったのか!」と思わせてくれる本などそうそうない。私は何度も感嘆の声をあげた。著者は、まるで犯人を執念深く追い詰めていくたたきあげの刑事のようでもある。だから、私は最近読んだ本の中で、いちばんわくわくしたのである。
ただ、次の瞬間にはこんな葛藤に悩まされる。この本は、「本能寺の変」の真実を語っている本である。それを読んでブログに書きたくなった。だが、何を書くのか。その真実を語ってしまえば、その本に興味を持った人に失礼になる。それこそ、本格推理の作品を語るのに、いきなり犯人を話してしまう愚におちいる。かといって、その真実にまったくふれずして、この本を読んだ興奮を伝えることができるだろうか。そんな迷いが出てきた。
だから、少しはふれながら、それができるだけわからぬようにがんばってみたい。勘のいい人なら、真実を読み込めるかもしれないが、この本の最大の醍醐味は、その真実にいたった筋道を知ることである。その精緻な論理構築をおっていくと、結論に納得するだけでなく、その過程の中に美しさも見出すことになるだろう。まるで、数学に美が存在するように、論理にも美が存在する。そんなことを感じられる論理がきらめく本と私は感じている。
私の理解している「本能寺の変」とは、繰り返し小説やらテレビで見ているものからの影響をうけているステレオタイプなものだ。中国征伐に出かける途中、信長が手勢をわずかに引き連れて本能寺にいたときに、明智光秀の謀反にあい、討ち取られてしまう。最後には、みずから本能寺に火をかけ、信長は非業の最後を迎える。明智光秀は、その後、中国地方(毛利との和睦をして)から大返りで戻ってきた秀吉との山崎に合戦に敗走し、逃げる途中の山の中で、落ち武者がりをしている農民に殺されてしまう。そんな筋書きだ。なぜ、光秀が信長を裏切るかは、信長への恨み辛みであり、信長も光秀を嫌っているからで、その二人に確執がはじけたものが本能寺の変にいたったという理解をしていた。
これは果たして正しいのか。そう問われると、答える術ももたず、ただおろおろしてしまう。明智憲三郎は、私たちの一般的にとらえている「本能寺の変」が、虚構であり誇張であり策略であったことをあきらかにしてゆく。歴史とはいつだって、その時の権力者が、みずからの正当を突き通すため書かれたご都合主義の産物である。そして、私たちが抱いている「本能寺の変」と、信長と光秀の関係なども、そのあと誰かの意図のもとにつくられたものが出発点になっている。そこに輪をかけて、物語のモチーフになる題材でもあるので、たびたび、誇張され、うそがまじり、面白おかしく、物語と仕上げられている。そんなことが、どういう文献で、どのようにされたか。誰が首謀者で、誰が実行してきたか。なぜ、それを結論づけできるのか。そんなことを、巨大なジグソーパズルを組み立てるように、明智憲三郎はそれをちまちまと合わせては確認し、これまで誰もが見ることができなかった絵を見せてくれる。
良くテレビドラマでも、映画でも、明智光秀は信長に恨みつらみがたまり、ついには裏切ることになるのだが、それを明智憲三郎は「三面記事史観」と呼び、真実のことが都合が良いように書き替えられているという。そして、それを書き替えたのはいうまでもなく、そのあと天下を掌握した男、豊臣秀吉なのである。だから後世の私たちは、秀吉がプロデュースした「ワイドショー的な説明」のもとに、「本能寺の変」を理解してしまったのである。数々の小説やドラマがそれを後押しし、私たちの「本能寺の変」のイメージはしかと固められていった。
そもそも「本能寺の変」とは何だったのか。あの用心深そうで、いつも論理的に考えただろう信長が、なぜすきだらけで本能寺にいたのか。そこはずっとしっくり来ていなかった。なぜ、明智光秀は謀反を起こしたのか。恨み辛みだけで、一国一城の大名が謀反など起こすのであろうか。そもそも、秀吉の大返りのような技がどうしてできたのか。あまりにも都合がつきすぎではないか。そんな歴史の中で、しばしば映画や小説になっていたところは、なんとも説明がつかないことが多い。だからこそ、そこに想像が広がり、創造がなされ、娯楽として面白い物語がたくさん誕生した。だが、そのことは実際に起こった出来事に肉迫することはない。そこを明智憲三郎は、まるで地面に埋まっている遺跡を発掘するようにやさしく、ていねいに、あきらめることなく、誇りを払い、その形が見えるまで気の遠くなるような作業を続けていく。
また、ひとつの視点から導かれた仮説、「唐入りする暴挙への反動」が、光秀の謀反を引き起こし、千利休の自死をいたらしめ、豊臣秀次を自死に追い込んだ。なぜ、「唐入り」だったのかー「織田信長や豊臣秀吉の唐入りは彼らの誇大妄想ではなかった。『御恩と奉公』の時代には領地の拡大が武将にとっては必然の目的であり、天下統一した後には国外に領地を求めるしかないと考えるのも必然の論理であった。唐入りは天下統一の先にある戦国武将の論理の帰結であったのだ」(p323、エピソード)ーそしてこのあとに、続く言葉が家康のことだー「徳川家康をその論理を断ち切ることによって二百六十年の平和国家を実現した」(p323、エピソード)
なんだか、たくさん書きたいのだが、書けば書くほど、少しずつその真実の断片を明かしてしまうことになりそうである。それは、避けたいと言っていたので、このあたりで今回の「立ち読み」は終えておきたい。ただ、本屋の宣伝で明かされている秘密ならば、ここで述べても構わないだろうと思うので、ひとつ私がショックを受けたことも述べておきたい。「本能寺の変」とは、信長が企てた徳川家康を暗殺するための罠であり、そこを明智光秀に討たせることになっていたと…。もちろん、歴史はそう動かなかった。真相なんだろうか。そんな問いをいただきながら、ぜひ読みすすめてほしい。そして、明智憲三郎の証明をあなたはどう判断するだろうか。いずれにしろ、真相は闇に葬られている。だからこそ、たくさんの物語ができ、あまたのドラマがつくられたのだ。さあ、431年目に明かされた真実をあなたはどう判断するのか!?
【2014年5月12日追記】No17
読書メーターに掲載されたgetsukiさんの感想です。確かに従来の本とはレベルが違うのです。
---------------------------
今までたくさんの本能寺の変に関する本は読んでいたけれど、ここまで徹底して史料を駆使して検証していなかった気がします。本能寺の変の後に天下を取った秀吉の情報操作のやり方などは、現代社会にも通用しそうな位に高度で、そりゃ騙されるよなぁと。面白かったです。
【2014年5月7日追記】No16
amazonカスタマーレビューに「日本アイン・ランド研究会」さんから「素晴らしい労作である!歴史研究の模範である!!」と題して 書評をいただきました。NHK大河ドラマ見たいですね。
---------------------------
作者は、明智光秀の子孫のひとりである。織田信長殺しには諸説あるが、私は、これが真実にもっとも近いと思う。
ネタばれになるから、詳しくは書かない。素晴らしい労作である。丹念な歴史研究の模範のような研究だ。
従来の「歴史研究」というものは、科学論文のコピペみたいなもんで、意外といい加減なもんなんだな。
軍記物みたいな物語を、歴史的資料として扱っちゃあ、あかんでしょ。
勝者が、自分の為政に都合良いように書かせた捏造歴史書(物語)を、事実の記録と思っちゃいかんでしょ。
実は、織田信長は、スペシャルに残虐非道でもなかったし、明智光秀と相性はすっごく良かった。
豊臣秀吉は、織田信長の忠犬ではなかったし、徳川家康は実は織田信長にとっては、もっとも排除したい存在だった。
そもそも織田信長ともあろう人物が、たった100人の手勢で寺なんかにいたのは、それなりの意図が信長にあったからだった。
その意図とは?
意外なことに、逆臣明智光秀の子孫は、今でもあちこちで健在である。
つまり、子孫たちを守る人々は多かったということだ…
是非とも読んでみてください。おもろいです!
NHK大河ドラマで「大沢たかお」で、「真実の明智光秀」っていうの制作されないかなあーー
【2014年5月4日追記】No15
「千のレゴリス」さんが「本能寺の変 431年目の真実が語る仰天の真相」を書いてくださいました。その中から抜粋しました。
---------------------------
本書が語る真相には、自分はかなりびっくりしたと同時にとても興奮したし、たしかにこれこそ真実にちがいない! と思わせる説得力もあります。著者はみずからの研究を「歴史捜査」と名付けていますが、まさにミステリーのようなエキサイティングな謎解き展開で、有酸素運動中はもちろん(自分の主な読書タイムは有酸素運動中)、風呂の中にも持参して、一気に読んじゃいましたよ!
最後までだらだら結論を先延ばしにせず、前半で結論を述べたうえで、後半では史実と照らし合わせながら時系列順に天正10年6月2日までの流れを丁寧に検証していく構成も非常によい。また読んでいると当然、誰もが頭に浮かんでくるであろうツッコミや疑問にも、都度都度、証拠を提示して説を補完していくという展開の仕方も著者の手練ぶりを思わせます。編集者がよかったのかもしれません。
そういうわけで、ネタバレになるので内容にはいっさい触れませんが、非常に良書です。自分、読書好きなんですが、ベストセラーものにはほとんどいつも目もくれないんですよね。だけど、これは本当にスリリングで面白かった。本書で提示される天下人や武将たちの隠された力学が真実だとすれば、信長~秀吉~家康と移行していく戦国の歴史もまったくちがって見えてくるでしょう。
【2014年4月20日追記】No14
須藤元気さんが2014年4月18日22:53にツイートしてくださいました。
---------------------------
明智憲三郎氏の「本能寺の変431年目の真実」(文芸社文庫)かなり面白いよ。司馬遼太郎で歴史を学んだ僕としては目からウロコでした。
【2014年4月15日追記】No13
ショウ井上の「黒革の投資手帳」さんから書評をいただきました。「子孫の色眼鏡」と誤解して拙著を読まない方も多いと思いますので、的確なうれしいコメントです。
---------------------------
明智憲三郎著の「本能寺の変 431年目の真実」を読んだ。
明智憲三郎氏は光秀の末裔でおられるので、単なる光秀贔屓のファンタジー小説ではないかと思って読み始めた。
しかし、なんのなんの過去の資料を丹念に読み解き、過去の定説の矛盾を論理的に解き明かしてある。
「信長公記」やイエズス会の資料、現存する数々の日記、記録を調べ上げて、当時の色眼鏡によって書かれた「惟任退治記」、「甫庵信長記」、「綿考輯録」などの矛盾を丁寧に修正している。
地道に積み上げた歴史捜査の先に、驚愕の結論が待ち受けている。
読書の春に、読むに値する一冊だ。
【2014年4月14日追記】No12
「戦国時代の魔女のブログ」さんから書評をいただきました。
---------------------------
高校生の時、明智光秀に狂っていた。生身の男性には興味はなく、ひたすら彼が好きだった。文学少女であった私は、粗野で権力志向で突き進む武将より、有職故実をはじめとする朝廷のマナーを熟知し、文芸面に優れ、洗練された光秀に憧れた。
その光秀が起こした「本能寺の変」は日本史上謎とされ、いろいろな憶測がされてきたが、近年、研究が進み、絡み合った糸が少しずつ解けてきている感がある。
著者は光秀の子・於つる丸の子孫。天正10年6月2日未明の謎を、詳細なデータ分析で書き上げた。人の心のミステリーが一点に集結した時の恐ろしさ。その時、歴史が動く!
>>> 本能寺の変:当日に発生した謎が解けるか
【2014年2月23日追記】No11
単身赴任おじさん「卓球三昧」さんのブログに書評をいただきました。途中のネタバレ部分を省略して最初と最後をご紹介します。
---------------------------
著者があの明智光秀の末裔と言うのにまずは興味惹かれます。天下の逆臣の末裔が現存していたなんてね。しかも本の内容が、歴史小説ではなく、過去に残された古文書や記録を丁寧に調査し、あの日に本当はなにがあったのかを推論する学術論文のようで、これまた興味惹かれました。
ということで、いくつか記録に残しておこうと思いますが、本の内容は膨大で緻密なので、それこそ要点のみ記載しておこうと思います。(中略(ネタバレになりますので本ブログには割愛しました))
というのが、この本の超概略ではないかと思います。すでに400年以上前の事件であるため、普段は面白おかしくドラマなどで見ている者としては、非常に新鮮な内容でした。また、最後の警鐘については、はるか昔から、歴史は繋がっているということを認識させて頂いたような気がします。本能寺の変については多くの謎と諸説が出されていますが、今回の説はなかなか説得力あると思います。
【2014年2月18日追記】No10
amazonカスタマーレビューの「福田正文」様の書評です。ありがとうございます。
---------------------------
文句なく面白いです!中盤までにざっと驚くべき説明があって、その後に精査していくのですが、そこでも愕然とする事実が浮かび上がってきて凄く面白かったです。歴史捜査という手法は説得力ありすぎ!
【2014年2月5日追記】No9
書店さんからの書評をいただきました。ブックエキスプレス・エキュート上野店さんです。
---------------------------
ズバリ「本能寺の変」の謎を解いてしまった作品だと思います。
無理のある通説、諸説にまどわされることなく、史料による裏づけを丁寧に行い、より自然に組み立てており、非常によく出来ていると思います。私はほぼすべて納得です
私の中の「本能寺の変」にまつわる「もやもや」は、これで完結しました。

【2014年1月24日追記】No9
amazonカスタマーレビューの「マリの兄」様の書評です。的確なご評価をいただきました。
---------------------------
歴史上の人物の評価は難しい。処々の経緯により、「定説」ができてしまうと、くつがえすことが難しくなる。明智光秀には豊臣秀吉の強力な反キャンペーンが存在していて、「いじめ抜かれて、ついに切れた」の人物評が定着してしまった。しかし有能な武将だからこそ、常に信長の側近であったという事実も無視できない。しかしなぜ叛いたか。
著者は、いわゆる定説に流されず、「その当時」の公家、僧侶、武将及びその家士の信書、日記など多数集め、それらを互いに突き合わせして、光秀像とその行動を再現してみせた。歴史の検証とはこのようにすべきだと学ばされた良書である。歴史マニアの必見の書と真に思う。
また、本能寺の変の前後の家康の行動が、いきいきと浮かび上がってきて、確信に満ち溢れていることにも注目されたい。
【2014年1月15日追記】No8
西洋史学に見識のある「フロイス・2」様からコメントをいただきました。西洋史学の視点から「歴史捜査」を高く評価してくださっています。
---------------------------
前著427を読んだときも、驚きの展開と同時に、論証の正確さ、裏づけの確かさなどに斬新な驚きを覚えましたが、431が単なるバージョンアップに留まらず、この手の歴史研究書としては例外的とも言えるレベルにまで深化されていることに更なる感慨を受けました。
ブログ、講演などを通して、427以来の著者のご活躍はずっと拝見してきましたが、その私にとっても期待を超える良書にめぐり会えてうれしく思っています。日本における歴史研究が方法論をあまりにも軽視し、その結果として論争の共通土壌さえ構築されていないことのもどかしさは、歴史好きの私にとっても忸怩たる思いでした。論拠も示さず「奇説」などと断罪された著者の心中は察するに余りあります。
そもそも方法論とは論証の概念化であり、研究者にとっての説明責任でもあります。
427の時から卓越した方法論であった歴史捜査を、今回は前面に出してさらに精緻な論証を展開されていることで、従来の歴史論争と称する結論のぶつけ合い、あえて言えば幼稚なけんか(これに関われば「怨恨説」に力を与えるところでしたね)と一線を画し、やっとまともな議論が出来る枠組みを独力で作られたことに感服しています。
ご存知のように私は欧米の歴史書はそこそこ読みます。だから言えるのですが、論拠の提示と資料の質・量、さらに史料の扱いに関して、日本の歴史研究とは雲泥の差があります。私見では、431は日本の歴史研究として例外的なレベルで、少なくとも本能寺に関しては初めてのワールドスタンダードであろうと感じています。
事実上すべての推論に根拠が明示され、その多くに史料的な裏づけがあり、さらに一次史料が多く含まれていること、史料・情報にかかっている潜在的なバイアスが考慮されていること、先行する研究を無批判に権威付けとして用いないこと、
これらが歴史研究の良書に必要なエレメントだと思いますが、それを高いレベルで実現されている事は間違いありません。 それ故、今まで見過ごしていたことにも気づきが得られました。
ひとつだけ例を挙げると、私は日本の歴史研究の遅れは史料が少ないことも原因かと安直に考えていましたが、史料の少なさだけでなく、史料の発掘努力の無さこそ問題なのではないかと…、これは特に「愛宕百韻」の解明を再読して感じた次第です。
【2014年1月14日追記】No7
「アフィシオナード!」さんも「子孫」でマイナス・イメージを抱き、読んで「歴史捜査」に納得していただいたとのことです。
---------------------------
日本史の中で未だに不可解とされている事柄は多々ありますがその中でも著名なのが 本能寺の変 ですよね。
現在、信じられていることは 織田信長の家臣 明智光秀が個人的な怨みを持って信長に謀反を起こし織田信長を本能寺で殺害し一時的に天下を取ったが 秀吉の予想外の速さで戻ってきた中国大返しと思いのほか光秀の元に協力者が集まらずに あえなく山崎の合戦で破れ逃亡途中、竹槍で刺されて落命した という 大筋のことが流布されてます。
明智光秀の子孫である著者が この本能寺の変 自体を根本から見直し歴史調査ではなく、 事件なので 歴史捜査を長い年月をかけて捜査をした結果を記したもので
これが真実である。 と 頑迷な人でない限り納得するでしょう。
その歴史捜査は半端なくすごいのです。
参考にした文献の数はおそらく 過去最多ではないでしょうか?
歴史、とりわけ戦国時代に惹かれる人は 是非とも読んでもらいたい。
著者が明智光秀の子孫ということもあり 創作だとか読む前に思う人もいるでしょう。私も最初は どうせ先祖の汚名をすすぎたい一心で 捻じ曲げているんだろうと思っていました。
しかし この歴史調査ではなく歴史捜査という科学的な切り口と証拠物件を照らし合わせる現在で行われている犯罪捜査と同じように積み重ねていったことによる結果を突き立てられると
これこそが真実ではないか! と思った次第です。
この本を読んでも どうせ脚色だ とか思う人も中にはいるかもしれません。
そういう人は 頑迷な人なので 勝者による嘘と利権にまみれて脚色された歴史で満足していてください。
明智光秀が一時的な感情で一族郎党が路頭に迷うようなことをする人ではないのは客観的資料から光秀の人となりが記された書物が多々ある中でわかります。(浅野内匠頭とは違うんです・・・)
現在も肖像画の主が 詳しく確認をしないまま決められていて最近になって こうした科学的な捜査の目で見直しされてますね。これと同じように見直しが必要となっている歴史上の事件は多々ありそうです。
【2014年1月12日追記】No6
拙著『本能寺の変 431年目の真実』の表紙をデザインしてくださった「デザイン軒」さんの書評をFacebookで偶然見つけました。「子孫」で持たれたマイナスの先入観を、読んでいただいて完全払拭できてよかったです。
---------------------------
『本能寺の変 431年目の真実』(明智憲三郎・著/文芸社文庫社)のカバーデザインを担当させていただきました。
著者は明智光秀の末裔の方。感情的な内容かと思いきや膨大な史実を照らし合わせ、数々の矛盾点を指摘また論理的な解釈から「本能寺の変」の謎に挑みます。
歴史解明本なのにミステリーを読んでいる感があり「本能寺の変」の謎(主犯は誰か?)では今までにない、新たな答えを提示。驚嘆させらます!
【2013年1月5日追記】No4
Facebookに書き込まれたTYさん(仮名)のレビューコメントを掲載します。秀吉は家康を殺さなかったために子の代に家康の手による一族滅亡を招きました。でも、秀吉の失敗はもうひとつあった、という卓見に感服しました。
---------------------------
早すぎた豊臣秀吉の「中国大返し」が、明智光秀の謀反「本能寺の変」の破綻に繋がった。光秀は秀吉の前に敗れ「本能寺の変」は永遠に"一件落着"したかに見えた。
しかし私は思う。秀吉がこの時犯したひとつの失敗があると。
それは「明智残党狩りを徹底しなかった事」だ。
残党狩りの手を逃れた光秀の子於寉丸の子孫が、431年の時を超え「本能寺の変」の謎を1から解明していく。
解明方法は、現代の警察が行う「犯罪捜査」の手法をとるという斬新さ。それだけではない、著者は当時の公家や武家の日記等もつぶさに読み解き、「定説」と言われている事と「真実」の照合を計っている。
歴史の人物は、「ヒーロー」である前に「人間」だ。
更に誤解を恐れず書けば、有名戦国武将は今で言えば有名大企業経営者のようなものかも知れない。
大きなビジネスを動かす「人間」なら、どう動くか。
そう思いながら読んでみると、この「本能寺の変の真実」が臓腑にストンと、落ちて来るのである。
【2013年12月28日追記】No3
amazonカスタマーレビューに掲載された中野義雄様の書評を掲載いたします。この本の面白さをよく表現していただいています。多少ネタバレにご注意してお読みください。
---------------------------
天正十年五月二十四日。五月雨。「時は今あめが下なる五月かな」―
秀吉による愛宕百韻改竄の事実が見事に暴かれることを皮切りに、これまで定説とされてきたことの怪しさが次々に指摘され、本能寺の変の真実がみるみるうちに解き明かされていくのが痛快です。『信長公記』をベースに、イエズス会の資料や現存する数々の日記、記録を丹念に調べ上げ、『惟任退治記』や『甫庵信長記』、『綿考輯録』などのバグを丁寧に取り除くことで真実の像を結んでいく歴史捜査の先には、驚愕の結論が待ち受けています。
主君信長のために身を粉にして八面六臂の戦闘を繰り広げてきた光秀が、本能寺での家康討ち計画を利用して信長を討ったのはなぜか?自分の家来だった光秀が信長に抜擢されていくのを見て、藤孝が下した決断とは?光秀との打ち合わせどおりに織田軍切り崩しにかかった家康が、光秀敗死を知ってどう動いたか?光秀の信長討ちを事前に知りながらも、秀吉はなぜ信長を見限り、どうやって誰よりも上を行って頂点までのし上がったのか?信長が警戒したとおり最終勝利者となった家康が、竹千代の元服を4年も延期して家光と命名した裏には何があるのか?これまで謎とされてきたことは今回の歴史捜査で全て解決されており、もはや謎ではありません。上記のような謎解きこそがこの本の醍醐味です。また、石谷頼辰、松井康之、杉原家次、彌介、島井宗室など、これまで見向きもされなかった人物が、今後は本能寺の変を語る上で超重要人物として知られることになるでしょう。
巻末の付録は、本編を読みながら逐一流れを確認するために重宝しました。欲を言えば、主要人物の動きが一目でわかる城入りの地図があると良かったです。しかし、全体の流れを一番理解し易くするためには、やはり本書の小説化、ドラマ化でしょう。各登場人物の思惑や策謀、誤算や決断が入り乱れる極上のエンターテイメントになること必至ですし、定説を覆して真実を広く世に問う絶好の機会となります。口に指を当てて、「余は余自ら死を招いたな。」と最初に演じる役者は誰がベストだろうかと思い巡らしながら、ドラマ化される日を心待ちにしています。
【2013年12月27日追記】No2
拙著「本能寺の変 431年目の真実」のamazonカスタマーレビューに「感動の書評」が掲載されました。このようにインテリジェンスに富んだ書評はこれまで見たことがありません。その中で、研究資料としての価値をご評価をいただきました。
さらに、このレビューコメントは拙著「本能寺の変 431年目の真実」批判(明智憲三郎批判)への見事な反論ともなっています。著者が言うよりもはるかに説得力があると思います。
-----------------------
明智氏の研究の特徴は、情報の4W1Hがしっかりしていること、つまり誰がどこで、いかなる情報をどのようにして知ったのか、そのプロセスのチェックを軸にしているところです。ご本人は「捜査」という言葉を使われていますが、伝統的には「認識論」と呼ばれる議論で、認識論的に吟味することで「誤った知識」と「正しい知識」を分けていく、本来の科学的姿勢を忠実に実行するものです。
歴史関連の本には、ある史料が「権力者の書かせたもので信用できない」といいながら、筆者の主張も同じ史料を根拠にしていたりと、正直読むに耐えないものが多いですが(とくに古代史関連では)、本書はそうした凡百の本と一線を画するものです。その意味でこの本は、「研究」とは何かを知りたい大学生など、初学者にも有益でしょう。
明智氏が「蓋然性の高い」と判断して最終的に提出した「仮説」を、「明智説」のように矮小化して取り出し、他の誰かも言っているとか、あるいは他のいい加減な説と並置して紹介したりするやり方では、この本の価値が損なわれることになります。批評をする人は、この本の史料批判と推論のプロセスにフォーカスすべきでしょう。
硬いことを書いてしまいましたが、研究にとってだけでなく歴史を生きる当事者たちにとっても、どんな情報をどのタイミングで手に入れ、自分の判断・行動に結び付けるのかはきわめて重要です。その意味で本書の描き出すドラマは、当時を生きた人々の緊張感が伝わってくるほど真実味のあるものでした。
歴史には不可解な事件が数多くあります。その意味で「本能寺の変」という事件について、自分が生きているうちにここまで綿密な研究にふれることができて幸せ、と感じました。
【2013年12月24日記事】No1
「調査と防犯ハマの私立探偵バンノリサーチ横浜・神奈川 ブログ」様の書評を転載いたします。好評価ありがとうございます。ご心配なく、「言い過ぎ」ではないです! ^_−☆
-----------------------
むむむ!?
この本は何年か前に出たやつの文庫版かな?
そんな本が12月にでました。
「本能寺の変 431年目の真実」明智憲三郎著 文芸社文庫
4年程前にでた
「本能寺の変 427年目の真実」明智憲三郎著
からさらに4年間の追跡捜査を盛り込んだ本が、「本能寺の変431年目の真実」だそうです。
もちろん買って熱心に読んでしまいました。。。
読んだ感想はですね。
「前回のよりとてもわかり易く、納得できた。一番しっくりくる」
「私が疑問に思っていたことも、この本で解決しちゃった♪」
です。
歴史資料の信憑性から、その裏付けまで徹底的に調べあげ、いわば本能寺の変の真相についての調査報告書のようです。
言い過ぎかな!?(笑)
これからの歴史ドラマやNHKの大河で戦国時代をやる場合、この説でやると、おそらくみんな、
「なるほど。そうだったかもしれないな。」
と共感される作品になるでしょうね。
NHK大河でやる場合、この「本能寺の変 431年目の真実」明智憲三郎著 を元にすることをお奨めしたい。そんな内容でした。
あえてここでは内容は書きませんが、興味のある人は是非読んでみてはいかがでしょう。
------------------------
 | 【文庫】 本能寺の変 431年目の真実 (文芸社文庫 あ 5-1) |
| クリエーター情報なし | |
| 文芸社 |










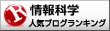















先日、Amazonに新著の書評を書き込んだマーシーズです。思い切って内容紹介は他の方にゆだね、方法論の秀逸さを強調しましたが、拙文を好意的に受け止めていただけてホッとしております。
私の書き込みとは無関係に、ものすごい売れ行きではないでしょうか。ちょっと早く売れすぎて、アマゾンが品切れ状態なのが残念。お正月にこの本をこたつで読もうと楽しみにされていた方も少なくないでしょうから。
私は、昨年明智様の岐阜の講演を聴いた後で一度、ここにも何か書いた覚えがあります。その後、名古屋在住なのに名古屋講演は聞きに行けず、多忙にかまけてすっかりご無沙汰しておりました。
今回の文庫版、読み終えて驚いたのは前著からの研究の進化です。このブログ上でのやりとりも一応フォローしているつもりでしたので、失礼ながらそれを再確認するくらいの目的で手に取りましたが、期待をはるかに越えた完成度でした。自分がこの3、4年間のあいだにどのくらい進歩しただろう、と考えると恥ずかしくなります。
私は歴史学が専門ではないし、残念ながら作家でもありませんが、この本を読んでいると各場面を脚本化してみたい欲求にかられました。今後、そうした波紋も広がっていくことを楽しみにしております。
私にお手伝いできるのは、大学のフレッシュマンセミナーでこの本を手本として紹介することくらいですが、今後ともよろしくお願いいたします。
それではよいお年を。
自説を強固にお持ちの方は拙著を読んでもなかなかご理解いただけないようですが(それも一面で仕方のないことではあるのですが)、そのような方に申し上げたかったのは正に「批評をする人は、この本の史料批判と推論のプロセスにフォーカスすべきでしょう」というお言葉でした。
「本能寺の変」については「これで解ききった」と思っていますが、あくまで検事調書のレベルです。「なぜ信長は光秀をあれほど信頼していたのか」「光秀はなぜあれほど急速に出世することができたのか」など、もっと深層を流れていた真実を知りたいと思っています。
まだまだ先は長いですが引き続き頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
よいお年をお迎えください。
本屋さんに注文します!例の物有り難う御座いました!
著書「本能寺の変431年目の真実」拝読致しました。
多くの史料から紡ぎ出された独自の解釈、いちいち頷かされました。
何が真実かは僕には判りませんが、
光秀は無計画な謀反を起こす愚かな人物でない事は確かです。
これからもさらなるご活躍をお祈りしております。
ちなみに…
僕は先日真保裕一さんの「覇王の番人」も読んだのですが、
明智さんと真保さんとはお付き合いがおありなのでしょうか?
解釈がかなりの部分で似通っていると感じましたので
個人的興味でお尋ねさせて頂きました。
差し支えなければ…
失礼致します。
真保裕一さんとは残念ながらお付き合いがございません。垣根涼介さんには「光秀の定理」、伊東潤さんには「王になろうとした男」に拙著(前著『本能寺の変 四二七年目の真実』)の解明した真実の一部を採用していただきました。
以前、「似ている」という情報があり、真保裕一さんも同様かと思って確認してみたら「覇王の番人」の方が拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』より五ケ月ほど出版が早かったです。その際に内容も拾い読みしてみましたが、あまり似ている印象は受けませんでした。
歴史の中での真実は実際に見たことと違い書物、文献といった物でしか推測できないのが現実であろうと思います。本書のように数多くの資料を照らし合わせ矛盾点を追及し真実であろう点を導き出されている点では私のような無知な人間にも解りやすく、これまでの自分が持っていた明智光秀という人物に対する人物観も大きく変わった気がします。
福知山では明智光秀は智将として語られています。この地に住むものとして本当の真実が解ったような気がします。
本自体はとても面白く拝読いたしました。
しかし、以下の点について、本書のストーリーでは明らかに不自然というか不合理な矛盾が残っていると思います。
①家康が信忠を打つという計画が無謀である。
堺にいた家康の供回りは30人ほどです。信忠には100人~500人と言われる馬廻り衆が同行していたとされ、いくら家康が四天王を始め精鋭を揃えていたとしても、信忠を打つという計画は無謀すぎます。
このような無謀な計画を慎重な光秀と家康が立てたのでしょうか。
②なぜ家康は信忠が京都にいることを知らせなかったのか。
信忠は堺から、予定を変更して妙覚寺に入りました。もし家康が光秀と結託して、信忠を打つつもりであれば、当然信忠の動きは監視していたでしょう。それならば、信忠が堺を出たことを逐一光秀に伝えるはずです。
ところが、光秀は全く信忠の動きを察知していなかったというのです。これは明らかに不自然です。
③なぜ家康は伊賀越をしたのか。
光秀と家康が結託していたから、家康は伊賀越を難なく成功させたと本書には書かれています。
しかし、そもそも光秀と家康が結託しているのなら、なぜ、家康はわざわざ堺から岡崎に戻ったのでしょう。
クーデターを成功させるなら、そのまま堺に残って光秀と合流するほうがよほど合理的です。岡崎には本田作左衛門等が残留していましたので、彼らに兵を引きさせ上洛させれば良かったのではないでしょうか。
秀吉の大返しが予想外だったと言われますが、当時の畿内には、池田、中川といった摂津勢を始め、蒲生、細川、伊勢の信孝と敵とも味方とも分からぬ連中がいたのですから、光秀、家康はなにより、畿内の制圧を急ぐべきでした。信濃攻めなどしている暇はありません。
謀反を知っていたにしては、家康の動きは遅すぎるのです。
④家康、幽斎、秀吉で秘密を共有していたとはいえない。
家康と、細川幽斎、秀吉で秘密を共有し三者の利益を守っていたということですが、その後の小牧長久手の戦いで秀吉、家康両者が対立していることの説明がつきません。
また、豊家滅亡後にもその秘密を家康が守る理由がありません。家康が明智を再興させたということですが、かつての盟友である光秀の名誉を回復させるための取り組みが一切ないのです。
豊家を滅ぼした後に、本当は本能寺の変は信長が自分を殺そうとしていた。そこで光秀ともに返り討ちにした。ところが、秀吉に天下を簒奪されたのだ、と公にすれば良かったのではないでしょうか。
歴史は常に勝者の手の中にあるのですから。
以上の疑問について明確な答えがない限り、光秀、家康共謀説は説得的なものとは言えません。
そして、これを前提としてストーリーを進めておられる本書も歴史ロマンの域を出ないのではないでしょうか。