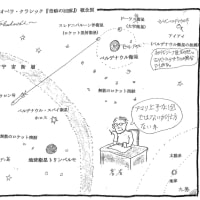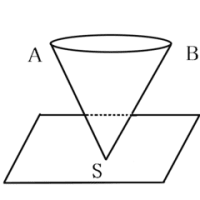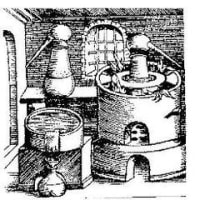知覚はどこにあるのか、と聞けば、それが視覚であれば、小学生でさえ、眼球にあると答えるだろう。聴こえるのはどこかと聞けば、耳と答えるに違いない。
ところが、ベルクソンが知覚はその対象があるところにある、本を読んでいれば本に、テレビを見ていればテレビの画面に、としか言えないと答えるのだから、戸惑ってしまう。それを奇異と感じられなくなれば、ベルクソン哲学のかなり部分がわかってきたと言えるかも知れない。
反省してみれば、ベルクソンの答えは、ごく自然なことがわかる。眼球の所在を知らない人間がいるとすれば、ただ見えるだけが事実なのだから、見える対象に視覚はある、対象に張り付くように視覚があると言うだろう。眼球は、眼球を知った後の説明に過ぎないのだ。見えるという事実と眼球は原因と結果の関係にない。耳の聴覚や舌の味覚にしても同じである。
正確には、眼球は「見える」ための補助的な器官なのだ。それは意識についても同じだ。意識は脳にあると一般には言うであろう。ベルクソンは繰り返して、意識は脳にあるのではないときっぱりと答えている。
「正確に言うと脳は思考・感情・意識の器官ではありません。そうではなくて、脳は意識・感情・思考が現実の生活に向けていられるようにし、その結果として、効果的な行動が出来るようにしているのです。お望みならば、脳は生への注意の器官であると言っておきましょう」(『精神のエネルギー』宇波彰訳・レグルス文庫・61頁)
現在の脳科学者の多くはベルクソンに同調している。いや、ベルクソンは、「知覚はどこにあるか」という問題の立て方が間違っていると答えるかもしれない。
「どこ」は一般に所在の位置を示唆しており、固定した場所を求めているかに見える。本来、場所にないもの、流動的なもの、循環するものに、誘導尋問のような問いは不当なのである。(以下、知覚をそのもっとも端的な知覚器官である視覚と読み替えると理解しやすいと思われる。)
説明的になるが、基礎的な確認は必要である。
まず、物質的な対象をなす切れ目のない物質世界がある。それは固定したものでなく、イマージュとして作用と反作用によって成り立っている。そのイマージュを私たちは物質世界として知覚する。生物である人間は、学習と記憶によって、おのれが生きるのに都合がいいように、あるいは、おのれにとって有効であるように、その生涯と生活をかけて、物理世界のイマージュから分割して像を結び作り上げる。その手段として機能するのが知覚機能である。人間と蝿では利害が違うのだから知覚も当然違うであろう。
したがって、人間の知覚イマージュは、外界の全体であるべき物理世界のイマージュとその広がりを同じくするとは言えない。
ところが、ベルクソンが知覚はその対象があるところにある、本を読んでいれば本に、テレビを見ていればテレビの画面に、としか言えないと答えるのだから、戸惑ってしまう。それを奇異と感じられなくなれば、ベルクソン哲学のかなり部分がわかってきたと言えるかも知れない。
反省してみれば、ベルクソンの答えは、ごく自然なことがわかる。眼球の所在を知らない人間がいるとすれば、ただ見えるだけが事実なのだから、見える対象に視覚はある、対象に張り付くように視覚があると言うだろう。眼球は、眼球を知った後の説明に過ぎないのだ。見えるという事実と眼球は原因と結果の関係にない。耳の聴覚や舌の味覚にしても同じである。
正確には、眼球は「見える」ための補助的な器官なのだ。それは意識についても同じだ。意識は脳にあると一般には言うであろう。ベルクソンは繰り返して、意識は脳にあるのではないときっぱりと答えている。
「正確に言うと脳は思考・感情・意識の器官ではありません。そうではなくて、脳は意識・感情・思考が現実の生活に向けていられるようにし、その結果として、効果的な行動が出来るようにしているのです。お望みならば、脳は生への注意の器官であると言っておきましょう」(『精神のエネルギー』宇波彰訳・レグルス文庫・61頁)
現在の脳科学者の多くはベルクソンに同調している。いや、ベルクソンは、「知覚はどこにあるか」という問題の立て方が間違っていると答えるかもしれない。
「どこ」は一般に所在の位置を示唆しており、固定した場所を求めているかに見える。本来、場所にないもの、流動的なもの、循環するものに、誘導尋問のような問いは不当なのである。(以下、知覚をそのもっとも端的な知覚器官である視覚と読み替えると理解しやすいと思われる。)
説明的になるが、基礎的な確認は必要である。
まず、物質的な対象をなす切れ目のない物質世界がある。それは固定したものでなく、イマージュとして作用と反作用によって成り立っている。そのイマージュを私たちは物質世界として知覚する。生物である人間は、学習と記憶によって、おのれが生きるのに都合がいいように、あるいは、おのれにとって有効であるように、その生涯と生活をかけて、物理世界のイマージュから分割して像を結び作り上げる。その手段として機能するのが知覚機能である。人間と蝿では利害が違うのだから知覚も当然違うであろう。
したがって、人間の知覚イマージュは、外界の全体であるべき物理世界のイマージュとその広がりを同じくするとは言えない。