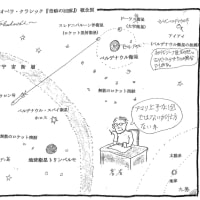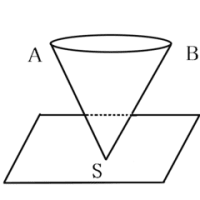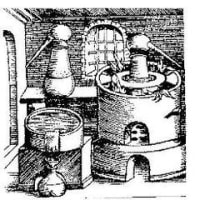フロイトの『マゾヒズムの経済論的問題』を読む。小論文だが、生の欲動(エロス)とそれに対立する死の欲動(タナトス)の関係について論じた最重要な論考だと思った。
以下ほんの抜粋「リビドーは、この破壊欲動(死の欲動のこと=タナトス)を無害なものにする役割を果たす」「そのために破壊欲動をできるだけ外部に向けようとする」「この欲動の一部が性的機能のために向けられ、ここで重要な役割を果たすことになる。これが本来のサディズムである。この欲動の別の部分は、外部に振り向けられることなく、器官の内部にとどまり」「ここにリビドー的に結合される。ここに本来の性愛的なマゾヒズムを認めることが出来る」。
要約すれば、死の欲動である原サディズムとマゾヒズムは同一起原に発する。「純粋な死の欲動や生の欲動ではなく、さまざまな分量で二つの欲動が混合したものだけが生じる」。ポオに置き換えれば拡散はエロスであり、収斂はタナトス。ポオは『ユリイカ』で宇宙存在を拡散と収斂の反復と捉えて神の心臓の鼓動と称している。ジャン・ジャック・ルソーは前者を自然状態、後者を社会状態と見なしている。
人間の意識の在り方は、本来、雑念の脈絡のない不連続な記憶が線状にある。それを社会的な状況が無理矢理に自我に追い込んだのが、人間の自己意識なのだ。意識以前にフロイトがエロスとタナトスの欲動を見たのは卓見。紙を傷つけることによって、なにものかを生み出すエクリチュール(涅槃原則=メタファとして性交の後の安らぎ)のメタファと言えるが、実際は、エクリチュールはなにものをも生み出さない。そこで際限もなく持続せねばならない。エクリチュールの思想は持続の思想以外でありえない。
たが、エクリチュールという文脈の上でのタナトスの作用は、個別の嗜好の問題に過ぎないが、人類史という文盲のエクリチュールに忍び寄るタナトスの影は不気味である。
以下ほんの抜粋「リビドーは、この破壊欲動(死の欲動のこと=タナトス)を無害なものにする役割を果たす」「そのために破壊欲動をできるだけ外部に向けようとする」「この欲動の一部が性的機能のために向けられ、ここで重要な役割を果たすことになる。これが本来のサディズムである。この欲動の別の部分は、外部に振り向けられることなく、器官の内部にとどまり」「ここにリビドー的に結合される。ここに本来の性愛的なマゾヒズムを認めることが出来る」。
要約すれば、死の欲動である原サディズムとマゾヒズムは同一起原に発する。「純粋な死の欲動や生の欲動ではなく、さまざまな分量で二つの欲動が混合したものだけが生じる」。ポオに置き換えれば拡散はエロスであり、収斂はタナトス。ポオは『ユリイカ』で宇宙存在を拡散と収斂の反復と捉えて神の心臓の鼓動と称している。ジャン・ジャック・ルソーは前者を自然状態、後者を社会状態と見なしている。
人間の意識の在り方は、本来、雑念の脈絡のない不連続な記憶が線状にある。それを社会的な状況が無理矢理に自我に追い込んだのが、人間の自己意識なのだ。意識以前にフロイトがエロスとタナトスの欲動を見たのは卓見。紙を傷つけることによって、なにものかを生み出すエクリチュール(涅槃原則=メタファとして性交の後の安らぎ)のメタファと言えるが、実際は、エクリチュールはなにものをも生み出さない。そこで際限もなく持続せねばならない。エクリチュールの思想は持続の思想以外でありえない。
たが、エクリチュールという文脈の上でのタナトスの作用は、個別の嗜好の問題に過ぎないが、人類史という文盲のエクリチュールに忍び寄るタナトスの影は不気味である。