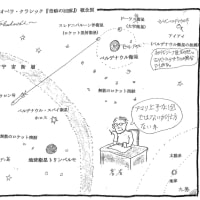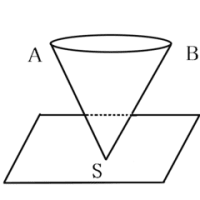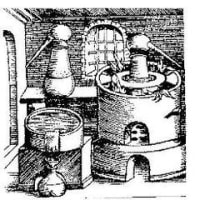いとうせいこう著『想像ラジオ』(河出文庫、一〇一三年)は、東日本大地震の津波でさらわれて山の中腹の杉の木まで運ばれ、枝に仰向けに引っかかった遺体が、ラジオのデスクジョッキーのように語り出すという、奇想天外な設定の、ベストセラーになった小説である。その小説を書いている作者Sは、大震災の五年前に最愛の恋人を事故で失って未だに心の傷は癒えていない。何でも語り合えた愛人であった。この小説はラジオのジョッキーのおしゃべりに相当する「想像ラジオ」と亡くなった愛人との対話形式の独り言の、想像力による二つの「語り」で成り立っている。いずれも死者との対話であって、一種の鎮魂の霊的な対話と言える。
その一方で、文学の本質を問うている。なぜなら、エクリチュールである文字もまた、私たちが想像力を駆使して、語りかけなければ死体と同じで、決して生きてこないから。杉の木の上の遺体も、私たちの想像力がそれに向けて語りかけ問わない限り、なにも語らない。愛人との対話でSが語る、こんな一節があった。
「僕は別に霊界の存在をここで否定したいわけじゃないんだけど、ただ、もし霊界があるなら人間絶滅の瞬間にそこは最も栄えるだろう。でも僕が言ってる死者の世界は逆だ。そこは生者がいなければ成立しない。生きている人類が全員いなくなれば、死者もいないんだ」(同書・河出文庫・一四六頁)
わたしがゴシックを付した部分「人類絶滅の瞬間」を読んで、ふと、アンドレイ・タルコフスキーの映画「サクリファイス」(犠牲とか生け贄の意味)を思い浮かべた。
この映画の冒頭、言葉を失っている少年――彼は声帯の手術を受けていて話せない――が枯れかかった松の木に父親のアルクサンデルに言われるままにバケツで運んできた水をやっている。枯れ木を生き返らそうとする幼子の繰り返される行為で始まる。
当日は父親の誕生日でもある。彼は著名な文筆家であり、妻は一世を風靡した舞台女優、二人の仲は険悪である。年頃の娘と女中一人が同居しており、ほかに通いの召使いがいて、それぞれに葛藤を抱えている。誕生日祝いに、親友の郵便配達夫と医師がやって来る。病身の少年を二階の部屋に寝かしつけて、サロンで祝いが始まろうというときに、テレビで核戦争が勃発して世界が消滅の危機にあることが告げられる。全員がパニック状態になって、無神論者のアレクサンデルでさえ神に救いを求める。ふらふらと家を出た彼は、通いの召使いマリア――家庭の内情をもっとも深く理解していると思われる――のところへやってきて救いを求める。
翌朝、報道は間違いであったことが判明する。あの前日の混乱と動揺は何であったのか。アレクサンデルは、家に誰もいないことを確認すると、火を放って全焼させる。もちろん、それがサクリファイス(神への生贄)の意味であろう。
映画の最後は、言葉を失った少年が言葉を取り戻して、たった一人で枯れ木に水をやっているシーン。心配して自転車で駆け付けたマリアが少年の無事を見届け、声をかけずにそのまま引き返すところで映画は終わる。
ちなみに、タルコフスキーがこの作品についてインタビューで次のように語っていることを記しておく。ライプニッツ哲学に裏打ちされた極めて深遠な思想が表明されている。
「私が、異教徒、カトリック教徒、ロシア正教徒、あるいは単にキリスト教徒の何等かの観念や偏見を持っているかどうか知ることは、それほど重要だとはおもいません。重要なのは作品それ自体です。私の考えでは、作品は全体で判断すべきであり、そのなかには必ず含まれている矛盾を探索すべきではないのです。作品の細部は、必ずしも、芸術家の内的世界の反映ではないのです。細部同士のかかわりのなかには、芸術家の内的まなざしとは矛盾した理論が存在することもあります。この映画を撮りながら、この映画は出来るかぎり多様な観客に向けられるべきだ、と私は、確信しました」(昭和六十二年四月発行の「サクリファイス」のパンフレットより)
『想像ラジオ』の遺体が引っ掛かっている山の中腹の杉の木も、映画「サクリファイス」の海辺近くに立つ枯れた松の木も、いずれも同じ、作家の執筆のペンであり、書きつつ読み、読みつつ書く、エクリチュールの象徴なのではないか。
もちろん、ペンで書くためには、紙が必要だ。水は紙の象徴である。いや、逆に、紙こそ水の象徴かもしれない。ついでながら、「サクリファイス」(生贄)のための火は、逆さにしたペンの形であり、上空の世界へ向けてのエクリチュールのペンの象徴でもあることを指摘しておかねばならない。「古代ユダヤ教で生け贄の動物を祭壇で焼き、神に捧げる儀式」、いわゆる燔祭(はんさい)である。
エクリチュールの犠牲に捧げられる家は、あらゆる外形的な枠組み――惰性的な習慣や怠慢やエゴイズム、あるいは物質的富を意味し象徴していよう。
誤解がないように、強調しておきたい。ペンと紙をエクリチュールの象徴として、そこにすべてを思弁的に帰すことではなく、私たちが、芸術に接すると言うことが、ただ、創作にかかわらない傍観者として読むのではなく、ペンと紙で執筆する、無から有を作り上げる、作者自身の想像力の原点から、捉え問い直すことにほかならないこと。たとえそれが多くの犠牲者をもたらした大震災や最終戦争を扱った小説であったとしても。(了)
その一方で、文学の本質を問うている。なぜなら、エクリチュールである文字もまた、私たちが想像力を駆使して、語りかけなければ死体と同じで、決して生きてこないから。杉の木の上の遺体も、私たちの想像力がそれに向けて語りかけ問わない限り、なにも語らない。愛人との対話でSが語る、こんな一節があった。
「僕は別に霊界の存在をここで否定したいわけじゃないんだけど、ただ、もし霊界があるなら人間絶滅の瞬間にそこは最も栄えるだろう。でも僕が言ってる死者の世界は逆だ。そこは生者がいなければ成立しない。生きている人類が全員いなくなれば、死者もいないんだ」(同書・河出文庫・一四六頁)
わたしがゴシックを付した部分「人類絶滅の瞬間」を読んで、ふと、アンドレイ・タルコフスキーの映画「サクリファイス」(犠牲とか生け贄の意味)を思い浮かべた。
この映画の冒頭、言葉を失っている少年――彼は声帯の手術を受けていて話せない――が枯れかかった松の木に父親のアルクサンデルに言われるままにバケツで運んできた水をやっている。枯れ木を生き返らそうとする幼子の繰り返される行為で始まる。
当日は父親の誕生日でもある。彼は著名な文筆家であり、妻は一世を風靡した舞台女優、二人の仲は険悪である。年頃の娘と女中一人が同居しており、ほかに通いの召使いがいて、それぞれに葛藤を抱えている。誕生日祝いに、親友の郵便配達夫と医師がやって来る。病身の少年を二階の部屋に寝かしつけて、サロンで祝いが始まろうというときに、テレビで核戦争が勃発して世界が消滅の危機にあることが告げられる。全員がパニック状態になって、無神論者のアレクサンデルでさえ神に救いを求める。ふらふらと家を出た彼は、通いの召使いマリア――家庭の内情をもっとも深く理解していると思われる――のところへやってきて救いを求める。
翌朝、報道は間違いであったことが判明する。あの前日の混乱と動揺は何であったのか。アレクサンデルは、家に誰もいないことを確認すると、火を放って全焼させる。もちろん、それがサクリファイス(神への生贄)の意味であろう。
映画の最後は、言葉を失った少年が言葉を取り戻して、たった一人で枯れ木に水をやっているシーン。心配して自転車で駆け付けたマリアが少年の無事を見届け、声をかけずにそのまま引き返すところで映画は終わる。
ちなみに、タルコフスキーがこの作品についてインタビューで次のように語っていることを記しておく。ライプニッツ哲学に裏打ちされた極めて深遠な思想が表明されている。
「私が、異教徒、カトリック教徒、ロシア正教徒、あるいは単にキリスト教徒の何等かの観念や偏見を持っているかどうか知ることは、それほど重要だとはおもいません。重要なのは作品それ自体です。私の考えでは、作品は全体で判断すべきであり、そのなかには必ず含まれている矛盾を探索すべきではないのです。作品の細部は、必ずしも、芸術家の内的世界の反映ではないのです。細部同士のかかわりのなかには、芸術家の内的まなざしとは矛盾した理論が存在することもあります。この映画を撮りながら、この映画は出来るかぎり多様な観客に向けられるべきだ、と私は、確信しました」(昭和六十二年四月発行の「サクリファイス」のパンフレットより)
『想像ラジオ』の遺体が引っ掛かっている山の中腹の杉の木も、映画「サクリファイス」の海辺近くに立つ枯れた松の木も、いずれも同じ、作家の執筆のペンであり、書きつつ読み、読みつつ書く、エクリチュールの象徴なのではないか。
もちろん、ペンで書くためには、紙が必要だ。水は紙の象徴である。いや、逆に、紙こそ水の象徴かもしれない。ついでながら、「サクリファイス」(生贄)のための火は、逆さにしたペンの形であり、上空の世界へ向けてのエクリチュールのペンの象徴でもあることを指摘しておかねばならない。「古代ユダヤ教で生け贄の動物を祭壇で焼き、神に捧げる儀式」、いわゆる燔祭(はんさい)である。
エクリチュールの犠牲に捧げられる家は、あらゆる外形的な枠組み――惰性的な習慣や怠慢やエゴイズム、あるいは物質的富を意味し象徴していよう。
誤解がないように、強調しておきたい。ペンと紙をエクリチュールの象徴として、そこにすべてを思弁的に帰すことではなく、私たちが、芸術に接すると言うことが、ただ、創作にかかわらない傍観者として読むのではなく、ペンと紙で執筆する、無から有を作り上げる、作者自身の想像力の原点から、捉え問い直すことにほかならないこと。たとえそれが多くの犠牲者をもたらした大震災や最終戦争を扱った小説であったとしても。(了)