――彼らは屍体になろうとする。その意志をみとめようではないか。この死人たちがめざめないように、この生ける棺桶をうち壊さないように、用心しようではないか。――(ニーチェ『ツァラトゥストラかく語りき』佐々木中訳・河出文庫七三頁)
かねてから懸案であった高橋和巳(一九三一~一九七一)の長編小説『邪宗門』(一九六六)を一読した。若い頃、法学を志したこともあって、彼の文壇デビュー作『悲の器』を何度も読んで感動した記憶があった。今でも、戦後が生んだ数少ない名作の一編という思いは変わらない。
本書、分厚い文庫本二冊にもなる一大長編を読み終わり、がっかりしたというのが率直な感想である。あれから五十年以上も経過した、私の気持ちのありようも大きく変容したことを踏まえても、期待を裏切られたと感じている。
本書『邪宗門』を未読の読者のために、ごく簡単に物語の概要を記せば、
明治期に雨後の竹の子のように発生した新興宗教の一つである〈ひのもと救霊会〉の大正期・昭和、そして戦後と、左翼運動と同様に、絶対天皇制の国家権力から激しい弾圧に遭い、施設の徹底的な破壊、幹部の検挙・投獄にめげずに、戦後までなんとか命脈を保ち、戦後、一転して、新憲法も未だ発布されない進駐軍制下の政府に反逆して無謀な武力闘争の末に殲滅される宗教団体の消息を延々と綴られる。
*
モデルに近い教団――出口王仁三郎(一八七一~一九四八)の大本教――は存在する。類似は、前半部分の外形だけといって良い。著者が、小説による思考実験と称しているように、歴史的な現実をリアリティとして踏まえながら、いわば空想的な観念小説である。読みどころは、現実の日本近代史の中で、観念的な可能性を探ることが狙いである。だが、両者の密接なつながりを保つためには、歴史のリアリティに徹しなければならず、観念的な思考に重点を移せばリアリティが失われるという背反的な関係にある。著者は、この無謀な企てを思考実験と名付けていると思われる。まず、読んでいて気になるのは、主要な登場人物ばかりでなく、人物の性格や容姿などの描写が類型的で繰り返しが多く、心理的な実在感に欠けていること。いわば膨大な固有名詞の羅列の物語である。
例えば、主人公と思われる千葉潔少年は、不幸な来歴を秘めて教団に迷い込む、死に神のような、陰鬱な性格に設定されている。登場する女性達の誰もが、彼に惹きつけられるのだが、人物像が最後まで不透明で捉えどころがない。彼は、一部の教団仲間の感化を受けて、伊勢神宮で、天皇への直訴を敢行、それに失敗した後、官憲の追求を逃れ、教団本部のある神部の街に極秘の内に舞い戻る。以降、彼が再登場するのは、京都三高のボード部のリーダーとしてである。いったいその間、宿無しの少年がどういう経過を辿ったのか、重要な形跡が描かれていない。後に、従軍したらしく、南方の戦線で捕虜の処刑に関与したにもかかわらず、そこにくわしい記述がない。敗戦後帰国、また、教団に舞い戻り、教団の権力を簒奪して教主までなる。が、彼のイニシアチブが充分に描かれていない。もともと彼は指導者というよりも参謀役なのだ。
一方のヒロインであるべき、初代教主の行徳仁二郎に甘やかされて育てられた、長女の阿礼は、ヒステリー的な傲慢な性格とエゴイスティックな行動が付与されて、著者は、やたらに胸の豊満さを強調するなど稚拙な描写に終始している。事ほどさように、すべての登場人物が、役柄と外形的な特徴――小児麻痺で足を引きずるとか、寡黙であるとか、思わせぶりな性格付け以外に、行動に至る心理を克明に描かれることはない。
教団という組織の役割に重点が置かれていて人物描写は常に後手に回っていると云えよう。じつは、組織の名称――長老会・幹事会・組織・宣教・財務・企画・機関誌・青年部・婦人部・顧問など――があるとはいえ、その実体となると雲を掴むような図式的な概念に過ぎない。さらにストーリー展開は、切り貼りのように次々と場面と登場人物が入れ替わり、その間の記述の欠落部分は、読み手の想像力に委ねられている。教団の下部組織と労働団体との提携にしても、具体的な実体となると、組織が人間を度外視して、図式的に進行しているに過ぎない。彼らの組織は、かつて集団農場や作業所、病院、植物園を保有し、布教のために都市の貧民窟での診療や瀬戸内海のレプラ隔離棟への医師派遣・果ては開拓団に参加して満州渡航、南海の玉砕の島にまで活動範囲が及ぶ。しかし、〈ひのもと救霊会〉なる教団の全国的な規模の活動諸点や信者の数なども、恣意的で捉えどころがない。
*
長大な小説の目次を挙げてみよう。いくらかの参考にはなろう。
序章・第一部――廃墟・再建会議・薪造り・疑惑と苦渋・慎ましい日常・予審決定・晦日から新年へ・保釈・病床指令・ストライキ・繭と剣・湯崎温泉・失踪・四面楚歌・公判①・諫暁・召集・公判②・死の影・宗教と生・闇から闇へ・教姉教弟・農村改革案・生(エロス)と死(タナトス)の情熱・正統と異端・暗殺・清野作戦・壊滅。
第二部――かくれ宗教・貧民窟・湖畔・本部・闇の思想・牢獄・南洋・参禅・廃者の島・再会・捕虜・西と東・感傷旅行・満蒙開拓団・特赦・産業報国会・吉報?・甘美な惑い・夢幻の能・総転向。
第三部――一九四五・虚脱と悲哀・七哀詩・死の釈放・残党・兄弟・進駐軍・姉妹・失われた時・復員・学校騒動・冬・喪中の正月・再生・不吉な前進・供養塔・世代交代・宗教裁判・節分・強制寄進・誓約・抗議デモ・突発事故・白虹・簒奪・あり得ざりし歴史・三日天下・浮城・破局・餓死・終末――は、戦後の武力闘争と敗北の部分をなしている。
掲げた章は、いずれも二つか三つの部分に区切られて構成されていて、映画の場面転換に似ている。この長編小説は、劇画のコマ割りや映画の手法に類似した章割なのだ。
人物描写も劇画的に類型化されていて、書かずもがなの常套的な心理的描写そのものが図式化されている。主役の千葉潔自体が、劇画の登場人物にふさわしい、思わせぶりなキャラクターであって、好意的に読んでも、そこに思想性を見出すのは難しい。
だが、第一部の章に「生と死の情熱」があるように、〈エロスとタナトスの欲動〉の葛藤が、大きな意味の小説の主題であり、「死」の衝動に導かれ、教団に壊滅をもたらす役割は、死に神のような千葉潔である。生の衝動を、わずかに示しているのが、教主行徳仁次郎の次女阿貴であろう。だが、存在感は、姉の阿礼と比べると極めて薄い。
教主仁二郎の獄死後の教団の混乱は、獄中で伝えられた二つの相反する遺言、教団の存続を熱望する「生」の遺言と怨念に充ちた「死」の遺言によってもたらされたといえよう。千葉は「死」の遺言の実行者なのだが、必ずしも積極的なアジテーターではなく、教団に染みこんだタナトスの衝動を顕在化させるための活動家に過ぎないと見なすことも出来る。物語の終末で、阿礼は壮絶な自殺を遂げる。一方、千葉潔は、潔い戦死を回避して、死に装束で落ち延び、餓死を選ぶのにも、つねに生者につきまとうタナトスの必然性が見える。二人の主人公にいささかの共感も覚えないのはこの文学作品の致命的な欠陥だろう。
*
私は必ずしも、この長大な小説を否定的にばかり捉えているわけではない。戦後文学を代表する陰鬱な小説群の総括として、『邪宗門』があるとすれば、後に大流行した劇画ブーム、そして今日のアニメ全盛時代の心理的な下地として、戦後文学が位置しているのではないかと疑っている。アニメ的な世界観――画一化・映像化・短絡化――に耐えがたい違和感を持っているとはいえ、劇画や映像芸術を侮るような文学的な視点にいるわけではない。
もともと死体である組織を生きかえらせる作業で組織は成り立つ。組織とは、死体なのであって、実体ではない、それは作家の執筆というエクリチュール作業に似ている。高橋和巳は『邪宗門』において、〈ひのもと救霊会〉なる組織をでっち上げるために心血を注いで書き続けたのだ。だが、エロスを代表するはずの行徳阿礼は、時代の閉塞状況の中で突破口を奪われ、そこへ、タナトスの千葉潔という著者の分身を紛れ込ませる事によって、必然的な破滅の途を選んだ。思考実験は失敗に帰した。だが、文学の両義性は、その欠陥をも前向きに捉え得るとだけ指摘しておこう。
*
ラカンの鏡像段階論を参照すると、高橋和巳の思考実験は、象徴的な脱皮を遂げることなく、精神病の様相に終わったと云えようか。(「鏡像段階においては、主体は鏡のなかの像を自らの存在として予知的に掴むことで現在の欠如を隠そうとしているに過ぎない」向井雅明『ラカン入門』一七一頁)
それも人間の一つの側面であることに変わりがない。障害者施設を襲って「彼らは生きている価値がない」と重度障害者十九名を殺害した男も実在している。もちろん、ペンで書くのと、麻薬中毒を疑われようが現実に手を下すのとの相違を承知の上でだが。
ただし、私が詩や文学に求めているのは、紙とペンで描くエクリチュールの道であって誤解を恐れずに書けば、秘教的で、ごくマイナーなものであることを断っておきたい。(了)
かねてから懸案であった高橋和巳(一九三一~一九七一)の長編小説『邪宗門』(一九六六)を一読した。若い頃、法学を志したこともあって、彼の文壇デビュー作『悲の器』を何度も読んで感動した記憶があった。今でも、戦後が生んだ数少ない名作の一編という思いは変わらない。
本書、分厚い文庫本二冊にもなる一大長編を読み終わり、がっかりしたというのが率直な感想である。あれから五十年以上も経過した、私の気持ちのありようも大きく変容したことを踏まえても、期待を裏切られたと感じている。
本書『邪宗門』を未読の読者のために、ごく簡単に物語の概要を記せば、
明治期に雨後の竹の子のように発生した新興宗教の一つである〈ひのもと救霊会〉の大正期・昭和、そして戦後と、左翼運動と同様に、絶対天皇制の国家権力から激しい弾圧に遭い、施設の徹底的な破壊、幹部の検挙・投獄にめげずに、戦後までなんとか命脈を保ち、戦後、一転して、新憲法も未だ発布されない進駐軍制下の政府に反逆して無謀な武力闘争の末に殲滅される宗教団体の消息を延々と綴られる。
*
モデルに近い教団――出口王仁三郎(一八七一~一九四八)の大本教――は存在する。類似は、前半部分の外形だけといって良い。著者が、小説による思考実験と称しているように、歴史的な現実をリアリティとして踏まえながら、いわば空想的な観念小説である。読みどころは、現実の日本近代史の中で、観念的な可能性を探ることが狙いである。だが、両者の密接なつながりを保つためには、歴史のリアリティに徹しなければならず、観念的な思考に重点を移せばリアリティが失われるという背反的な関係にある。著者は、この無謀な企てを思考実験と名付けていると思われる。まず、読んでいて気になるのは、主要な登場人物ばかりでなく、人物の性格や容姿などの描写が類型的で繰り返しが多く、心理的な実在感に欠けていること。いわば膨大な固有名詞の羅列の物語である。
例えば、主人公と思われる千葉潔少年は、不幸な来歴を秘めて教団に迷い込む、死に神のような、陰鬱な性格に設定されている。登場する女性達の誰もが、彼に惹きつけられるのだが、人物像が最後まで不透明で捉えどころがない。彼は、一部の教団仲間の感化を受けて、伊勢神宮で、天皇への直訴を敢行、それに失敗した後、官憲の追求を逃れ、教団本部のある神部の街に極秘の内に舞い戻る。以降、彼が再登場するのは、京都三高のボード部のリーダーとしてである。いったいその間、宿無しの少年がどういう経過を辿ったのか、重要な形跡が描かれていない。後に、従軍したらしく、南方の戦線で捕虜の処刑に関与したにもかかわらず、そこにくわしい記述がない。敗戦後帰国、また、教団に舞い戻り、教団の権力を簒奪して教主までなる。が、彼のイニシアチブが充分に描かれていない。もともと彼は指導者というよりも参謀役なのだ。
一方のヒロインであるべき、初代教主の行徳仁二郎に甘やかされて育てられた、長女の阿礼は、ヒステリー的な傲慢な性格とエゴイスティックな行動が付与されて、著者は、やたらに胸の豊満さを強調するなど稚拙な描写に終始している。事ほどさように、すべての登場人物が、役柄と外形的な特徴――小児麻痺で足を引きずるとか、寡黙であるとか、思わせぶりな性格付け以外に、行動に至る心理を克明に描かれることはない。
教団という組織の役割に重点が置かれていて人物描写は常に後手に回っていると云えよう。じつは、組織の名称――長老会・幹事会・組織・宣教・財務・企画・機関誌・青年部・婦人部・顧問など――があるとはいえ、その実体となると雲を掴むような図式的な概念に過ぎない。さらにストーリー展開は、切り貼りのように次々と場面と登場人物が入れ替わり、その間の記述の欠落部分は、読み手の想像力に委ねられている。教団の下部組織と労働団体との提携にしても、具体的な実体となると、組織が人間を度外視して、図式的に進行しているに過ぎない。彼らの組織は、かつて集団農場や作業所、病院、植物園を保有し、布教のために都市の貧民窟での診療や瀬戸内海のレプラ隔離棟への医師派遣・果ては開拓団に参加して満州渡航、南海の玉砕の島にまで活動範囲が及ぶ。しかし、〈ひのもと救霊会〉なる教団の全国的な規模の活動諸点や信者の数なども、恣意的で捉えどころがない。
*
長大な小説の目次を挙げてみよう。いくらかの参考にはなろう。
序章・第一部――廃墟・再建会議・薪造り・疑惑と苦渋・慎ましい日常・予審決定・晦日から新年へ・保釈・病床指令・ストライキ・繭と剣・湯崎温泉・失踪・四面楚歌・公判①・諫暁・召集・公判②・死の影・宗教と生・闇から闇へ・教姉教弟・農村改革案・生(エロス)と死(タナトス)の情熱・正統と異端・暗殺・清野作戦・壊滅。
第二部――かくれ宗教・貧民窟・湖畔・本部・闇の思想・牢獄・南洋・参禅・廃者の島・再会・捕虜・西と東・感傷旅行・満蒙開拓団・特赦・産業報国会・吉報?・甘美な惑い・夢幻の能・総転向。
第三部――一九四五・虚脱と悲哀・七哀詩・死の釈放・残党・兄弟・進駐軍・姉妹・失われた時・復員・学校騒動・冬・喪中の正月・再生・不吉な前進・供養塔・世代交代・宗教裁判・節分・強制寄進・誓約・抗議デモ・突発事故・白虹・簒奪・あり得ざりし歴史・三日天下・浮城・破局・餓死・終末――は、戦後の武力闘争と敗北の部分をなしている。
掲げた章は、いずれも二つか三つの部分に区切られて構成されていて、映画の場面転換に似ている。この長編小説は、劇画のコマ割りや映画の手法に類似した章割なのだ。
人物描写も劇画的に類型化されていて、書かずもがなの常套的な心理的描写そのものが図式化されている。主役の千葉潔自体が、劇画の登場人物にふさわしい、思わせぶりなキャラクターであって、好意的に読んでも、そこに思想性を見出すのは難しい。
だが、第一部の章に「生と死の情熱」があるように、〈エロスとタナトスの欲動〉の葛藤が、大きな意味の小説の主題であり、「死」の衝動に導かれ、教団に壊滅をもたらす役割は、死に神のような千葉潔である。生の衝動を、わずかに示しているのが、教主行徳仁次郎の次女阿貴であろう。だが、存在感は、姉の阿礼と比べると極めて薄い。
教主仁二郎の獄死後の教団の混乱は、獄中で伝えられた二つの相反する遺言、教団の存続を熱望する「生」の遺言と怨念に充ちた「死」の遺言によってもたらされたといえよう。千葉は「死」の遺言の実行者なのだが、必ずしも積極的なアジテーターではなく、教団に染みこんだタナトスの衝動を顕在化させるための活動家に過ぎないと見なすことも出来る。物語の終末で、阿礼は壮絶な自殺を遂げる。一方、千葉潔は、潔い戦死を回避して、死に装束で落ち延び、餓死を選ぶのにも、つねに生者につきまとうタナトスの必然性が見える。二人の主人公にいささかの共感も覚えないのはこの文学作品の致命的な欠陥だろう。
*
私は必ずしも、この長大な小説を否定的にばかり捉えているわけではない。戦後文学を代表する陰鬱な小説群の総括として、『邪宗門』があるとすれば、後に大流行した劇画ブーム、そして今日のアニメ全盛時代の心理的な下地として、戦後文学が位置しているのではないかと疑っている。アニメ的な世界観――画一化・映像化・短絡化――に耐えがたい違和感を持っているとはいえ、劇画や映像芸術を侮るような文学的な視点にいるわけではない。
もともと死体である組織を生きかえらせる作業で組織は成り立つ。組織とは、死体なのであって、実体ではない、それは作家の執筆というエクリチュール作業に似ている。高橋和巳は『邪宗門』において、〈ひのもと救霊会〉なる組織をでっち上げるために心血を注いで書き続けたのだ。だが、エロスを代表するはずの行徳阿礼は、時代の閉塞状況の中で突破口を奪われ、そこへ、タナトスの千葉潔という著者の分身を紛れ込ませる事によって、必然的な破滅の途を選んだ。思考実験は失敗に帰した。だが、文学の両義性は、その欠陥をも前向きに捉え得るとだけ指摘しておこう。
*
ラカンの鏡像段階論を参照すると、高橋和巳の思考実験は、象徴的な脱皮を遂げることなく、精神病の様相に終わったと云えようか。(「鏡像段階においては、主体は鏡のなかの像を自らの存在として予知的に掴むことで現在の欠如を隠そうとしているに過ぎない」向井雅明『ラカン入門』一七一頁)
それも人間の一つの側面であることに変わりがない。障害者施設を襲って「彼らは生きている価値がない」と重度障害者十九名を殺害した男も実在している。もちろん、ペンで書くのと、麻薬中毒を疑われようが現実に手を下すのとの相違を承知の上でだが。
ただし、私が詩や文学に求めているのは、紙とペンで描くエクリチュールの道であって誤解を恐れずに書けば、秘教的で、ごくマイナーなものであることを断っておきたい。(了)










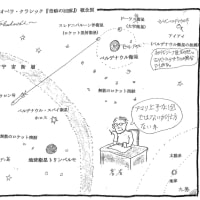
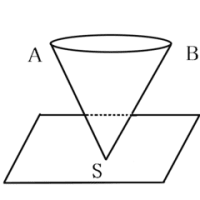
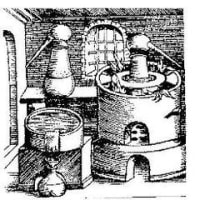




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます