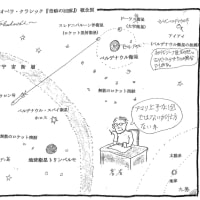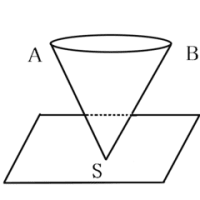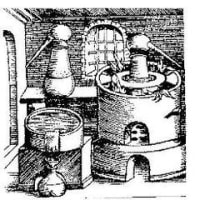勝俣鎮夫『一揆』(岩波新書・一九八二)の初版本を持っている。当時の製本が悪くて読むと頁が一枚ずつ剥がれてしまう。だが、初読したとき、斬新な一揆論に魅了され、処分を免れて書棚に残っていた。たまたま、書店の店頭で復刊された本書を目にし、購入した。
改めて読み直した冒頭、「はじめに」の文章で、勝俣氏は著作の意図を明らかにしている。
「昭和のはじめ、民俗学者柳田国男氏は、当時社会経済史の興隆とともにさかんとなったわが国の農民史研究が、農民の歴史を一揆や飢饉災害の事件史にしてしまっていることを厳しく批判され、農民の生活を「日常性」の歴史として解明する必要を強調された。たしかに柳田氏のいわれるとおり、一揆は非日常性をその本質とする歴史的事象である。
しかし、私は、柳田氏が同じ非日常的な場である「祭」を素材として常民の生活のなかにおける日常的深層意識を見事に解明したように、一揆をとおして、日本の歴史の基層に生きつづけた集団心性を掘りおこすことが可能であると考える。」
このように勝俣氏は、「祭」という祝祭空間を、集団心性を通して、様式空間に転換させて捉えようとしている。柳田民俗学を、思想的に超克する試みと言えよう。確かに、従来の民俗学は、抒情性を脱しない限りで、通時的な記述に偏っており、そうした共時的構造的な観点での整理を欠いている。しかし、「明治大正史・世相編」に見るように、常民の思想には共時的な観点は、不可欠な要素であって内在している。勝俣氏の本書は、柳田民俗学を継承していると言えよう。
冒頭の部分で、一揆には「一味神水」という儀式が不可欠であること、それを説明して次のように記している。「参加する全員が神社の境内に集合し、一味同心すること、その誓約にそむいた場合いかなる神罰や仏罰をこうむってもかまわない旨を書きしるし、全員が署名したのち、その起請文を焼いて神水にまぜ、それを一同がまわし飲みするというものがこの時代のオーソドックスな方法であった。」(同書・二八頁)と。さらに、「一味同心をつくって抵抗する習慣は、ほぼ一四世紀には広く農民のあいだに定着していた」「もちろん、この一味神水という作法は、農民特有であったのではない。おそらく、さきにみた幕府(鎌倉幕府のこと―引用者注)の評定衆の一味にも、中世寺院の一味にもこのような作法がその前提とされていたと思われる。」(二九頁)
私が勝俣氏の文章で注目したのは、何よりも、エクリチュール=記述にほかならない起請文の存在である。単なる象徴的な標章ではなく、それを記憶に焼き付けるためでもなく、ショーペンハウァーが「読書について」でいう〈決心の成熟〉を経た、共通理解としての法的な了解を与えられなければエクリチュールとは言えない。それは国の法から文法に至るまであらゆる文化が内包している、善悪好悪の判断の前の、一つの水準である。起請文は、文面を理解するばかりでなく、参加者全員の心情と行動を一つに支えあげる能動的な力をそれ自体で持っているとされる。さらに参加者相互を拘束する力であるばかりか、それをはみ出て、他者にも有効な力なのだ。少なくても一揆参加者にとって、要求を突きつけられた側も、その権威を認めねばならないと意識される。彼らにとって正当でない一揆は存在しない。領主側にとっても、歴史的に見れば、一揆の一般的な権威が認められた時代もあった。神前での集合と起請文の作成は、そうしたエクリチュールの権威の反復であろう。つまり、神前での行事の有無にかかわらず本来的に一揆起請文というエクリチュールはその書かれた内容と参加者の意思の確認である以前に、神的な呪物としての威力を持っていると言える。
今日においても、契約的合意の意識の中には、不可解で不合理なものを内在させている。なぜ、合意は守らねばならないのか。実際、合意のために約束は守られるのでなく両者の力関係で決まるのではないか。そうした疑問は常につきまとう。一揆禁制の江戸時代のように、封建制度の圧倒的な力の前で、絶対的な劣勢の一揆勢力が、一定の手続きを経た一揆に神的な威力をあてにしたのは、当然であったろう。
「血縁的な関係で結ばれた人びとなどの結合をのぞいて、他者との連帯や共同がきわめて困難であった当時の社会状況のなかでの「同心」、私的な縁にもとづく行為を最大の行為基準としていた社会のなかで、その「縁」をこえたところにうまれる「公正さ」、参加メンバーの集団内部における「主体性」の実現、一揆集団の上部権力からの強い「自律性」など、これまでみてきた一揆の諸特性は、このような一味神水にもとづく神と人、神を媒介にした人と人の一体化の意識が大きく作用していたと思われる。またその裏返しの一揆の狂気性、神がかり性などもまた同じ観点から把握しうるものと思われる。」(同書三四頁)
要求を書き付け連名で署名された起請文がいったん焼かれ、灰となり、水に漬けられて飲み下される。エクリチュールの威力に己を一体化する儀式は、意味深長である。呪術めいているが、エクリチュールの神秘は、今もって完全に解明されたわけではない。起請文は燃やされても威力を失ったのではなく、灰にすることによって、元の「文字」と「紙」に戻される。水の象徴である「水」に溶かされ、それを飲み下すことによって象徴の「文字」が再生され、共同のエクリチュールの場で威力は取り戻される。
改めて読み直した冒頭、「はじめに」の文章で、勝俣氏は著作の意図を明らかにしている。
「昭和のはじめ、民俗学者柳田国男氏は、当時社会経済史の興隆とともにさかんとなったわが国の農民史研究が、農民の歴史を一揆や飢饉災害の事件史にしてしまっていることを厳しく批判され、農民の生活を「日常性」の歴史として解明する必要を強調された。たしかに柳田氏のいわれるとおり、一揆は非日常性をその本質とする歴史的事象である。
しかし、私は、柳田氏が同じ非日常的な場である「祭」を素材として常民の生活のなかにおける日常的深層意識を見事に解明したように、一揆をとおして、日本の歴史の基層に生きつづけた集団心性を掘りおこすことが可能であると考える。」
このように勝俣氏は、「祭」という祝祭空間を、集団心性を通して、様式空間に転換させて捉えようとしている。柳田民俗学を、思想的に超克する試みと言えよう。確かに、従来の民俗学は、抒情性を脱しない限りで、通時的な記述に偏っており、そうした共時的構造的な観点での整理を欠いている。しかし、「明治大正史・世相編」に見るように、常民の思想には共時的な観点は、不可欠な要素であって内在している。勝俣氏の本書は、柳田民俗学を継承していると言えよう。
冒頭の部分で、一揆には「一味神水」という儀式が不可欠であること、それを説明して次のように記している。「参加する全員が神社の境内に集合し、一味同心すること、その誓約にそむいた場合いかなる神罰や仏罰をこうむってもかまわない旨を書きしるし、全員が署名したのち、その起請文を焼いて神水にまぜ、それを一同がまわし飲みするというものがこの時代のオーソドックスな方法であった。」(同書・二八頁)と。さらに、「一味同心をつくって抵抗する習慣は、ほぼ一四世紀には広く農民のあいだに定着していた」「もちろん、この一味神水という作法は、農民特有であったのではない。おそらく、さきにみた幕府(鎌倉幕府のこと―引用者注)の評定衆の一味にも、中世寺院の一味にもこのような作法がその前提とされていたと思われる。」(二九頁)
私が勝俣氏の文章で注目したのは、何よりも、エクリチュール=記述にほかならない起請文の存在である。単なる象徴的な標章ではなく、それを記憶に焼き付けるためでもなく、ショーペンハウァーが「読書について」でいう〈決心の成熟〉を経た、共通理解としての法的な了解を与えられなければエクリチュールとは言えない。それは国の法から文法に至るまであらゆる文化が内包している、善悪好悪の判断の前の、一つの水準である。起請文は、文面を理解するばかりでなく、参加者全員の心情と行動を一つに支えあげる能動的な力をそれ自体で持っているとされる。さらに参加者相互を拘束する力であるばかりか、それをはみ出て、他者にも有効な力なのだ。少なくても一揆参加者にとって、要求を突きつけられた側も、その権威を認めねばならないと意識される。彼らにとって正当でない一揆は存在しない。領主側にとっても、歴史的に見れば、一揆の一般的な権威が認められた時代もあった。神前での集合と起請文の作成は、そうしたエクリチュールの権威の反復であろう。つまり、神前での行事の有無にかかわらず本来的に一揆起請文というエクリチュールはその書かれた内容と参加者の意思の確認である以前に、神的な呪物としての威力を持っていると言える。
今日においても、契約的合意の意識の中には、不可解で不合理なものを内在させている。なぜ、合意は守らねばならないのか。実際、合意のために約束は守られるのでなく両者の力関係で決まるのではないか。そうした疑問は常につきまとう。一揆禁制の江戸時代のように、封建制度の圧倒的な力の前で、絶対的な劣勢の一揆勢力が、一定の手続きを経た一揆に神的な威力をあてにしたのは、当然であったろう。
「血縁的な関係で結ばれた人びとなどの結合をのぞいて、他者との連帯や共同がきわめて困難であった当時の社会状況のなかでの「同心」、私的な縁にもとづく行為を最大の行為基準としていた社会のなかで、その「縁」をこえたところにうまれる「公正さ」、参加メンバーの集団内部における「主体性」の実現、一揆集団の上部権力からの強い「自律性」など、これまでみてきた一揆の諸特性は、このような一味神水にもとづく神と人、神を媒介にした人と人の一体化の意識が大きく作用していたと思われる。またその裏返しの一揆の狂気性、神がかり性などもまた同じ観点から把握しうるものと思われる。」(同書三四頁)
要求を書き付け連名で署名された起請文がいったん焼かれ、灰となり、水に漬けられて飲み下される。エクリチュールの威力に己を一体化する儀式は、意味深長である。呪術めいているが、エクリチュールの神秘は、今もって完全に解明されたわけではない。起請文は燃やされても威力を失ったのではなく、灰にすることによって、元の「文字」と「紙」に戻される。水の象徴である「水」に溶かされ、それを飲み下すことによって象徴の「文字」が再生され、共同のエクリチュールの場で威力は取り戻される。