3.韓国併合から大震災直前までの国民の意識
①朝鮮人の増加と軋轢
日本には1910年の韓国併合以前から朝鮮人が多く渡航していたが、その画期は1917年頃といわれる。この時期には朝鮮総督府による「サーベル政治」ともいわれる過酷な支配のもとで多くの農民が土地を奪われ小作農に転落したり、都市に流入して貧民化したりした。労働者の間にも日本人労働者とははっきりした労働時間や賃金のうえで格差がついていた。このような朝鮮人の切羽詰った生活状況がある中で、日本では第一次世界大戦下の好況で、生産拡大などのよる労働者不足という状況があった。
こうした中で、低賃金による人件費節約、日本人労働者によるストライキ抑止力、いつでも解雇できるという利点を持った朝鮮人労働者への着目となった。長崎の高島炭鉱などは朝鮮でも労働者募集を積極的に進めたという。しかし、大戦後に不況になると、このような朝鮮人労働者の日本への渡航は日本人労働者との間にいろいろな軋轢を生み出した。
②官憲やマスコミがつくった差別意識
1919年に三・一独立運動が起き、独立を叫ぶ朝鮮人は1年間に死者7645人負傷者4万5552人、逮捕者4万9811人にのぼったという。所がこれを日本の新聞は軍部の発表や「という話である。」「と某氏は語った。」などという不確実な情報をそのまま国民に事実のように報道した。「朝鮮各地の暴徒、しきりに警察を襲う」「見るも無残な憲兵の死体」「ウラジオ在留の鮮人も陰謀を企つ」(いずれも東京日日新聞)、「市内各所に出没して陰謀を図る不逞鮮人団」(東京朝日新聞)などの記事が各紙を飾ったのである。
日本国内の人々はこのような記事によって運動のもとになった侵略や植民地化を考えることもなく「不逞鮮人」を恐れ、怖いというイメージを作られていった。
同じころ、海外では「日本はかねてから朝鮮を制圧してその国民的尊厳も民族的意識も根絶せんと努めてきた。・・・。彼らの死すとも日本に屈服すまいとする意気込みを我々は絶賛してやまないのである。」(1920年2月10日付「ホノルルスタープレッチン」紙)という論調が一般的な中で日本人のみが朝鮮人に対する憎悪の念を持つようにされていったのである。1923年の関東大震災までに以上のような国民的な常識や雰囲気が官憲やマスコミによって形成されていたのである。
4.為政者の行動と意識
①だれが流言を流したのか
警視庁『大正大震火災誌』によると9月1日の午後1時ごろはじめて流されたのは「さらに大地震の来襲あるべし」といった自然災害に関すもので、それが午後3時ごろになると「社会主義者及び鮮人の放火多し」というデマが発生したという。この後2日には東京全域でデマが起こり、それと同時に迫害が始まったという。
神奈川県警察部『大正大震火災誌』によると、午後3時ごろから川崎署管内で朝鮮人暴動の流言が伝えられ、2日になると関東一円から全国に広がり、関東一帯で軍隊、警察、民衆による朝鮮人・中国人虐殺事件が起こった。ところが、警察発表では誰がと言う部分は隠蔽されている。
これについては『報知新聞』(1923年10月29日)の報道がある。本郷の議員や自警団が開いたもので、警察官が朝鮮暴動のデマを流した責任を棚上げにして自警団を検挙したことへの抗議集会であった。
これによると、町の村田代表は「9月1日夕方曙町交番巡査が自警団に来て『各町で不平鮮人が殺人放火しているから気をつけろ。』と二度まで通知に来たほか、よく2日には警視庁の自動車が『不平鮮人が各所において暴威を逞うしつつあるから各自注意せよ』との宣伝ビラを撒布し、すなわち鮮人に対して自警団其の他が暴行を行なうべき原因を作ったのだ。」と報告したという。このように警察がデマをつくったほか伝播する役目を果たしたことは多くの証言があると言う。
同じく『報知新聞』(1923年10月23日)では関東自警団同盟が作った檄文でも「心ある者は胸に手を当てて考えよ。災害の当時、彼等我等に告げて『某々方面より襲来の虞あり。男子は武装せよ。女子は避難せよ。鮮人と見れば倒しても差し支えない。主義者と判らば殴っても宜い。彼等は凶器を携えて到る所に殺人強盗凌辱放火投毒等あらゆる悪事を働いている。』とふれ回ったのは何者であったか。」云々とそれを伝えたのが詰め襟の警官であったことを報じている。
さらに国会での質問からは9月1日には電報で各地方の長官宛てに不逞鮮人による暴動への注意を促す通達が届けられたことが明らかになった。裁判でも群馬県の裁判で検事の「官辺より布令を回せしことは当職においてもこれを認め居れば」(上毛新聞1923年11月6日)とデマを流した責任は、郡長や警察などの官憲にあることが明らかになった。にもかかわらず証人の喚問しないなどその究明は避けられた。
②官憲の朝鮮人に対する意識
必死になって責任の回避につとめる官憲の責任隠蔽工作は今日では明らかになっているが、彼等はなぜこのような布令をするに至ったのだろうか。かれらの社会的性格ともいうべき意識としては朝鮮人・社会主義者に対する疑心暗鬼から来る恐怖感があるといわれる。
1919年の三・一独立運動やそれがもたらした民族意識の高揚に対し支配者は大きな衝撃を持って迎えた。それは運動後、国内では「内鮮係」を設けて在日朝鮮人に対する警戒を強めたことや高官の談話でも明らかである。
朝鮮総督府総監が「東京朝日新聞」(1919年10月22日)に「一般鮮人が倣岸不遜になってきた。・・・・。なお教育に対する鮮人の態度はすこぶる悪化し来たり、あるいは忠君愛国に関しても穏やかならざる態度を有するものもある。」といい、同化政策についても「今尚研究中であり今茲に断言することはできない。」と話している。また、1920年刊行の内務省警保局保安課『朝鮮人概況』では「不逞鮮人の排日思想が大正八年の独立騒擾発生以来益々硬化の跡あるは注目すべきところなり。」としているがこの『概況』は毎年詳しい朝鮮人の情報を把握している。
また、1923年の三・一独立運動記念日には警視庁が「小森特別高等課長、立山内鮮係長は市郡の鮮人の集合している神田錦町、西神田、小石川、富坂、本所、相生、南千住、千住、亀戸、小松川の各署長と打ち合わせ、万一の挙ある時は一挙これを検挙すべく目下警戒中。」と「東京朝日新聞」(3月1日)は伝えた。こうした治安当局の動向は彼等が今まで朝鮮国内や日本国内でやってきたことへの官憲の怯えをあらわしているといえる。
ここには1909年の伊藤博文暗殺などをはじめとする支配するものへの反撃に対する怯えが伺える。このような意識であるから彼等は大震災の翌日9月2日にはすぐ戒厳令を布告するに至る。これによっていわゆる「不逞鮮人による騒擾」等は事実とされることになり、民衆による朝鮮人殺害を一層あおることになる。
自らの侵略と植民地化政策は支配者としての満足感とともに、その支配を覆そうとする朝鮮人に対しては武力で対処せざるを得ない不安感も生じさせずにはおかない。朝鮮人に対して不逞鮮人という呼称で対処する裏には驕りとともにこうせずに入られない彼等の自己瞞着と独立運動への恐れが見られる。
作家の高見順は『わが胸のそこのここには』の中で「根本は、朝鮮人に対して日本人全体が感じていた一種の罪悪感、それが原因になっていたことは確かだ。いつか朝鮮人に復讐されるのではないかという恐怖、それがあんなデマを生んだ下地であったことは疑いのないことだ。」といっている。これは一般国民についてのものだが直接彼等を責め、迫害している官憲にとっては一層の恐怖感があったことであろう。
4.大衆の行動とその意識
支配する官憲にとっての意識は既に見てきたが、特に一般国民がどうして彼等と一緒になって朝鮮人虐殺を行なったのだろうか。ここに当時の国民の権威主義にもとづくサディスト的な側面とマゾヒスト的な側面が見られる。長い江戸時代を通じて日本人は「お上」のいうことはご無理ごもっともという感情を持たせられてきた。「長いものには巻かれろ」という諺にある通り大きな権力には逆らっても無駄という意識をもっていた。
これが明治時代になってもそれが殿様から国家になっただけで強いものに対する服従の意識は変わりはしなかった。特に、明治国家は教育・マスコミなどあらゆる機関を通して国家の威信を高揚させ、その前に従順な国民を育成してきた。国民は強力な国家への憧憬と服従する喜びの意識を形成されてきた。
侵略して強力な国家になっていくことへの国民の喜びは日清戦争、日露戦争、韓国併合と続く中でいっそう強められた。強力な国家に服従することによってアジア諸国の上に立てるという心理状態を獲得することができた。国家への無条件な信頼はこうしてお上によって形成されたものであるが多くの国民自らもそのことによって精神的な満足感と安心感、帰属感を獲得してきたのであった。
このようなアジア諸国、特に朝鮮人に対する意識であったので官憲により「不逞鮮人に関する」通達や戒厳令布告という錦の御旗が出されるに及んではわれがちに朝鮮人への虐殺に走ったのであろう。また先に見たように朝鮮人の渡航が増えて日本国内の朝鮮人労働者が低賃金と劣悪な労働条件で働いていることに対する労働者をはじめとする国民の反感があったという。
このように一方では国家という強力なものへの服従をしながら、他方では自らの低い労働条件より低い朝鮮人への蔑視と言う心理的な満足感をもっていたといえる。これについては組織された労働者や社会主義者でも自警団に入って朝鮮人の虐殺に参加した例などがある。当時の労働者が朝鮮人や中国人に対する民族的な蔑視をさらに反感や憎しみへと増幅させていったところへ流言やデマが流されることになった。
この朝鮮人虐殺の中心となったのは各地に作られた自警団であった。その自警団は戒厳司令部が在郷軍人や青年団・消防団などを中心に組織させた民衆の自衛組織であり、関東大震災時には関東一円で3689団体あったという。
彼等はお上によって公認されたという意識もあって各地で厳重な検問を行い、不審者は容赦なく殺した。埼玉県では本庄警察署まで襲撃してそこに収監されている朝鮮人を撲殺するということまでしたのであった。そこでは9月4日には警官が虐殺を制止したがそれに対して「このような国家緊急な時には人一人殺せないじゃないか、俺達は平素ためかつぎをやっていても、夕べは十六人も殺したぞ。」というものも出たという。
これらは国家によって作られてきた優越感や差別意識が根底にあってそこに恐怖感が加わるとブレーキが効かなくなる例であり、山田昭次氏がいう「暴君治下の臣民は暴君より暴である。」(魯迅)と言える。即ち、これらの暴虐をなしたのは天皇制国家に忠良な皇国民であり、「一旦緩急あれば義勇公に奉じ以って天壌無窮の皇運を扶翼すべし」と言う教育勅語をそのまま実践するような精神構造をもっていたのであった。
このような精神構造を形成してきたのは、幕末以来の征韓論、福沢諭吉らの脱亜論に基づく朝鮮蔑視の思想であろう。また、政府による宣伝機関と化した新聞の役割や、国家によって歴史的に作られたアジア、特に朝鮮への蔑視政策を伝えてきた教育の役割も大きい。
5. おわりに=今日に残る課題
日本の国民が封建時代から培われてきた「お上」の観念や「長いものには巻かれろ」という服従の精神、滅私奉公という心理は明治時代になってアジア諸国、特に朝鮮への差別感・蔑視感となって拡大再生産された。こうしたアジア各国への侵略をはじめ関東大震災時における悲劇などの大きな原因の一つになった国民の心理は今日、払拭されたであろうか。残念ながら否と言わなければならない。
戦後の民主化を徹底してできなかった歴史的な積み残しともいうべき課題が今に至っている。これは国際化と言うことが声高に叫ばれている現在でもその実態は国民の草の根からの声とは言い難く、政治や経済の必要性から来るものが多いことからも分かる。特に政府の政策のため未だに解決しない従軍慰安婦問題や新たな教科書問題などを見ても明らかである。また、まだ続く朝鮮学校生徒への差別事件や「第三国人」発言などは真の自由と民主主義の実現の難しさを示している。
特に情報社会といわれる今日、間違った情報によって、あるいは意図的な情報操作によって国民が正しい判断ができなくなる可能性が益々多くなると思われる。国民一人ひとりが正しい知識と判断力を持つことが大切であるが、歴史的に作られてきた国民としての心理的傾向のことも考えていかなければならない。
*引用文献
大正の朝鮮人虐殺事件 北沢 文武著 鳩の森書房 1980年
日本近代史の虚像と実像2 藤原彰他編 大月書店 1990年
*参考文献
福沢 諭吉 鹿野政直著 清水書院 1996年
誤報 後藤文康著 岩波書店 1998年
歴史公論 特集 近代の日本と朝鮮 雄山閣 1980年
神奈川の韓国・朝鮮人 神奈川県自治総合研究センター編 公人社
写真報告 関東大震災 朝鮮人虐殺 裵 昭著 影書房 1988年
座間むかしむかし4、5集 座間市教育委員会編 1976年
新しき朝鮮 復刻版 朝鮮総督府情報課編纂 風濤社 1982年
日本史のエッセンス 荒木敏夫他著 有斐閣 1997年
①朝鮮人の増加と軋轢
日本には1910年の韓国併合以前から朝鮮人が多く渡航していたが、その画期は1917年頃といわれる。この時期には朝鮮総督府による「サーベル政治」ともいわれる過酷な支配のもとで多くの農民が土地を奪われ小作農に転落したり、都市に流入して貧民化したりした。労働者の間にも日本人労働者とははっきりした労働時間や賃金のうえで格差がついていた。このような朝鮮人の切羽詰った生活状況がある中で、日本では第一次世界大戦下の好況で、生産拡大などのよる労働者不足という状況があった。
こうした中で、低賃金による人件費節約、日本人労働者によるストライキ抑止力、いつでも解雇できるという利点を持った朝鮮人労働者への着目となった。長崎の高島炭鉱などは朝鮮でも労働者募集を積極的に進めたという。しかし、大戦後に不況になると、このような朝鮮人労働者の日本への渡航は日本人労働者との間にいろいろな軋轢を生み出した。
②官憲やマスコミがつくった差別意識
1919年に三・一独立運動が起き、独立を叫ぶ朝鮮人は1年間に死者7645人負傷者4万5552人、逮捕者4万9811人にのぼったという。所がこれを日本の新聞は軍部の発表や「という話である。」「と某氏は語った。」などという不確実な情報をそのまま国民に事実のように報道した。「朝鮮各地の暴徒、しきりに警察を襲う」「見るも無残な憲兵の死体」「ウラジオ在留の鮮人も陰謀を企つ」(いずれも東京日日新聞)、「市内各所に出没して陰謀を図る不逞鮮人団」(東京朝日新聞)などの記事が各紙を飾ったのである。
日本国内の人々はこのような記事によって運動のもとになった侵略や植民地化を考えることもなく「不逞鮮人」を恐れ、怖いというイメージを作られていった。
同じころ、海外では「日本はかねてから朝鮮を制圧してその国民的尊厳も民族的意識も根絶せんと努めてきた。・・・。彼らの死すとも日本に屈服すまいとする意気込みを我々は絶賛してやまないのである。」(1920年2月10日付「ホノルルスタープレッチン」紙)という論調が一般的な中で日本人のみが朝鮮人に対する憎悪の念を持つようにされていったのである。1923年の関東大震災までに以上のような国民的な常識や雰囲気が官憲やマスコミによって形成されていたのである。
4.為政者の行動と意識
①だれが流言を流したのか
警視庁『大正大震火災誌』によると9月1日の午後1時ごろはじめて流されたのは「さらに大地震の来襲あるべし」といった自然災害に関すもので、それが午後3時ごろになると「社会主義者及び鮮人の放火多し」というデマが発生したという。この後2日には東京全域でデマが起こり、それと同時に迫害が始まったという。
神奈川県警察部『大正大震火災誌』によると、午後3時ごろから川崎署管内で朝鮮人暴動の流言が伝えられ、2日になると関東一円から全国に広がり、関東一帯で軍隊、警察、民衆による朝鮮人・中国人虐殺事件が起こった。ところが、警察発表では誰がと言う部分は隠蔽されている。
これについては『報知新聞』(1923年10月29日)の報道がある。本郷の議員や自警団が開いたもので、警察官が朝鮮暴動のデマを流した責任を棚上げにして自警団を検挙したことへの抗議集会であった。
これによると、町の村田代表は「9月1日夕方曙町交番巡査が自警団に来て『各町で不平鮮人が殺人放火しているから気をつけろ。』と二度まで通知に来たほか、よく2日には警視庁の自動車が『不平鮮人が各所において暴威を逞うしつつあるから各自注意せよ』との宣伝ビラを撒布し、すなわち鮮人に対して自警団其の他が暴行を行なうべき原因を作ったのだ。」と報告したという。このように警察がデマをつくったほか伝播する役目を果たしたことは多くの証言があると言う。
同じく『報知新聞』(1923年10月23日)では関東自警団同盟が作った檄文でも「心ある者は胸に手を当てて考えよ。災害の当時、彼等我等に告げて『某々方面より襲来の虞あり。男子は武装せよ。女子は避難せよ。鮮人と見れば倒しても差し支えない。主義者と判らば殴っても宜い。彼等は凶器を携えて到る所に殺人強盗凌辱放火投毒等あらゆる悪事を働いている。』とふれ回ったのは何者であったか。」云々とそれを伝えたのが詰め襟の警官であったことを報じている。
さらに国会での質問からは9月1日には電報で各地方の長官宛てに不逞鮮人による暴動への注意を促す通達が届けられたことが明らかになった。裁判でも群馬県の裁判で検事の「官辺より布令を回せしことは当職においてもこれを認め居れば」(上毛新聞1923年11月6日)とデマを流した責任は、郡長や警察などの官憲にあることが明らかになった。にもかかわらず証人の喚問しないなどその究明は避けられた。
②官憲の朝鮮人に対する意識
必死になって責任の回避につとめる官憲の責任隠蔽工作は今日では明らかになっているが、彼等はなぜこのような布令をするに至ったのだろうか。かれらの社会的性格ともいうべき意識としては朝鮮人・社会主義者に対する疑心暗鬼から来る恐怖感があるといわれる。
1919年の三・一独立運動やそれがもたらした民族意識の高揚に対し支配者は大きな衝撃を持って迎えた。それは運動後、国内では「内鮮係」を設けて在日朝鮮人に対する警戒を強めたことや高官の談話でも明らかである。
朝鮮総督府総監が「東京朝日新聞」(1919年10月22日)に「一般鮮人が倣岸不遜になってきた。・・・・。なお教育に対する鮮人の態度はすこぶる悪化し来たり、あるいは忠君愛国に関しても穏やかならざる態度を有するものもある。」といい、同化政策についても「今尚研究中であり今茲に断言することはできない。」と話している。また、1920年刊行の内務省警保局保安課『朝鮮人概況』では「不逞鮮人の排日思想が大正八年の独立騒擾発生以来益々硬化の跡あるは注目すべきところなり。」としているがこの『概況』は毎年詳しい朝鮮人の情報を把握している。
また、1923年の三・一独立運動記念日には警視庁が「小森特別高等課長、立山内鮮係長は市郡の鮮人の集合している神田錦町、西神田、小石川、富坂、本所、相生、南千住、千住、亀戸、小松川の各署長と打ち合わせ、万一の挙ある時は一挙これを検挙すべく目下警戒中。」と「東京朝日新聞」(3月1日)は伝えた。こうした治安当局の動向は彼等が今まで朝鮮国内や日本国内でやってきたことへの官憲の怯えをあらわしているといえる。
ここには1909年の伊藤博文暗殺などをはじめとする支配するものへの反撃に対する怯えが伺える。このような意識であるから彼等は大震災の翌日9月2日にはすぐ戒厳令を布告するに至る。これによっていわゆる「不逞鮮人による騒擾」等は事実とされることになり、民衆による朝鮮人殺害を一層あおることになる。
自らの侵略と植民地化政策は支配者としての満足感とともに、その支配を覆そうとする朝鮮人に対しては武力で対処せざるを得ない不安感も生じさせずにはおかない。朝鮮人に対して不逞鮮人という呼称で対処する裏には驕りとともにこうせずに入られない彼等の自己瞞着と独立運動への恐れが見られる。
作家の高見順は『わが胸のそこのここには』の中で「根本は、朝鮮人に対して日本人全体が感じていた一種の罪悪感、それが原因になっていたことは確かだ。いつか朝鮮人に復讐されるのではないかという恐怖、それがあんなデマを生んだ下地であったことは疑いのないことだ。」といっている。これは一般国民についてのものだが直接彼等を責め、迫害している官憲にとっては一層の恐怖感があったことであろう。
4.大衆の行動とその意識
支配する官憲にとっての意識は既に見てきたが、特に一般国民がどうして彼等と一緒になって朝鮮人虐殺を行なったのだろうか。ここに当時の国民の権威主義にもとづくサディスト的な側面とマゾヒスト的な側面が見られる。長い江戸時代を通じて日本人は「お上」のいうことはご無理ごもっともという感情を持たせられてきた。「長いものには巻かれろ」という諺にある通り大きな権力には逆らっても無駄という意識をもっていた。
これが明治時代になってもそれが殿様から国家になっただけで強いものに対する服従の意識は変わりはしなかった。特に、明治国家は教育・マスコミなどあらゆる機関を通して国家の威信を高揚させ、その前に従順な国民を育成してきた。国民は強力な国家への憧憬と服従する喜びの意識を形成されてきた。
侵略して強力な国家になっていくことへの国民の喜びは日清戦争、日露戦争、韓国併合と続く中でいっそう強められた。強力な国家に服従することによってアジア諸国の上に立てるという心理状態を獲得することができた。国家への無条件な信頼はこうしてお上によって形成されたものであるが多くの国民自らもそのことによって精神的な満足感と安心感、帰属感を獲得してきたのであった。
このようなアジア諸国、特に朝鮮人に対する意識であったので官憲により「不逞鮮人に関する」通達や戒厳令布告という錦の御旗が出されるに及んではわれがちに朝鮮人への虐殺に走ったのであろう。また先に見たように朝鮮人の渡航が増えて日本国内の朝鮮人労働者が低賃金と劣悪な労働条件で働いていることに対する労働者をはじめとする国民の反感があったという。
このように一方では国家という強力なものへの服従をしながら、他方では自らの低い労働条件より低い朝鮮人への蔑視と言う心理的な満足感をもっていたといえる。これについては組織された労働者や社会主義者でも自警団に入って朝鮮人の虐殺に参加した例などがある。当時の労働者が朝鮮人や中国人に対する民族的な蔑視をさらに反感や憎しみへと増幅させていったところへ流言やデマが流されることになった。
この朝鮮人虐殺の中心となったのは各地に作られた自警団であった。その自警団は戒厳司令部が在郷軍人や青年団・消防団などを中心に組織させた民衆の自衛組織であり、関東大震災時には関東一円で3689団体あったという。
彼等はお上によって公認されたという意識もあって各地で厳重な検問を行い、不審者は容赦なく殺した。埼玉県では本庄警察署まで襲撃してそこに収監されている朝鮮人を撲殺するということまでしたのであった。そこでは9月4日には警官が虐殺を制止したがそれに対して「このような国家緊急な時には人一人殺せないじゃないか、俺達は平素ためかつぎをやっていても、夕べは十六人も殺したぞ。」というものも出たという。
これらは国家によって作られてきた優越感や差別意識が根底にあってそこに恐怖感が加わるとブレーキが効かなくなる例であり、山田昭次氏がいう「暴君治下の臣民は暴君より暴である。」(魯迅)と言える。即ち、これらの暴虐をなしたのは天皇制国家に忠良な皇国民であり、「一旦緩急あれば義勇公に奉じ以って天壌無窮の皇運を扶翼すべし」と言う教育勅語をそのまま実践するような精神構造をもっていたのであった。
このような精神構造を形成してきたのは、幕末以来の征韓論、福沢諭吉らの脱亜論に基づく朝鮮蔑視の思想であろう。また、政府による宣伝機関と化した新聞の役割や、国家によって歴史的に作られたアジア、特に朝鮮への蔑視政策を伝えてきた教育の役割も大きい。
5. おわりに=今日に残る課題
日本の国民が封建時代から培われてきた「お上」の観念や「長いものには巻かれろ」という服従の精神、滅私奉公という心理は明治時代になってアジア諸国、特に朝鮮への差別感・蔑視感となって拡大再生産された。こうしたアジア各国への侵略をはじめ関東大震災時における悲劇などの大きな原因の一つになった国民の心理は今日、払拭されたであろうか。残念ながら否と言わなければならない。
戦後の民主化を徹底してできなかった歴史的な積み残しともいうべき課題が今に至っている。これは国際化と言うことが声高に叫ばれている現在でもその実態は国民の草の根からの声とは言い難く、政治や経済の必要性から来るものが多いことからも分かる。特に政府の政策のため未だに解決しない従軍慰安婦問題や新たな教科書問題などを見ても明らかである。また、まだ続く朝鮮学校生徒への差別事件や「第三国人」発言などは真の自由と民主主義の実現の難しさを示している。
特に情報社会といわれる今日、間違った情報によって、あるいは意図的な情報操作によって国民が正しい判断ができなくなる可能性が益々多くなると思われる。国民一人ひとりが正しい知識と判断力を持つことが大切であるが、歴史的に作られてきた国民としての心理的傾向のことも考えていかなければならない。
*引用文献
大正の朝鮮人虐殺事件 北沢 文武著 鳩の森書房 1980年
日本近代史の虚像と実像2 藤原彰他編 大月書店 1990年
*参考文献
福沢 諭吉 鹿野政直著 清水書院 1996年
誤報 後藤文康著 岩波書店 1998年
歴史公論 特集 近代の日本と朝鮮 雄山閣 1980年
神奈川の韓国・朝鮮人 神奈川県自治総合研究センター編 公人社
写真報告 関東大震災 朝鮮人虐殺 裵 昭著 影書房 1988年
座間むかしむかし4、5集 座間市教育委員会編 1976年
新しき朝鮮 復刻版 朝鮮総督府情報課編纂 風濤社 1982年
日本史のエッセンス 荒木敏夫他著 有斐閣 1997年










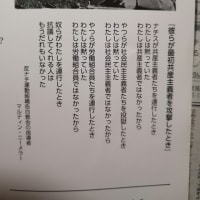









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます