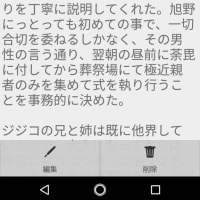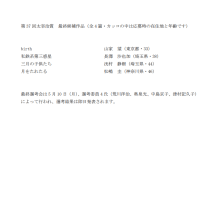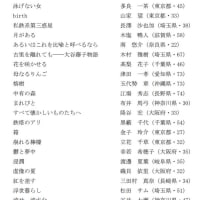8月も下旬を迎えようとしている頃,その年の夏の暑さはテレビのニュースで「外出すると癌になる」といったレポートが毎日伝えられる程,例年のものに比べて熾烈を極めていて木陰にいれば涼しいという定説も崩される有様だった。
僕は6月いっぱいで語学学校も終了していたから,帰国してからの3週間程の間は特に何をするでもなく毎日を無為に過ごしていた。学生時代に塾講師のアルバイトで貯めた資金も大分残っていたし,せいぜい住んでいたフラットの家賃よりも安い住処を探すべく動き始めているくらいだった。それだって実を言うと,邦子と直美が僕のフラットを気に入ってしまい2人でシェアして住みたいという話が出て,ベンが知り合いの不動産屋を紹介してくれたのがきっかけでもあった。以前以上に僕のアパートで過ごす時間が多くなったカリンも思いの外乗り気で,ウィルソンというそのエージェントとの交渉の中で,カリンが入学を希望していたブライトンカレッジの近くに2人で住む場所を探すことになってしまった。カリンと僕は同い年だったしお互いに家族の様な存在になっていて,帰国した日にカリンからは好意を告白された様な状態ではあったが,決してお互いを求め合う程の強烈なエロスは不在だったから,僕自身も特に抵抗感もなく流れに従っていた。プレストンから少しだけブライトン側に入ったインウッドクレセントに早々2階建てのフラットを借りたマシューがドーナツ工場で働き始めて,ベンはそのフラットに間借りしながら“インテリアデザイナー”と称してウィルソン氏から時々依頼を受けている様なことを言っていた。知り合って間もない2人の日本人の素性は良く分からなかったが,どうやら一月以上もB&B生活をしていたから裕福な家の出だと思っていると,彼女らに言わせれば朝食や風呂,トイレも付いて1泊8ポンドなら日本で下手なアパート生活をするより快適で格安だという論に舌を巻いた。ただ,僕の住むフラットが1ヶ月150ポンドだという事を聞いて,それを目当てにしていたのか僕が通っていた英語学校への9月入学を決めたのだと言ってきた。
ウィルソン氏はとても知的で日本通だった。彼が所有する店舗やフラットの内装デザインをベンが手伝っている関係で僕たちの物件探しに協力してくれた。偶々コレクションの日本刀を自慢された際,その柄部分に刻まれた文字を僕が解説したことを大層喜んで,僕たちの引越しについていろいろと配慮してくれたので有り難かった。僕とカリンが住もうと決めたフラットはブライトンの海岸通りから緩やかな上り坂になったロワーロックガーデンズという通りに面していた。ウィルソン氏曰く,その近隣にはゲイのコミュニティが多く集まっているから家賃も格安で,電気やガス,水道など一切込みで一月100ポンドという耳を疑うほどの提示だった。当時の英国では男女問わず同性愛者が堂々と暮らしていたから意外だったが,不動産の価値が若干下がって家賃が安くなるのは大歓迎だった。しかもカリンがカレッジに通うという話を聞くと勉強机やスタンドまで用意してくれ,僕たちが生活するのに何の不自由もなかったが,彼の早合点でダブルベッドが1つだけ用意されたことに僕は若干尻込みした。
サマーバンクホリデーの26日の昼過ぎ,ウィルソン氏の手解きもあって僕たちは一斉に引越しと手続きを済ませることができた。前日の昼前に突然遊びに来たジエイが「間に合って良かった」と喜んでいた。彼と食べた日本の即席ラーメンがそのフラットでの最後の食事になった。その後出かけた近所のバーでは「引越祝い」だと称してジエイがカールスベルグを1杯奢ってくれて,彼はその足でガトウィックへ向かった。ブライトンターミナルでの別れ際「もう大丈夫そうだな」と優しい笑顔を向けてくれたジエイと力強く抱き合った時,彼とは今生の別れをしたつもりだった。
僕が元々使っていたフラットの仲介は別の不動産エージェントで契約も大分残していたが,その辺もウィルソン氏が上手にやりくりしてくれて,移動の時間も含めて引っ越しは3時間ほどで終了した。新しい居所からはブランズウィックがかなり遠ざかってしまったし,週末のマシューとの約束にはバスを使わなければならなくなったが,残念な気持ちは殊更なかった。
その日の夜、ベン達がブランズウィックでの引越祝いを計画していたが,カリンと僕はそれを丁寧に断って,先ずは新生活に必要な物を買いに出かけることにした。坂を少し上ったセントジェームズストリートにはセインズベリーという休日も営業しているスーパーもあったし,リサイクルショップ,金物屋等々,ウィルソン氏がそこまで考えてくれたとは思わないが,とにかく欲しい物は何でも手に入る通りだった。僕たちはカーテンやシーツ,当面の食料の他に,屋台で売られていたケバブと冷えた瓶ビールを買い込んできて,2人で新生活の門出を祝うことにした。その日は夏らしい暑さで1時間ほどの買い出しでも大分汗をかいたが,地下室の様な造りのフラットに戻るとひんやりとして心地良かった。部屋に入ってすぐにカリンがベッドの上に飛び込んだ。彼女はすぐに身体を起こしてマットの上に足を組んで座ると,自分の左側をポンポンと叩いて僕のことを招いた。僕は少し照れ臭かったが,彼女の横に静かに座ってみると,カリンが小柄なこともあったが,思いの外広々としたベッドに安心した。僕が「大きいね」と言うと,彼女は上目遣いに少し頬を赤らめた。
20畳程のワンルームの小さなキッチンの前には2人掛けのテーブルと椅子が据えられていたから,僕たちはそこで祝杯を挙げた。僕たちの定番メニューになることを予見できるほど美味しいケバブをプレートの上でフォークを使いながら食べていると,突然カリンが切り出した。
「あなたもカレッジに行かない?」
僕の留守中にケンブリッジ大学主催の英語検定に合格したカリンは以前より自信に満ち溢れていた。それとは反対に,帰国してからの3週間をただ思い出だけを人生の拠所にして過ごしていた僕は,きっと彼女にはとても荒んで見えていたのかもしれない。明かりのない真っ暗なトンネルの中を歩いているような日々を過ごしていた僕にとって,カリンのその一言がさり気なく足下を照らしてくれた気がして,その提案を断る理由など何一つ見当たらなかった。