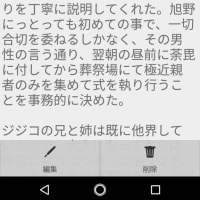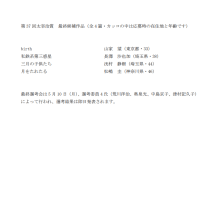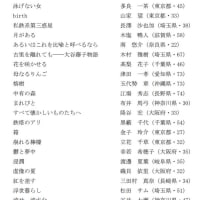9月2日。かくして僕はカリンと地元のカレッジに通うことになった。教頭のムーディ氏は日本のユニバーシティを卒業している僕の入学については手続きが不可能だとは言いながらも,所謂「聴講生」としての通学は許可してくれた。
通ってみれば楽しいもので,コミュニティカレッジの性格上ヨーロッパからの留学生も僅かながらいたし大半が地元のイギリス人で年齢層も広かったから,以前通っていた語学学校に比べれば何倍も有意義な時間を過ごすことができた。自転車での通学は急な坂が多い街中では少々骨を追ったものの下り坂を風を切りながら走る時はこの上なく爽快だった。
カリンとは選択している授業時間が区々だったから一緒のクラスで学ぶことがない上に登下校の時間も別々だったけれど,朝食と夕食は2人で仲良く食べた。特に夕食では週に数回は例のケバブで済ませる事が多かったから,水曜日の夕方6時前に僕がセントジェームズストリートの上り坂を自転車を引きながら歩いて行くと,屋台から身を乗り出して僕の姿を確認したアハメッドという店員が予め2人前料理して待っているのが当たり前にもなってしまっていた。そんなとき僕が冗談で「今日は要らないよ」というと,愛想の良い笑顔を振りまきながら「特別サービスで大盛りにしてあるし,チリソースもいっぱいかけてあって美味しいよ」と語りかけてくるのがルーティーンだった。
カリンと僕の中途半端な関係はある意味「良好」に続いていた。最初は一緒に床に就くのも,シャワーを浴びた後Tシャツと下着1枚で過ごすカリンの露わな姿にドギマギしたものだが,2週目に入る頃にはすっかり慣れてしまい目のやり所に困ることも少なくなっていった。確かに女性としては意識してはいたが,その頃はまだ僕の中でのアジャの存在が大きすぎて,失礼な言い方だがカリンのことを愛おしく思うまで至らなかった。
マシューとの作業も順調にいっていた。彼は元々のんびりとしている性格だったから,素人の僕がモタモタしていても全然気にしなかったし,時々説明書とにらめっこして彼が考え込んでいる間もそっとしておくのが常だったからきっと気楽だったのかもしれない。それでもナイト夫妻が「調子はどうだ」とか「いつ完成するんだ」とか根掘り葉掘り聞いてくる時には唇をへの字に結んで答えるのに苦慮している様だった。ナイト夫妻とマシューは組み立て作業より紅茶を飲みながらたわいない話題でお喋りする方を優先したから作業は遅々として進まなかった。僕は主に配線の整理を担当していたが,無数のカラフルな配線コードを束ねたりボディの内側に取り付けたりしている時に,あの“カーボム”のことが脳裏から離れなかった。リアノは自動車には爆弾となる素質が備えられていると言っていた。ちょっとだけ配線を弄ってやることで自動車は小規模なロケットの働きをするのだという。僕があの日のことを思い出しながら1本1本確認しながら作業しているのを見て,一度だけマシューが「丁寧だな」と言ったが,それは決して嫌みではなかったはずだ。
アジャの国の政情はイギリスでもトップニュースとして扱われることが多くなっていた。僕が活動していた場所にも8月中旬に“連邦軍”から大規模な攻撃が加えられたし,9月22日の日曜日には首都も総攻撃を受け,視察の為に上空を飛んでいた国連のヘリコプターも撃墜されて16人の職員が亡くなったという。イレイナの消息が分からなかったこともあったし,未だにアジャとイーゴの死を受け入れることのできなかった僕にとって,そんなニュースを目にする度,頭を金属の棒で力一杯殴られるような激しい衝撃を受けた。
10月5日。朝早くからナイトさんの家へ行く準備をしていると,カリンが学校からもらってきたガーディアンの束が何となく気になって天辺に無造作に置かれていた古い新聞を開いた。「ヨーロッパ研究」という科目の資料に使うスクラップブック用に,カリンは廃棄する新聞を1週間分まとめてもらってきてはせっせと記事の整理に勤しんでいた。土曜日はナイトさんの家で夕食を頂くのが楽しみになっていたから,翌日のサンデーサービスの準備があるカリンは昼間は自分の研究と教会の支度で忙しなく過ごしていた。普段はお互いの生活を尊重してスクラップブックに目を通すことはなかったが,まだ作業の途中らしき新聞の赤いペンで枠が付けられた記事に僕は釘付けになった。
「戦地で戦う日本人」という題は勿論のことだが,強烈に目に飛び込んだのは新聞の1/6程を占める大きな写真の中でこちらを殺気立った表情で睨み付ける髪や髭を伸ばし切ったミリシエマンの姿だった。身体の右側に巨大な重機関銃を携え,そのチャンバーにつなげられたアモーを左手で支えている様子はまるで映画の「ランボー」そのままだった。記事にはアジャの国の内戦で勇敢に戦う“平和主義の国”日本から来た多くの青年達の武勇伝が取り上げられていた。僕はカリンの勉強机の椅子にドサっと座り込んで,バスの時間も忘れてその写真に見入っていた。朝食の後片付けをしていたカリンがその様子に気づいて僕の両肩に手をかけて話しかけてきた。
「驚くでしょ。戦っている日本人がいるなんて・・・」
「君がみつけたのか」
「アジャの国のことだもの。研究課題はこれしかないと思ったのよ」
「いや,そうじゃなくて・・・」
僕はスタンドを灯してもう1度記事の写真を見つめた。
「円山さん・・・」
「え?」
そんな恐ろしい形相をしたところを僕は見たことがなかったけれど,その写真は間違いなく円山さんのものだった。僕たちはしばらくの間言葉を失った。そして薄らいでいたはずの悲しい記憶が一気に僕の中で目覚めていった。帰りのトラックの荷台でのリアノの一言が僕の耳元に蘇って目の前が真っ暗になった。
「お前にも引き金を引く理由ができたのか」
円山さんがそんな結論に達したのだという事実を僕はその時信じることができなかった。