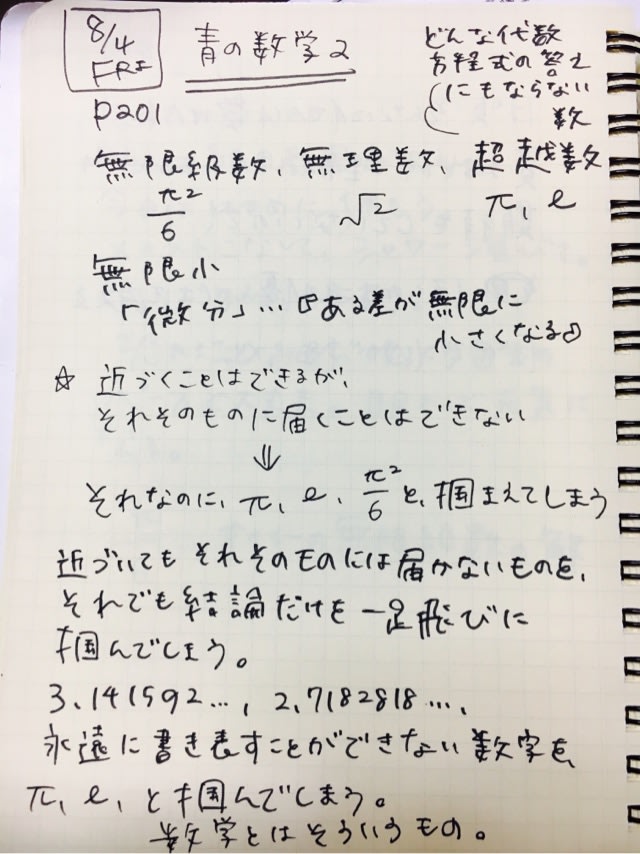積み本の一冊。
どうして買ったのか、ピンと来たのか、もう覚えてなくて、すこし首を傾げながら読んだのだけれど…すごく、良い本だった。
最近、読む本によくバッハのゴールドベルク変奏曲が出てくる。
好きな曲なので、嬉しくなる。
数年前、不眠症で苦しんでいた時に、眠れない夜のための音楽だよ、と母が、CDを棚から出してくれた。
眠れない長い夜に、何度も何度も繰り返し聴いていた。それはまるで慰めのように、わたしのなかに沁み渡っていた。
酷い不眠が治ってからも、すっかり好きになって定期的に聴いている大事な曲。