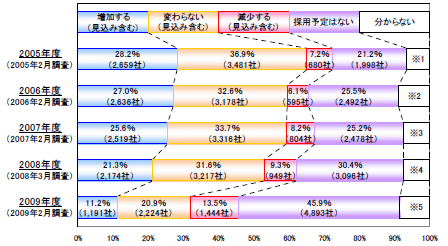米調査会社comScoreが1月22日に公表したデータによると、Googleの878億件という検索数は前年同月比で58%の増加となるもの。この圧倒的な検索数が貢献し、Googleは2009年10~12月期、49億5000万ドルの売り上げに対して19億7000万ドルの利益を確保した。
Googleではこの数字をさらに伸ばすために、モバイル分野の検索、広告、アプリケーションの融合に注力する方針だ。この取り組みには、ソーシャルネットワーキング機能を盛り込んだロケーションベース技術も活用される。
Googleで製品管理を担当するジョナサン・ローゼンバーグ上級副社長によると、同社の10~12月期の好調な業績は、検索、検索連動広告のAdWords、ディスプレイ広告への取り組み強化の成果だという。
「昨年は検索事業が極めて好調だった。これは取り組みを強化することで、われわれが何を達成できるのかを示す好例だ」――1月21日に行われた 10~12月期決算発表の電話会見でローゼンバーグ氏はこう語った。さらに同氏は、Google検索の品質を高めるために、インデックスの拡大と高速化、ユニバーサル検索の拡張、Googleの新しい音楽検索サービスなど550件の機能強化が施されたことを明らかにした。
しかし何といってもGoogle検索で達成された最大の機能強化は、12月7日に発表されたリアルタイム機能だ。 GoogleはTwitterのツイート(つぶやき)、Facebookのパブリックステータスの更新、MySpace、ニュースサイト、ブログなどからの情報をリアルタイムで検索できるようにしたのだ。これらのコンテンツは、ネット上に公開されてからわずか数秒でインデックス化される。
「2週間前にカリフォルニア州を襲ったマグニチュード4.1の地震発生から2分後には、Googleのリアルタイム検索アルゴリズムにより、現地からの Twitterのツイートや報道が検索結果に反映されるようになった」とローゼンバーグ氏は語った。こういったタイプのコンテンツを取り込むことによってユーザーをGoogleに引き付ける、というのが同社の狙いだ。
リアルタイム検索機能が収益に与える効果を測定するのは困難だが、Googleのエリック・シュミットCEOは電話会見で「リアルタイム検索は大成功だった」と述べた。
GoogleのライバルであるYahoo!とMicrosoft Bingも、Googleの“大成功”の気分を味わいたいだろうが、Yahoo!とMicrosoftが今年、首尾よく手を結ぶことができたとしても、検索市場での両社のシェアは28~30%にすぎないだろう。comScoreの発表によると、昨年12月の米国の検索市場でのGoogleのシェアは 65.7%だった。
MicrosoftとYahoo!の検索提携は当局の承認待ちの段階だが、ローゼンバーグ氏によると、Googleは今年、検索ビジネスの取り組みをさらに強化する方針だという。Googleが今後も成功を継続する上で1つの鍵となるのが、検索結果を表示するまでの時間を短縮することだ。すなわち、 Webページ、地図、ビデオ、各種Webサービスを競合検索エンジンよりも素早くユーザーに提供するということだ。
Googleはソーシャル検索技術も強化する計画だ。といっても、FacebookやMySpaceなどに対抗するソーシャルネットワークを Google自身が立ち上げるというわけではない。ローゼンバーグ氏によると、Googleは自社のすべての既存製品のソーシャル化を進めるのだという。
「人々は他人から聞いたレストランや映画の評価よりも、友人による評価の方を信用するのではないだろうか」と同氏は話す。Googleはこの分野で「Google Social Search」という基盤を(ラボの中ではあるが)既に構築した。この技術は、Googleのユーザーベース内で友人や知人のレビューやブログなどのコンテンツを検索結果として表示するというもの。
さらにGoogleは、ソーシャル検索の取り組みと並行して、ロケーションベースの検索と電子商取引の技術も活用する考えだ。同社はユーザーの地元の企業や店舗を検索結果によりよく反映させる「Place Pages」を立ち上げたほか、自社の地域情報検索技術を強化するためにYelpの買収にも動き出した。
モバイルデバイス愛好家に耳よりなニュースもある。ローゼンバーグ氏によると、Googleは今年、モバイル技術にさらに力を入れる方針だという。
「当社の検索とそのほかのサービスに携帯端末からアクセスするユーザーが増えている。最近の携帯電話は、GPSやカメラなど多数の機能を搭載しているため、モバイルベースのWebがPCベースのWebよりも優れた環境になる可能性もあると思う」と同氏は語る。
GoogleのモバイルOSであるAndroidを搭載したスマートフォン(GoogleのNexus Oneなど)を、モバイルベースの検索、アプリケーション、広告と組み合わせるというのは、Googleが検索市場の支配をPCから携帯端末に拡大するための優れた手段であるように思える。
Googleは今年、Microsoft、Yahoo!、Appleと対抗するための武器としてモバイル技術を駆使するものとみられる