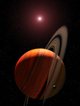|
The pressure Rublev is subject to is not an exception. An artist never works under ideal conditions. If they existed, his work wouldn't exist, for the artist doesn't live in a vacuum. Some sort of pressure must exist: the artist exist because the world is not perfect. Art would be useless if the world were perfect, as a man wouldn't look for harmony but would simply live in it. Art is born out of an ill designed world. This is the issue in "Rublev": the serch for harmonic relationships amone men, between art and life, between time and history. That's my film is all about. Another important theme is man's experience. In this film my message is that it's impossible to pass on experience to others or learn from others. We must live our own experience, we cannot inherit it. People often say: use your fathers' experience! Too easy: each of us must get its own. But once we've got it, we no longer have time to use it. And the new generations rightly refuse to listen to it: they want to live it, but then they also die. This is the law of life, its real meaning: We cannot impose our experience on other people or force them to feel suggested emotions. Only through personal experience we understand life. Rublev, the monk, lived a complex life: He studied with master Rodonevsky at the Holy Trinity, but he lived at variance with his teaching. He got to see the world through his master's eyes only at the end of his life that he lived his own way. |
ルブリョフがさらされていたプレッシャーは例外ではありません。芸術家は理想的な条件のもとで仕事ができることは決してありません。もし理想的な状況が存在するなら、仕事は存在しません、芸術家は何もないところに生きているのではないからです。ある程度のプレッシャーは存在しなければなりません。芸術家が存在するのは世界が完全ではないからです。世界が完全なら芸術は無用の長物です。人間は調和を求めるのではなくその中に生きているのですから。芸術は世界がうまく作られていないから生まれたのです。これが『ルブリョフ』の問題なのです。人間間の、芸術と人生の間の、時間と歴史の間の調和の探求なのです。それが私の映画が扱っているすべてなのです。 もう一つの大切なテーマは人間の経験です。この映画での私のメッセージは経験を他の人に伝えたり、他の人から学ぶことはできないとういことです。私たちは自分の経験を生きなければなりませんが、それを伝えることはできません。お父さんが教えてくれたでしょ、とよく言われます。安易すぎます、一人一人が自分で経験しなければならないのです。いったん経験してしまえば、もう使うことはありません。新しい世代はそれに耳を貸しません。自分たちで生きたいのですが、彼らもまた死にます。これが生命の法、生命の本当の意味なのです。私たちは自分の経験を他の人たちに押しつけることはできませんし、推奨された感情を無理に感じさせることはできません。個人的に経験することで私たちは人生を理解するしかないのです。僧であるルブリョフは複雑な人生を生きています。師であるロドネフスキーとともに三位一体について研究していましたが、彼の教えに納得できず生きています。彼が師の目で世界を見れるようになったのは自分なりに生きた死ぬ間際になってからでした。 |
|
Andrey, what is art? |
芸術とは何ですか。 |
|
Before defining art or any concept--we must answer a far broader question: what's the meaning of man's life on Earth? Maybe we are here to enhance ourselves spiritually. If our life tends to this spiritual enrichment, then art is a means to get there. This, of course, in accrodance with my definition of life. Art should help man in this process. Some say that art helps man to kwow the world. I don't believe in this possibility of knowing, I am almost an agnostic. Knwoledge distracts us from our main purpose in life. The more we know, the less we know; getting deeper our horizon becomes narrower. Art enriches man's own spiritual capabilities and he can then rise above himself to use what we call "free will" |
芸術またはどのような概念も定義する前に、もっとずっと大きな質問に答えなければなりません。この地上における人間の人生の意味は何かという問題です。たぶん私たちがここにいるのは精神的に自己を高めるためです。もし私たちの人生が精神的な豊かさへ向かうのなら、芸術はそこへ到達するための手段です。このことはもちろん私の人生の定義と一致しています。芸術はこの過程にある人間を助けるものなのです。芸術は人間が世界を知るのを助けてくれる、と言う人がいます。私は知ることはできないと思います。私はほとんど不可知論者です。知識は私たちを人生の主目的から引き離してしまいます。知れば知るほど、わからなくなります。深くなればなるほど、私たちの地平は狭くなります。芸術は私たち自身の精神的な力を豊かにします。そうなると私たちが「自由意志」と呼ぶもので自分を超えていけるようになるのです。 |
|
What would you like to tell young people? |
若い人たちに伝えたいことはございますか。 |
|
Learn to live solitude, to be more alone with yourselves. The problem with young people is their carrying out noisy and aggressive actions not to feel lonely. And this is a sad thing. The individual must leran to be on his own as a child for this doesn't mean to be alone: it means not to be bored with oneself, which is a very dangerous sympton... almost a disease. Hey, beauty, come here! How beautiful.. Fabulous animal! How nice is the sound of a horse passing by... |
孤独に生きることを学ぶことです、もっと自分だけでいることを学ぶことです。若い人の問題は寂しさを感じないように騒がしいことや攻撃的なことを行うということです。ですがこれは悲しいことです。個人個人が子どものころに自分自身であることを学ばなければなりません。このことは1人っきりでいるということではありません。自分だけでも退屈しないということです。そのこと自体危険な兆候で、ほとんど病気です。 さあ美よ、ここに来い。何て美しい…素晴らしい生き物。馬が通り過ぎていく音は何て素晴らしいんだ。 |
|
Signor Oshima, lei ha detto che ha iniziato a fare film per caso. Non andava al cinema da giovane? |
大島監督、映画の仕事を始めたのは偶然だとおっしゃいましたが、若い頃は映画を見なかったのですか。 |
|
No, at that time. I was grown up in wartime, so it was very difficult to see movies. But after war, we had nothing to amuse us. So movie is the only one thing to amuse us. So generally we young Japanese liked films very much, every films. But I had no special intention to get in a film world, to become a film director at all. I thought the film business was very far away to our ordinary life. |
当時は見ませんでした。戦争中でしたので映画を見るのは難しかったです。ですが、戦後、楽しみがありませんでしたので、映画が唯一の楽しみでした。ですから大体日本の若者は映画が大好きでした。どんな映画でも。ですが、映画の世界に身を投じ、映画監督になろうとは全く考えていませんでした。映画業界は日常生活からずっと遠く離れている感じがしていました。 |
|
Cosa sognava di fare prima di diventare regista? |
映画監督になる前には何をするおつもりでしたか。 |
|
But when I was a student, I committed a student theater and student movement, so I know something about art and theater or literature. But at that time I didn't think this kind of art thing a lot to be a business of a man, man's life. I think this literature or theater or movie, this kind of things were too soft or too weak to do in my life. |
学生時代には劇団や学生運動にもかかわりましたので、演劇や文学についてはちょっとはわかっています。ですが当時私はそういう芸術のようなものが男の仕事、人生の仕事になるとはあまり思っていませんでした。こういう文学とか演劇とか映画、こういうものは人生をかけるにはゆるいというか弱いと思っていました。 |
|
Ad ogni modo lei ha iniziato a girare dei film. Anche prima che ci incontrassimo qui a Monteux. Dei suoi film emerge un aspetto, un aspetto molto evidente in tutte le sue opera: il suo interesse per la sensualitá. Da dove nasce la sua vision della sensualitá? |
あらゆる方法で映画を撮られていますが、モントゥーでお会いする前から、あなたの映画には特徴があります。あなたのどの映画でも非常にはっきりとしている特徴、つまり官能性への関心です。その官能性のヴィジョンはどこで生まれたのでしょうか。 |
|
So I became…No. I entered film business because I didn't have any other job. I took the examination of the assistant director of Shochiku Ofuna Studio and I entered this studio. But as I told you before, I was not so interested in, not particularly interested in cinema, so I thought “Why I do cinema?” or “What is cinema to me?” I thought about it a lot. For example, some other directors like the cinema very much; they don't think about cinema or they don't think about the relation of cinema and them. On the contrary I thought a lot about cinema and the relation of cinema and me. So it added something very… too much explanation, no, no explanation but too much theory, or theoretical like that added these. So from the beginning of my director's career, I always feel, I have something different from ordinary cinema world. So in any way I wanted to make very peculiar film by my own. |
まあ、私が映画監督に、いや、映画の世界に入ったのは他に仕事がなかったからです。松竹大船スタジオの助監督の試験を受けて、このスタジオに入りましたが、前にもお話ししました通り、私はあまり、特に映画に興味があったわけではありませんので、「なんで映画をするのか」ですとか「映画とは私にとって何なのか」ということをよく考えました。たとえば、ほかの監督は映画が大好きで映画についてとか映画と自分の関係について考えません。それに対して私は映画についても映画と自分の関係についてもよく考えました。ですのでそれによって何かがつけ加わりました、いろんな説明、いや説明ではなくていろんな理論、理論的な部分、そういうものが加わってきました。そういうわけで監督として初めから、いつも普通の映画の世界とは違うものを持っていたと思っています。まあ、多少なりとも自分特有の映画を作りたいと思っていました。 |
|
Vedendo I suoi film e conoscendola di persona, mi chiedo perché abbia deciso di indagare la cultura occidentale, e la sua relazione con il Giappone. Forse perché ha vissuto durante la guerra? |
あなたの映画を見、じかにお会いしますと、あなたが西洋文化と日本文の関係について探求しているのは戦時中に育ったことと関係があるのでしょうか。 |
|
Yes, in any way I think there is a very big misunderstanding existing in the occidental world to Japan. You think Japanese people are grown up purely as Japanese and after that we learn something from occidental culture. But it's not true. From the beginning of our grown up, for example, we hear song lullaby from European lullaby and also we read books of Grimm, or Aesop, like that. And at the beginning of primary school, we learn Shakespeare. We are all Japanese grown up with Japanese culture and also Western culture. So not peculiar to Western culture. So from the beginning we Japanese people are very interested in, are very strongly influenced by Western culture. But I have a special reason because when I was thirteen Japan defeated in the Second World War. So we were very keen why we were defeated by European, by American. So we wanted to learn very keenly European culture or American culture. And also we thought we're our faults of Japanese culture, which was defeated. We thought this is not only military defeat but also this is a cultural defeat. So we are very keen to learn European or American culture. And when I entered film business, I thought total Japanese cinema was very bad. The biggest reason is always Japanese movies describe people very passive way. The protagonist is always passive, passive from society. They are always not attacker, but always passive. And they always suffer by the war and federalism of Japan and poorness of Japan. These three things are very close to every protagonist in Japanese cinema. So the directors always weep or very sympathize with this passive people. And people want to cry about this. I don't like this passive way. I think human beings must be very independent himself, not to be slave of society in mentality. So I want to change this situation of Japanese cinema and also this situation of Japan. So of course before I entered the studio I saw a lot of European and American cinema I wanted to take good things from these European culture and European cinema. |
はい、多少なりとも、西洋世界には日本に対する誤解があると思います。日本人は純日本的に育ってから西洋文化を学んでいくと思われているようですが、そうではありません。私たちは子供のころから、たとえば、歌、子守歌、西洋の子守歌を聞きますし、グリムやイソップの本やそういうものも読みます。小学校の初めにシェイクスピアを学びます。私たちはみな日本文化と西洋文化とともに成長した日本人なのです。西洋文化に限ったことではありませんが。ですから小さいころから私たち日本人は西洋文化にとても興味がありますし、とても強く影響を受けているのです。ですが私に特別な理由があるのは、私が13歳の時に日本が第2次世界大戦に負けたからなのです。ですので、私たちはなぜヨーロッパやアメリカに負けたのかに強い関心を持っていましたし、ヨーロッパやアメリカの文化をよく知りたいと思っていました。さらに戦争に負けたことで日本文化が間違っているとも思っていました。軍事的な敗北だけではなく文化的な敗北でもあると思っていたのです。ですので私たちはヨーロッパやアメリカの文化を学ぶことに強い関心を持っているのです。映画の世界に入ったとき、私は日本映画全体がとてもひどいものだと思っていました。その一番の理由は日本映画の登場人物はいつも受け身なのです。主人公はいつも受け身、社会のなすがままなのです。攻撃することは一度もなく、常に受け身なのです。いつも戦争と日本の封建制度と日本の貧しさに苦しめられています。日本映画の主人公はこの3つのとても近くにいます。映画監督は常にこの受け身の人たちに涙し同情しているのです。観客もこういうのを見て泣きたがっているのです。ですが私はこういう受け身は好きではありません。私は人間は自立するものだと思っています。精神的に社会の奴隷になってはいけないと思っています。ですから私はこの日本映画と日本の状況を変えたいと思っています。もちろん映画界に入る前に、たくさんの洋画を見ていましたので、ヨーロッパの文化やヨーロッパの映画の良いところは使いたいと思っていました。 |