わたしは特に相撲に興味はない。それでも若貴兄弟が活躍していた頃は
何人かの力士は知っていたかなー。今はほぼ知らない。
現役力士の名前を挙げろと言われても一人も出て来ない。
そんなわたしには、この本に書いてあることはほとんど全て、初めて知ることばかりだった。
といっても、著者は芸風としてハズシ技の人なので、
そもそも多少相撲を見る人・好きな人が読んでもこの本は聞いたことがないことばかり
なのではないだろうか。
たとえば。
力士たちは「気がついたらここにいた」。勉強が苦手なのでどうしようと思っていたら、
周囲に勧められるままなんとなく相撲部屋に入っていた。
相撲を取る時はとても怖い。稽古でさえとても怖く、遠慮してしまう。
厳しい稽古が想像されるが、実際に取り組みの練習をしている時間はとても短い。
朝から11時頃まで練習し、その後は食事をし、昼寝をし、起きて掃除などをし、
夜ご飯を食べ、そして寝る。
お相撲さんが太れるのは食べ続けられるから。食べ続けられるコツは、限界が来たら
一点を見つめ、体も動かさないようにしてひたすら機械的に物を口に運ぶこと。
などなど。
まあこういう細かいことならまだわかるが、
相撲が「国技」になった経緯は、明治初期に相撲常設館を「国技館」と名付けたことから
始まる。その名前のアイディアは江見水蔭という小説家から。
設立委員長であった板垣退助はのちにそのネーミングの選択を後悔し、
「武育館とつければ良かった」と書いている。
それまでは相撲は国技とされてはいなかった。
こうなると「え!?」というしかない。
この人はユルい視点で笑わせる芸風だが、いや、これほんと?と思うと、
今までわたしが知っているつもりだった「相撲」という存在が、まったく違うものである
可能性が出て来て愕然とする。
相撲好きの人に一度読んでみて欲しい本。これが事実だとすれば、おすもうって何?と
思いませんか。
そして愕然とするといえば、わたしはこの人の本をここんとこ10冊近く読んで来た
というのに、今回名前の読みが「たかはし・ひでみね」であることを知って一驚した。
「ひでみ」だと思っていた。せめて「ひでざね」までだろう。
何人かの力士は知っていたかなー。今はほぼ知らない。
現役力士の名前を挙げろと言われても一人も出て来ない。
そんなわたしには、この本に書いてあることはほとんど全て、初めて知ることばかりだった。
といっても、著者は芸風としてハズシ技の人なので、
そもそも多少相撲を見る人・好きな人が読んでもこの本は聞いたことがないことばかり
なのではないだろうか。
たとえば。
力士たちは「気がついたらここにいた」。勉強が苦手なのでどうしようと思っていたら、
周囲に勧められるままなんとなく相撲部屋に入っていた。
相撲を取る時はとても怖い。稽古でさえとても怖く、遠慮してしまう。
厳しい稽古が想像されるが、実際に取り組みの練習をしている時間はとても短い。
朝から11時頃まで練習し、その後は食事をし、昼寝をし、起きて掃除などをし、
夜ご飯を食べ、そして寝る。
お相撲さんが太れるのは食べ続けられるから。食べ続けられるコツは、限界が来たら
一点を見つめ、体も動かさないようにしてひたすら機械的に物を口に運ぶこと。
などなど。
まあこういう細かいことならまだわかるが、
相撲が「国技」になった経緯は、明治初期に相撲常設館を「国技館」と名付けたことから
始まる。その名前のアイディアは江見水蔭という小説家から。
設立委員長であった板垣退助はのちにそのネーミングの選択を後悔し、
「武育館とつければ良かった」と書いている。
それまでは相撲は国技とされてはいなかった。
こうなると「え!?」というしかない。
この人はユルい視点で笑わせる芸風だが、いや、これほんと?と思うと、
今までわたしが知っているつもりだった「相撲」という存在が、まったく違うものである
可能性が出て来て愕然とする。
相撲好きの人に一度読んでみて欲しい本。これが事実だとすれば、おすもうって何?と
思いませんか。
そして愕然とするといえば、わたしはこの人の本をここんとこ10冊近く読んで来た
というのに、今回名前の読みが「たかはし・ひでみね」であることを知って一驚した。
「ひでみ」だと思っていた。せめて「ひでざね」までだろう。










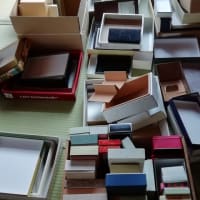













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます