安定と信頼の吉川弘文館人物叢書。
長いシリーズなので出版は遠い昔。
とはいえ現在もシリーズは出続けており、いずれギネスにも乗るのではなかろうか。
がんばって欲しいものです。
この本自体は昭和61年刊。1986年。まあ40年前ですか。
40年の間に研究も進んだかもしれないけど。著者は大正7年生まれ。
渡辺崋山は「風雲児たち」で読んだ時に、妙に心に残ったのよ。
その哀れな一生が。
貧乏な藩の貧乏な武士の家に生まれ。家を支えるためにも若い頃に絵を志すも、
お家に仕えるためにその絵の道はあきらめなければならなかった。
それほど家格の高い家ではなかったようだが、父祖の頃から藩主のそば近く使える立場で、
のちに本人が家老の一人になり、藩の立て直しに尽力するようになる。
しかし結果的に立て直しは出来なかった。
それを本人の力量の問題にするのはあまりにも酷だろう。
絵も描き、西洋の知識も広く修め、頭も良く、人付き合いも誠実で、孝養を尽くし、
藩主に忠誠心――およそ人としては美点を十分以上に持っていても、
不幸は避け得なかった。
西洋知識の大家として知られるようになった。蘭学関係の知人も増えた。
だが幕府に睨まれ、蛮社の獄へ。
その後、渥美半島の領地への蟄居。自藩とはいえ江戸生まれの江戸育ちには馴染みの薄い地。
絵を描いて生計を立てていたが、蟄居の身には派手に売り出す術もなく。
それでも高名な崋山の絵は引き合いも多かったが、それにより幕府に目をつけられてしまう。
追い詰められた崋山は腹を切る。老母と妻と、子供たちを残して。
良い本だった。崋山のアウトラインは最初の30ページでほぼわかる。
その最初の30ページで生涯の哀れさがもうわかる。
その後はディテイル。それも面白かった。
しかし一番読みたいところである、
1.なぜ鳥居耀蔵は崋山をそんなに目の敵にしたのか。
2.あれほど孝養を言い立てていた崋山がなぜ老母を残して自殺したのか。
この辺は詳しくなかった。もう少し深く読みたかった。
まあこの部分は想像でしか到達出来ないので、学者としては掘り下げは難しいんだろうなあ。
一応、1については
儒学の林家出身(鳥居家へ養子)の鳥居耀蔵は、元々儒門だった崋山が蘭学に
鞍替えしたことに腹を立てていたからといってるし、
2については、罪人がさらにお咎めを受ければ藩主に迷惑がかかるから、と
理由を言っている。
崋山は、――せめて在所で生まれ育っていたら、ここまで悲惨な人生ではなかっただろうなあ。
江戸生まれ江戸育ちであることが良かれ悪しかれ大きな分かれ目だった。
江戸育ちであることで、当時の知識人・趣味人との交わりも広かっただろうし、
情報も比較的入手しやすかっただろう。そのことが当然視野の広さにはつながっただろう。
反面、在所の人々との日々の繋がりがなかったせいで、家老になっても藩政改革の壁は
高かっただろう。近くに住んで、昔から知ってる人が言い出すワケノワカラン新説の方が、
なんぼか受け入れやすかったに違いない。
遠い江戸にいる名のみ高い渡辺崋山――むしろ反感の下地でこそあれ、
受け入れる要素としてはマイナスだろうな。
現状に対する認識は、江戸と田原では違うだろうし。
もう少し忠誠心がなければ。脱藩して生き延びる道もあったのかもしれないが。
誠実だったことの裏目。
だが誠実さを失って生き延びる意味はなかったのかもしれないね。本人は。
面白かったので、崋山関係の本をもう2、3冊読んでみる。
長いシリーズなので出版は遠い昔。
とはいえ現在もシリーズは出続けており、いずれギネスにも乗るのではなかろうか。
がんばって欲しいものです。
この本自体は昭和61年刊。1986年。まあ40年前ですか。
40年の間に研究も進んだかもしれないけど。著者は大正7年生まれ。
渡辺崋山は「風雲児たち」で読んだ時に、妙に心に残ったのよ。
その哀れな一生が。
貧乏な藩の貧乏な武士の家に生まれ。家を支えるためにも若い頃に絵を志すも、
お家に仕えるためにその絵の道はあきらめなければならなかった。
それほど家格の高い家ではなかったようだが、父祖の頃から藩主のそば近く使える立場で、
のちに本人が家老の一人になり、藩の立て直しに尽力するようになる。
しかし結果的に立て直しは出来なかった。
それを本人の力量の問題にするのはあまりにも酷だろう。
絵も描き、西洋の知識も広く修め、頭も良く、人付き合いも誠実で、孝養を尽くし、
藩主に忠誠心――およそ人としては美点を十分以上に持っていても、
不幸は避け得なかった。
西洋知識の大家として知られるようになった。蘭学関係の知人も増えた。
だが幕府に睨まれ、蛮社の獄へ。
その後、渥美半島の領地への蟄居。自藩とはいえ江戸生まれの江戸育ちには馴染みの薄い地。
絵を描いて生計を立てていたが、蟄居の身には派手に売り出す術もなく。
それでも高名な崋山の絵は引き合いも多かったが、それにより幕府に目をつけられてしまう。
追い詰められた崋山は腹を切る。老母と妻と、子供たちを残して。
良い本だった。崋山のアウトラインは最初の30ページでほぼわかる。
その最初の30ページで生涯の哀れさがもうわかる。
その後はディテイル。それも面白かった。
しかし一番読みたいところである、
1.なぜ鳥居耀蔵は崋山をそんなに目の敵にしたのか。
2.あれほど孝養を言い立てていた崋山がなぜ老母を残して自殺したのか。
この辺は詳しくなかった。もう少し深く読みたかった。
まあこの部分は想像でしか到達出来ないので、学者としては掘り下げは難しいんだろうなあ。
一応、1については
儒学の林家出身(鳥居家へ養子)の鳥居耀蔵は、元々儒門だった崋山が蘭学に
鞍替えしたことに腹を立てていたからといってるし、
2については、罪人がさらにお咎めを受ければ藩主に迷惑がかかるから、と
理由を言っている。
崋山は、――せめて在所で生まれ育っていたら、ここまで悲惨な人生ではなかっただろうなあ。
江戸生まれ江戸育ちであることが良かれ悪しかれ大きな分かれ目だった。
江戸育ちであることで、当時の知識人・趣味人との交わりも広かっただろうし、
情報も比較的入手しやすかっただろう。そのことが当然視野の広さにはつながっただろう。
反面、在所の人々との日々の繋がりがなかったせいで、家老になっても藩政改革の壁は
高かっただろう。近くに住んで、昔から知ってる人が言い出すワケノワカラン新説の方が、
なんぼか受け入れやすかったに違いない。
遠い江戸にいる名のみ高い渡辺崋山――むしろ反感の下地でこそあれ、
受け入れる要素としてはマイナスだろうな。
現状に対する認識は、江戸と田原では違うだろうし。
もう少し忠誠心がなければ。脱藩して生き延びる道もあったのかもしれないが。
誠実だったことの裏目。
だが誠実さを失って生き延びる意味はなかったのかもしれないね。本人は。
面白かったので、崋山関係の本をもう2、3冊読んでみる。










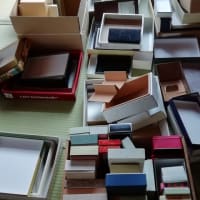















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます