 農業体験や自然探索を楽しみながら子供たちの自然への興味、関心を養う
農業体験や自然探索を楽しみながら子供たちの自然への興味、関心を養う
 「森のようちえん」の取り組みが注目されている。
「森のようちえん」の取り組みが注目されている。鹿児島県環境技術協会も、2008年4月から未就園児を対象にした
「かごしま森のようちえん」事業を計画。今年11月から試行的なプレイベント
を開いて宣伝している。
 「森のようちえん」は、北欧で発祥し世界に広がりつつある自然体験
「森のようちえん」は、北欧で発祥し世界に広がりつつある自然体験重視の保育活動で、自然とのふれあいを通して子供の感性を育て、自然や
環境への関心を深めるねらいがある。
 11月10日、鹿児島市吉野町で開かれた1回目のイベント。
11月10日、鹿児島市吉野町で開かれた1回目のイベント。内容は芋ほりで、未就園の親子約40人が参加した。
 スタッフたちが無農薬で育てたサツマイモは、つるが生い茂り、
スタッフたちが無農薬で育てたサツマイモは、つるが生い茂り、掘り当てるのも、ひと苦労。スコップや手で土を掘ると、子供の手で掘れる
ものから、頭ほどもあるものまで、いくつも連なって顔を出し、歓声が
上がった。
 子供の一人が、カナヘビを発見。「ニホンカナヘビだよ。トカゲと比べて
子供の一人が、カナヘビを発見。「ニホンカナヘビだよ。トカゲと比べて表面がザラザラしているでしょう。もうすぐ冬眠なんだね」指導員の説明を
周りの親子は手を休めて聞き入る。
 お芋そっちのけで、アリやダンゴムシをいじる子も多く、芋ほりを通じて
お芋そっちのけで、アリやダンゴムシをいじる子も多く、芋ほりを通じて、自然との触れ合いを楽しんでいる。
芋ほりが終わると、4~5歳児は芋を天ぷら用にスライス。参加者全員で
主催者が用意したお芋の豚汁や天ぷら、アイスクリームを味わった。
畑の生き物やサツマイモの成長過程の説明もあり、興味深そうに
聞いていた。
22日には、同じ敷地で2回目の催しがあり、5組の親子が冬野菜の
植え付けや焚き火で焼くパン作りに取り組んだ。集めた落ち葉の上でジャンプ
するなど、こちらも親子で楽しむ姿が見られた。
姶良町西餅田の橋口良子さん(34)は、長男和生くん(3)、長女あいちゃん
(1)と、2回とも参加。
 「上の子は初め、土で手が汚れるのを嫌がっていたが、
「上の子は初め、土で手が汚れるのを嫌がっていたが、むしろ楽しむようになってきた。最近は公園でも、汚れを気にせずダイナミック
に遊ぶようになった」と、子供の成長ぶりを実感したという。

 来年4月スタート予定の「かごしま森のようちえん」は、同市吉野町にある
来年4月スタート予定の「かごしま森のようちえん」は、同市吉野町にある広さ約760㎡の民有地をフィールドに、2~4歳の子供を集めて
月1、2回のペースで行う予定。
 環境教育指導者や保育士、ボランティアがスタッフとなり、スウェーデン
環境教育指導者や保育士、ボランティアがスタッフとなり、スウェーデンの多くの保育園で取り入れられている「ムッレ教室」のプログラムを
使って、発達段階に合わせて自然の面白さを感じられるよう働きかける。
 フィールドには、クヌギやイチョウ、クロガネモチ、桜など多くの木々が
フィールドには、クヌギやイチョウ、クロガネモチ、桜など多くの木々が植えられ、小鳥や虫など小動物も多い。
 事業を企画した同協会の環境教育指導員、市川雪絵さん(35)は、
事業を企画した同協会の環境教育指導員、市川雪絵さん(35)は、「継続的に訪れると、季節の移り変わりや天候による変化を感じてもらえる。
自然を好きになることが、環境について考えることにもつながっていく」
と話す。
 また、これまでのプレイベントでは、ボランティアや保護者も生き生きしていた
また、これまでのプレイベントでは、ボランティアや保護者も生き生きしていたといい、「親や地域の人も巻き込んで、みんなで楽しく子供の成長を
見守れるような場にもしていきたい」と語る。
協会は、来年3月にかけて月1~2回ずつプレイベントを開き、
参加者の反応を見ながら4月以降の運営方針を検討していく。
 次回は12日、「ぺたぺたペイント秋色さがし」を開く。
次回は12日、「ぺたぺたペイント秋色さがし」を開く。先着20組、親子で¥1,000
 お問い合わせ。
お問い合わせ。同協会=099(805)0158










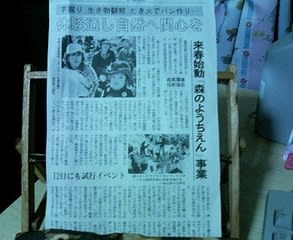

 鹿児島市の桜ヶ丘夢子ども劇場が主催し、毎月第3木曜の午前10時~正午
鹿児島市の桜ヶ丘夢子ども劇場が主催し、毎月第3木曜の午前10時~正午 子供が小中学生になった先輩ママが託児などを手伝ってくれる。
子供が小中学生になった先輩ママが託児などを手伝ってくれる。 こども劇場の会員以外は参加料1回100円。
こども劇場の会員以外は参加料1回100円。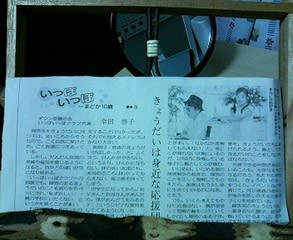
 「なかなか理解してもらえない」と、常に心が晴れない状態にいるのだ。
「なかなか理解してもらえない」と、常に心が晴れない状態にいるのだ。 でも、いくら考えてもやはり近道はない。親が頑張って理解の道を
でも、いくら考えてもやはり近道はない。親が頑張って理解の道を 共感できる仲間が身近にいることも、大きな支えになるだろう。
共感できる仲間が身近にいることも、大きな支えになるだろう。