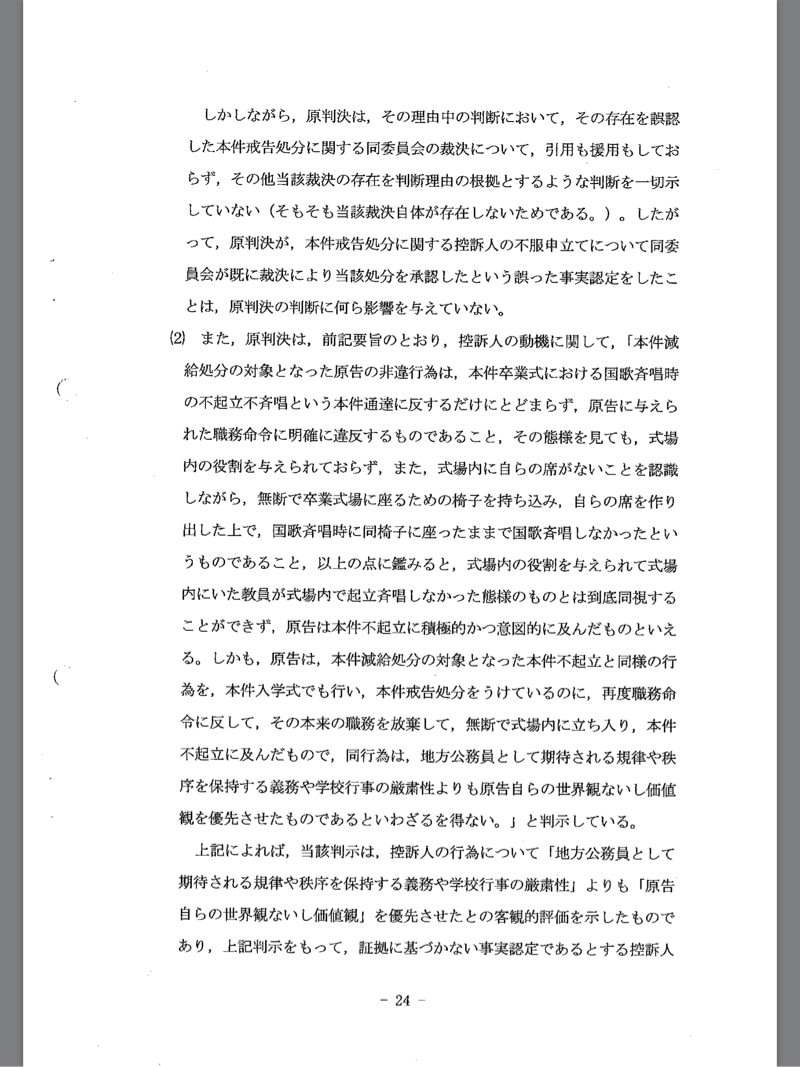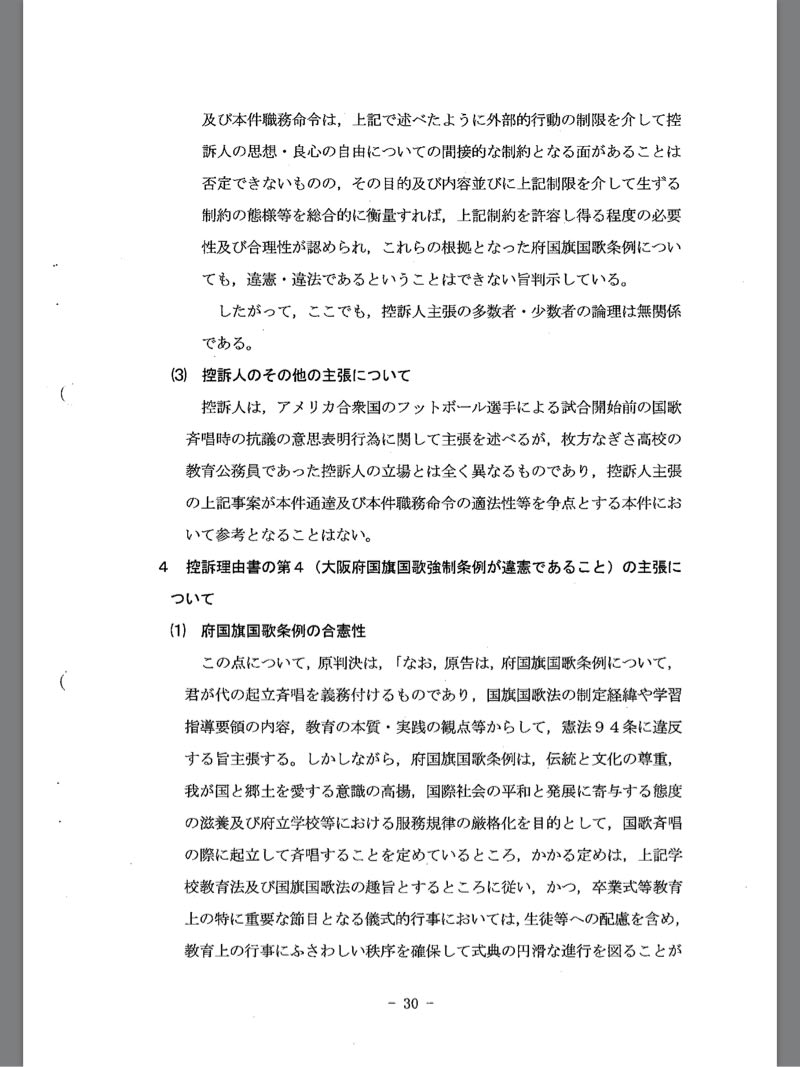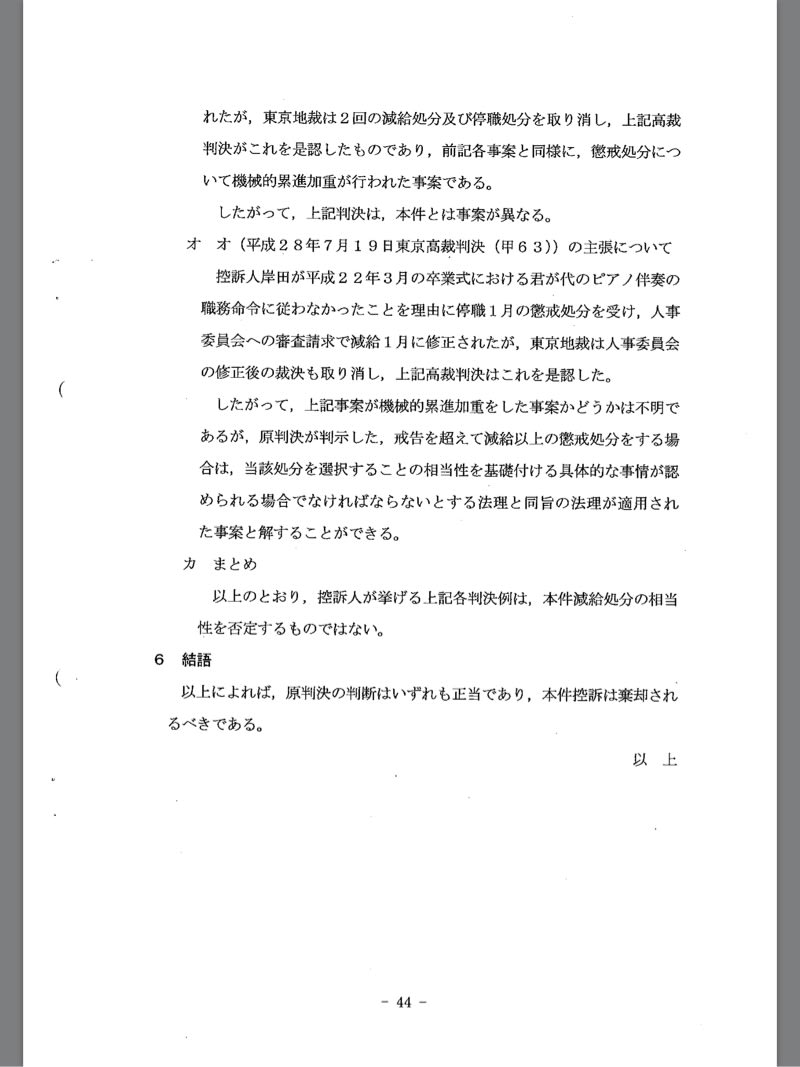1月26日の控訴審第1回口頭弁論を終え、4月18日の第2回口頭弁論に向け、本日、控訴人第2準備書面を大阪高等裁判所に提出します。
提出後、当ブログにも掲載します!まずは、目次を紹介します!
第1 はじめに
第2 西原鑑定意見書に基づく主張の補充(その1、裁量権の逸脱濫用について)
1 裁量権濫用についての判例の枠組み
2 本件における減給処分を基礎づける具体的な事情が存在しないこと
3 比例原則違反及び判断過程の瑕疵
第3 西原鑑定意見書に基づく主張の補充
(その2、思想・良心の自由に対する直接的侵害)
1 最高裁判例の枠組みを超える大阪府の条例の規範構造
2 大阪府国旗国歌条例における特定思想に対する意図的攻撃
3 本件処分の背景としての大阪府基本条例27条2項
4 思想・良心の自由に対する直接の侵害は証拠上明白
5 小括
第4 被控訴人の準備書面に対する再反論
1 人事委員会の裁決についての原判決の事実誤認について
2 控訴人の卒業式参列の動機と「君が代」の起立斉唱をしなかった理由
(1) はじめに
(2)人権教育主担当として7期生(卒業生)を祝福したいという気持ち
(3)「君が代」の起立斉唱が大阪府の人権教育の方針に矛盾すること
3 「君が代」を起立斉唱できない控訴人の思想に着目した処分であること
(1)卒業式の意義について
(2)控訴人の正門警備の役割分担についての事実誤認
(3)厳粛や秩序を脅かしていない事実を無視し思想への処分がされていること
(4)原判決が「世界観を優先した」ことを処分の理由に挙げていること
第5 教員による教育の自由について(主張の補充)
1 原判決の争点判断について
2 旭川学テ事件の理解について
3 教員の責務としての教育の自由について
4 憲法26条により教員の教育の自由が保障されること
第6 さいごに
提出後、当ブログにも掲載します!まずは、目次を紹介します!
第1 はじめに
第2 西原鑑定意見書に基づく主張の補充(その1、裁量権の逸脱濫用について)
1 裁量権濫用についての判例の枠組み
2 本件における減給処分を基礎づける具体的な事情が存在しないこと
3 比例原則違反及び判断過程の瑕疵
第3 西原鑑定意見書に基づく主張の補充
(その2、思想・良心の自由に対する直接的侵害)
1 最高裁判例の枠組みを超える大阪府の条例の規範構造
2 大阪府国旗国歌条例における特定思想に対する意図的攻撃
3 本件処分の背景としての大阪府基本条例27条2項
4 思想・良心の自由に対する直接の侵害は証拠上明白
5 小括
第4 被控訴人の準備書面に対する再反論
1 人事委員会の裁決についての原判決の事実誤認について
2 控訴人の卒業式参列の動機と「君が代」の起立斉唱をしなかった理由
(1) はじめに
(2)人権教育主担当として7期生(卒業生)を祝福したいという気持ち
(3)「君が代」の起立斉唱が大阪府の人権教育の方針に矛盾すること
3 「君が代」を起立斉唱できない控訴人の思想に着目した処分であること
(1)卒業式の意義について
(2)控訴人の正門警備の役割分担についての事実誤認
(3)厳粛や秩序を脅かしていない事実を無視し思想への処分がされていること
(4)原判決が「世界観を優先した」ことを処分の理由に挙げていること
第5 教員による教育の自由について(主張の補充)
1 原判決の争点判断について
2 旭川学テ事件の理解について
3 教員の責務としての教育の自由について
4 憲法26条により教員の教育の自由が保障されること
第6 さいごに