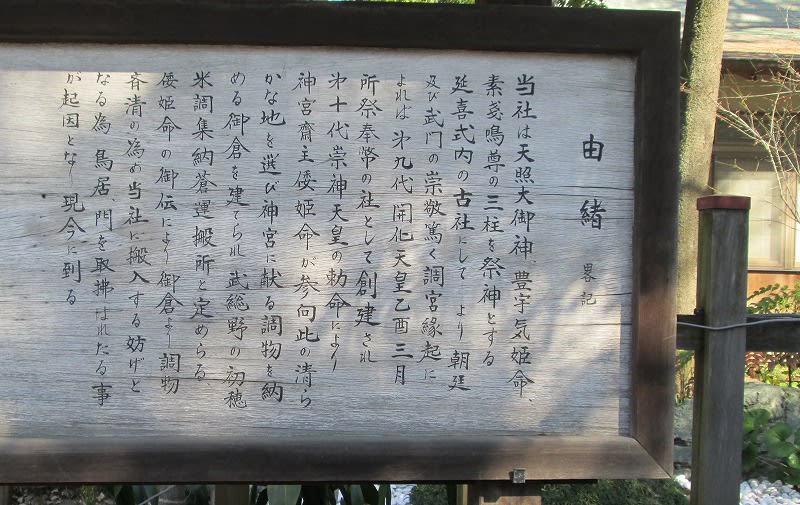2018年1月31日。
家内と志村坂上駅から日本橋まで旧中山道を歩きました。
2015年9月20日~22日、第3番目・浦和宿から第35番目・藪原宿まで。
2015年11月15日~19日、第36番宿・宮ノ越宿から第57番宿・垂井宿まで。
車で廻りました。
2016年2月17日に第3番目・浦和宿から中山道の起点となる日本橋へ向い、
志村坂上駅まで歩きました。
今回は、その続きです。
行程は、ほとんどが国道17号沿いです。
10:05 都営三田線志村坂上駅出発。

2分ほど歩いた所に「志村一里塚」がありました。


南禅院。本尊は、十一面観世音菩薩ですが、承応3年(1654年)に造立されたという庚申地蔵が
あるので寄ってみました。まだ雪が残っています。


縁切榎。江戸時代に道を挟んだ向かい側に屋敷があり、その垣根に榎があって縁切榎と呼ばれたとのことです。
男女の悪縁を切りたい時に、この樹皮を剥いで煎じて飲ませると願いが叶い、霊験あらたかな神木として庶民の
信仰を集め、現在も板橋区の名所として親しまれているとのことです。


中山道板橋上宿。


石神井川に掛かる「板橋」。この橋の名前が板橋という地名なったとのことです。

「石神井川」。

仲宿商店街を通りました。


11:05 この公園でちょっと一休み。

この公園に「加賀藩前田家下屋敷」の案内板があったので、そちらへと寄ってみることしました。

道に迷ってようやく着きました。


この下屋敷は、二万八千坪におよぶ広大な敷地だったとのことです。
また、板橋区は金沢市と友好交流都市協定を結んでいるとのことです。
36分後に旧中山道に戻りました。
会津若松のさざえ堂に似た建物がありました。

12:08 都電荒川線・庚申塚駅を通過。

とげぬき地蔵尊の巣鴨地蔵通商店街を通りました。

赤パンツが有名です。

とげぬき地蔵尊の「高岩山」前を通過。以前、来たことがあるので寄りませんでした。

12:30 この先のイタリアンで昼食。
サラダ、野菜スープ、自家製フォカッチャ。

私が、鶏肉とほうれん草のカレークリームソース。

家内が、ツナのプッタネスカ。

ソーズが美味しい平麺のパスタでした。
13:15 再スタート。
JR山手線巣鴨駅通過。

八百屋お七を供養するために建立した「ほうろく地蔵」がある「高圓寺」へ寄りました。


50m先右側の坂を降りた所にある圓乗寺に「八百屋お七」のお墓があるので寄ってみました。


圓乗寺。



14:10 東大農学部とぶつかったので東大構内を歩くいてみました。

大きな木が多いですね。


正門から出ました。

赤レンガ壁が続いています。

赤門です。

「赤門は、文政10年(1827年)加賀藩主前田斉泰に嫁いだ11代将軍徳川家斉の息女溶姫のために建てられた
朱塗りの御守殿門であり、重要文化財に指定されています。」
「神田明神」前を通り、

鳥居から出ました。

30年ほど前に、ここで会社の後輩が結婚式を挙げた時に仲人をしました。
それ以来ですね。
15:30 ようやく日本橋が目の前に。

日本橋は五街道(東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道)の起点でした。
1601年(慶長6年)に徳川家康が全国支配のために江戸と各地を結ぶの5つの街道を整備し始め、
2代将軍秀忠の代になって基幹街道に定められました。

獅子像。


現在の日本橋は、明治44年(1911年)に完成しました。麒麟像。日本の道路の起点となる日本橋から飛び立つ
イメージから、それまでの麒麟像作品には見られない羽根を付けることを決めたとのことです。



志村坂上からここまでは約20km、5時間20分の歩きでした。
この後、喫茶店で一休みしてから、2kmほど歩いて大手町にある「平将門首塚」へ寄りました。
16:15 首塚。

「一説では京都で処刑され、切られた首が、この地に飛んで来て葬られたのが、大手町将門首塚とされる。
神田明神に祀られており、この地は神田明神創建の地であった。」とのことです。



この後、地下鉄千代田線大手町から帰宅しました。
総行程:約22km、約31000歩でした。
これで、旧中山道:日本橋から第57番宿・垂井宿までが繋がりました。
58番宿・関ヶ原宿から69番宿・大津宿、そして京都までが残り、心残りですが今は続きを考えていません。
●地図

家内と志村坂上駅から日本橋まで旧中山道を歩きました。
2015年9月20日~22日、第3番目・浦和宿から第35番目・藪原宿まで。
2015年11月15日~19日、第36番宿・宮ノ越宿から第57番宿・垂井宿まで。
車で廻りました。
2016年2月17日に第3番目・浦和宿から中山道の起点となる日本橋へ向い、
志村坂上駅まで歩きました。
今回は、その続きです。
行程は、ほとんどが国道17号沿いです。
10:05 都営三田線志村坂上駅出発。

2分ほど歩いた所に「志村一里塚」がありました。


南禅院。本尊は、十一面観世音菩薩ですが、承応3年(1654年)に造立されたという庚申地蔵が
あるので寄ってみました。まだ雪が残っています。


縁切榎。江戸時代に道を挟んだ向かい側に屋敷があり、その垣根に榎があって縁切榎と呼ばれたとのことです。
男女の悪縁を切りたい時に、この樹皮を剥いで煎じて飲ませると願いが叶い、霊験あらたかな神木として庶民の
信仰を集め、現在も板橋区の名所として親しまれているとのことです。


中山道板橋上宿。


石神井川に掛かる「板橋」。この橋の名前が板橋という地名なったとのことです。

「石神井川」。

仲宿商店街を通りました。


11:05 この公園でちょっと一休み。

この公園に「加賀藩前田家下屋敷」の案内板があったので、そちらへと寄ってみることしました。

道に迷ってようやく着きました。


この下屋敷は、二万八千坪におよぶ広大な敷地だったとのことです。
また、板橋区は金沢市と友好交流都市協定を結んでいるとのことです。
36分後に旧中山道に戻りました。
会津若松のさざえ堂に似た建物がありました。

12:08 都電荒川線・庚申塚駅を通過。

とげぬき地蔵尊の巣鴨地蔵通商店街を通りました。

赤パンツが有名です。

とげぬき地蔵尊の「高岩山」前を通過。以前、来たことがあるので寄りませんでした。

12:30 この先のイタリアンで昼食。
サラダ、野菜スープ、自家製フォカッチャ。

私が、鶏肉とほうれん草のカレークリームソース。

家内が、ツナのプッタネスカ。

ソーズが美味しい平麺のパスタでした。
13:15 再スタート。
JR山手線巣鴨駅通過。

八百屋お七を供養するために建立した「ほうろく地蔵」がある「高圓寺」へ寄りました。


50m先右側の坂を降りた所にある圓乗寺に「八百屋お七」のお墓があるので寄ってみました。


圓乗寺。



14:10 東大農学部とぶつかったので東大構内を歩くいてみました。

大きな木が多いですね。


正門から出ました。

赤レンガ壁が続いています。

赤門です。

「赤門は、文政10年(1827年)加賀藩主前田斉泰に嫁いだ11代将軍徳川家斉の息女溶姫のために建てられた
朱塗りの御守殿門であり、重要文化財に指定されています。」
「神田明神」前を通り、

鳥居から出ました。

30年ほど前に、ここで会社の後輩が結婚式を挙げた時に仲人をしました。
それ以来ですね。
15:30 ようやく日本橋が目の前に。

日本橋は五街道(東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道)の起点でした。
1601年(慶長6年)に徳川家康が全国支配のために江戸と各地を結ぶの5つの街道を整備し始め、
2代将軍秀忠の代になって基幹街道に定められました。

獅子像。


現在の日本橋は、明治44年(1911年)に完成しました。麒麟像。日本の道路の起点となる日本橋から飛び立つ
イメージから、それまでの麒麟像作品には見られない羽根を付けることを決めたとのことです。



志村坂上からここまでは約20km、5時間20分の歩きでした。
この後、喫茶店で一休みしてから、2kmほど歩いて大手町にある「平将門首塚」へ寄りました。
16:15 首塚。

「一説では京都で処刑され、切られた首が、この地に飛んで来て葬られたのが、大手町将門首塚とされる。
神田明神に祀られており、この地は神田明神創建の地であった。」とのことです。



この後、地下鉄千代田線大手町から帰宅しました。
総行程:約22km、約31000歩でした。
これで、旧中山道:日本橋から第57番宿・垂井宿までが繋がりました。
58番宿・関ヶ原宿から69番宿・大津宿、そして京都までが残り、心残りですが今は続きを考えていません。
●地図