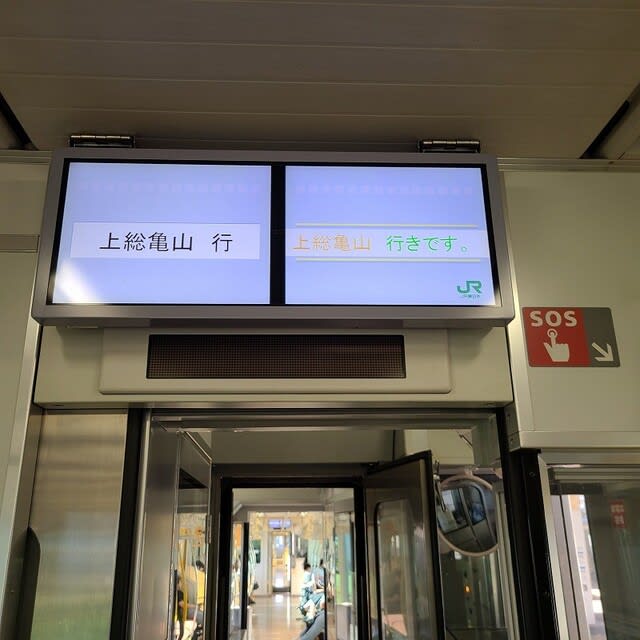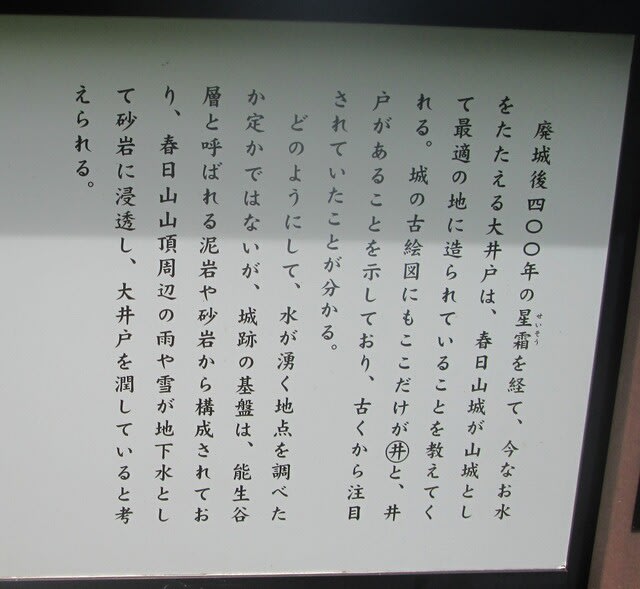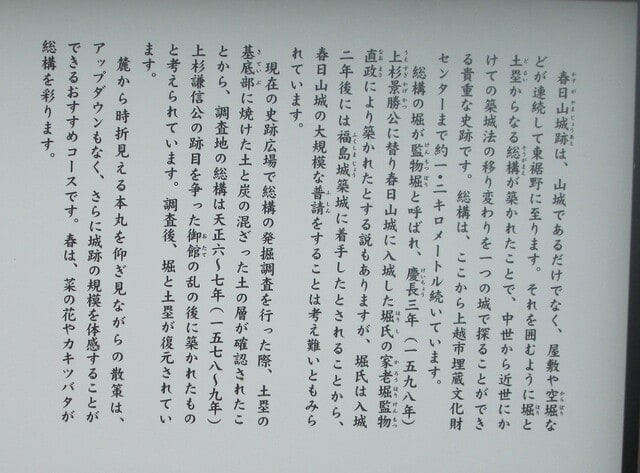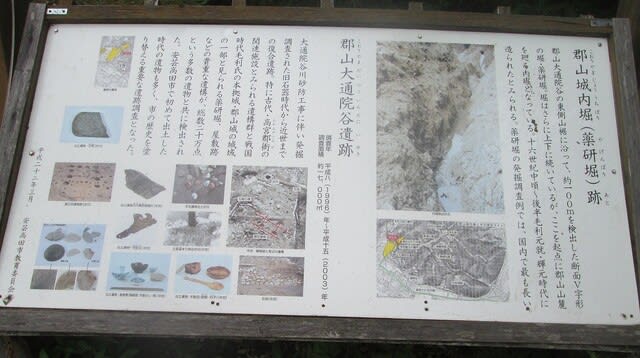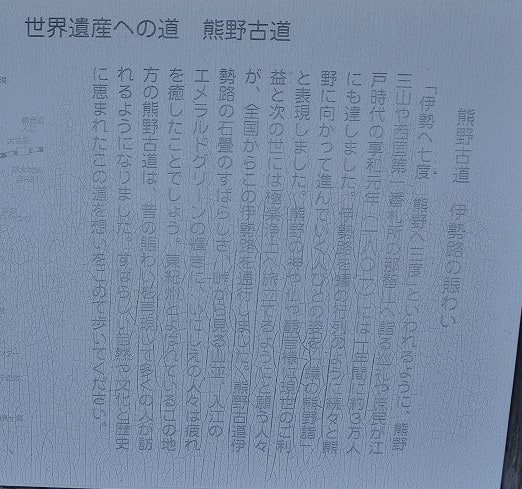2025年2月28日。
家内と千葉県勝浦市にひな祭りを見学に行って来ました。
馬橋駅 6:20発。
勝浦駅 8:20着。
勝浦駅。





河津桜が咲いていました。


③墨名交差点。


街中にもひな人形が。

②覚翁寺門前。
「覚翁寺は、勝浦朝市の歴史を示す定書が奉納されていて、勝浦藩主であった植村家の菩提寺。
寛永11年(1634年)勝浦城主植村泰勝が死去した時、勝浦城内にあった浄林寺をここに移し、
泰勝の幼名覚翁丸をとって出水山覚翁寺としたという。
境内には植村氏三代泰朝、四代忠朝、五代正朝の墓宝筺印塔(ほうきょういんとう)があり、
市指定文化財となっています。また、本堂には江戸彫刻の名人といわれている通称・波の伊八(武志伊八郎信由)
の欄間が残されています。」との事です。




旅館松の家。
つるしひなやひな人形が飾られていました。


明治時代のものです。

江戸後期時代。


⓵遠見岬神社。


毎日片づけて、翌日、飾るとの事です。大変ですね。

④勝浦市芸術文化センターKuste(キュウステ)。
登り坂の上にありました。

入場料は、一人500円でした。





内閣総理大臣賞です。


江戸末期。

江戸中期。

明治時代。

大正時代。



圧倒されます。














ここで、終わりとして街中へ戻り、昼食としました。

地魚の店まるろです。

刺身定食と金目鯛塩焼きでした。

美味しかったです。満足しました。
土日は混んでいたとの事ですが、混雑なく見学出来ました。
駅に戻り帰宅しました。
馬橋駅着 16:13 でした。
家内と千葉県勝浦市にひな祭りを見学に行って来ました。
馬橋駅 6:20発。
勝浦駅 8:20着。
勝浦駅。





河津桜が咲いていました。


③墨名交差点。


街中にもひな人形が。

②覚翁寺門前。
「覚翁寺は、勝浦朝市の歴史を示す定書が奉納されていて、勝浦藩主であった植村家の菩提寺。
寛永11年(1634年)勝浦城主植村泰勝が死去した時、勝浦城内にあった浄林寺をここに移し、
泰勝の幼名覚翁丸をとって出水山覚翁寺としたという。
境内には植村氏三代泰朝、四代忠朝、五代正朝の墓宝筺印塔(ほうきょういんとう)があり、
市指定文化財となっています。また、本堂には江戸彫刻の名人といわれている通称・波の伊八(武志伊八郎信由)
の欄間が残されています。」との事です。




旅館松の家。
つるしひなやひな人形が飾られていました。


明治時代のものです。

江戸後期時代。


⓵遠見岬神社。


毎日片づけて、翌日、飾るとの事です。大変ですね。

④勝浦市芸術文化センターKuste(キュウステ)。
登り坂の上にありました。

入場料は、一人500円でした。





内閣総理大臣賞です。


江戸末期。

江戸中期。

明治時代。

大正時代。



圧倒されます。














ここで、終わりとして街中へ戻り、昼食としました。

地魚の店まるろです。

刺身定食と金目鯛塩焼きでした。

美味しかったです。満足しました。
土日は混んでいたとの事ですが、混雑なく見学出来ました。
駅に戻り帰宅しました。
馬橋駅着 16:13 でした。