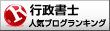模試の解説で、もう少し丁寧に、書いた方がよりわかりやすいところを、せっかくですから“このブログ”で書こうと思います。
今回は、第2回 問題39 肢2 「代金が億を超える場合」についての☆補足解説 出題の意図 です。
代金の5%、10%の問題では、いろいろなミスをしないようにしておかなければなりません。
そのために、この問題を作問しました。
・・・・・
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億200万円の宅地の売買契約(手付金600万円、中間金5,000万円、残代金4,600万円)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 宅地建物取引業者でないBと当該宅地の造成工事完了前に契約を締結し、所有権移転登記及び引渡しを残代金と引き換えに行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、宅地建物取引業法第41条に定める保全措置を講じなければならない。
・・・・・
となっています。
本問題の趣旨は、数字を丁寧にチェックできているかにあります。
そして、本試験では、個数問題もあり、アバウトに認定すると致命的になることもあるからここで痛い目に遭っておきましょう。
そこで、物件が○○億を超えるものは特に注意してくださいね。
今回の問題は、その一つに当たり、本問は「1億200万円」であって、「1億2,000万円」ではありません。ですから、解説でもあるように、5%は510万円であって、600万円ではありませんね。
きっと、ざーっと読む人は、これミスをします。
ちなみに、もう一つは5%、10%は超えていないが、もう一つの要件である1,000万円を超えている問題が考えられます。過去にも出ています。
いずれも1億を超えている問題の引っかけとして、今回は2つのうち一方を出題しました。
きっと解き方としては、ミスをして、肢2を○となり肢4も○にして、そこで初めて気づき、そのときやはり数字をミスしていないかをよーくみて、気がつくとよかった、問題なのです。
次回は注意して読む癖がついていると思いますから、もう大丈夫だと思います。
ですから、2回、3回目にチャレンジしてください。1回だけでは身に付いてなくてダメです。
以上が出題意図です。
では、また。


 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

今回は、第2回 問題39 肢2 「代金が億を超える場合」についての☆補足解説 出題の意図 です。
代金の5%、10%の問題では、いろいろなミスをしないようにしておかなければなりません。
そのために、この問題を作問しました。
・・・・・
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億200万円の宅地の売買契約(手付金600万円、中間金5,000万円、残代金4,600万円)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 宅地建物取引業者でないBと当該宅地の造成工事完了前に契約を締結し、所有権移転登記及び引渡しを残代金と引き換えに行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、宅地建物取引業法第41条に定める保全措置を講じなければならない。
・・・・・
となっています。
本問題の趣旨は、数字を丁寧にチェックできているかにあります。
そして、本試験では、個数問題もあり、アバウトに認定すると致命的になることもあるからここで痛い目に遭っておきましょう。
そこで、物件が○○億を超えるものは特に注意してくださいね。
今回の問題は、その一つに当たり、本問は「1億200万円」であって、「1億2,000万円」ではありません。ですから、解説でもあるように、5%は510万円であって、600万円ではありませんね。
きっと、ざーっと読む人は、これミスをします。
ちなみに、もう一つは5%、10%は超えていないが、もう一つの要件である1,000万円を超えている問題が考えられます。過去にも出ています。
いずれも1億を超えている問題の引っかけとして、今回は2つのうち一方を出題しました。
きっと解き方としては、ミスをして、肢2を○となり肢4も○にして、そこで初めて気づき、そのときやはり数字をミスしていないかをよーくみて、気がつくとよかった、問題なのです。
次回は注意して読む癖がついていると思いますから、もう大丈夫だと思います。
ですから、2回、3回目にチャレンジしてください。1回だけでは身に付いてなくてダメです。
以上が出題意図です。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |