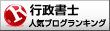今回は、新設住宅着工戸数を書こう。
まず、気になるのが、今年は年度計(4/1~3/31)で出題されるのか、年計(1/1~12/31)で出題されるかだろう。
昨年は、年計でした。以前は、年度の方が多かったんですよ。
とりあえず、年計でいくと、ポイントは。
前年の減少から再び増加となった、戸数は約82万戸(正確には、819,020戸)だ。あと、100万戸を切ったのは2年連続だ、ということか。
ちなみに、年度でも、前年の減少から再び増加となった点同じで、戸数は約81万戸(正確には、813,126戸)はちょっと少ない。あと、100万戸を切ったのは2年連続、これは同じだ。
ほぼ、同じなんだから、どちらでもこい。ということで、覚えるの頑張りましょう。
これで地価公示と2つ制覇だ。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
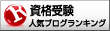
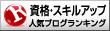
まず、気になるのが、今年は年度計(4/1~3/31)で出題されるのか、年計(1/1~12/31)で出題されるかだろう。
昨年は、年計でした。以前は、年度の方が多かったんですよ。
とりあえず、年計でいくと、ポイントは。
前年の減少から再び増加となった、戸数は約82万戸(正確には、819,020戸)だ。あと、100万戸を切ったのは2年連続だ、ということか。
ちなみに、年度でも、前年の減少から再び増加となった点同じで、戸数は約81万戸(正確には、813,126戸)はちょっと少ない。あと、100万戸を切ったのは2年連続、これは同じだ。
ほぼ、同じなんだから、どちらでもこい。ということで、覚えるの頑張りましょう。
これで地価公示と2つ制覇だ。
では、また。