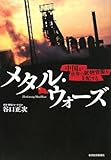| ダライ・ラマのビジネス入門 「お金」も「こころ」もつかむ智慧!ダライ・ラマ14世,ローレンス・ファン・デン・ムイゼンバーグマガジンハウスこのアイテムの詳細を見る |
ダライ・ラマがビジネスのあり方について語ってる。
「DALAI LAMA THE LEADER'S WAY」というタイトルが、なぜ邦訳では
『ダライ・ラマのビジネス入門 「お金」も「こころ」もつかむ智慧!』
になるんだろうか。
タイトルはひねりすぎて疑問ですが、中身はなかなか示唆に富んでます。
ダライ・ラマが経営コンサルタントをコンビを組んで、仏教とビジネスを
組み合わせながら、「正しい理解」と「正しい行い」を軸にまとめてある。
正直、経営コンサルタントさんの記述部分ではあまり惹かれないというか、
どっかで読んだ本の焼き直しみたいなんだけど、ダライ・ラマさんの部分では
心に留めておきたい言葉がたくさん。
特に、富の正しい創出と正しい分配あたり(下の抜き出しの3つめ)は、
意識しておきたいこと。
「 仏教では、収益に関する考えは非常に明快です。収益は、まっとうな方法
で得られる限り、立派な目的です。しかし、ビジネスの役割は収益をあげる
ことだと言うのは、人間の役割は食事や呼吸をすることだというのと同じく
無意味です。損失を出す会社と同様、食事をとらない人間は死を迎えます。
だからといって、人生の目的は食べることだということにはなりません。
企業の役割は、『時価総額を最大にする』だけではなく、責任ある行動を
とり、『顧客を生み出し、満足させる』こと。企業がそう考えてくれれば
いいと私は思っています。」
「 わたしは、収益が企業の唯一の目的であるべきかという際限ない議論に
耳を傾け、参加もしてきました。私にとって答えはシンプルです。
収益は生存に必要な条件ですが、企業の目的は、社会全体の利益に貢献
することです。」
「 アダム・スミスやその他の経済学者は、富の創出にこだわりましたが、富
の分配に関しては何も考えを述べていません。その一方でカール・マルクス
は、これと反対に富の分配だけに興味をもち、富の創出には関心がなかった
のです。富の正しい創出と正しい分配は、そのどちらも非常に大切だと私は
考えます。それを実現するためには、正しい政策と、『正しい理解』『正しい
行い』の実践が必要です。」
「 この世界で起こっていること、またこれから起こることに対して、私たち
みんなが責任を負っています。私たちひとりひとりに、未来を変える力があ
るのです。」
自己の存在意義を認識して、適切な行動をとること。
難しいけれど、逃げちゃいけない話だしね。
宗教に浸かるつもりはないけれど、昔から人の拠り所になっていたところから、
現在に置き換えて学ぶことも大事なんではないかと。
最近特に感じているしだいです、ハイ。
★★★★