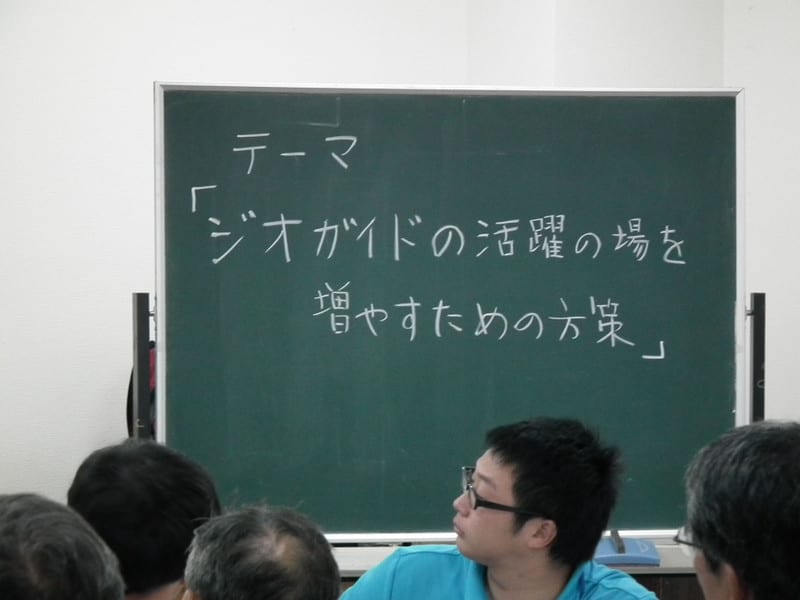今日は年に一度の経ヶ岬灯台の一般公開。GeoParkの仲間と見学に行った。
経ヶ岬の途中に屏風岩がある。ここには普段は現れない幻の滝がある。雨が降るとたまった雨水が崖から流れ落ちるのである。一度見たいと思っていたが、昨日から今朝まで雨天。経ヶ岬周辺の散策には嬉しくない天気だが、もしやと思い立ち寄ってみた。
滝が姿を現していた。雨の量が少なかったためか、水量は大したことはないが、確かに滝が出現していた。
次は大雨の時を期待しよう。
経ヶ岬駐車場入り口脇の小道を海岸のまで下り、経本に見える柱状節離を身近に見た。
ここでは、安山岩(流紋岩?)の表面に無数の小さな穴が空いていたが、穴がどのようにしてできたのか知りたいものだ。
火山活動の時のガスの跡かそれともマグマに閉じ込められた凝灰岩が風化してできた穴か、あるいはそれ以外の何かか、わからない。今後の課題としよう。



海岸線の見学のあとは一気に頂上の展望台まで登り、やっと昼食。
いつものことだが、コーヒーや手製のランチやら、いろいろごちそうになった。
以前来たときは展望台と言っても周囲に大きな木が生えていてすこぶる見通しが悪かったが、一般公開に備えて手入れをしたのか、丹後松島や袖石の棚田、そして舞鶴の冠島や沓島、さらには越前海岸までよく見えた。
また、袖石の棚田や丹後松島がいつもとは違う角度で新鮮な風景だった。



いよいよ、灯台の中の見学だ。入り口では海上保安庁の制服が準備してあり、希望者は制服を来て記念撮影ができた。
灯台の中は予想以上に狭くランプのところまでは傾斜角が70度はありそうなほど急で、しかも大人一人通るのがっやっとという狭さ。今は点検の時だけしか灯台には来ないということだが、ご苦労なことだ。
隊員さんから聞いた話だが、点滅の周期は灯台ごとに決まっていて、経ヶ岬の灯台は20秒毎だということだった。周期を決めることで、位置が確認できていないときも、どこの灯台だとわかるようになっている。
なるほど。



下の写真は海食洞である。?万年前にできたもので、当時この洞穴は海面下にあったことを物語っている。