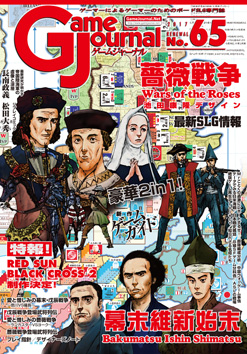茨城会ブログ、移転後長らく休止状態で申し訳ありません。
とりあえず復活第一弾として、War-Gamers Advent Calendar 2022 参加記事となります。

以前は年末年始時代劇の定番だった「忠臣蔵」ものですが、時代劇不遇の時代に加えてコロナ禍が加わった現状では、若い世代の方々には随分と馴染みが薄くなってしまったのではないでしょうか。 本日は(新暦旧暦の違いはありますが)12月14日ということで、この元禄赤穂事件のクライマックス、吉良邸討ち入りを扱ったウォーゲーム日本史第4号「討入忠臣蔵」を取り上げたいと思います。
和モノで本作のように屋内戦闘を扱った作品は、商業ベースでは当方が知る限り古くは「伊賀対甲賀」(バンダイ)、新しくは新生タクテクス内の「本能寺の変」、合わせて3作ではないでしょうか。 (もしかしたらRPG系では何かあるかもしれませんが。)ですので本作の存在は大変貴重かと思われます。
本作は、「赤穂事件:吉良邸討入」の完全な史実というよりは、脚色された「忠臣蔵」ドラマの再現に傾いており、登場人物能力など設定がその方向で(吉良方にバランスを傾けて)調整されております。そのためか、プレイヤーの経験度に拠りますが、ゲーム上の最適解を求めて行動すると赤穂浪士側の勝利は困難になっていく傾向にあると思われました。 (この辺りはプレイ指針にも記載あり、出版時点からWGJ編集部も認識はされていたようですが。)
そこで、このゲームを複数回対戦しても赤穂浪士が本懐が遂げられない、「忠臣蔵」が成立しない、とお嘆きの諸兄に私的ディベロップ案(選択ルール提案)を提示したいと思います。 本年度のアドベンドカレンダーのお題「第一ターン特別ルール」にも繋がっております。 原版にある選択ルールも含めて、以下の1つ、または複数を、プレイヤー両者の合意で導入してみてください。 いずれも赤穂浪士方に有利となるルールです。
10.7 清水一学の戦闘力は5剣でなく4剣に変更する。(これでも史実よりは強力かと。)
10.8 吉良方は、第一ターンはスタックで行動できない。 また、吉良方は、第二ターンはスタックでの行動は2枚までとする。(赤穂浪士から攻撃を受けた場合は通常通り、スタックで応戦可能。)
10.9 吉良上野介の脱出が成立しても、その時点で吉良左兵衛が除去されていれば 吉良方勝利でなく「引き分け」とする。
10.10 吉良方の移動力無制限を24スクエア(赤穂方の倍)までとする。
上記案に至った経緯を2つほど提示します。
その前に、戦闘解決方法から。 通常、1マスに存在できるのは3駒まで。手番側は未行動ユニットを指定して移動、敵に隣接したら戦闘を解決します。行動開始時にスタック状態にあれば、そのままグループとしても行動可能です。 戦闘時にはそれぞれ代表ユニットを選び、攻撃側は行動したグループの枚数、防御側はスタックの枚数分ダイスを振り、その中の最大値を代表駒の戦闘力に加えたものを比較して勝敗を決めます。同数ならそのまま引き分け膠着。差があればその差分駒を除去し、残存駒を退却させます(連鎖退却あり)。
この時、「剣」修正を持つユニットは特例で更にダイス一個余計に振れます。
ということで、サイコロ1個~4個振った時の出目最大値の分布確率をグラフ化しました。 4個振りだと半数以上「6」が出る計算です。 
事例1:「裏門開けたら、清水一学」
かつてTVCMで「玄関開けたら2分でごはん」というのがありましたが。 当ゲームでは「裏門開けたら清水一学」「裏門通れずゲーム終了」ということが(結果としてルールミスだったのですが)起こりました。
本ゲーム、赤穂浪士方の戦力配分は史実準拠で固定されています。 そして表門側は侵入経路が門3カ所と梯子7挺利用可能ですが、裏門側は「裏門」一箇所のみです。ですので裏門組は何としてもここを突破突入せねばなりません。

添付図は、赤穂方の初手、「槌」能力あるスタックが裏門扉を破壊し、門内に前進した図です。 異変を察知した吉良方は、早速これを排除すべく、最強剣士「5剣」の清水一学を含む3枚スタック(一学に茶坊主2枚でOK)を急行させます。
ここで、赤穂方のスタック構成が要検討となります。まず、清水一学と同様に、ゲーム中最高「5剣」能力の「堀部安兵衛」が居るとして計算してみましょう。
両者(堀部vs清水)の能力は互角、補助人員2枚も互角となれば、戦闘結果で「膠着」となるのが、 4割弱、どちらかが勝利し堀部あるいは清水が後退するのがそれぞれ3割強となります。 両者譲らず、第2、第3、第4ターンと膠着が続けば(確率1.87%)、裏門組は吉良邸敷地に全く入れずに朝を迎えゲーム終了・・・・。 ええ、確率は低いんですけど、私が関わってプレイすると発生するのですよ、希少案件が、看過できない割合で・・・。
これは、ちょっとオカシイのでは、とWGJ編集部に質問したところ、以下のことが判明。
「移動後」はスタック判定対象時期ではない。
ルール原文には「行動組の移動中、及び戦闘時は一時的にこの制限をオーバーしても構いません」とあり、戦闘時の連鎖退却判定を指して「一時的」と表現したもので「移動後」はスタック制限対象なのかと解釈しておりました。しかし、この「裏門問題」から疑問を生じ、質問したところ、移動~戦闘(または射撃・照合)の一連の行動中は(移動後も含めて)スタック制限なし、が正しい解釈とのことでした。
ですので、既に制限いっぱい自軍3駒いるマスにも進入した上で行動可能。場合にては連鎖退却を利用する形で既存ユニットを1マス前進させることも可能なようですので、御留意願います。(公式Q&Aには未掲載)
さて、これならば、裏門口に清水一学スタックが居座っても、順次行動組スタックを突入させればいずれ突破できるだろうと予想されましたが。 早速検証テスト・・・あれ、清水一学スタック、やはり排除困難・・・。
すんなりと堀部で勝てればよいのですが、ダメだと次は「4剣」の不破数衛門のスタックでチャレンジです。この時の勝率は勝ち12.2%、膠着19.3%、負け68.5%。一気に勝率ダウンです。
それ以外の戦闘力3のユニットが代表者では当然もっと確率は悪くなります。下手すると、裏門突破はなんとか成功したが、負傷者続出で裏門組は半壊状態といった事態に。プレイ指針にある「2ターンまでには長屋戸口を封鎖」など到底困難です。

まあ、対策が全くないわけではなく、条件が揃えば、例えば清水一学スタックが不用意に裏門スクエア(ロ三)に戦闘後前進をした場合、(イ二)からは射線が通るので、「弓」能力駒で狙撃、(6のみ命中を最大4回)とか、

表門組の早水藤左衛門の「射」で背後から遠距離狙撃(5、6命中)などで打開できるかもしれませんが。
しかし、それぞれセットアップ時からある程度想定準備しておく必要があります。
吉良方もまたこれらへ対策する余地があったりします。
総合的に見て吉良方の裏門死守策はサイの目次第ですが非常に有効性が(ゲームバランスを崩すほど)高いと考えます。
事例2:「上野介全力脱出作戦」
プレイ指針には「赤穂浪士が慎重にプレイすれば、吉良方の脱出は容易ではない。」とあるが、筆者の意見は異なります。
前述のように赤穂浪士は表門側、裏門側に戦力が分散しています。そして表門側には戦闘力4は一人だけ(かつ「剣」ではない) 。ならば、裏門は必要最小限の人数で遅滞戦術で凌ぎ、残りの全戦力を表門側に集中投入する作戦です。 出口は表門、新門、厩門の三カ所。赤穂浪士方からすると、分散して守る必要があり。そして恐らく地形的に厩門が突破目標になるのではないでしょうか。 移動力無制限を活用し、吉良方が順次スタック梯団を組んで押し込んでいくイメージ。最後は清水一学に「山」「川」両方の上野介で組んだグループで盤外突破タッチダウンを図ります。
これを準備周到・計画的に行えば、「必勝」とは言えませんが、吉良方勝率は50%は下らない印象でした。
でも・・・最初から脱出前提というのは何だかな、という意見はごもっとも。 当時の人々からすれば城を捨てて逃げだした、ともとられるのではないでしょうか。この辺りは勝利条件設定をどこに置くか、判断が必要な部分でしょう。
さて2つの事例を提示しましたが、どちらも「清水一学」が強すぎるのが問題に思えました。 そこで私案1はまず「清水一学の評価を落とす」を提示しました。
一方で、印刷されたユニットの数字を変えるのは抵抗感があるのも事実です。 そこで、私案2は史実準拠の状況設定?と理由づけして、奇襲を受けて指揮系統が混乱、当初は各個に行動せざるをえなかった吉良方を表すルールとしてみました。 こうすれば序盤に「最凶スタック」が形成される事態はかなり低減されると思われます。
私案3、4は上野介計画的逃亡の成功率、勝率を落とすことを目的としています。 私案4の「24」という数字は、赤穂方の倍であることと、直線ならば屋敷の東西を移動できることから設定しました。完全無制限よりは僅かでも制限あるほうが良いと考えました。
恐らく、効果としては、私案2が一番強く、次いで1、3、4の順かと。
競争シナリオ「大石父子手柄争い」に適用させるのはどれが良いかは今後の検討課題です。
既に版元絶版品ですので、なかなか新規入手は難しいかと思いますが、押し入れ本棚に入れっぱなしはもったいなく思われる作品です。お手持ちの方は是非再注目をお願い致します。(国通さん、BOX再版お願いします。)
対戦御希望の方は「茨城歴史ゲームの会」でお待ちしております。