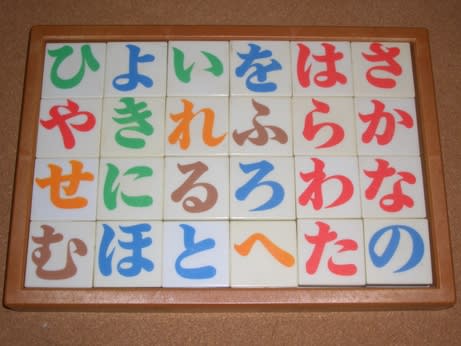まだまだ怪奇小説を読んでいる。
またまた言うが、ホラーでもファンタジーでもなく、怪奇小説。
まあ、supernatural (超自然)ってところか。
考えてみると、子どもの頃に読む「おはなし」ってのは、超自然が多い。
たとえば、桃太郎……鬼は明らかに超自然だ。そもそも、桃から生まれたというのが、怪奇である。(旧いバージョンでは、桃を食べたおばあさんから生まれたらしいが、それだってかなり超自然かもしれない)
シンデレラ……魔法使いが超自然でなくてなんであろう。お城とか出てくるところも、ゴシック小説を思わせるじゃないか。
少し大きくなると、シャーロック・ホームズなどの探偵・犯罪ものなども読む。ホームズは超自然ではないけれども、たとえば「バスカヴィル家の犬」なんて読むと、かなりゴシックな雰囲気がある。
SFなんてのも好んで読んだりする。SFには、やっぱり超自然的なものがある。宇宙人なんてのが出て来るけど、かなり超自然くさいものが多い。
これが大人になると、超自然的な小説を読む機会がずっと減ってくる。
子どもの、本を読んでわくわくした感覚が大人になると味わえないなあと思っていたが、これはたんに、大人の読む小説に超自然を(少なくとも中心的モチーフとして)扱わないものが多いからかもしれない。
またまた言うが、ホラーでもファンタジーでもなく、怪奇小説。
まあ、supernatural (超自然)ってところか。
考えてみると、子どもの頃に読む「おはなし」ってのは、超自然が多い。
たとえば、桃太郎……鬼は明らかに超自然だ。そもそも、桃から生まれたというのが、怪奇である。(旧いバージョンでは、桃を食べたおばあさんから生まれたらしいが、それだってかなり超自然かもしれない)
シンデレラ……魔法使いが超自然でなくてなんであろう。お城とか出てくるところも、ゴシック小説を思わせるじゃないか。
少し大きくなると、シャーロック・ホームズなどの探偵・犯罪ものなども読む。ホームズは超自然ではないけれども、たとえば「バスカヴィル家の犬」なんて読むと、かなりゴシックな雰囲気がある。
SFなんてのも好んで読んだりする。SFには、やっぱり超自然的なものがある。宇宙人なんてのが出て来るけど、かなり超自然くさいものが多い。
これが大人になると、超自然的な小説を読む機会がずっと減ってくる。
子どもの、本を読んでわくわくした感覚が大人になると味わえないなあと思っていたが、これはたんに、大人の読む小説に超自然を(少なくとも中心的モチーフとして)扱わないものが多いからかもしれない。