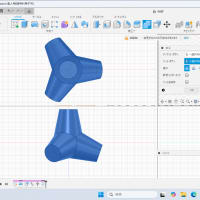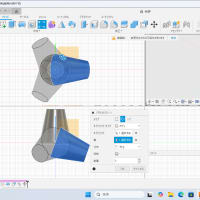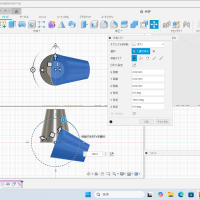○自律とは自発の中にある。
「好きなことばかりをして、多数迎合や権威への服従をすることを覚えないと、社会的責任判断をしなくなる。」という規範意識の観念には論理的根拠がない。
文科系大衆観念的には、自分の好きなことと、他人の顔色を窺うことはバランス問題だと思われているようだが。他人の顔色を窺い、表面的/外見的に取り繕うことでは自律というのは育たず、決してバランス問題ではない。
自律というものは自発の中にあり、他にはない。これは定理であり構造原理である。
個人が主体的に社会の調和/持続可能性を追求するためには、何よりも自発性が重要であり。この自発性というものの解釈の仕方に曖昧さが存在するため、本質的には自発性ではないものを自発性であると錯覚している場合が少なくない。
「やる気。」「意欲。」といったものには、環境依存的なものとして。他者との比較競争や差別化を主体とした意欲というものがあるが、これはあくまで「比較差別を行う多数他者との関係性。」という環境依存性を伴うものであり、本質的な主体性ではない。
学力成績が高い割には自主的に何かを考えることが大嫌いなヒトというのは、成績評価という抽象化された「エサ」報酬に対する条件反射として成績に執着していただけであって。具体的に主体的目的意識も何もなく、ただ無意識に流されるまま強迫観念だけで学力成績を追求してきたヒトである。
こういうヒトには自律がない。
なぜなら自分の行動自体に本質的主体性がなく、環境依存的に提供される「エサ」報酬を動機としてしか行動が促されないように行動「学習」されてしまっているため。「エサ」報酬の約束どころか身の安全の保証すらない自律判断など最初からするつもりは一切ないからである。
「学力成績さえ高ければ、人生の全てが保証されるものである。」という短絡的で安易な大衆観念を鵜呑みにしていなければ、こうした自律のない「高学歴なバカ。」は出てこない。
では、自律はどのようにして行われるようになるのか。
身の安全性の保証すらない自律判断を行うためには、環境依存性を伴うあらゆる「動機」を排除し、本質的に主体性のある純粋で自発的な意欲によって、自分から「生きよう」とする主体的意志が必要不可欠である。
文科系大衆観念的には「社会から生かされている。」などと「生存」自体を絶対視した観念に基づき、現状世間に服従迎合することこそが「社会のため。」だと勘違いしておけば安心満足なのであろうが、こうした主体性の欠落こそが個人から自律を喪失させるのである。
自分自身から「生きよう」とすることで、逆に「いつ死ぬべきか。」も自律的には選択可能となるのであり。その自律選択こそが、本質的な社会安全性にもつながるのである。
事故が起こる前に原発の危険性を訴えていれば、東電内部から排除されるであろうことは予測に難くない。それを「生きるためには。」などと称して東電幹部に服従したからこそ、原発の危険性は放置されたのである。
文科系大衆観念的には、従順で扱い易い子供であれば、常に都合の良い判断の全てをしてくれるものであると勝手に勘違いする傾向があろうが。「自分にとって取り扱い易い。」子供であることが、人間として社会的責任判断を行うことの論理的証明が存在しないことを、多くのヒトは認識していない。
自分にとって取り扱い易い従順なヒトでさえあれば、多くのヒトは安心満足することによって。そのヒトが誰にとっても従順で取り扱い易いという安易さをも兼ね備えていることにまで意識が働いていない。
東電幹部達にとって、従順で取り扱い易い社員は便利で、組織の金儲けを行う上において有利な存在であるため、原発の危険性を隠蔽黙殺させるためには「必要」な存在なのである。
ヒトの多くは自律的な社会的責任判断の重要性にまで配慮することはなく、目先の生活の便利さや、他人との比較による優位性といった物質的豊かさにしか意識が働いていない。
経済学上における自由市場原理というものも、個人が目先の利益効用にしか配慮が回らないという意識狭窄性が生み出すものであり。一人一人が社会全体の公益性にまで配慮する意識の広さを持たないことが自由市場原理の根源的劣悪性を作り出しているのである。
こういった話をすると、大抵の場合、「それは難しい。」などと称して、あたかも論理的に不可能を証明したかのように言い張るバカが少なくないが。「難しい」ことを根拠に「やらなくて良い。」ことにすり替えて良いようなものではない。
入学試験だのビジネスにおいては、やたらと「難しい。」ことを他人に強要する癖に。社会にとって最も重要な安全性に関わる話になると突然「それは難しい。」などと称して拒絶するのは支離滅裂無責任というものである。
こうした論理的には支離滅裂で無責任な観念を、何ら自律的には論理検証せずに漫然と鵜呑みにしているからこそ、ヒトはいつまでもバカが治らないのである。
ヒトの多くは何を優先しなければならないのかという根源的優先順位を忘れ、目先の世間的成功だの評価報酬、他人との比較優位性といったものばかりに意識を奪われている状態というのは、どう考えても「バカ」としか形容不能である。
一部の思想家においては、民主主義自体を否定する向きもあるようだが、これは理想というものを放棄したとんでもないオカルトである。
確かに従来世間においては多数大衆の迎合性判断というものは、社会を破綻にしか導かない傾向性はあったが。それなら専門家である東電原発安全担当者達による判断が正しいと言えるであろうか。
問題の本質というのは制度自体にあるのではなく、個人の自律的な社会的責任判断にあるのであって、バカしかいないから民主主義が「バカ主義」に陥るのであって。これは専門家の集団であっても結果は同じことである。
ナチズムにおいても、当時のドイツ国民の多くはナチズムという権威専門家集団にお任せしておきさえすれば全ては上手く行くものであると錯覚したからこそ、ナチズムに傾倒してしまったとも言えるのであり。権威専門家の全てが常に正しい判断を下すものであると決め付けることこそが独裁政権を生み出す高い危険性を孕んでいる。
航空機の運行や原発の運転など、専門家でなければ危険な事柄というものが存在することは確かであるが。専門家であっても、専門家個人が自律的に社会的責任判断を下せないのであれば、バカげた結果に陥ることは明らかである。
従って最も重要なのは制度そのものではなく、制度の具体的問題点にまで言及可能な個人の自律判断能力の獲得であって。外形である制度そのものを批判することこそがトンチンカンと言える。
原発の過酷事故のような特殊な場面以外においては、原発行政の在り方については市民の意見も採り入れる必要性はあり、決して権威専門家だけに任せ切りにすべきものでもない。利権が絡む以上権威専門家が必ずしも社会的責任判断を優先するとは限らないからである。
制度というのは外形であり、形式の話であって。どのような制度であろうと個人に自律的な社会的責任判断があることが重要なのであり、個人の自律を尊ぶ民主主義制度自体を批判するというのは「何も考えていない。」のと等しい。
「何も考えていない。」ポンコツを「思想家。」として扱うマスコミにも問題がある。
「企業が利益を追求しなければ、公益法人だ。」などというバカげた見解を読んだことがあるが、企業としてのマスコミが単に視聴率だけを追求していれば無責任に数字の採れそうな映像ばかりを垂れ流しておくことも正当化されるのであり。それは東電の原発事故までをも正当化するような話である。
企業であれ、個人であれ、ヒトである以上は社会的責任を負うことから免れることなど構造原理的に出来ない。
それが嫌で、どうしても目先の利益だけしか考えることが出来ない、意識出来ないというのであれば、もはや人間として社会的存在価値など存在せず、動物園の檻の中にでも閉じ込めておく他あるまい。
企業の利益というのは、企業存続のための「手段」であって、企業自体の存在「目的」ではない。これを忘れて利益追求だけを正当化することなど本来出来るわけがないのである。
Ende;
「好きなことばかりをして、多数迎合や権威への服従をすることを覚えないと、社会的責任判断をしなくなる。」という規範意識の観念には論理的根拠がない。
文科系大衆観念的には、自分の好きなことと、他人の顔色を窺うことはバランス問題だと思われているようだが。他人の顔色を窺い、表面的/外見的に取り繕うことでは自律というのは育たず、決してバランス問題ではない。
自律というものは自発の中にあり、他にはない。これは定理であり構造原理である。
個人が主体的に社会の調和/持続可能性を追求するためには、何よりも自発性が重要であり。この自発性というものの解釈の仕方に曖昧さが存在するため、本質的には自発性ではないものを自発性であると錯覚している場合が少なくない。
「やる気。」「意欲。」といったものには、環境依存的なものとして。他者との比較競争や差別化を主体とした意欲というものがあるが、これはあくまで「比較差別を行う多数他者との関係性。」という環境依存性を伴うものであり、本質的な主体性ではない。
学力成績が高い割には自主的に何かを考えることが大嫌いなヒトというのは、成績評価という抽象化された「エサ」報酬に対する条件反射として成績に執着していただけであって。具体的に主体的目的意識も何もなく、ただ無意識に流されるまま強迫観念だけで学力成績を追求してきたヒトである。
こういうヒトには自律がない。
なぜなら自分の行動自体に本質的主体性がなく、環境依存的に提供される「エサ」報酬を動機としてしか行動が促されないように行動「学習」されてしまっているため。「エサ」報酬の約束どころか身の安全の保証すらない自律判断など最初からするつもりは一切ないからである。
「学力成績さえ高ければ、人生の全てが保証されるものである。」という短絡的で安易な大衆観念を鵜呑みにしていなければ、こうした自律のない「高学歴なバカ。」は出てこない。
では、自律はどのようにして行われるようになるのか。
身の安全性の保証すらない自律判断を行うためには、環境依存性を伴うあらゆる「動機」を排除し、本質的に主体性のある純粋で自発的な意欲によって、自分から「生きよう」とする主体的意志が必要不可欠である。
文科系大衆観念的には「社会から生かされている。」などと「生存」自体を絶対視した観念に基づき、現状世間に服従迎合することこそが「社会のため。」だと勘違いしておけば安心満足なのであろうが、こうした主体性の欠落こそが個人から自律を喪失させるのである。
自分自身から「生きよう」とすることで、逆に「いつ死ぬべきか。」も自律的には選択可能となるのであり。その自律選択こそが、本質的な社会安全性にもつながるのである。
事故が起こる前に原発の危険性を訴えていれば、東電内部から排除されるであろうことは予測に難くない。それを「生きるためには。」などと称して東電幹部に服従したからこそ、原発の危険性は放置されたのである。
文科系大衆観念的には、従順で扱い易い子供であれば、常に都合の良い判断の全てをしてくれるものであると勝手に勘違いする傾向があろうが。「自分にとって取り扱い易い。」子供であることが、人間として社会的責任判断を行うことの論理的証明が存在しないことを、多くのヒトは認識していない。
自分にとって取り扱い易い従順なヒトでさえあれば、多くのヒトは安心満足することによって。そのヒトが誰にとっても従順で取り扱い易いという安易さをも兼ね備えていることにまで意識が働いていない。
東電幹部達にとって、従順で取り扱い易い社員は便利で、組織の金儲けを行う上において有利な存在であるため、原発の危険性を隠蔽黙殺させるためには「必要」な存在なのである。
ヒトの多くは自律的な社会的責任判断の重要性にまで配慮することはなく、目先の生活の便利さや、他人との比較による優位性といった物質的豊かさにしか意識が働いていない。
経済学上における自由市場原理というものも、個人が目先の利益効用にしか配慮が回らないという意識狭窄性が生み出すものであり。一人一人が社会全体の公益性にまで配慮する意識の広さを持たないことが自由市場原理の根源的劣悪性を作り出しているのである。
こういった話をすると、大抵の場合、「それは難しい。」などと称して、あたかも論理的に不可能を証明したかのように言い張るバカが少なくないが。「難しい」ことを根拠に「やらなくて良い。」ことにすり替えて良いようなものではない。
入学試験だのビジネスにおいては、やたらと「難しい。」ことを他人に強要する癖に。社会にとって最も重要な安全性に関わる話になると突然「それは難しい。」などと称して拒絶するのは支離滅裂無責任というものである。
こうした論理的には支離滅裂で無責任な観念を、何ら自律的には論理検証せずに漫然と鵜呑みにしているからこそ、ヒトはいつまでもバカが治らないのである。
ヒトの多くは何を優先しなければならないのかという根源的優先順位を忘れ、目先の世間的成功だの評価報酬、他人との比較優位性といったものばかりに意識を奪われている状態というのは、どう考えても「バカ」としか形容不能である。
一部の思想家においては、民主主義自体を否定する向きもあるようだが、これは理想というものを放棄したとんでもないオカルトである。
確かに従来世間においては多数大衆の迎合性判断というものは、社会を破綻にしか導かない傾向性はあったが。それなら専門家である東電原発安全担当者達による判断が正しいと言えるであろうか。
問題の本質というのは制度自体にあるのではなく、個人の自律的な社会的責任判断にあるのであって、バカしかいないから民主主義が「バカ主義」に陥るのであって。これは専門家の集団であっても結果は同じことである。
ナチズムにおいても、当時のドイツ国民の多くはナチズムという権威専門家集団にお任せしておきさえすれば全ては上手く行くものであると錯覚したからこそ、ナチズムに傾倒してしまったとも言えるのであり。権威専門家の全てが常に正しい判断を下すものであると決め付けることこそが独裁政権を生み出す高い危険性を孕んでいる。
航空機の運行や原発の運転など、専門家でなければ危険な事柄というものが存在することは確かであるが。専門家であっても、専門家個人が自律的に社会的責任判断を下せないのであれば、バカげた結果に陥ることは明らかである。
従って最も重要なのは制度そのものではなく、制度の具体的問題点にまで言及可能な個人の自律判断能力の獲得であって。外形である制度そのものを批判することこそがトンチンカンと言える。
原発の過酷事故のような特殊な場面以外においては、原発行政の在り方については市民の意見も採り入れる必要性はあり、決して権威専門家だけに任せ切りにすべきものでもない。利権が絡む以上権威専門家が必ずしも社会的責任判断を優先するとは限らないからである。
制度というのは外形であり、形式の話であって。どのような制度であろうと個人に自律的な社会的責任判断があることが重要なのであり、個人の自律を尊ぶ民主主義制度自体を批判するというのは「何も考えていない。」のと等しい。
「何も考えていない。」ポンコツを「思想家。」として扱うマスコミにも問題がある。
「企業が利益を追求しなければ、公益法人だ。」などというバカげた見解を読んだことがあるが、企業としてのマスコミが単に視聴率だけを追求していれば無責任に数字の採れそうな映像ばかりを垂れ流しておくことも正当化されるのであり。それは東電の原発事故までをも正当化するような話である。
企業であれ、個人であれ、ヒトである以上は社会的責任を負うことから免れることなど構造原理的に出来ない。
それが嫌で、どうしても目先の利益だけしか考えることが出来ない、意識出来ないというのであれば、もはや人間として社会的存在価値など存在せず、動物園の檻の中にでも閉じ込めておく他あるまい。
企業の利益というのは、企業存続のための「手段」であって、企業自体の存在「目的」ではない。これを忘れて利益追求だけを正当化することなど本来出来るわけがないのである。
Ende;