7/1(金)~2(土)に再び東北 宮城県へ。
今回は亘理町の隣街の山元町に行ってきました。
同じ亘理郡の町です。
山元町もイチゴの産地としてイチゴ農家さんが多いのですが、亘理町よりも海側にあるため、イチゴ農家の9割が被災しており、農地はもとより農家さんの家自体が被災しているケースが多く、復興の道のりは長いように感じられた。

今回はマイクロバス2台、80名以上で赴きました。
1号車は、JAみやぎ亘理が管轄する山元町の男性は周辺農地の瓦礫拾い、女性は汚泥の除去が終わったイチゴ農家の苗の作付け準備作業を行い、2号車は亘理町内の7件の農家に分かれて作業をしました。
震災より100日以上が過ぎていることもあり、
ボランティア作業のニーズも多岐にわたってきているようです。
私がお手伝いさせていただいた農家は、先週までのボランティアさんたちによってハウス内の汚泥除去が終わっていたことと、
ここの農家は“高設栽培”といって、立って作業ができるように台の上にイチゴが植わっています。
こちらの農家さんの場合、高設栽培が幸いして、津波もあと10cmというところで、土とイチゴの株は塩害を免れました。
3月11日はちょうど最後の収穫の最中で、次の日には終わるはずでした。
結局震災により出荷はできず、津波によりスプリンクラーなどの電気系統などの被害も大きかったようですが、他の農家さんに比べれば、とおとうさんもおかあさんも明るく元気に振舞っていました。
私たちの作業は生き残ったイチゴの株からランナーというツルがでていて、そこに子株がついているのですが、
この子株を今年の苗として育てる為に小さなポットに詰めていくという作業です。
親株からでたランナーの株を“太郎さん”、太郎さんから出たランナーの先の株を“次郎さん”、次郎さんから出たランナーの先の株を“三郎さん”と呼ぶそうですが、これをランナーにつながったままポットに挿し、クリップでとめて根っこがでてくるまで待ちます。
根っこが出てきたらランナーを切り、苗のポットをケースに入れて冷蔵庫で冷やします。
これはイチゴが一旦冬を経験してから暖かくならないと花をつけないという習性から、イチゴを冬が来たと勘違いさせて、収穫時期をずらす為だそうです。


作業はポッドにクリップを挿していく作業から始まり、終わった段階でポッドに太郎さんと次郎さんたちを挿していく作業をやりました。



現地に到着する前に、ボランティアのジョイントをやっていただいているスタッフの方から、農家の方々がボランティアの人とたわいもない世間話をすることも大きなボランティアの1つで、農協の方にも楽しいひと時を過ごせたと反響があったという話しを聞いていましたので、みんな積極的におかあさんといろんなお話をしました。
おかあさんはとっても明るく可愛らしい方で、
“実はね、震災で2キロも痩せちゃったの~”
と明るく語っていましたが、この笑顔の裏にあったであろう苦労と悲しみは如何ばかりだったかを思うともらい泣きしそうになりました。
おかあさんは、ボランティアの私たちに気を使いちょこちょこ休憩をいれてくれましたが、私たちは逆にそんなやさしいおかあさんの気持ちに応えるためにも限られた時間の中で少しでも作業をやりたいという気持ちが強くなりました。
朝9時半~14時45分まで、思ったよりも進まなかった気がしましたが、おかあさんは、
“ポッドにクリップ挿すだけで終わると思ってたけど、みんなの力を見くびっちゃってたわね~。”
と、とても可愛らしく笑いました。
写真もおかあさんの方から皆で撮りたいと言っていただき、
記念撮影もたくさんさせていただきました。
帰りのバスで、瓦礫拾いの作業をしてきた男性陣とお話しましたが、
こちらは屋外での単純作業ということもあり、結構大変なようでした。

今回は男性と女性で分かれて作業をしたので、あまり男性陣とお話できませんでしたが、
作業が一緒だった女性陣の何人かといろいろお話をしたところ、私のブログを見てくれた方や、
家庭がありながらも旦那さんやお子さんたち(結構大きいお子さんみたいです)と協力しながら参加された方もいました。
こういう場所でのボランティア同士の情報交換もとても有意義で、モチベーションUPにもつながり、
私はいつも楽しみにしています。
私は5月からボランティア活動に参加していますが、
(派遣される農家も違うということもあると思いますが)
最初の方に比べ、ボランティア活動のニーズの変化だけでなく、被災者たちの気持ちもどこか明るく前向きになっているように感じました。
絶望感から脱却し、今は苦しくとも1歩ずつ前へ前へ踏み出しているような、重みとともに力強さも感じるようになりました。
1日のボランティアでは本当に微々たることしかできませんが、被災者の方々がそれを励みに復興へと前向きになってくれていれば、それだけでも意味のあることなのかもしれません。
そして私たちボランティア参加者も、家族や友人たちに自分の目で見てきた被災地の現状を話すことで、支援の輪もつながっていくと信じています。
また、復興支援はまだまだこれからです!
この先1年、2年と続けていかなければいけません。
阪神大震災のように大都市近隣ではないことと、原発のこともあり、今回のボランティア総数は阪神大震災の時の半分以下だそうです。
どんな形でもいいので、自分のできる形でみなさんが支援を続けていただけることを祈っています。
追記:
JAの会長さんと少しお話する時間があったのですが、とても印象的だったので追記します。
「物資の支援やお金の支援ももちろん大変ありがたいことだし、とても感謝しているが、靴下1枚もらった恩は必ずいつか忘れます。しかしこうしてボランティアに来て働いて
支援してもらったことは絶対に一生忘れない!だから意味があるんです!ボランティアに来た皆さんは必ず、たった1日数時間の作業で役に立てたんだろうかって言いますが、あなたたちが支援に来ていることで、どれだけの被災者が元気付けられ、立ち直って復興に前向きになれたことか。」
フォトアルバムに写真をUPしてますのでご興味のある方はそちらもご覧ください。
********************************************
◆一般社団法人 東日本大震災被災地支援の会
*復興支援ボランティアバスパック 0泊2日
http://hisaiti-24h-shien.mo-blog.jp/blog/2011/04/post_d27e.html
*復興支援 いちご農家一口オーナー制度
いちごが届くのを待ちながら、復興をみまもりませんか?
http://hisaiti-24h-shien.mo-blog.jp/hitokuti/
*********************************************











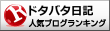



















コメありがとうございます。
このボランティアパックには3回目の参加でした。
前の2回も記事書いてますのでよかったら見てください(^^)
私も前の2回は汚泥の除去でした。
かなりハードな作業ですよね。
私も細くとも長く継続した支援をしたいので、自分の生活に無理のない範囲でボランティアには行こうと思ってます。
農協の会長さんと少しお話したのですが、
あ、これすごく印象的だったので、後で本文の最後に追記しておきます。
私は関東の人間ですが、私の周りは原発を心配する声は聞いても、最近東北の津波の被害を口にする人はめっきり減りました(T_T)
報道もそうです。
私の希望は、私たちのようにボランティアに1度でも行った人間が、自分の目で見て経験したことを周りの人たちに話すとか日記やブログに書いて、まだ戦いは終わってない!ということを広めることです。
私の同僚は、まだ片付いてない瓦礫の山の写真を見て、もうとっくに片付いてると思っててびっくりしたそうです。
時間が経てば誰かがやってくれるという認識を捨てて、少しでも気が向いたら1歩前に踏み出して皆が率先して支援をしてほしいと強く願います。
またどこかでお会いできるといいですね(^^)
班が違ったようですが、今回一緒にツアーに参加していたものです。
(2号車の前の方に座っていました)
大変おつかれさまでした!
ほかの班の作業の様子がわからなかったので
写真が見られてよかったです。
私たちは汚泥の除去をしました。
どろんこまみれで大変でしたが
勉強になりました。
また折を見て参加しようと思っています。