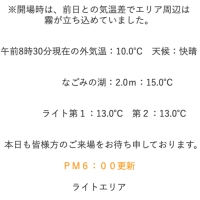サムソンが割れない液晶を開発中とか・・・。
実現はかなり難しいだろう。理由はこれだ。プラスチック(高分子)は寸法安定性が悪い事。これに尽きる。
液晶表示素子は基板上に画素をタイルの様に並べたものだ。写真製版に基づく半導体製造プロセスで画素と画素のON/OFFスイッチとなる素子(TFT)を作り込む。
タイルを並べるにしても、基板の寸法安定性が悪いとまっすぐな直線がグニャグニャの曲線になるだろう。これをどうやってまっすぐにするかが問題だ。
現在の技術では上記のスイッチとなる素子は無機系半導体でしか満足のいく性能を出すことができない。このような無機半導体は基本的に高温処理(普通の高分子が液体になる温度)が必要だ。ピザを焼く様なもので、チーズをどろりと溶かす為には生地ごと高温オーブンに突っ込む必要がある。半導体も同じで、基板の上に積み上げた材料をオーブンで熱処理して半導体のスイッチにする。
しかし、ここで問題になるのは高分子の上に描画して作ったTFT素子の番地というか、場所が常にいい加減ということだ。手書きの精度なら気になる事は無いが…。
つまり数十μmの素子を狙って炙るにしても番地が常にいい加減なので、狙うに狙えない。
これは有機半導体であろうがなんであろうが、同じ問題だ。
この寸法安定性の悪さは、まず線膨張係数がガラスの約10倍であることに基づく。
この線膨張係数がどのように寄与するのか・・・例えば100mm角の基板とする。
これは工程の温度管理をガラスを使用したときの1/10に制御することを要求している。
常にTFTを探し出してそこにレーザーを当てるとか、毎回画素やTFTを見ながら配線を描くとかするのならなんとかなるかもしれんが、それは量産ではない。
さらに高分子は吸湿膨張、残留応力による変形という厄介な問題を抱えている。
というのは上記の線膨張係数だけなら1m角のガラスで出来ている事を100mm角にすればいい。
ただし画素密度は1m角のガラスで作っているレベルだ。簡単に計算してみよう
そのような液晶表示素子が売れるとは思えんが・・・。
さらにポリカーボネートの吸湿膨張係数がおよそ0.03%⇒300ppmと、かなり酷い。アクリルに比べるとマシだが。
そしてこの吸湿膨張の厄介なのは、端面から吸湿するため、四隅は早く吸湿するが基板の真ん中まで水分が到達する時間が読めないという事。
そして水分を全部抜いてもすぐに吸う事だ。なお、四隅だけが伸びると長方形とか正方形ではなくなる。
そういう事をやめようとすると水分飽和か、完全脱水かどちらかを選ぶ必要がある。中途半端な吸湿状態だと制御できない。
こんな扱いにくい基板の上に最近の液晶表示素子を作るなんて、量産なんか全く考えてないだろう。
100mm角の基板の真ん中だけ使うという方法はある。大吟醸だ(笑)。
あと、TFT液晶表示素子の優位点を活かすとすれば、液晶を挟持する対向基板はパターニングが不要で単なるベタ基板で良いことだ。
となると、本来の素子側基板にTFTも作ってしまうことでなんとかできるかもしれない。ただし、100mm角の基板の真ん中だけ。
人間が気づくか気づかないかのレベルの歪みでRGBカラーフィルターを印刷する。
その上に必要な膜を形成して、各画素の上に素子となるTFTをレーザーで(職人技だな)描く。
ウェットエッチングは無理なのでドライエッチングで不要な膜を除去。
画素の上に描かれたTFT素子を狙ってパルスレーザーで光アニール。
なんとか配線してできあがり。
さて、ここでは触れなかったが高分子は複屈折を持つ。これは残留応力そのものが光学的に見えるもので、これがあると偏光を利用する液晶は非常に面倒だ。
詳細は書けないが・・・。
実現はかなり難しいだろう。理由はこれだ。プラスチック(高分子)は寸法安定性が悪い事。これに尽きる。
液晶表示素子は基板上に画素をタイルの様に並べたものだ。写真製版に基づく半導体製造プロセスで画素と画素のON/OFFスイッチとなる素子(TFT)を作り込む。
タイルを並べるにしても、基板の寸法安定性が悪いとまっすぐな直線がグニャグニャの曲線になるだろう。これをどうやってまっすぐにするかが問題だ。
現在の技術では上記のスイッチとなる素子は無機系半導体でしか満足のいく性能を出すことができない。このような無機半導体は基本的に高温処理(普通の高分子が液体になる温度)が必要だ。ピザを焼く様なもので、チーズをどろりと溶かす為には生地ごと高温オーブンに突っ込む必要がある。半導体も同じで、基板の上に積み上げた材料をオーブンで熱処理して半導体のスイッチにする。
ここで基板そのものを熱して、基板の上に設けた無機物を変成してTFTを作るのではなく、表面のTFTだけを「狙って」熱処理するという考えがある。UVエキシマーパルスレーザー(ピコ秒レーザーまたはフェムト秒レーザー)で数十μm四方の素子だけを「炙る」という方法だ。
しかし、ここで問題になるのは高分子の上に描画して作ったTFT素子の番地というか、場所が常にいい加減ということだ。手書きの精度なら気になる事は無いが…。
つまり数十μmの素子を狙って炙るにしても番地が常にいい加減なので、狙うに狙えない。
これは有機半導体であろうがなんであろうが、同じ問題だ。
この寸法安定性の悪さは、まず線膨張係数がガラスの約10倍であることに基づく。
線膨張係数を列記しよう
硬質ガラス:8.5ppm
SUS410: 10.4ppm
PC: 75ppm (polycarbonate: CDの材質、ポリカーボネート)
SUS410: 10.4ppm
PC: 75ppm (polycarbonate: CDの材質、ポリカーボネート)
この線膨張係数がどのように寄与するのか・・・例えば100mm角の基板とする。
線膨張係数が8.5(硬質ガラス)は1℃の温度変化で100mm*8.5*10-6=0.00085mm=0.85μm
線膨張係数が75(PC)は1℃の温度変化で100mm*75*10-6=0.0075mm=7.5μm
線膨張係数が75(PC)は1℃の温度変化で100mm*75*10-6=0.0075mm=7.5μm
これは工程の温度管理をガラスを使用したときの1/10に制御することを要求している。
常にTFTを探し出してそこにレーザーを当てるとか、毎回画素やTFTを見ながら配線を描くとかするのならなんとかなるかもしれんが、それは量産ではない。
さらに高分子は吸湿膨張、残留応力による変形という厄介な問題を抱えている。
というのは上記の線膨張係数だけなら1m角のガラスで出来ている事を100mm角にすればいい。
ただし画素密度は1m角のガラスで作っているレベルだ。簡単に計算してみよう
1m角のガラス基板から液晶表示素子が2枚取れると考える。50cm×100cmなので86.5cm=34inch。
頑張って4k2kを作ろう。100cmに4,000画素がある。RGBなので12,000画素。
1,000mm÷12,000画素=83μm/画素
これをスマートフォンで考えてみよう。
iPhone 5で326ppi(=326画素/25.4mm)⇒25.4mm÷(326*3)=26μm。解像度が3倍だ。
そこには辿り着けない。初代iPhoneにも及ばない。
頑張って4k2kを作ろう。100cmに4,000画素がある。RGBなので12,000画素。
1,000mm÷12,000画素=83μm/画素
これをスマートフォンで考えてみよう。
iPhone 5で326ppi(=326画素/25.4mm)⇒25.4mm÷(326*3)=26μm。解像度が3倍だ。
そこには辿り着けない。初代iPhoneにも及ばない。
そのような液晶表示素子が売れるとは思えんが・・・。
さらにポリカーボネートの吸湿膨張係数がおよそ0.03%⇒300ppmと、かなり酷い。アクリルに比べるとマシだが。
そしてこの吸湿膨張の厄介なのは、端面から吸湿するため、四隅は早く吸湿するが基板の真ん中まで水分が到達する時間が読めないという事。
そして水分を全部抜いてもすぐに吸う事だ。なお、四隅だけが伸びると長方形とか正方形ではなくなる。
そういう事をやめようとすると水分飽和か、完全脱水かどちらかを選ぶ必要がある。中途半端な吸湿状態だと制御できない。
こんな扱いにくい基板の上に最近の液晶表示素子を作るなんて、量産なんか全く考えてないだろう。
100mm角の基板の真ん中だけ使うという方法はある。大吟醸だ(笑)。
あと、TFT液晶表示素子の優位点を活かすとすれば、液晶を挟持する対向基板はパターニングが不要で単なるベタ基板で良いことだ。
となると、本来の素子側基板にTFTも作ってしまうことでなんとかできるかもしれない。ただし、100mm角の基板の真ん中だけ。
人間が気づくか気づかないかのレベルの歪みでRGBカラーフィルターを印刷する。
その上に必要な膜を形成して、各画素の上に素子となるTFTをレーザーで(職人技だな)描く。
ウェットエッチングは無理なのでドライエッチングで不要な膜を除去。
画素の上に描かれたTFT素子を狙ってパルスレーザーで光アニール。
なんとか配線してできあがり。
さて、ここでは触れなかったが高分子は複屈折を持つ。これは残留応力そのものが光学的に見えるもので、これがあると偏光を利用する液晶は非常に面倒だ。
詳細は書けないが・・・。